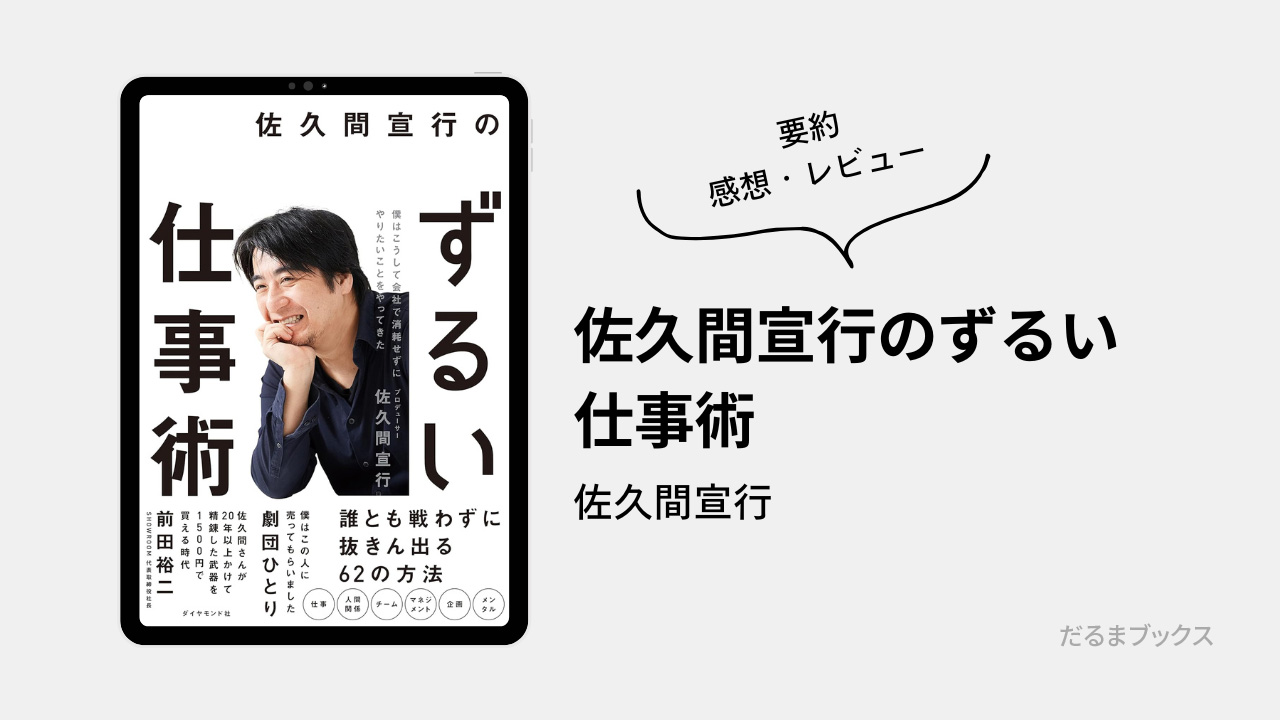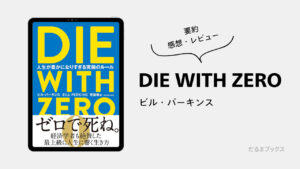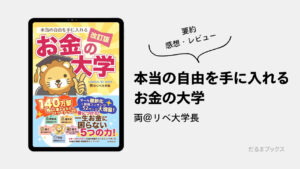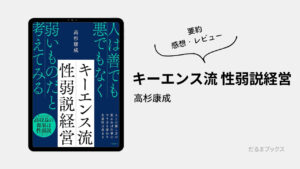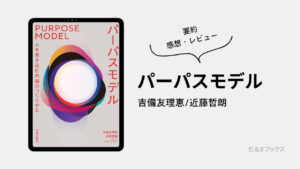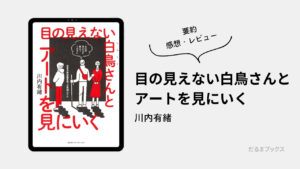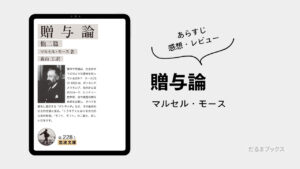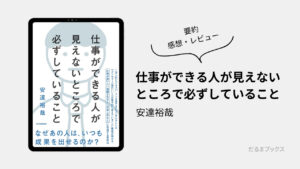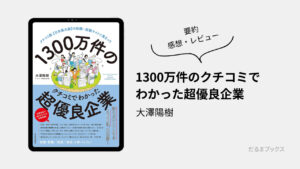テレビ東京の敏腕プロデューサーとして「ゴッドタン」や「あちこちオードリー」などのヒット番組を手がけ、サラリーマンでありながらラジオパーソナリティとしても活躍する佐久間宣行さん。
彼が22年のキャリアで培った「消耗せずに自分らしく働く」ための知恵が詰まった『佐久間宣行のずるい仕事術』は、組織に属しながらも自分のやりたいことを実現するためのヒントが満載です。
本記事では、この本の要点を掘り下げながら、「たかが仕事」と割り切りつつも成果を出す佐久間流の仕事術をご紹介します。
著者・佐久間宣行さんのプロフィール
テレビ東京で培った異色の経歴
佐久間宣行さんは1975年11月23日、福島県いわき市生まれのテレビプロデューサーです。テレビ東京に入社後、数々の人気番組を手がけてきました。一般的なテレビプロデューサーとは一線を画す存在として、社員でありながらも自分の名前を前面に出した活動を展開してきたことで知られています。
テレビ東京という組織に属しながらも、自分の色を出した番組作りを続け、いわゆる「会社員」の枠を超えた活動を展開してきた佐久間さん。彼の歩んできた道のりは、多くのサラリーマンにとって憧れの存在といえるでしょう。
組織の中で自分らしく生きるというのは、決して簡単なことではありません。しかし佐久間さんは、会社という枠組みの中でも自分のやりたいことを実現するための術を身につけてきました。それが本書で語られる「ずるい仕事術」の根幹となっています。
「ゴッドタン」「あちこちオードリー」などのヒット作
佐久間さんがプロデュースした代表作には、「ゴッドタン」「あちこちオードリー」「ピラメキーノ」「ウレロ☆シリーズ」「SICKS〜みんながみんな、何かの病気〜」「キングちゃん」などがあります。これらの番組は、既存の枠にとらわれない斬新な企画や演出で多くのファンを獲得してきました。
特に「ゴッドタン」は、深夜番組ながら熱狂的なファンを持つ人気番組となり、佐久間さんの名を世に知らしめる作品となりました。また「あちこちオードリー」では、お笑いコンビ・オードリーの魅力を最大限に引き出す企画で話題となりました。
2019年4月からは「佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)」のパーソナリティを担当し、YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」も運営するなど、活動の場を広げています。テレビプロデューサーという枠を超え、マルチな才能を発揮し続ける佐久間さんの活躍は、多くの人に影響を与えています。
「ずるい仕事術」の本質とは
たかが仕事と割り切る姿勢
佐久間さんが提唱する「ずるい仕事術」の根幹にあるのは、「たかが仕事」という割り切りです。これは決して仕事を軽視するという意味ではなく、仕事と自分の人生や健康とのバランスを取るための考え方です。
佐久間さんは本書の中で「心を壊してまでやるべき仕事なんてどこにもない。どんなに大きな仕事でも、どれだけ意義のある仕事でも、心を差し出すまでの価値はない。だって仕事なんて、『たかが仕事』なのだから」と語っています。
この言葉は、仕事に真摯に向き合いながらも、自分自身を犠牲にしないという姿勢を表しています。佐久間さん自身、かつては仕事に没頭するあまり心身を消耗した経験があったからこそ、「ずるく」仕事をすることの大切さに気づいたのです。
「真剣」にはなっても、「深刻」になってはいけない—この言葉は、仕事と適切な距離感を保ちながら取り組むことの重要性を教えてくれます。
消耗せずに成果を出す方法論
「ずるい仕事術」のもう一つの柱は、無駄な消耗をせずに効率的に成果を出す方法論です。佐久間さんは、組織の中で無用な争いを避けながら、自分のやりたいことを実現するための具体的な方法を提示しています。
例えば、会議の前に徹底的に準備をして一歩先を行く、ホウレンソウ(報告・連絡・相談)を戦略的に活用する、相談する相手を選ぶなど、日常の業務の中で実践できる具体的なテクニックが満載です。
これらの方法は、単に楽をするためのものではなく、限られたエネルギーを最も効果的に使い、本当に大切なことに集中するための知恵といえるでしょう。無駄な争いや消耗を避けることで、クリエイティブな仕事により多くのリソースを割くことができるのです。
佐久間さんの「ずるい仕事術」は、仕事を楽しみながらも成果を出し、自分らしいキャリアを築くための実践的な知恵が詰まっています。それは単なるテクニックではなく、仕事と向き合う姿勢そのものを変える力を持っているのです。
仕事術編の重要ポイント
「楽しそう」を最強のアピールにする
佐久間さんが強調するのは、仕事において「楽しそう」に見えることの重要性です。これは単に表面的な態度ではなく、仕事に対する本質的な姿勢に関わることです。
「楽しそうに仕事をしている人」は、周囲から見ても魅力的に映ります。そして、そういった人には自然と仕事が集まってくるものです。佐久間さんは、自分が本当に興味を持てる仕事に取り組むことで、自然と「楽しそう」に見え、それが最強のアピールになると説きます。
また、どんな仕事にも「楽しい側面」を見つける努力をすることも大切だと言います。一見つまらなく思える雑務でも、そこに面白さや学びを見出すことで、仕事への取り組み方が変わってきます。
この「楽しそう」という態度は、周囲の人を巻き込む力も持っています。楽しそうに仕事をしている人の周りには、自然と人が集まり、協力者が現れるものです。それは結果として、より大きな成果につながっていくのです。
ホウレンソウを使い倒す技術
ビジネスの基本とされる「ホウレンソウ(報告・連絡・相談)」ですが、佐久間さんはこれを戦略的に活用することの重要性を説いています。
ホウレンソウの本質的な目的は、上司を不安にさせないことだと佐久間さんは言います。特に共有すべき重要なポイントは「進捗状況」と「優先順位」です。これらを適切に伝えることで、上司は安心し、余計な介入をせずに任せてくれるようになります。
また、相談の際には「解決」をゴールにすることが大切です。単に悩みを打ち明けるだけでなく、解決策を一緒に考えられる相手を選び、なぜその人に相談したのかを明確に伝えることで、より建設的な助言を得ることができます。
ホウレンソウを形式的なものではなく、仕事をスムーズに進めるための戦略的なコミュニケーションツールとして活用する—これが佐久間流の「ホウレンソウを使い倒す技術」なのです。
会議は事前準備で勝つ
佐久間さんによれば、会議は「その他大勢から抜け出す場」であり、日々の会議こそが重要だと言います。そして、会議で存在感を示すための鍵は「事前準備」にあります。
会議の前に想定される質問に答えられるよう準備し、必要になりそうな資料はあらかじめ用意しておく。前回の会議で話題になったことを調べて次の会議に持っていくなど、一歩先を行く準備が大切です。
また、会議後の「5分」も重要だと佐久間さんは指摘します。会議で決まったことをすぐにメモにまとめ、次のアクションに移すことで、他の参加者より一歩先に進むことができます。
こうした準備と素早いフォローアップが、会議での存在感を高め、結果として自分の意見や提案が通りやすくなるのです。会議を単なる情報共有の場ではなく、自分の価値をアピールする機会として捉える視点は、佐久間流の「ずるい仕事術」の真髄といえるでしょう。
人間関係編で学ぶこと
コミュニケーションは「最短距離」より「平らな道」
職場での人間関係において、佐久間さんが重視するのは「最短距離」ではなく「平らな道」を選ぶコミュニケーションです。これは何を意味するのでしょうか。
「最短距離」とは、効率を重視して直線的に目的地に向かうコミュニケーションスタイルです。一方「平らな道」とは、多少遠回りになっても、摩擦を避けて円滑に進むコミュニケーションを指します。
例えば、相手のメンツを潰すような言い方や、正論を振りかざすことは「最短距離」かもしれませんが、人間関係に亀裂を生じさせる可能性があります。佐久間さんは、そうした「メンツ地雷」を踏まないよう注意することの重要性を説いています。
特に「メンツの地雷を踏んではいけない」「正論を吐くと大抵は嫌われる」といった指摘は、多くのビジネスパーソンが経験的に理解していることでしょう。しかし、つい感情的になったり、効率を優先したりして、この原則を忘れてしまうことも少なくありません。
佐久間さんは、長期的な人間関係構築のためには、時に遠回りに見えるコミュニケーションが実は最も効率的だと教えてくれます。これは単なる処世術ではなく、組織の中で自分の居場所を確保し、やりたい仕事を実現するための重要な知恵なのです。
「褒める」は最強のビジネススキル
人間関係を円滑にし、チームの力を引き出すために、佐久間さんが最も重視するスキルが「褒める」ことです。
「褒める」ことは、相手のモチベーションを高めるだけでなく、自分と相手の関係性も良好にします。特に、具体的な点を挙げて褒めることで、相手は自分が認められていると実感し、より良い仕事をするようになります。
佐久間さんは、「陰口」や批判よりも「褒める」ことの方がコスパが良いと指摘します。陰口は一時的なストレス発散になるかもしれませんが、長期的には人間関係を悪化させ、仕事の効率も下げてしまいます。
また、佐久間さんは「コント:嫌いな人」という独自の方法で、苦手な相手とのコミュニケーションを乗り切ることも紹介しています。苦手な人と対面したとき、心の中で「コント:嫌いな人」と唱えることで、その状況を客観視し、感情的にならずに対応できるというものです。
これらの方法は、職場での人間関係をストレスなく維持し、自分のエネルギーを本来の仕事に集中させるための知恵といえるでしょう。佐久間さんの「褒める」技術は、単なるテクニックを超えた、人間関係の本質を捉えた智慧なのです。
企画術編の秘訣
佐久間流発想法「反転法」と「掛け合わせ法」
佐久間さんが長年のキャリアで培ってきた企画発想法には、「反転法」と「掛け合わせ法」という二つの柱があります。
「反転法」とは、既存の概念や常識を逆転させて新しいアイデアを生み出す方法です。例えば「褒められて伸びるタイプ」が一般的とされる中で、「叱られて伸びるタイプ」に焦点を当てた企画を考えるなど、当たり前を疑い、逆の発想をすることで新鮮なアイデアが生まれます。
「掛け合わせ法」は、一見関係のない二つの要素を組み合わせて新しい価値を創造する方法です。例えば「お笑い」と「哲学」、「料理」と「旅行」など、異なるジャンルを掛け合わせることで、これまでにない企画が生まれる可能性があります。
佐久間さんはこれらの発想法を用いながら、さらに「自分だけの『原液』」を混ぜることの重要性も説いています。自分ならではの経験や価値観、興味関心を企画に反映させることで、オリジナリティのある企画が生まれるのです。
これらの発想法は、テレビ番組の企画だけでなく、あらゆるビジネスシーンでのアイデア創出に応用できる普遍的な方法論といえるでしょう。
企画は「仕組み」でつくる
佐久間さんが強調するのは、企画やアイデアは「時間を作って捻出する」のではなく、「仕組み」として日常に組み込むことの重要性です。
具体的には、日々浮かんだアイデアや思いつきをすべてメモする習慣をつけ、それを定期的に見直して企画に発展させるというプロセスを提案しています。佐久間さん自身は、「メモを見返す日(3日に1回)」「ノートを整理する日(2週に1回)」「企画書に練り上げる日(月1回)」をGoogleカレンダーに設定し、ルーティン化しているそうです。
このように企画づくりを「朝食や歯磨きのように日々のルーティン」に組み込むことで、アイデア出しがモチベーションに左右されにくくなります。「いいアイデアが浮かんだら…」と偶然を頼るのではなく、日々の中にクリエイティブな時間を意識的に組み込むことが、安定したアイデア創出につながるのです。
佐久間さんのこの方法論は、「時間がない」「アイデアが浮かばない」と悩む多くのビジネスパーソンに、具体的かつ実践的な解決策を提示しています。企画力を「才能」や「ひらめき」に頼るのではなく、「仕組み」として定着させる視点は、クリエイティブな仕事に携わる全ての人にとって貴重な指針となるでしょう。
メンタル編の心構え
メンタル第一、仕事は第二
佐久間さんが最も重視するのが「メンタル第一、仕事は第二」という考え方です。彼は自身の経験から、心を壊してまでやるべき仕事はどこにもないと断言しています。
「心を壊してまでやるべき仕事なんてどこにもない。どんなに大きな仕事でも、どれだけ意義のある仕事でも、心を差し出すまでの価値はない。だって仕事なんて、『たかが仕事』なのだから」という佐久間さんの言葉には、深い説得力があります。
実は佐久間さん自身も、かつては「ギリギリまでがんばって『ポキン』と心が折れてしまい、しばらく引き籠もり生活を送っていた」経験があるそうです。そんな経験があるからこそ、「死守すべきは仕事よりもメンタル」という考えに至ったのでしょう。
佐久間さんは「真剣」と「深刻」を区別することの重要性も説いています。仕事には真剣に取り組むべきですが、深刻になりすぎると心を蝕んでしまいます。適切な距離感を保ちながら仕事と向き合うことが、長期的に見て最も生産的だというのが佐久間さんの考えです。
この「メンタル第一」の姿勢は、現代のビジネスパーソンが見失いがちな大切な視点を教えてくれます。仕事の成果を追い求めるあまり、自分自身を犠牲にしてしまうことの危険性に警鐘を鳴らしているのです。
「運」を味方につける方法
佐久間さんは、仕事における「運」の重要性にも言及しています。しかし、それは単なる偶然の幸運を待つという意味ではありません。
佐久間さんによれば、「運」は自分でコントロールできる要素があります。例えば、常に前向きな姿勢でいること、人との縁を大切にすること、チャンスが来たときに逃さず掴むことなどが、「運」を味方につける方法だと言います。
特に人との縁については、「人と会うことを大切にする」「人の話をよく聞く」「人の紹介を断らない」といった具体的な行動指針を示しています。これらの行動が、思わぬチャンスや「運」につながることが多いのです。
また、佐久間さんは「運がいい人」の特徴として、「常に楽しそうにしている」「感謝の気持ちを持っている」「人のせいにしない」といった点を挙げています。これらの特徴は、周囲の人が自然とその人を助けたくなる雰囲気を作り出し、結果として「運」を引き寄せることにつながるのです。
「運」は完全にコントロールできるものではありませんが、自分の態度や行動によって、より「運」が巡ってくる確率を高めることはできる—これが佐久間流の「運」の考え方です。
省エネモードの活用法
佐久間さんが提唱する「ずるい仕事術」の中でも特に実践的なのが「省エネモード」の活用法です。これは、限られたエネルギーを効率的に使い、無駄な消耗を避けるための知恵です。
佐久間さんは、全ての仕事に100%のエネルギーを注ぐのではなく、仕事の重要度に応じてエネルギーの配分を変えることを推奨しています。例えば、重要なプレゼンや企画会議には全力を注ぎ、ルーティンワークや優先度の低い業務は「省エネモード」で対応するというものです。
具体的な「省エネモード」の例としては、「会議の発言回数を減らす」「メールの返信を一日一回にまとめる」「不要な飲み会は丁寧に断る」などが挙げられています。これらは単なる手抜きではなく、限られたエネルギーを本当に重要なことに集中させるための戦略的な選択なのです。
また、佐久間さんは「嫌いな人」との関わりをコント化する方法も紹介しています。苦手な相手と対面したとき、心の中で「コント:嫌いな人」と唱えることで、その状況を客観視し、感情的にならずに対応できるというものです。これも一種の「省エネモード」といえるでしょう。
このように、自分のエネルギーを戦略的に配分し、無駄な消耗を避けることで、長期的に見て高いパフォーマンスを維持することができる—これが佐久間流の「省エネモード」の真髄です。
感想・レビュー
普遍的な仕事の知恵が詰まった一冊
『佐久間宣行のずるい仕事術』を読み終えて最も印象に残ったのは、その普遍性です。この本に書かれている知恵は、テレビ業界に限らず、あらゆる職種や立場の人に当てはまる普遍的なものばかりです。
特に「メンタル第一、仕事は第二」という考え方は、現代社会において非常に重要なメッセージだと感じました。成果主義やパフォーマンス至上主義が蔓延する中、自分自身の心の健康を最優先にするという視点は、長期的に見て最も「賢い」選択なのだと改めて気づかされます。
また、佐久間さんの「ずるさ」は決して悪い意味ではなく、むしろ「賢さ」と言い換えられるものです。無駄な争いを避け、自分のエネルギーを大切にしながらも、成果を出し続ける—そんな「賢い」働き方のヒントが満載です。
佐久間さんの文体も魅力的で、時折挟まれるユーモアや具体的なエピソードが、読者を飽きさせません。難しい概念も、身近な例えを用いてわかりやすく説明されているため、誰でも実践できるように工夫されています。
この本は、新社会人から管理職まで、あらゆるビジネスパーソンにとって価値ある一冊だと言えるでしょう。
特別ではない人が特別になるための処方箋
佐久間さんは本書の中で、自分は特別な才能を持った人間ではなく、むしろ「普通の人」だと繰り返し述べています。そして、そんな「普通の人」が、どのようにして特別な成果を出してきたのかを赤裸々に語っています。
この点が、本書の最大の魅力の一つだと感じました。多くの「成功者」の著書は、読者には真似できないような特別な才能や環境を前提としていることが少なくありません。しかし佐久間さんは、誰でも実践できる具体的な方法論を提示しています。
例えば、「楽しそうに仕事をする」「ホウレンソウを徹底する」「会議の前に準備をする」といったことは、特別な才能がなくても実践できることばかりです。しかし、それらを徹底することで、周囲との差別化を図り、自分の居場所を確保していく—そんな地道な努力の積み重ねが、結果として「特別」な成果につながるのだということを教えてくれます。
また、佐久間さんの「企画は仕組みでつくる」という考え方も、クリエイティブな仕事に対する新たな視点を与えてくれます。アイデアや企画は、神秘的な「ひらめき」を待つのではなく、日々の習慣や仕組みの中から生まれるものだという考え方は、多くの人に希望を与えるものでしょう。
この本は、「自分には才能がない」と思い込んでいる人に、「才能」以外の方法で成功する道があることを教えてくれる、貴重な処方箋だと言えます。
まとめ
『佐久間宣行のずるい仕事術』は、テレビ東京の敏腕プロデューサーとして数々のヒット番組を生み出してきた佐久間宣行さんが、22年のキャリアで培った「消耗せずに自分らしく働く」ための知恵を詰め込んだ一冊です。
本書で語られる「ずるさ」とは、単なる悪知恵ではなく、組織の中で自分のやりたいことを実現するための戦略的な思考法です。「メンタル第一、仕事は第二」という基本姿勢のもと、「楽しそうに仕事をする」「ホウレンソウを徹底する」「会議は事前準備で勝つ」といった具体的な方法論が示されています。
また、人間関係においては「最短距離」より「平らな道」を選ぶこと、「褒める」ことの重要性が説かれ、企画術としては「反転法」「掛け合わせ法」という発想法や、企画を「仕組み」として日常に組み込む方法が紹介されています。
佐久間さんの「ずるい仕事術」は、仕事に真摯に向き合いながらも自分自身を犠牲にしない、長期的に見て最も「賢い」働き方を教えてくれます。特別な才能がなくても、工夫次第で特別な成果を出せることを示した本書は、あらゆるビジネスパーソンにとって価値ある一冊といえるでしょう。