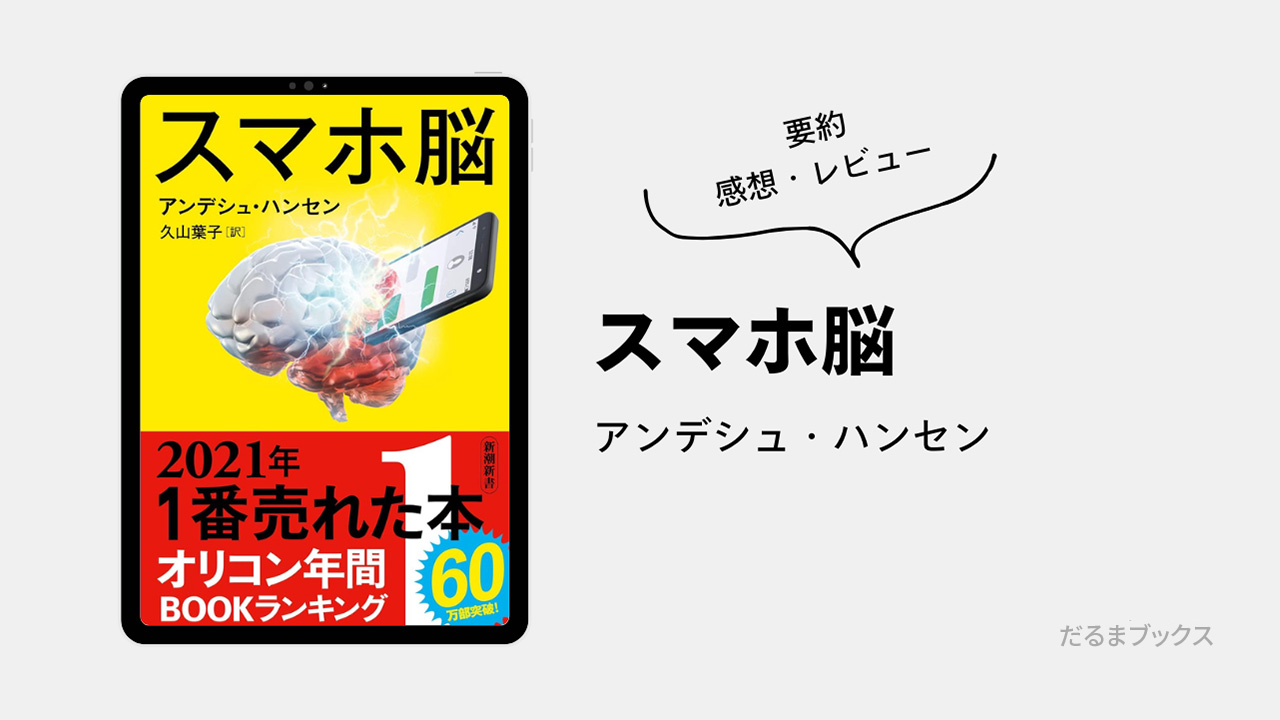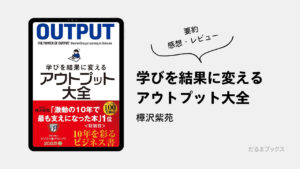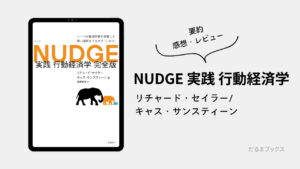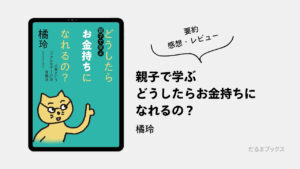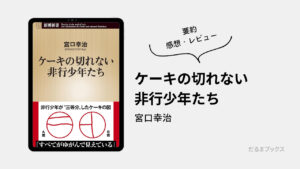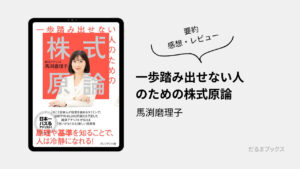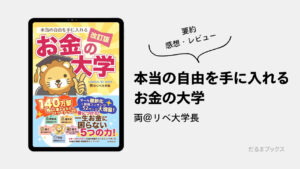スマホを手放せない現代人の悩みに科学的な解答を示す「スマホ脳」。
スウェーデンの精神科医アンデシュ・ハンセンさんによるこのベストセラーは、私たちが日常的に使うスマホが脳にどのような影響を与えているのかを脳科学の観点から解説しています。
- 集中力の低下
- 睡眠障害
- 依存症
など、スマホがもたらす様々な問題と、その対策法について詳しく知ることができる一冊。
著書「スマホ脳」のあらすじや要点を紹介しながら、デジタル時代を健全に生きるためのヒントをお伝えします。
「スマホ脳」とは何か
「スマホ脳」の大前提として、ハンセンさんが強調するのは「人間の脳はデジタル社会に適応していない」という事実です。
人類は地球上に現れてから大半の時間を、狩猟と採集によって暮らしてきました。著者の言葉を借りれば、私たちの脳は今もサバンナで暮らしているのです。
本書では、スマホが私たちの脳に与える影響について、科学的根拠と生物学的な視点から分かりやすく解説しています。平均で一日四時間、若者の二割は七時間も使うスマホ。
だがスティーブ・ジョブズを筆頭に、IT業界のトップはわが子にスマートフォンなどを与えないという事実。
なぜなのか?その答えは、スマホの便利さに溺れているうちに私たちの脳が確実に蝕まれていくからだと本書は指摘しています。
「スマホ脳」出版の背景
ハンセンさん自身、本書を著す1年前に自分がスマホに1日3時間近く費やしていることに気づき、ショックを受けたといいます。何をしていても手がスマホに伸びる。読書が好きだったはずなのに、本に集中するのが難しくなった。そんな自分の変化に気づいたのです。
同時に、精神科医として診察する中で、メンタルの不調を訴えて受診する人の数が激増していることも感じていました。デジタル化したライフスタイルは何をもたらしたのか。その疑問を解明するために、ハンセンさんは多くの先行研究を参照しながら「スマホ脳」の危険性を解き明かしていきました。
アンデシュ・ハンセンさんのプロフィール
「スマホ脳」の著者であるアンデシュ・ハンセンさんは、スウェーデンの精神科医です。
ノーベル賞選定で知られる名門カロリンスカ医科大学を卒業後、ストックホルム商科大学で経営学修士(MBA)を取得しました。現在は王家が名誉院長を務めるストックホルムのソフィアヘメット病院に勤務しながら執筆活動を行っています。また、テレビ番組でナビゲーターを務めるなど、精力的にメディア活動も続けています。
ハンセンさんの前作「一流の頭脳」は、人口わずか1000万人のスウェーデンで60万部を突破する大ヒットとなりました。そして今回の「スマホ脳」も、世界13カ国以上で翻訳される世界的ベストセラーとなっています。日本でも2021年上半期のベストセラーランキングで新書・ノンフィクション部門の1位を獲得し、オリコンの調べでは2020年11月から2021年11月までの書籍ベストセラーランキングでも1位となりました。
スマホが脳に与える影響
集中力の低下メカニズム
スマホが私たちの集中力に与える影響は想像以上に深刻です。大学生500人を対象に集中力と記憶力を調べるテストをしたところ、スマホを教室の外に置いた学生の方が、サイレントモードにしてポケットにしまっておいた学生より良い結果が出たという研究結果があります。
これはなぜでしょうか。ポケットに入っているだけでも、スマホを無視することに脳の処理能力を使ってしまうからだと著者は説明しています。つまり、「何かを無視する」というのは脳に働くことを強いる能動的な行為なのです。机の上にスマホを置いておくだけで、私たちの脳は処理能力の何割かを常に、スマホを「無視する事」に費やす羽目になり、結果、作業の効率はガタ落ちしてしまいます。しかも、自分では集中していると思っているので始末が悪いのです。
商談の時も気をつけた方がいいでしょう。テーブルの上にスマホを置いた群と、置いていない群で、知らない人と話してもらう実験では、視界にスマホが入っていた人たちの方が「あまり楽しくない」「共感しづらい」と感じていました。これもまた、スマホに気を引かれ、目の前の相手に集中できなかった結果だと考えられます。
記憶力への悪影響
スマホは私たちの記憶力にも悪影響を及ぼします。スマホを傍らに置くだけで学習効果、記憶力、集中力は低下するという研究結果があります。
何か勉強しているとき横にスマートフォンをおいていると、通知でスマートフォンが光るたびに目線がスマートフォンの方に移ってしまい、なかなか進まないという経験は多くの人が共感できるのではないでしょうか。
集中力や記憶力が衰えたとしても、覚えられる数字の桁数が少なくなる程度なら、それほど問題ないと感じるかもしれません。今や、あらゆる情報はインターネットの中にあり、覚えていなくても検索すれば事足りると思うかもしれません。
しかし、記憶は個人的な体験と融合され、「知識」として構築されるのです。知識とはもちろん、情報の羅列ではありません。私たちは脳内に根づいた知識を用いて、世の中をあらゆる角度から捉え、深く考察しています。スマホ脳によって、そうした思考力が失われているとしたら、取り返しがつかないでしょう。
ストレスと睡眠の問題
スマホの使用は、ストレスと睡眠にも大きな影響を与えます。特に就寝前のスマホ使用は、ブルーライトの影響で睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を抑制し、睡眠の質を低下させます。
また、SNSの過剰な使用は、他者との比較によるストレスを増大させます。セオドア・ルーズベルトは「比較は喜びを奪う」という言葉を残しましたが、21世紀の私たちは「何百万人もの相手と張り合っている」状態です。何をしても、自分より上手だったり、賢かったり、かっこよかったり、リッチだったり、より成功していたりする人がいます。そんな状況では、心が折れるのも無理はありません。
デジタル認知症の実態
「デジタル認知症」という言葉をご存知でしょうか。これは、デジタル機器への依存によって脳の機能が低下する状態を指します。
スマホに依存することで、私たちは自分の脳を使わなくなっています。電話番号を覚える必要はなく、道を覚える必要もなく、計算する必要もありません。すべてスマホがやってくれるからです。しかし、使わない脳の機能は衰えていきます。
著者は「スマホというテクノロジーが、人間を2.0バージョンにするよりも、むしろ0.5バージョンにしてしまう」と警告しています。これは非常に重要な指摘です。テクノロジーの進化が必ずしも人間の能力の向上につながるわけではないのです。
スマホ依存のメカニズム
脳内報酬系とドーパミンの関係
なぜ私たちはこんなにもスマホが手放せないのでしょうか。その理由は、スマホを使うとき「ドーパミン」という、脳が報酬を期待したときに放出されるホルモンが分泌されているからです。
ドーパミンの最も重要な役割は、何に集中するかを選択させることです。つまり人間の原動力となるものなのです。スマホは、脳の報酬メカニズムである「新しいもの好き、期待、可能性」をハッキングして、使う人の脳内にドーパミンを常に放出させます。