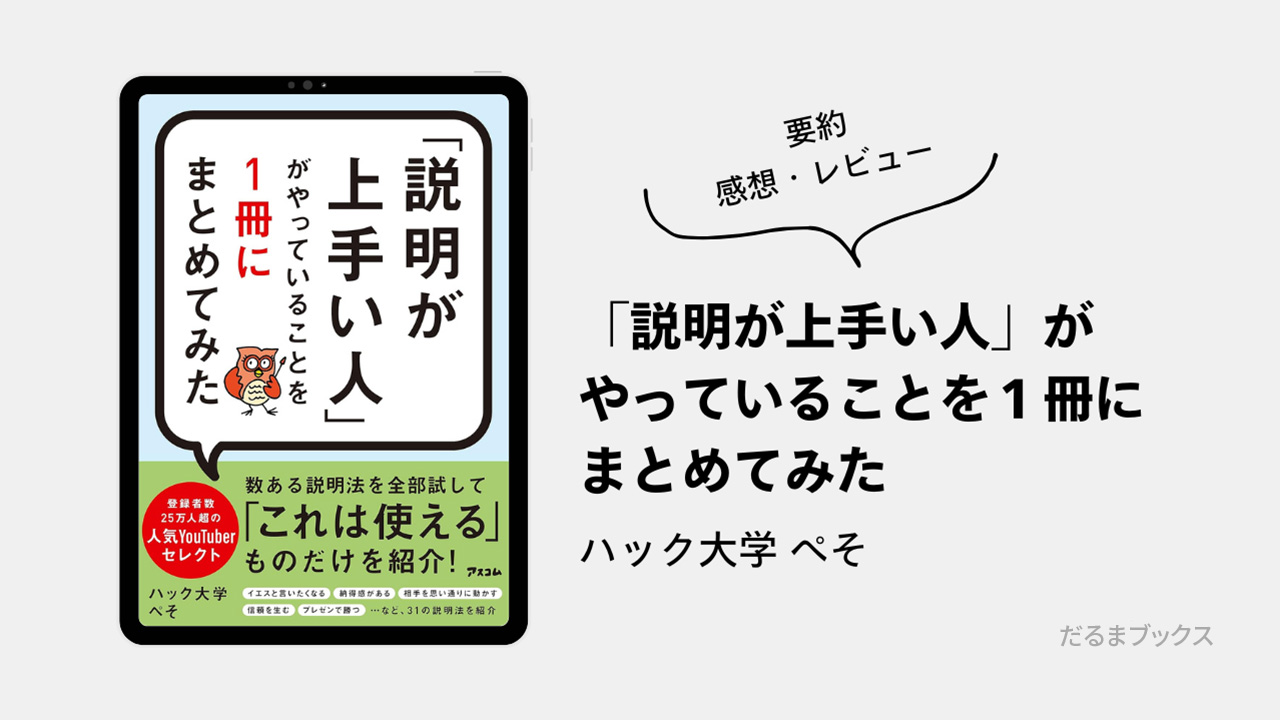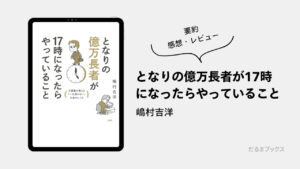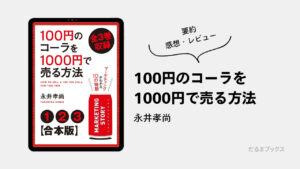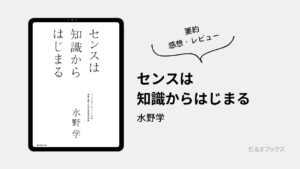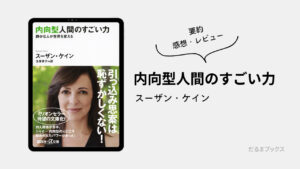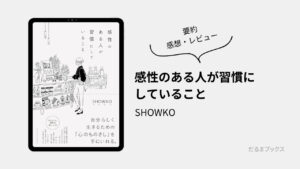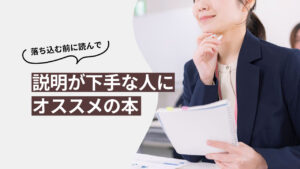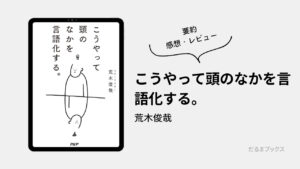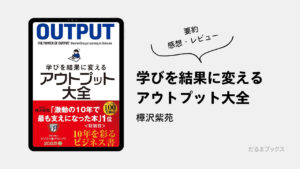説明が上手になりたい!
と思ったことはありませんか?
ビジネスの現場でも日常生活でも、自分の考えや情報を相手に伝えることは非常に重要です。
この本は、説明の達人たちが実践している具体的なテクニックを惜しみなく紹介した一冊。
説明下手を克服したい方、より効果的なコミュニケーションを目指す方必見の内容です。
この本の概要
この本は、ビジネスの最前線で結果を出し続けるプロフェッショナルたちが実践している説明のコツを一冊にまとめた実用書です。
アスコム社から出版され、数ある説明法を全部試して「これは使える」ものだけを厳選して紹介しています。
すぐに使える具体的な方法が満載で、説明の基本から応用まで幅広くカバーしています。
著者ぺそさんについて
ハック大学ぺそさんは、YouTubeチャンネル「ハック大学」を運営する人気ビジネス系クリエイターです。
チャンネル登録者数は27万人を超え、仕事術やキャリア戦略、マネーリテラシーなど、ビジネスパーソンに役立つ情報を発信し続けています。
本業では外資系金融機関のマーケティング部門でマネージャーを務め、年収約2000万円を稼ぐ現役ビジネスパーソン。
1988年生まれのアラサー世代で、事業会社やコンサルティングファームを経て現在のポジションに至っています
大学は偏差値の高い工学部出身とのことですが、具体的な大学名は公表されていません。
他の著書には
などがあり、どれも実践的なノウハウが詰まった良書として評判です。
本書が注目される理由
なぜこの本が注目されているのか、それは「説明力」がビジネスパーソンにとって必須のスキルでありながら、きちんと学ぶ機会が少ないからです。
学校でも会社でも、説明の仕方を体系的に教えてくれる場はほとんどありません。
また、説明が上手いか下手かで、仕事の評価や周囲からの信頼度が大きく変わってくるという現実もあります。
上司や同僚への報告、顧客へのプレゼン、部下への指示出しなど、ビジネスシーンのあらゆる場面で説明力が問われるのです。
さらにこの本では「説明が上手い人」と「説明が下手な人」の違いを明確にし、後者が前者になるための具体的な方法を示しています。
これは単なる「話し方のコツ」ではなく、相手の理解度や心理状態を考慮した戦略的なコミュニケーション術であり、その実用性の高さが多くの読者の支持を集めています。
「説明が上手い人」の核心
説明上手になるための基本姿勢
説明上手になるための第一歩は、自分の頭で考えることです。本書によれば、「意見がない」というのは「自分の頭で考えていない」と白状しているようなもの。ビジネスにおいて、これは致命的な弱点になります。
説明上手な人は、まず自分なりの考えや意見を持ち、それを相手に伝えようとする姿勢を持っています。単に情報を羅列するのではなく、「なぜそれが重要なのか」「どうしてそう考えるのか」という理由や根拠を明確にしているのです。
また、相手目線で考えることも重要です。説明の目的は「自分が言いたいことを言う」ことではなく、「相手に理解してもらう」ことにあります。相手の知識レベルや関心事、時間的制約などを考慮した上で、最適な説明方法を選ぶ柔軟性が求められるのです。
伝わる説明の3つの条件
伝わる説明の3つの条件として以下を挙げています。
まず1つ目は「結論から先に伝える」こと。
これは多くのビジネス書でも言われていることですが、それだけ重要なポイントです。
相手にとっては、提示された結論の理由や根拠を精査することが何より重要で、最初に結論を知ることで「聞く効率」が格段に上がります。
2つ目は「構造化された説明をする」こと。
情報を整理し、論理的な順序で伝えることで、相手の理解を助けます。
特に「アウトライン化」は有効で、「今日お伝えしたいことは3つあります」のように、最初に全体像を示すことで、相手は見通しを持って話を聞くことができます。
3つ目は「相手の理解度に合わせる」こと。
専門用語や業界用語を多用すると、相手にイライラされるだけでなく、「配慮の行き届かない人」「無礼な人」と思われるリスクがあります。
相手が理解できる言葉で、かみ砕いて説明することが大切です。
相手の理解度に合わせた説明術
前提知識の見極め方
説明上手な人は、相手の前提知識を素早く見極める能力に長けています。これは「聞く力」と密接に関連しており、相手の反応や質問から理解度を推し量り、説明の深さや速度を調整しているのです。
具体的な方法としては、説明の冒頭で「この件についてどの程度ご存知ですか?」と率直に尋ねる、相手の表情や反応を注意深く観察する、質問を投げかけて理解度を確認するなどがあります。
また、説明する前に相手との心理的距離を縮めることも効果的です。本書によれば、「相手との心理的距離が近いというだけで、そうでない場合と比べると説明は非常に通りやすくなります」。共通の話題や経験を見つけて会話することで、相手の心を開き、説明を受け入れやすい状態に導くのです。
専門用語をわかりやすく言い換える技術
専門用語や業界用語は、同じ分野の人間同士なら会話の効率を高めますが、異なる分野の人に対しては障壁になります。説明上手な人は、専門用語を相手が理解できる言葉に言い換える技術を持っています。
例えば、「ROI」という言葉を使う代わりに「投資に対してどれだけリターンがあるか」と言い換えたり、「アジャイル開発」を「小さな単位で素早く開発と改善を繰り返す方法」と説明したりします。
重要なのは、言い換えることで情報の正確性を損なわないこと。簡略化しすぎると誤解を招く恐れがあるため、相手の理解度に合わせながらも、本質的な意味を伝えることを心がけましょう。
相手のペースに合わせるコツ
説明のペースも相手に合わせることが重要です。早すぎると理解が追いつかず、遅すぎると退屈させてしまいます。
相手の反応を見ながら、「ここまでよろしいでしょうか?」「何か質問はありますか?」と確認の機会を設けることで、ペースを調整できます。また、重要なポイントでは少し間を置いたり、声のトーンを変えたりして、相手の注意を引くことも効果的です。
さらに、相手の学習スタイルに合わせることも大切です。視覚型の人には図や表を使い、聴覚型の人には丁寧な言葉での説明を、体験型の人には実際に試してもらうなど、多様なアプローチを用意しておくと良いでしょう。
構造化された説明の作り方
全体像を最初に示す重要性
構造化された説明の第一歩は、全体像を最初に示すことです。これにより、相手は「今どこの話をしているのか」「あとどれくらい話が続くのか」を把握でき、安心して説明を聞くことができます。
例えば、「今日は3つのポイントについてお話しします。1つ目は~、2つ目は~、3つ目は~です」というように、最初に説明の骨組みを示します。これは「アウトライン化」と呼ばれる技術で、複雑な内容を説明する際に特に効果を発揮します。
アウトライン化によって、聞き手の「いつまで続くんだろう」「結局ポイントはいくつあったんだっけ」といった混乱を防ぎ、理解を促進することができるのです。
「木構造」で情報を整理する方法
情報を整理する際に役立つのが「木構造」の考え方です。これは、情報を階層的に整理し、大項目から中項目、小項目へと枝分かれさせていく方法です。
例えば、「新商品の特徴」という大項目があれば、その下に「デザイン」「機能」「価格」という中項目を置き、さらにその下に具体的な特徴を小項目として配置します。このように情報を整理することで、説明に一貫性と論理性が生まれます。
木構造で情報を整理する際のコツは、同じ階層の項目は同じ性質のものにすること。例えば、「デザイン」「機能」「発売日」というように、カテゴリーが混在すると相手を混乱させる恐れがあります。
抽象と具体を行き来する説明テクニック
効果的な説明では、抽象的な概念と具体的な事例を行き来することが重要です。抽象的な説明だけでは理解しづらく、具体的な事例だけでは全体像が見えにくいからです。
例えば、「この施策によって顧客満足度が向上します」という抽象的な説明に続けて、「実際に、Aさんは以前こんな不満を持っていましたが、この施策によって問題が解決し、大変喜んでいただきました」という具体例を挙げると、相手の理解が深まります。
このテクニックを使いこなすコツは、抽象と具体のバランスを取ること。抽象的すぎると「結局何が言いたいの?」と思われ、具体的すぎると「で、それがどう重要なの?」と疑問を持たれる可能性があります。相手の反応を見ながら、適切なバランスを見つけましょう。
具体例とたとえ話の効果的な使い方
身近な例で複雑な概念を伝える
複雑な概念や専門的な内容を説明する際、身近な例を用いると相手の理解が格段に深まります。抽象的な概念を具体的なイメージに置き換えることで、相手の脳内に鮮明な絵を描くことができるのです。
例えば、「サーバーの負荷分散」という技術的な概念を説明する際、「一人のウェイターがすべてのテーブルを担当するより、複数のウェイターで分担した方が効率的なのと同じ原理です」と例えれば、IT知識がない人でも理解しやすくなります。
身近な例を選ぶ際のポイントは、相手の知識や経験に合わせること。スポーツが好きな人にはスポーツの例、料理が好きな人には料理の例というように、相手が親しみを感じる分野から例を選ぶと効果的です。
比喩表現のパターンと選び方
比喩表現は説明を生き生きとさせ、相手の記憶に残りやすくする効果があります。本書では、効果的な比喩表現のパターンとして以下のようなものを紹介しています。
まず「直喩」は「AはBのようだ」という形式で、最も基本的な比喩です。「このプロジェクトはマラソンのようなもので、スタートダッシュよりも持続力が重要です」といった使い方をします。
次に「隠喩」は「AはBである」という形式で、より強いイメージを与えます。「時間はお金です」「あなたはこのチームの太陽です」などの表現がこれにあたります。
比喩表現を選ぶ際は、相手が理解できるものであること、誤解を招かないこと、ネガティブな印象を与えないことに注意しましょう。また、使いすぎると逆に混乱を招くこともあるので、要所要所で効果的に使うことが大切です。
具体例の量と質のバランス
具体例は説明を分かりやすくする強力なツールですが、量と質のバランスが重要です。多すぎると本題からそれてしまい、少なすぎると理解を助ける効果が薄れてしまいます。
質の高い具体例の条件は、①相手の知識や経験に合っていること、②本題と明確に関連していること、③記憶に残りやすいインパクトがあることです。これらの条件を満たす具体例を2〜3個用意しておくと、説明の効果が高まります。
また、具体例を出す順序も考慮しましょう。一般的には、シンプルな例から複雑な例へ、身近な例から専門的な例へと進めていくと、相手の理解が段階的に深まります。
説明の順序と流れの設計
論理的な説明の組み立て方
論理的な説明の基本は、情報を適切な順序で並べることです。本書では、効果的な順序として以下のパターンを紹介しています。
まず「時系列順」は、出来事を時間の流れに沿って説明する方法です。「まず最初に~、次に~、最後に~」というように進めると、相手は自然な流れで理解できます。プロジェクトの経過報告や手順の説明に適しています。
次に「重要度順」は、最も重要な情報から順に説明する方法です。ビジネスの場では特に有効で、忙しい相手に対して短時間で核心を伝えることができます。例えば、「最も重要なのは~、次に重要なのは~」というように説明を進めると、相手は優先順位を把握しやすくなります。
さらに「原因と結果」の順序も効果的です。「なぜそうなったのか」という因果関係を明確にすることで、相手の理解が深まります。特に問題解決の場面では、「この問題が起きた原因は~で、その結果~という状況になっています」という説明が説得力を持ちます。
論理的な説明を組み立てる際のコツは、相手に「次に何が来るか」を予測させることです。情報の順序に一貫性があれば、相手は話の流れを追いやすくなり、理解度が高まります。
ストーリー仕立ての説明術
人間の脳は、論理的な情報よりもストーリー(物語)の形で提示された情報の方が記憶に残りやすいという特性があります。この特性を活かした「ストーリー仕立ての説明」は、特に複雑な内容や抽象的な概念を伝える際に効果を発揮します。
ストーリー仕立ての説明の基本構造は、「導入(状況設定)→展開(問題発生)→山場(解決への試み)→結末(解決と教訓)」です。例えば、新しいプロジェクトを提案する際、「現在の市場状況」から始め、「直面している課題」を説明し、「解決策としての新プロジェクト」を提示し、「期待される成果」で締めくくるといった流れです。
効果的なストーリーを作るコツは、相手が共感できる要素を盛り込むこと。「あなたと同じような立場の人がこんな問題に直面しました」というように、相手が自分事として捉えられる内容にすると、説明の効果が高まります。
「なぜ」から始める説明の効果
「なぜ」から説明を始めることで、相手の関心を引き、理解を促進する効果があります。これは「ゴールデンサークル」と呼ばれる考え方で、「なぜ(WHY)→どのように(HOW)→何を(WHAT)」の順で説明するアプローチです。
例えば、新しいシステムの導入を提案する場合、「業務効率を30%向上させるため(なぜ)、AIを活用した自動化システムを(どのように)、来月から導入します(何を)」という順序で説明すると、相手は目的を理解した上で具体的な内容を聞くことができます。
「なぜ」から始めることのメリットは、相手のモチベーションを高められること。人は「何をするか」よりも「なぜするのか」に共感することで行動が促されるからです。特に、チームメンバーに新しい取り組みを説明する際には、目的や意義を最初に伝えることで、前向きな反応を引き出しやすくなります。
視覚的要素を活用した説明法
図解の基本と応用
複雑な情報や抽象的な概念を説明する際、言葉だけでなく図解を活用すると理解度が格段に上がります。人間の脳は視覚情報を言語情報よりも速く処理できるため、適切な図解は説明の強力な武器になります。
基本的な図解のパターンとしては、「フローチャート」(プロセスや手順を示す)、「マトリックス」(2つの軸で情報を整理する)、「ベン図」(共通点と相違点を示す)などがあります。説明する内容に合わせて、最適な図解のパターンを選びましょう。
図解を作る際のポイントは、シンプルさを保つこと。情報を詰め込みすぎると逆に理解を妨げてしまいます。また、色や形、大きさなどの視覚的要素を使い分けて、重要なポイントが目立つようにすることも大切です。
ジェスチャーの効果的な使い方
対面での説明では、ジェスチャーを効果的に使うことで、言葉だけでは伝わりにくいニュアンスや感覚を補うことができます。研究によれば、適切なジェスチャーを交えた説明は、相手の記憶に残りやすく、理解度も高まるとされています。
効果的なジェスチャーの例としては、「大きさや量を表現する手の動き」「方向や位置関係を示す指さし」「順序や段階を表す指の折り曲げ」などがあります。例えば、「市場は3つの段階で成長しました」と説明しながら、指を1本、2本、3本と順に立てていくと、相手は情報を視覚的にも捉えることができます。
ただし、過剰なジェスチャーは逆効果になる可能性があるため、自然な範囲で使うことが大切です。また、文化によってジェスチャーの意味が異なる場合もあるので、国際的な場面では注意が必要です。
視覚資料作成のポイント
プレゼンテーションやミーティングで使用する視覚資料(スライドやハンドアウトなど)は、説明を補強する重要なツールです。効果的な視覚資料を作るためのポイントをいくつか紹介します。
まず、「1枚のスライドに1つのメッセージ」を心がけましょう。情報を詰め込みすぎると、相手は何に注目すべきか分からなくなります。また、文字よりも図やグラフを多用し、視覚的に情報を伝えることを意識しましょう。
色使いも重要です。色の数は3〜4色程度に抑え、一貫性を持たせることで、見やすさと専門性を両立させることができます。特に重要なポイントは、色や大きさ、配置などで目立たせると良いでしょう。
さらに、資料と口頭説明のバランスも考慮しましょう。資料にすべての情報を載せるのではなく、要点だけを示し、詳細は口頭で補足するという使い分けが効果的です。
質問力と傾聴の技術
相手の理解度を確認する質問術
説明の途中や終了後に、相手の理解度を確認する質問を投げかけることは、コミュニケーションを双方向にし、説明の効果を高める重要な技術です。
効果的な確認質問の例としては、「ここまでの説明で不明点はありますか?」「〇〇の部分はいかがでしょうか?」などがあります。ただし、「理解できましたか?」という単純な質問では、相手は「はい」と答えるだけで、本当に理解しているかどうかは分かりません。
より効果的なのは、「今説明した内容を、ご自身の言葉で要約していただけますか?」「この考え方を、あなたの業務にどう活かせそうですか?」といった、相手に考えてもらう質問です。これにより、相手の理解度を正確に把握し、必要に応じて補足説明ができます。
「聞き返し」の効果的な方法
「聞き返し」とは、相手の発言を自分の言葉で言い換えて確認する技術で、相互理解を深める効果があります。例えば、相手が「このプロジェクトは時間がかかりそうです」と言ったら、「つまり、予定よりも納期を延ばす必要があるということですね?」と聞き返します。
聞き返しの効果は、①相手が自分の言いたいことを正確に伝えられたか確認できる、②自分が相手の意図を正しく理解しているか確認できる、③相手に「ちゃんと聞いてもらえている」という安心感を与える、の3点です。
効果的な聞き返しのコツは、単に相手の言葉をオウム返しするのではなく、要点を自分の言葉でまとめること。また、聞き返しの後に「それでよろしいですか?」と確認の質問を添えると、より効果的です。
フィードバックを活かす循環的説明
説明は一方通行ではなく、相手からのフィードバックを取り入れながら改善していく循環的なプロセスであるべきです。フィードバックを活かすことで、説明の質が向上し、相互理解が深まります。
フィードバックを得るためには、相手が意見を言いやすい雰囲気を作ることが大切です。「どう思いますか?」「他に考慮すべき点はありますか?」といった開かれた質問を投げかけ、相手の意見を積極的に求めましょう。
得られたフィードバックは、防衛的にならずに受け止めることが重要です。「なるほど、その視点は考えていませんでした」「ご指摘ありがとうございます、確かにその点は改善の余地がありますね」といった姿勢で対応すると、建設的な対話が生まれます。
また、フィードバックを基に説明を修正し、「先ほどのご指摘を踏まえて、改めて説明します」と伝えることで、相手は自分の意見が尊重されていると感じ、より前向きに話を聞いてくれるようになります。
説明が苦手な人の特徴と改善法
よくある説明の失敗パターン
説明が苦手な人によく見られる失敗パターンを理解することで、自分の弱点を把握し、改善につなげることができます。本書では、以下のような失敗パターンが紹介されています。
一つ目は「情報の羅列」です。関連性や優先順位を示さずに情報を並べるだけの説明は、相手に「で、結局何が言いたいの?」と思わせてしまいます。これを避けるには、情報を整理し、重要なポイントを強調する習慣をつけましょう。
二つ目は「専門用語の多用」です。自分にとって当たり前の用語でも、相手にとっては難解な場合があります。専門用語を使う場合は、簡単な言葉で言い換えるか、補足説明を加えることが大切です。
三つ目は「抽象的な表現」です。「良い」「悪い」「改善する」といった曖昧な表現では、具体的なイメージが伝わりません。数字や具体例を用いて、明確に伝えることを心がけましょう。
説明下手を克服するための練習法
説明力は練習によって確実に向上します。本書では、効果的な練習方法として以下のようなものが紹介されています。
まず「録音・録画して客観視する」方法です。自分の説明を録音・録画し、後で見返すことで、話し方のクセや改善点を発見できます。特に、言葉の選び方、話すスピード、声の大きさなどに注目してみましょう。
次に「簡潔な説明を繰り返し練習する」方法です。例えば、複雑なトピックを30秒以内で説明する練習をすると、要点を絞る力が鍛えられます。最初は難しくても、繰り返すうちに上達します。
また「フィードバックを求める」ことも重要です。信頼できる同僚や友人に説明を聞いてもらい、分かりにくかった点や改善点を指摘してもらいましょう。第三者の視点は、自分では気づかない問題を発見する助けになります。
即興で説明する力の鍛え方
予期せぬ質問や突然のプレゼンなど、準備なしで説明しなければならない場面は少なくありません。即興で説明する力を鍛えるための方法をいくつか紹介します。
一つ目は「PREP法」の習得です。PREP法とは、Point(結論)→Reason(理由)→Example(例)→Point(結論の再確認)という流れで説明する方法で、この型を身につけておくと、どんなトピックでも筋道立てて説明できるようになります。
二つ目は「日常的な思考整理」です。日々の出来事や読んだ記事について「これを誰かに説明するなら、どう伝えるか」と考える習慣をつけると、情報を整理する力が自然と身につきます。
三つ目は「イメージトレーニング」です。様々なシチュエーションを想定し、「こんな質問が来たらどう答えるか」をあらかじめ考えておくことで、実際の場面でも冷静に対応できるようになります。
即興力を鍛える上で大切なのは、完璧を目指さないこと。多少のつまずきや言い直しがあっても、誠実に伝えようとする姿勢があれば、相手は理解しようとしてくれるものです。
オンラインでの説明スキル
リモートコミュニケーションの特性
コロナ禍以降、オンラインでのコミュニケーションが一般化し、リモート環境での説明スキルの重要性が高まっています。対面とオンラインでは、コミュニケーションの特性が異なるため、それぞれに適した説明方法を身につける必要があります。
オンラインコミュニケーションの特性として、①非言語情報(表情、ジェスチャーなど)が伝わりにくい、②相手の反応がつかみにくい、③集中力が続きにくい、④技術的な問題(通信障害など)が発生する可能性がある、などが挙げられます。
これらの特性を踏まえ、オンラインでの説明では、より明確で簡潔な言葉遣いを心がけ、定期的に相手の理解度を確認する質問を挟むことが重要です。また、表情や声のトーンを普段より少し大げさにすることで、感情や意図が伝わりやすくなります。
画面共有を活用した説明テクニック
オンライン会議の大きな利点は、画面共有機能を使って視覚資料を共有できることです。この機能を効果的に活用するためのテクニックをいくつか紹介します。
まず、共有する資料は対面よりもシンプルに作ることが大切です。画面越しでは細かい情報が見えにくいため、フォントサイズを大きくし、1枚のスライドに含める情報量を減らしましょう。
次に、ポインターやハイライト機能を活用して、今話している箇所を明示することが効果的です。「ここをご覧ください」と言うだけでは、相手がどこを見ればいいのか分からない場合があります。
また、画面共有と自分の映像を併用することで、人間味のあるコミュニケーションを維持できます。資料だけを見せていると、相手は話し手の表情や反応を見ることができず、一方通行の説明になりがちです。
オンライン特有の注意点
オンラインでの説明には、対面とは異なる注意点があります。これらを意識することで、より効果的なコミュニケーションが可能になります。
まず、説明の時間を短めに区切ることが重要です。オンラインでは集中力が続きにくいため、15〜20分ごとに質疑応答や意見交換の時間を設けると良いでしょう。
次に、参加者全員が発言する機会を作ることも大切です。「チャット機能を使って質問や意見を書き込んでください」「順番に一言ずついただけますか」など、積極的に参加を促すことで、一方通行のコミュニケーションを避けられます。
さらに、オンラインでは「沈黙」が対面よりも不自然に感じられるという特徴があります。質問を投げかけた後、すぐに回答がない場合、「聞こえていますか?」と確認したくなりますが、相手が考えている時間を尊重することも大切です。「今の質問について少し考える時間を取りましょう」と前置きすると、沈黙が気まずくなりません。
最後に、技術的なトラブルへの備えも重要です。画面共有がうまくいかない、音声が途切れるなどのトラブルは日常茶飯事。説明の要点をチャットに書き込んでおく、資料を事前に送付しておくなどの「プランB」を用意しておくと安心です。オンラインならではの制約を理解し、それを補う工夫をすることで、対面に劣らない効果的な説明が可能になります。
感想・レビュー
『「説明が上手い人」がやっていることを1冊にまとめてみた』を読んで、まず驚いたのは、説明上手になるためのテクニックがこれほど体系的にまとめられていることです。私たちは日々、様々な場面で説明をしていますが、その方法論を意識的に学ぶ機会はあまりありません。本書は、その盲点を突いた一冊だと感じました。
特に印象的だったのは、「説明下手な人」の特徴が具体的に示されていること。自分が無意識にやってしまっている「専門用語の多用」や「情報の羅列」などの問題点に気づかされました。鏡に映った自分の姿を見るような、少し恥ずかしくも貴重な体験でした。
ぺそさんの文体は、本書の内容そのものが「わかりやすい説明」の見本になっています。抽象的な概念を具体例で補強し、専門用語を使わず、読者の理解度に合わせた説明を心がけている様子が伝わってきます。YouTubeでの発信経験が活きているのでしょう。
また、本書の魅力は「すぐに使える」実践的なテクニックが満載なこと。例えば「PREP法」や「たとえ話は半径3メートル以内で」といった具体的なテクニックは、明日から使えるものばかりです。理論よりも実践を重視する著者の姿勢が、ビジネスパーソンの琴線に触れるのでしょう。
一方で、本書を読んで感じたのは、説明力は「テクニック」だけでは完成しないということ。根底には「相手を理解したい」「自分の考えを伝えたい」という誠実な姿勢が不可欠です。テクニックはあくまでその姿勢を効果的に表現するための道具に過ぎません。
それでも、コミュニケーションに悩む現代人にとって、本書は心強い味方になるでしょう。説明が上手くなれば、仕事の効率が上がるだけでなく、人間関係も円滑になり、自分の考えが世界に広がっていく可能性が開けます。そんな可能性を秘めた一冊だと思います。
まとめ
この本は、説明上手になるための具体的なテクニックを30個も紹介した実用書。
相手の理解度に合わせた説明、構造化された情報の伝え方、具体例の効果的な使い方など、すぐに実践できるノウハウが満載。
ハック大学ぺそさんの実体験に基づいた説明術は、ビジネスシーンだけでなく日常会話にも役立つでしょう。
説明下手を自覚している人はもちろん、さらに説明力を磨きたい人にもおすすめの一冊です。