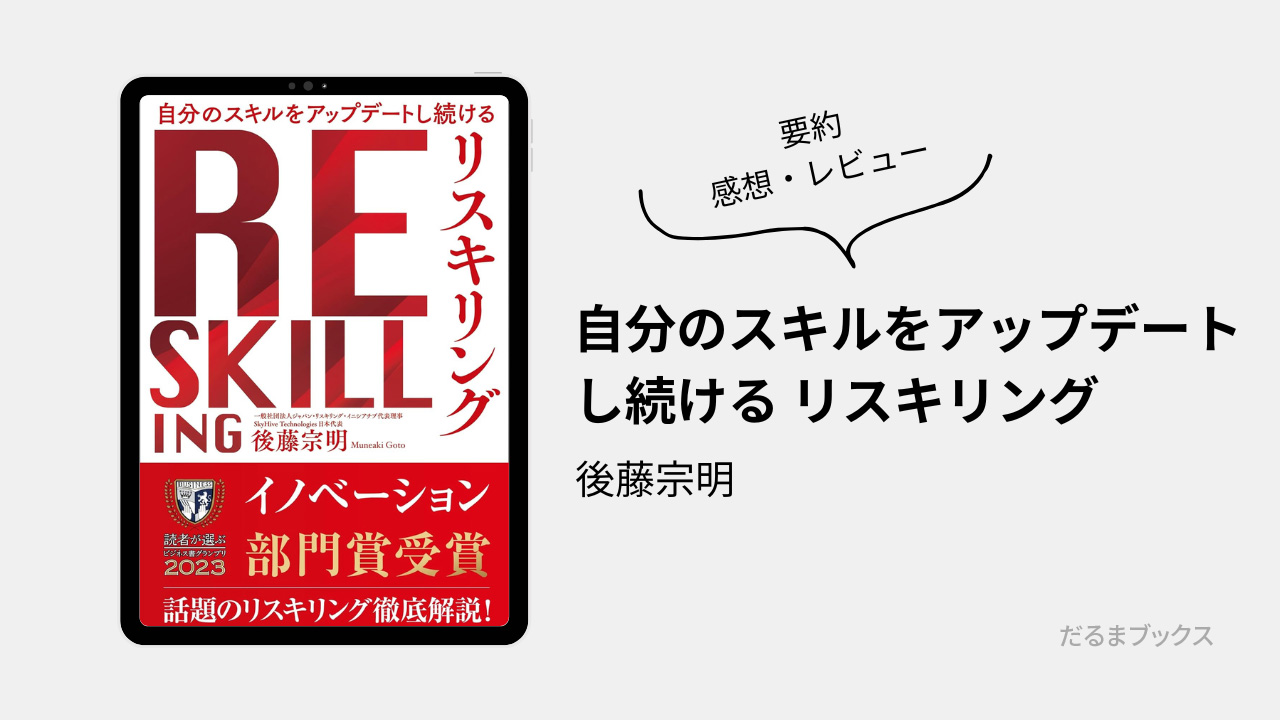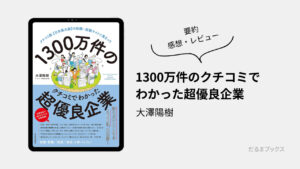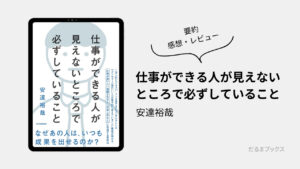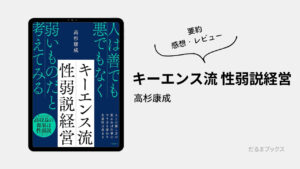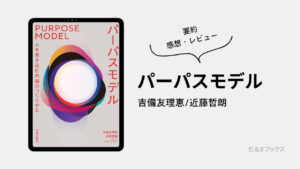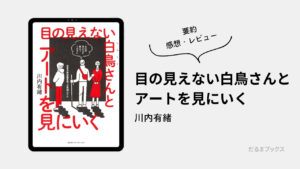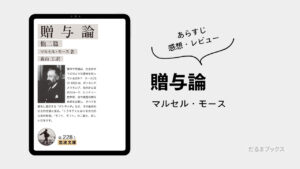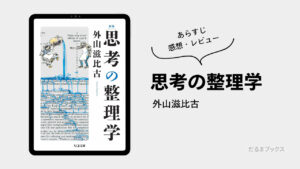「リスキリング」という言葉を最近よく耳にするようになりました。
新しいスキルを身につけて、新たな仕事や職業に就くこと。でも、具体的にどうすればいいのか、なぜ今それが必要なのか、よくわからないという方も多いのではないでしょうか。
後藤宗明さんの『自分のスキルをアップデートし続ける リスキリング』は、リスキリングの第一人者が、その概念から実践方法まで丁寧に解説した一冊です。
技術革新が加速する現代社会で、自分自身のキャリアを主体的に形作るための具体的な方法論が詰まっています。
リスキリングとは何か
リスキリングという言葉を聞いたことはあっても、その本当の意味を理解している人は意外と少ないかもしれません。後藤さんはこの本の中で、リスキリングを「新しいことを学び、新しいスキルを身につけ実践し、そして新しい業務や職業に就くこと」と定義しています。
単なる「学び直し」ではない
リスキリングは単なる「学び直し」とは異なります。日本では「リスキリング=学び直し」という訳が当てられていることが多いですが、これは少し誤解を招く表現です。リスキリングの本質は、学んだことを実際の業務や新しい職業に活かすところまでを含んでいます。
一方、リカレント教育は「学び直し」そのものが目的で、必ずしも職業と関係ない学びも含みます。リスキリングは新しい職業に就くことを目的としているため、職業に直結するスキル習得を指しているのです。この違いを理解することが、リスキリングの本質を捉える第一歩となります。
また、リスキリングと似た言葉に「アップスキリング」と「アウトスキリング」があります。アップスキリングは現在の職務に関連するスキルを向上させることを指し、アウトスキリングは従業員が会社を離れる際に新しい職場で必要となるスキルを身につけることを支援するプロセスを指します。これらの違いを理解することで、自分に必要なスキル開発の方向性が見えてくるでしょう。
世界と日本におけるリスキリングの現状
世界的には、2020年のダボス会議(世界経済フォーラムの年次総会)で「リスキリング革命(Reskilling Revolution)」が発表されたことが、リスキリングが注目を集めるきっかけとなりました。諸外国では、リスキリングを「全く異なる業務を行うために必要な新しいスキルを獲得するプロセス」と定義しています。
日本では、長らく終身雇用や年功序列が一般的で、キャリアチェンジの文化が根付いていませんでした。しかし、世界的なリスキリングの流れに加え、国内でもデジタル変革(DX)が進み、個人にも「学び直し」が求められるようになってきています。特に近年はDXに関するリスキリングの重要性が注目されており、国や企業でもリスキリングの取り組みが始まっています。
日本におけるリスキリングの課題としては、企業文化や雇用システムの違いから、欧米のようにスムーズに進まない面があります。しかし、少子高齢化による労働力不足や、技術革新による職業構造の変化に対応するためには、リスキリングは避けて通れない道となっています。
なぜ今リスキリングが必要なのか
リスキリングがこれほど注目されている背景には、いくつかの社会的・経済的要因があります。
技術的失業という社会問題
デジタルテクノロジーの急激な進歩とオートメーション化の加速により、人の仕事の多くがAIやロボットに代替される「技術的失業(Technological Unemployment)」の問題が浮上しています。世界経済フォーラムによれば、2025年までに8500万件の仕事が消失し、新たに9700万件の仕事が生まれると予測されています。
しかし、消失する仕事と新たに生まれる仕事の間には、必要とされるスキルに大きなギャップがあります。このスキルギャップを埋める手段として、リスキリングが重要視されているのです。技術的失業で仕事を失う前に、成長産業で必要なスキルを身につけることが、個人にとっても社会にとっても重要な課題となっています。
スキルのミスマッチと人材不足
日本では、特定の分野での人材不足と、別の分野での過剰が同時に起きている「スキルのミスマッチ」が深刻な問題となっています。例えば、IT人材の不足が叫ばれる一方で、従来型の事務職などでは人材過剰の状態が続いています。
このミスマッチを解消するためには、過剰分野から不足分野へと人材を移動させる必要がありますが、そのためには新しいスキルの習得が不可欠です。リスキリングは、このスキルのミスマッチを解消し、労働市場全体の効率を高める役割を担っているのです。
リスキリングの実践方法
リスキリングの必要性を理解したところで、次は具体的にどのように実践すればよいのかを見ていきましょう。
自己分析から始める6つのステップ
リスキリングを始めるにあたって、まずは自己分析が重要です。後藤さんは、以下の6つの要素を確認することを推奨しています。
まず、自分の強みと弱みを客観的に分析しましょう。得意なことや苦手なことを正直に見つめ直すことが大切です。次に、自分の好きなことと嫌いなことを明確にします。長期的にスキルを磨き続けるためには、ある程度の興味や関心が必要だからです。
また、これまでのキャリアを振り返り、どのような経験や知識を蓄積してきたかを整理します。さらに、現在持っているスキルを棚卸しし、それらがどの程度市場価値を持っているかを評価します。
組織における自分に対する評価も重要な視点です。他者からの評価と自己評価のギャップを認識することで、より客観的な自己像を描くことができます。最後に、自分の価値観や人生観を明確にし、リスキリングの方向性と一致しているかを確認しましょう。
これらの自己分析を通じて、自分にとって最適なリスキリングの方向性が見えてくるはずです。
様々な立場に応じたリスキリング戦略
リスキリングの具体的な方法は、個人の置かれた状況によって異なります。後藤さんは、大企業の社員、中小企業の社員、個人事業主・フリーランス、産休・育休からの復帰者など、様々な立場に応じたリスキリング戦略を提案しています。
大企業の社員の場合、社内研修やスキルアッププログラムを積極的に活用することが有効です。多くの大企業では、従業員のリスキリングを支援するための制度が整備されています。これらの制度を最大限に活用し、会社のサポートを受けながらスキルアップを図りましょう。
一方、中小企業の社員の場合、社内にリスキリングのための制度が整っていないことも多いでしょう。そのような場合は、自己投資としてオンライン講座や外部研修を活用することが重要です。また、業界団体や地域の支援機関が提供するプログラムを利用するのも一つの方法です。
個人事業主やフリーランスの場合は、市場のニーズを敏感に察知し、需要のあるスキルを戦略的に身につけていくことが求められます。時間と資金の制約がある中で効率的にスキルを習得するために、オンライン学習プラットフォームやコミュニティを活用するのが良いでしょう。
産休・育休からの復帰を控えた方には、復帰前の準備期間を利用して、最新のトレンドやツールについて学ぶことをおすすめします。特にデジタル技術の進化は早いため、離職期間中に大きな変化があった可能性があります。
リスキリングを実践する10のプロセス
リスキリングを効果的に進めるためには、体系的なアプローチが必要です。後藤さんは、リスキリングを10のプロセスに分けて説明しています。
現状評価からマインドセットづくり
リスキリングの第一歩は、現状評価から始まります。自分のスキルや市場価値を冷静に分析し、リスキリングの必要性と方向性を明確にしましょう。この段階では、前述した6つの自己分析のステップが役立ちます。
次に重要なのが、マインドセットづくりです。リスキリングは単なるスキル習得ではなく、自分自身の変化と成長を受け入れるプロセスでもあります。変化を恐れず、新しい挑戦に前向きに取り組む姿勢が求められます。
特に重要なのが「アンラーニング(学習棄却)」の考え方です。これは、既存の知識や習慣に固執せず、新しい考え方や方法を受け入れる柔軟性を指します。現状を変えたくないという執着や、過剰なプライドやノスタルジーから距離を置き、新しい学びに向けて心の準備をすることが大切です。
また、デジタルリテラシーの向上も基本的なステップとして挙げられています。デジタル分野の専門用語に慣れ、デジタル技術を使って何ができるのかを理解し、自分の強みとデジタルを掛け合わせたアイデアを具体的に考えることが重要です。
キャリアプランニングと新しい仕事の選択
リスキリングの方向性が定まったら、次はキャリアプランニングの段階に進みます。ストラテジックパートナーシップマネージャー、カスタマーサクセスなど、新しく登場した職業について理解を深め、自分がどのような新しい仕事に就けるのか、具体的なキャリアパスを描きましょう。
情報収集の仕組みづくりも重要です。業界のトレンドや最新技術に関する情報を継続的に収集するための習慣や環境を整えることで、常に最新の知識を取り入れることができます。
学習を開始したら、デジタルツールを積極的に活用しましょう。オンライン学習プラットフォームやアプリを使うことで、時間や場所の制約を受けずに効率的に学ぶことができます。
学んだことをアウトプットする機会も大切です。ブログやSNSでの発信、勉強会での発表など、学んだ内容を外部に発信することで理解が深まり、同時に自分の市場価値をアピールすることにもつながります。
学習履歴とスキル証明を蓄積し、最終的には新しいキャリアや仕事の選択へとつなげていきます。この段階では、獲得したスキルを活かせる具体的な職場や職種を選び、実際に応募や転職活動を行います。
スキルベース採用の時代の到来
リスキリングと密接に関連するのが、「スキルベース採用」の広がりです。従来の学歴や職歴中心の採用から、個人が持つスキルを重視する採用へと変化しています。
海外企業の動向
海外、特に欧米の企業では、すでにスキルベース採用が主流となりつつあります。例えば、IBMやGoogleなどの大手テック企業では、学歴よりも実際のスキルや能力を重視する採用方針を打ち出しています。
このような企業では、AIを活用した採用プロセスを導入し、応募者のスキルを客観的に評価する仕組みを構築しています。また、オンラインでのスキル証明や、実際のプロジェクトを通じた能力評価など、多様な選考方法を取り入れています。
日本企業も徐々にこの流れに追随し始めており、特にIT業界やスタートアップ企業を中心に、スキルベース採用の導入が進んでいます。
類似スキルと隣接スキルの重要性
スキルベース採用の時代においては、「類似スキル」と「隣接スキル」の概念が重要になります。類似スキルとは、異なる職種や業界でも共通して活用できるスキルのことです。例えば、データ分析のスキルは、マーケティング、財務、人事など様々な分野で応用が可能です。
隣接スキルとは、現在持っているスキルから比較的習得しやすい関連スキルを指します。例えば、Excelに習熟している人であれば、データベース管理やBIツールの操作などの隣接スキルを比較的短期間で習得できる可能性があります。
リスキリングを効果的に進めるためには、自分の持つスキルの類似性や隣接性を理解し、それを活かした学習計画を立てることが重要です。全く未知の分野に挑戦するよりも、現在のスキルと関連性のある分野から始めることで、学習の効率と成功率を高めることができます。
リスキリングとキャリアアップの関係
リスキリングは単なるスキル習得にとどまらず、キャリアアップや収入増加にもつながる可能性があります。
人材としての市場価値を高める方法
リスキリングを通じて新しいスキルを身につけることは、自分の人材としての市場価値を高めることにつながります。特に、需要の高い分野のスキルを習得することで、転職市場での競争力が大幅に向上します。
市場価値を高めるためには、単にスキルを習得するだけでなく、そのスキルを実際のプロジェクトや業務で活用した実績を作ることも重要です。また、獲得したスキルを可視化するために、資格取得やポートフォリオの作成、SNSでの発信なども効果的です。
さらに、業界のコミュニティやネットワークに積極的に参加することで、自分のスキルや実績を多くの人に知ってもらう機会を増やすことができます。人材としての市場価値は、スキルそのものだけでなく、そのスキルを知る人の数にも比例するからです。
リスキリングがもたらす昇給・昇格
リスキリングは、現在の職場での昇給や昇格にもつながる可能性があります。特に、企業がデジタル変革を進める中で、デジタルスキルを持つ人材の価値は高まっています。
社内でリスキリングを行い、新しいスキルを業務に活かすことで、上司や経営層からの評価が向上し、昇進や昇給のチャンスが広がるでしょう。また、新規プロジェクトやイニシアチブのリーダーに抜擢される可能性も高まります。
さらに、リスキリングによって獲得したスキルが社内で希少価値を持つ場合、給与交渉の際の強力な武器となります。自分のスキルが会社にどれだけの価値をもたらすかを具体的に示すことで、適正な評価と報酬を得やすくなるのです。
AIと人間の協働時代に向けて
最後に、AIやロボットが同僚となる新たな時代に向けて、リスキリングがどのような役割を果たすのかを考えてみましょう。
日本におけるリスキリングの浸透
日本では、欧米諸国に比べてリスキリングの取り組みが遅れていると言われています。世界デジタル競争力ランキングでは、日本は毎年ランクを落とし続け、2021年度の「人材の知識レベル」指標では全世界で47位という結果でした。デジタル後進国であることは明らかです。
さらに、PwCの調査によれば、職場に導入される新たなテクノロジーの活用への順応に「とても自信がある」と回答した日本人はわずか5%でした。これはインドの68%と比較すると大きな開きがあります。
しかし、2023年10月には岸田首相が「5年で1兆円をリスキリングに投じる」と所信表明演説で述べるなど、国レベルでもリスキリングの重要性が認識され始めています。今後は企業や個人レベルでも、リスキリングの取り組みが加速していくことが期待されます。
日本でリスキリングを浸透させるためには、企業文化や雇用システムの変革も必要です。終身雇用や年功序列といった従来の日本型雇用システムから、スキルや成果に基づく評価・報酬システムへの移行が求められています。また、企業主導のリスキリングと個人の自発的な学びのバランスをどのように取るかも重要な課題です。
グリーン・リスキリングの必要性
AIやデジタル技術に関するリスキリングだけでなく、「グリーン・リスキリング」と呼ばれる環境関連のリスキリングも今後重要性を増していくでしょう。気候変動対策や持続可能な開発目標(SDGs)の達成に向けて、環境配慮型の産業や職業が拡大しています。
例えば、再生可能エネルギー、サーキュラーエコノミー(循環型経済)、カーボンニュートラルなどの分野では、新たな専門知識やスキルを持つ人材が求められています。従来型の産業から環境配慮型の産業へと移行するためには、グリーン・リスキリングが不可欠です。
また、AIと環境技術の融合も進んでおり、例えばAIを活用した省エネルギーシステムや、環境データの分析・予測など、デジタルスキルと環境知識の両方を持つ人材の需要が高まっています。
将来的には、AIやロボットが人間の仕事の一部を代替する一方で、人間はより創造的で複雑な判断を要する仕事に集中するようになるでしょう。そのような時代において、リスキリングは単なる職業訓練ではなく、人間らしい能力を高め、AIと協働するための基盤となります。
感想・レビュー
個人の成長と社会変化をつなぐ視点
後藤宗明さんの『自分のスキルをアップデートし続ける リスキリング』を読んで最も印象に残ったのは、個人の成長と社会変化を有機的につなぐ視点です。リスキリングは単なるスキルアップではなく、社会全体の構造変化に対応するための戦略であるという考え方が、本書全体を通して一貫しています。
私自身、技術の進化によって仕事の形が急速に変わっていく現状を目の当たりにしてきました。特にChatGPTなどの生成AIの登場は、これまで人間にしかできないと思われていた仕事さえも変えつつあります。そんな中で、後藤さんが提示する「リスキリングを実践する10のプロセス」は、漠然とした不安を具体的な行動に変えるための道しるべとなりました。
また、本書では日本と海外の比較が随所に盛り込まれており、グローバルな視点でリスキリングを捉えることができます。日本がデジタル競争力ランキングで低迷している現状は厳しい事実ですが、だからこそ個人レベルでのリスキリングの重要性が高まっているのだと感じました。
実践的なアドバイスの価値
本書の最大の魅力は、抽象的な概念の説明にとどまらず、具体的で実践的なアドバイスが豊富に盛り込まれている点です。特に「自己分析から始める6つのステップ」は、自分自身の強みや弱み、好きなことや嫌いなことを客観的に分析する重要性を改めて認識させてくれました。
リスキリングを始める前に、まず自分自身を深く理解することが大切だという指摘は、とても納得できます。ともすれば「今流行りのスキルを身につけよう」と表面的に考えがちですが、自分の価値観や適性と合わないスキルを無理に習得しても長続きしないでしょう。
また、「アンラーニング(学習棄却)」の概念も非常に興味深いものでした。既存の知識や習慣に固執せず、新しい考え方や方法を受け入れる柔軟性が、リスキリングの成功には不可欠です。これは単にスキルの問題ではなく、マインドセットの問題であり、本書を通じて自分自身の思考の硬直性に気づかされました。
後藤さんが43歳で初めての転職活動で100社以上に落とされた経験から、リスキリングの重要性を説くに至ったというエピソードも心に響きました。実体験に基づいた言葉には説得力があります。
まとめ
『自分のスキルをアップデートし続ける リスキリング』は、変化の激しい現代社会を生き抜くための実践的なガイドブックです。リスキリングの概念から実践方法まで、体系的に解説されており、これからのキャリアに不安を感じている人にとって、大きな指針となるでしょう。
特に、リスキリングを10のプロセスに分けて説明している点や、様々な立場に応じたリスキリング戦略を提案している点は、読者が自分自身の状況に合わせて具体的な行動を起こすのに役立ちます。
技術革新が加速し、AIやロボットが同僚となる時代において、最も重要なスキルは「自分自身をリスキリングするスキル」だという著者の主張は、まさに核心を突いています。この本を読んで、リスキリングは一度きりのイベントではなく、生涯を通じて継続するプロセスであることを実感しました。