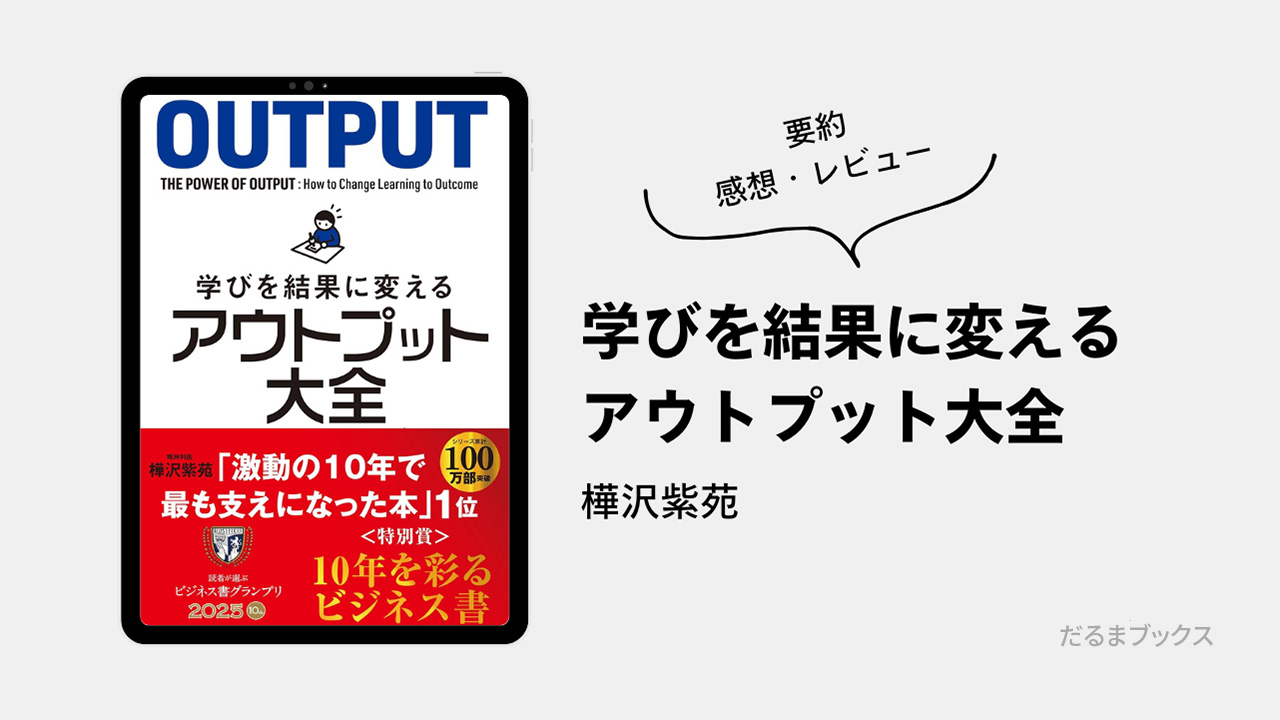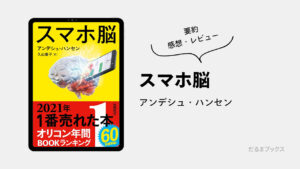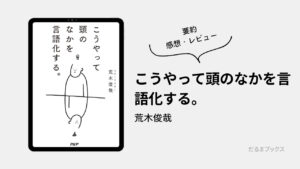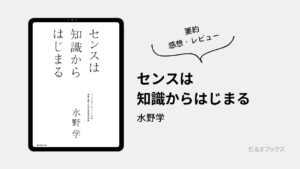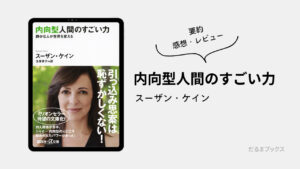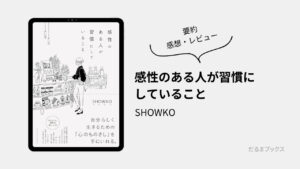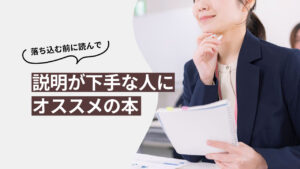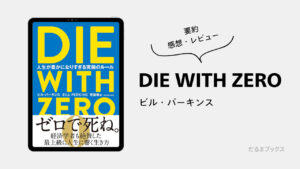知識を得ても行動に移せなければ意味がない
この当たり前の事実を科学的に解明し、具体的な方法論として示した樺沢紫苑さんの「学びを結果に変えるアウトプット大全」。
この本は、発売から数年経った今でも多くの読者に支持され続け、累計80万部を超えるベストセラーとなっています。
インプットした知識をいかに効果的にアウトプットし、実際の成果に結びつけるか。その具体的な方法と科学的根拠を詳しく解説します。
本書の概要
著者プロフィール
樺沢紫苑さんは精神科医であり作家としても活躍する「日本一アウトプットする精神科医」として知られています。メルマガを13年間毎日発行し、Facebookを8年間毎日更新、YouTubeも5年以上毎日更新して1500本以上の動画を投稿しています。さらに11年間毎日3時間以上の執筆を続け、10年間で年に2〜3冊のペースで書籍を出版し、9年間毎月2回以上の新作セミナーを開催するなど、まさにアウトプットの鬼とも言える実績の持ち主です。
「情報発信を通してメンタル患者、自殺を予防する」というビジョンを掲げ、精神医学や心理学、脳科学の知識をわかりやすく伝える活動を続けています。YouTubeチャンネル「精神科医・樺沢紫苑の樺チャンネル」では、3〜5分のコンパクトな動画で脳科学やメンタルヘルスについての知識を発信し、多くの視聴者から支持を得ています。
本書の特徴
「学びを結果に変えるアウトプット大全」は2018年8月にサンクチュアリ・パブリッシングから出版され、発売後すぐに日本出版販売のビジネス書売り上げランキングで1位を獲得しました。2018年には有隣堂の年間ビジネス書売り上げランキングで8位、2019年にはITエンジニア本大賞2019のビジネス書部門ベスト10に選ばれるなど、多くの賞を受賞しています。
本書の最大の特徴は、全80個以上のアウトプット術が体系的にまとめられていることです。文章は横書きで図解も多く使われており、読書が苦手な方でも読みやすい構成になっています。また、どこから読んでも理解できるよう工夫されているため、忙しい現代人でも自分の興味のある部分から読み進めることができます。
脳科学や心理学の知見に基づいた説明が多く、単なる「こうすべき」という主観的なアドバイスではなく、科学的な根拠に基づいた方法論が提示されているのも本書の魅力です。
インプットとアウトプットの黄金比率
本書の核となる考え方は「インプットとアウトプットの黄金比率」です。樺沢さんによれば、約9割のビジネスパーソンはインプット中心の学び方や働き方をしているといいます。しかし、知識を詰め込むインプットの学びだけでは現実は変わりません。
では、インプットとアウトプットの理想的な比率はどれくらいなのでしょうか。樺沢さんは「インプット3:アウトプット7」という黄金比率を提唱しています。初心者の場合は「インプット4:アウトプット6」が良いとしています。
多くの人は「月に10冊の本を読む人と3冊の本を読む人では、どちらが成長するか」と問われれば、10冊読む人と答えるでしょう。しかし、樺沢さんによれば答えは「変わらない」とのこと。なぜなら、3冊読んでしっかりアウトプットした方が、10冊読んでもアウトプットしない場合より記憶として定着するからです。
アウトプットの頻度としては、「2週間の内に3回以上」が効果的だと述べています。これにより、学んだ内容が長期記憶として定着しやすくなります。
アウトプットの基本法則
アウトプットの定義
そもそもアウトプットとは何でしょうか。本書ではアウトプットを「話す」「書く」「行動する」の3つに大別しています。
「話す」アウトプットには、感想を話す、説明する、プレゼンテーションする、議論するなどが含まれます。「書く」アウトプットには、メモを取る、日記を書く、SNSに投稿する、ブログを書くなどがあります。「行動する」アウトプットには、学んだことを実践する、習慣化する、教えるなどが挙げられています。
重要なのは、単に情報を受け取るだけでなく、自分の言葉や行動として外に出すことです。例えば、本を読んだだけでは完全なインプットにすぎません。その内容を誰かに話したり、感想を書いたり、実践したりして初めてアウトプットとなります。
記憶の定着とアウトプットの関係
アウトプットが重要な理由の一つは、記憶の定着に大きく関わるからです。アメリカの国立訓練研究所が提唱する「ラーニングピラミッド」によると、学習方法によって記憶の定着率が大きく異なります。
講義を聞くだけの場合の記憶定着率は約5%、読書は約10%、視聴覚教材は約20%、実験機材を使った学習は約30%、グループ討論は約50%、体験を通した学習は約75%、そして他人に教えた経験は約90%とされています。
つまり、最も効果的な学習方法は「教える」というアウトプットなのです。これは、教えるためには内容をしっかり理解する必要があり、また説明する過程で自分の理解度や不十分な点が明確になるためです。
また、本書では「運動性記憶」という概念も紹介されています。話す・書くといった行動を伴った記憶は忘れにくく、逆に読むだけの記憶は忘れやすいとされています。
自己成長の螺旋階段
樺沢さんは自己成長のプロセスを「螺旋階段」に例えています。この螺旋階段は「インプット」「アウトプット」「フィードバック」の3つのステップで構成されています。
まず「インプット」で知識や情報を取り入れ、次に「アウトプット」でそれを外に出します。そして「フィードバック」で自分のアウトプットの質を評価し、改善点を見つけます。このサイクルを繰り返すことで、螺旋階段を上るように少しずつ高いレベルへと成長していくのです。
特に「教える」というアウトプットは、この3つのステップをすべて含んだ「三位一体、完全、最強のアウトプット術」だと樺沢さんは述べています。教えるためには事前にしっかりとインプットし、実際に教えることでアウトプットし、相手の反応や質問からフィードバックを得ることができるからです。
効果的なアウトプット方法
「話す」アウトプット
「話す」アウトプットの基本は「感想を話す」ことから始めるのが良いでしょう。本を読んだ感想、映画を観た感想、テレビ番組を見た感想など、何から始めても構いません。
ここで重要なのは、単に「〇〇へ行ってきた」というだけではなく、「自分の意見」や「自分の気づき」を少なくとも1つは盛り込むことです。これにより、ただの情報共有ではなく、自分の思考を整理するアウトプットになります。
また、話す内容には努めてポジティブな言葉を含めるよう心がけましょう。ノースカロライナ大学の研究によると、職場内の会話でポジティブな内容とネガティブな内容の比率が3:1以上だと、高い利益を上げ、チームメンバーの評価も高くなるそうです。逆に3:1を下回ると離職率が高くなるという結果が出ています。
「悪口はネガティブ人生の始まり」とも樺沢さんは警告しています。悪口を言うとストレスホルモンが増え、人間関係が悪化し、悪いところばかり探す習慣がついてしまうというデメリットがあります。まさに「百害あって一利なし」なのです。
「書く」アウトプット
「書く」アウトプットの最大の利点は「圧倒的に記憶に残り自己成長を促す」ことです。特に手書きで書くことは、キーボード入力よりも長く記憶に残り、新しいアイデアにつながりやすいと樺沢さんは推奨しています。
書くアウトプットの具体的な方法としては、日記を書く、健康について記録する、読書感想を書く、情報発信する、SNSに書く、ブログを書くなどが挙げられています。
特に日記を書くことには多くのメリットがあります。アウトプット力が向上するだけでなく、自己洞察力や内省能力、ストレス耐性が高まり、「楽しい」を発見する能力も向上します。さらにストレス発散になり、幸福度もアップするとされています。
読書感想を書くことも効果的なアウトプット方法です。本の内容が圧倒的に記憶として定着し、より深く理解することができます。また、本の内容が整理され、文章力や思考力がアップし、自己洞察が進むというメリットもあります。
樺沢さんは読書感想のテンプレートとして、「ビフォー(この本を読む前)」「アフター 気づき(この本を読んで気づいたこと)」「アフター ToDo(今後実行してみること)」という3つの項目を提案しています。
「行動する」アウトプット
「行動する」アウトプットは、学んだことを実際に実践することです。知識を得ただけでは意味がなく、それを行動に移してこそ価値があります。
例えば、ビジネス書で学んだ時間管理の方法を実際に試してみる、語学書で学んだフレーズを実際の会話で使ってみる、料理本で見た料理を実際に作ってみるなどが「行動する」アウトプットに当たります。
行動するアウトプットのポイントは、失敗を恐れないことです。最初から完璧にできることはありません。むしろ、失敗から学ぶことで成長できるのです。樺沢さんは「失敗は成功の母」という言葉を引用し、失敗を恐れずに行動することの重要性を説いています。
最強のアウトプット法「教える」
樺沢さんは、本書で紹介されているアウトプット法の中で最も自己成長につながるのは「教える」ことだと断言しています。
ロンドン大学の暗記に関する研究では、「あとでテストをする」と言われたグループよりも「あとで他の人に教える」と言われたグループの方が、課題の暗記度合いが高かったという結果が出ています。これは、教えるためにはしっかりと理解する必要があり、また教える過程で自分の理解度や不十分な点が明確になるためです。
教える機会を得るためには、外部の勉強会に参加したり、社内で勉強会を開催したり、後輩に知識を伝えたりする方法があります。もし「〇〇について話してくれないか?」と講師役を頼まれたら、臆することなく引き受けることが成長につながります。
また、ブログやSNSで情報発信することも、広い意味では「教える」アウトプットに含まれます。自分の知識や経験を発信することで、多くの人に価値を提供すると同時に、自分自身も成長することができるのです。
アウトプットを習慣化するコツ
2週間で3回のルール
アウトプットを効果的に行うためには、頻度が重要です。樺沢さんは「2週間で3回以上アウトプットする」ことを推奨しています。これにより、学んだ内容が長期記憶として定着しやすくなります。
例えば、本を読んだら、その日のうちに感想を書き、翌日に友人に内容を話し、1週間後にブログで要約を公開するといった具合に、異なる形式でアウトプットを繰り返すことが効果的です。
このルールを守ることで、「忘却曲線」と呼ばれる記憶の減衰を防ぐことができます。人間は新しい情報を学んでから24時間後には約70%を忘れてしまうと言われていますが、適切なタイミングでアウトプットすることで記憶を定着させることができるのです。