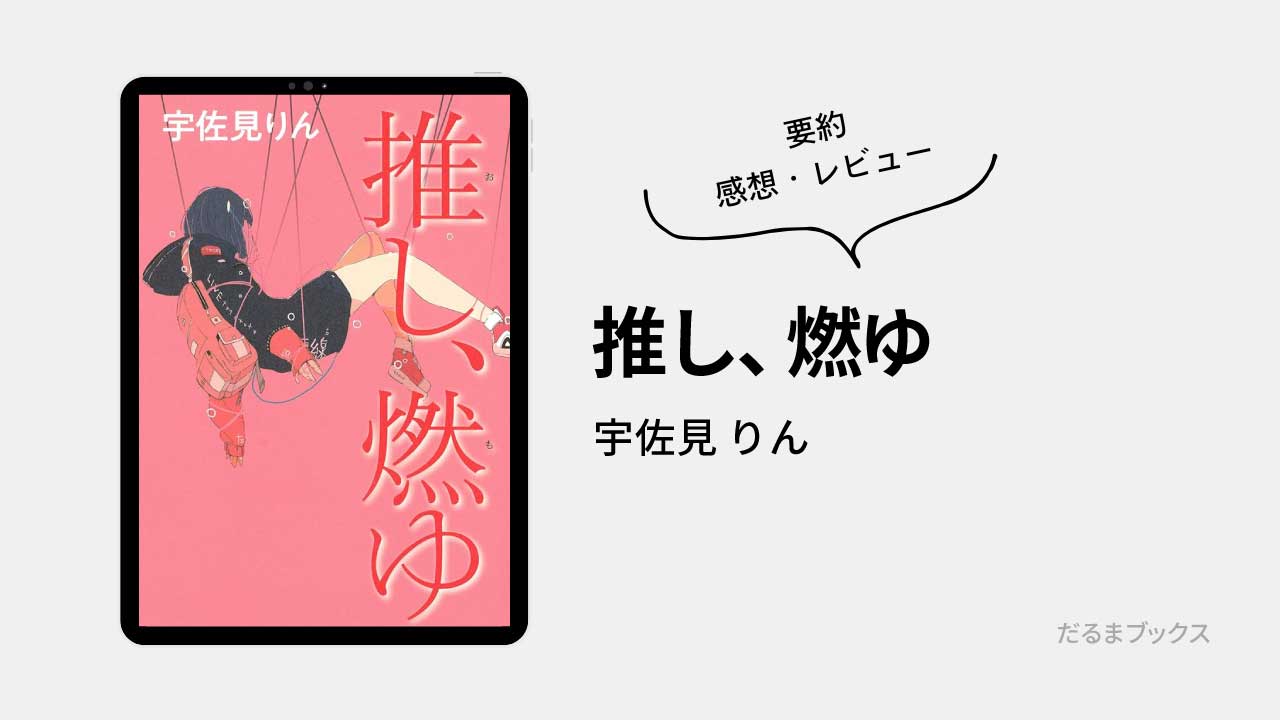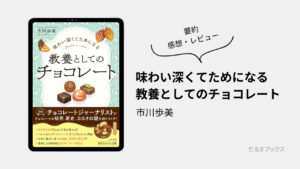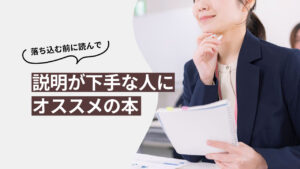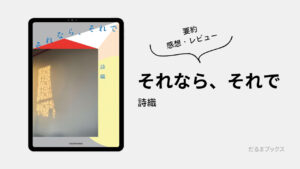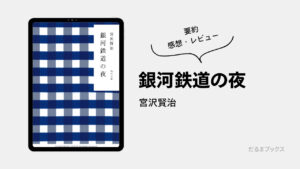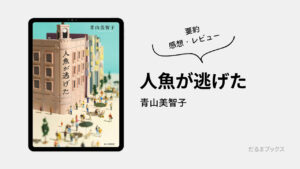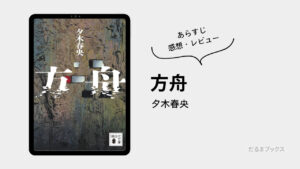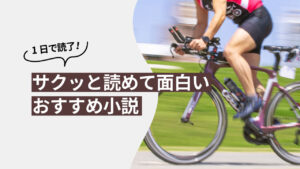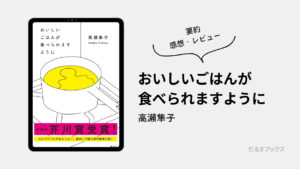宇佐見りんさんの芥川賞受賞作「推し、燃ゆ」は、
衝撃的な一文から始まり、主人公の心理と行動を通して現代社会における「推す」という行為の意味を深く掘り下げています。
あらすじや登場人物の解説、作品のテーマ、そして感想・レビューまで徹底的にご紹介します。
作品の概要
この作品は、SNSを日常的に使う人々の心に直接訴えかける
このたった短い2つの文が、これから展開される物語の核心を端的に表現しているのです。
主人公あかりと「推し」の関係性
高校生のあかりにとって、アイドルグループ「まざま座」のメンバー・上野真幸は唯一の生きがいです。
彼女は真幸のグッズを買い集め、インスタライブをチェックし、彼の発言をすべて記録・分析する日々を送っています。
あかりは学校でも家族との関係でもうまくいっていません。
「保健室で病院の受診を勧められ、ふたつほど診断名がついた」という描写からは、彼女が何らかの精神的な問題を抱えていることが示唆されます。
結局、最後まで病名は明かされません。
他の人が難なくこなせることが自分にはできない、という生きづらさを抱えるあかりにとって、「推し」は生きる支えそのもの。
真幸を推すことで、あかりは日常の苦しみから一時的に解放され、彼女にとって真幸は「寝起きするだけでシーツに皺が寄るように、生きているだけで皺寄せがくる」と感じる日常から逃れる唯一の手段なのです。
作者プロフィール
宇佐見りんさんは、1999年生まれの若手作家で、本作で第164回芥川龍之介賞を受賞しました。21歳での受賞は、綿矢りささん、金原ひとみさんに次ぐ史上3番目の若さです。2020年9月に河出書房新社から出版された本作は、2023年7月時点で累計発行部数80万部を突破する大ヒットとなりました。
この小説が多くの読者の心を掴んだのは、現代の若者文化、特に「推し」という概念を鋭く切り取ったからでしょう。「推し」とは応援する対象を指す言葉ですが、本作ではそれが単なる趣味を超えた、生きる支えとしての側面を持つことが描かれています。
物語の展開
炎上する「推し」と揺らぐ世界
物語は、あかりの「推し」である上野真幸がファンを殴打したというニュースが流れることから本格的に動き出します。この事件をきっかけに、あかりの世界は大きく揺らぎ始めます。
SNSでは真幸に対する批判が炎上のように広がり、あかりの心も焼かれていくように苦しみます。彼女は必死に真幸を擁護しようとしますが、一度燃え上がった炎は簡単には消えません。
あかりは真幸の言動を分析し、彼が悪くないと信じようとします。しかし、事実は変わらず、真幸の芸能活動は停止状態に陥ります。あかりの唯一の支えが揺らぐことで、彼女の日常生活も徐々に崩れていきます。
この展開は、現代のSNS社会における「炎上」の恐ろしさを鮮明に描いています。一度広がった情報は瞬く間に拡散し、真偽に関わらず人々の心に影響を与えます。あかりのように「推し」に強い感情を抱く人々にとって、その炎上は自分自身の存在基盤が揺らぐような体験となるのです。
生きづらさを抱える主人公
あかりの生きづらさは、物語を通じて繊細に描かれています。彼女は学校でクラスメイトとうまく関われず、アルバイト先でも周囲と馴染めません。家族との関係も複雑で、特に母親との間には埋めがたい溝があります。
「保健室で病院の受診を勧められ、ふたつほど診断名がついた」という描写からは、あかりが何らかの精神疾患や発達障害を抱えている可能性が示唆されます。しかし、宇佐見りんさんはあえてその診断名を明かさず、あかりの生きづらさを普遍的な形で描いています。
あかりにとって「推し」は、そんな生きづらさを抱えた自分を支える唯一の存在です。真幸を応援することで、彼女は自分の存在意義を見出し、日々を乗り切る力を得ています。しかし、その支えが揺らぐことで、彼女の精神状態も不安定になっていきます。
物語の中で、あかりは次第に現実と向き合わざるを得ない状況に追い込まれていきます。「推し」という依存対象を失いかけることで、彼女は自分自身と向き合う機会を得るのです。この過程は苦しみを伴いますが、同時に彼女の成長の物語でもあります。
「推し」という文化の考察
「推し」という言葉をよく耳にするようになりましたが、その意味や推し方は人それぞれ。
この本は「推しとは一体何なのか」という問いに一つの回答を示しています。
あかりにとって「推し」は、単なる趣味や娯楽ではなく、生きる支えそのものです。彼女は真幸の言動をすべて記録し、分析し、彼の人生に自分の人生を重ね合わせています。それは一種の依存関係とも言えますが、同時に彼女が生きるための必要な手段でもあります。
本作が描くのは、「推し」という行為が持つ複雑な側面です。それは単なるファン活動を超えた、現代人のアイデンティティ形成に関わる重要な要素となっています。特に若い世代にとって、「推し」は自分を表現する手段であり、コミュニティに属する方法でもあるのです。
宇佐見りんさんは、この「推し」という現象を通して、現代社会における人間関係の在り方や、若者たちの生きづらさを鋭く描き出しています。それは単なる流行現象の描写ではなく、人間の根源的な「依存」や「帰属」への欲求を掘り下げた普遍的なテーマとなっています。
距離感がもたらす安らぎ
あかりが真幸との関係に見出す重要な要素の一つが「距離感」です。彼女は推しとの間にある適切な距離に安らぎを見出しています。
具体的で直接的な人間関係は常に変動する多くの変数から成り立っています。家族や友人、恋人との関係は、常に相手の反応や感情に左右され、時に大きなストレスとなります。しかし、推しを推す関係では、こちらから金銭を支払う以外に変化を与えず、壊れる恐れのない安定した関係を維持できるのです。
あかりにとって真幸は、近すぎず遠すぎない絶妙な距離感を持つ存在です。彼女は真幸のことを知り尽くしていると感じながらも、実際には直接的な交流はありません。この「片思い」のような関係性が、彼女に安心感を与えているのです。
しかし、真幸の炎上事件は、この安定した距離感を揺るがします。あかりは真幸を守りたいという気持ちから、これまで維持してきた距離を越えようとします。この変化が、物語の重要な転換点となっているのです。
宇佐見りんさんは、この「距離感」というテーマを通して、現代社会における人間関係の複雑さを描いています。SNSの普及により、私たちは見知らぬ人の生活を覗き見ることが可能になりました。その結果、実際には交流のない相手に対して強い感情を抱くという新しい形の人間関係が生まれています。本作はそうした現代特有の関係性を鋭く切り取っているのです。
現代社会を映し出す鏡
SNS時代の推し文化
本作は推し文化とSNS文化の親和性を見事に描いています。SNSを通じて推しの情報を得て満たされる一方で、炎上時にはSNSにあふれる言葉に心を焼かれるというあかりの姿は、現代のファン文化の縮図とも言えます。
あかりは真幸のインスタライブを欠かさずチェックし、彼の言動をすべて記録しています。SNSがなければ、このような密接なファン活動は不可能だったでしょう。SNSは推しとファンの距離を縮め、より深い関係性を可能にしました。
しかし同時に、SNSは炎上の場ともなります。真幸の不祥事がSNSで拡散されると、あかりは無力感に苛まれます。彼女は真幸を擁護するコメントを投稿しますが、それは炎上の大きな流れの中で埋もれてしまいます。
この描写は、SNS時代における個人の無力感を象徴しています。誰もが発信できる時代だからこそ、一人の声は簡単に埋もれてしまうのです。また、SNSでは情報が断片的に切り取られ、文脈を無視した批判が広がりやすいという問題も描かれています。
宇佐見りんさんは、こうしたSNS時代の光と影を繊細に描き出しています。それは単なる時代背景ではなく、物語の本質的な要素となっているのです。
令和初期の文化記録としての価値
「推し、燃ゆ」は令和初期の文化を記録する上でも重要な作品です。50年後、100年後の世界で、21世紀初めの日本に存在していた「推し」という感情が伝わるとすれば、本作はその貴重な資料となるでしょう。
宇佐見りんさんは、現代の若者文化を鮮明に切り取っています。アイドルグループの存在、ファンの行動様式、SNSでの交流、炎上現象など、現代特有の文化現象が細部まで描かれています。これらは将来の読者にとって、この時代を知る手がかりとなるでしょう。
特に「推し」という概念は、現代日本の若者文化を象徴するものです。それは単なるファン活動を超えた、アイデンティティ形成に関わる重要な要素となっています。本作はそうした「推し」の本質を深く掘り下げることで、この時代の若者の心理を記録しているのです。
また、本作が描く「生きづらさ」も、現代社会を反映しています。SNSの普及により、他者の生活が可視化され、比較の対象となる時代において、若者たちが感じる孤独や不安は特有のものです。本作はそうした現代的な「生きづらさ」を繊細に描き出しています。
「推し、燃ゆ」は、文学作品としての価値だけでなく、文化人類学的な資料としても重要な意味を持つ作品なのです。
感想・レビュー
宇佐見りんさんの「推し、燃ゆ」は、現代の若者文化を鋭く切り取った傑作です。特に印象的なのは、冒頭の「推しが燃えた。ファンを殴ったらしい。」という二文の持つ力です。この短い文章だけで、推しを持つ人の喉が詰まるような感覚を見事に表現しています。
本作の魅力は、「推し」という現代的なテーマを扱いながらも、その根底にある普遍的な人間の感情を描き出している点にあります。あかりの真幸への感情は、一見特殊な「推し」という形を取っていますが、その本質は人間の「依存」や「帰属」への欲求という普遍的なものです。
また、あかりの生きづらさの描写も秀逸です。彼女の感じる違和感や孤独感は、多くの読者の心に響くものでしょう。特に、他の人が難なくこなせることが自分にはできないという感覚は、現代社会を生きる多くの人が共感できるものではないでしょうか。
文体も特筆すべき点です。宇佐見りんさんの文章は簡潔でありながら、強い印象を残します。特に、あかりの内面描写は繊細かつ鋭く、彼女の感情の機微を見事に捉えています。
本作が芥川賞を受賞したのも納得です。21歳という若さで、これほど成熟した作品を書き上げた宇佐見りんさんの才能は驚異的です。彼女の視点は若い世代ならではの鋭さを持ちながらも、普遍的なテーマを掘り下げる深さを備えています。
ただ、平野啓一郎さんが選評で指摘したように、「寄る辺なき実存の依存先という主題は、今更と言っていいほど新味がなく」という側面もあるかもしれません。しかし、それを現代の「推し」文化という切り口で描き出した点に、本作の新しさがあると感じます。
「推し、燃ゆ」は、現代日本の若者文化を知るための重要な作品であると同時に、人間の普遍的な感情を描いた文学作品としても価値があります。
推し文化に興味がある方はもちろん、現代社会における人間関係や若者の心理に関心がある方にもぜひ読んでいただきたい一冊です。
まとめ
「推し、燃ゆ」は、宇佐見りんさんが21歳という若さで芥川賞を受賞した話題作です。
「推し」という現代的なテーマを通して、若者の生きづらさや人間関係の複雑さを鋭く描き出しています。
冒頭の「推しが燃えた。ファンを殴ったらしい。」という衝撃的な書き出しから始まり、主人公あかりの心理と行動を通して、現代社会における「推す」という行為の意味を深く掘り下げた本作は、文学作品としての価値だけでなく、令和初期の文化を記録する重要な資料としても価値があります。
現代の若者文化に興味がある方はもちろん、人間の普遍的な感情に関心がある方にもぜひ読んでいただきたい一冊です。