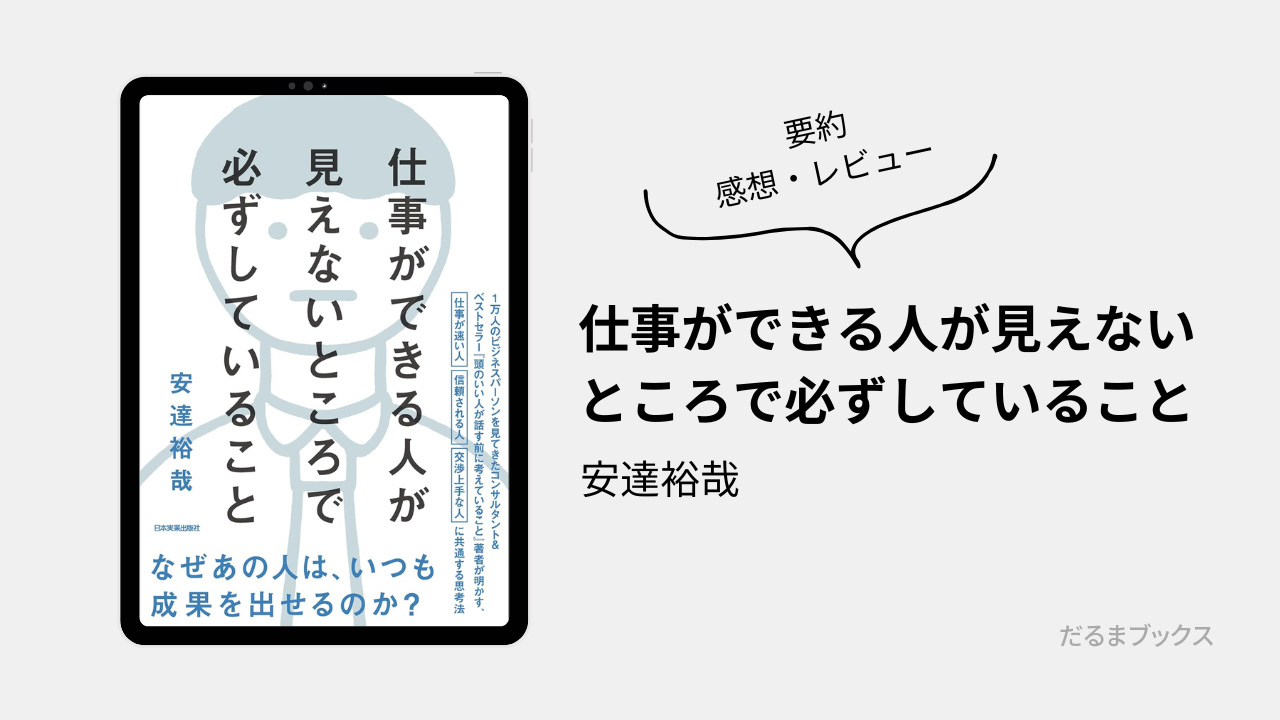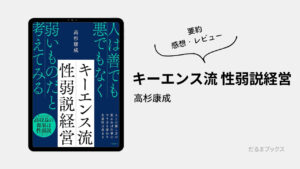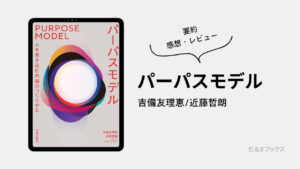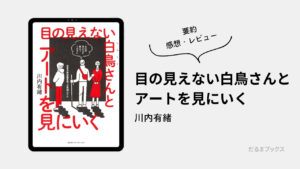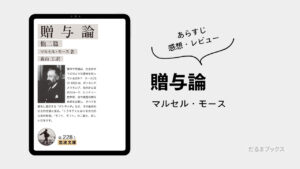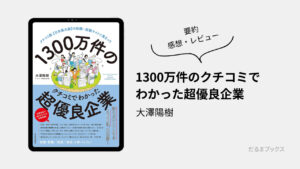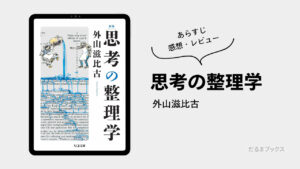ビジネス書の棚を眺めていると、「仕事ができる人」になるための方法論を説く本が数多く並んでいます。
その中でも安達裕哉さんの「仕事ができる人が見えないところで必ずしていること」は、1万人以上のビジネスパーソンと向き合ってきた著者だからこそ見えてきた、成果を出す人たちの共通点を明らかにしています。
この本では、
- 実行力
- 決断力
- コミュニケーション力
- 考え抜く力
- 働きかけ力
という5つの核心能力を軸に、仕事ができる人が日常的に行っている習慣や思考法を紐解いていきます。
安達裕哉さんが明かす「仕事ができる人」の思考法
安達裕哉さんは1975年東京都生まれ。筑波大学環境科学研究科を修了後、世界最大級の会計事務所であるDeloitteで12年間コンサルティングに従事しました。
東京支社長、大阪支社長を歴任した後に独立し、現在はオウンドメディア支援の「ティネクト株式会社」を設立。自身が運営するメディア「Books&Apps」は月間200万PVを超える人気を誇ります。
「実行力」は人生を変える最強の武器
安達さんは本書の中で、「実行力」こそが人生を変えるための最強の武器だと説きます。多くの人が「やってみたい」と思うだけで終わってしまう中、実際に「やってみた」人だけが成長できるのです。
安達さんは知人の経営者の言葉を引用しています。「『やってみたい』と『やってみた』の2つはまったく違う次元の話だ。これは『本気度』のような抽象的な差ではない」。その経営者によれば、「やってみれば、データが取れる。それをもとに、もっとうまいやり方を考えられる。実験ができて、きちんと検証でき、再現できれば科学だ」と言います。一方で、やったことのない人は「単なる思い込みや推測でしか動けない。要するに、迷信めいたものをあてにしている」のです。
実行力を高めるためには、小さな習慣から始めることが大切です。人生を変えるのは、一発逆転の出来事ではなく、些細な日常の習慣なのです。例えば、早起きをする、通勤時間に必ず本を読むといった小さな習慣から人生は変わっていきます。ただし、無理してできないことを続ける必要はありません。1つ挫折したら、次のものを設定すればいいのです。
50歳以上しか採用しない会社の社長の教え
本書では、50歳以上しか採用しない会社の社長の話も紹介されています。
その社長が若い人を採用しない理由は、若い人は「頭がいい」ことを武器にしがちだからだと言います。
しかし、ビジネスの世界では「頭がいい」よりも「行動力がある」人の方が支持されるのです。
部下は、リーダーに間違いを犯さないことを求めているのではありません。
それよりも率先して行動し、間違えたときはその非を認めて素早く修正することを求めています。
人間的な魅力があるリーダーが支持される傾向にありますが、その「人間的な魅力」とは「最小限の力で正確に仕事をこなす」よりも「精一杯、力の限り働く」という部分によって形成されているのです。
「仕事ができる人」の5つの核心能力
本書では、仕事ができる人に共通する5つの核心能力として、「実行力」「決断力」「コミュニケーション力」「考え抜く力」「働きかけ力」を挙げています。これらの能力を高めることで、ビジネスパーソンとしての成長が加速します。
「決断力」と判断軸の重要性
ビジネスの世界では、日々さまざまな決断を迫られます。その際に重要なのが、一貫した「判断軸」を持っているかどうかです。仕事ができる人は、一生役立つ判断軸を持っています。
判断軸とは、物事を判断する際の基準や価値観のことです。例えば、「顧客第一」「長期的な視点」「効率性」などが判断軸となります。これらの判断軸を持っていると、迷いなく決断を下すことができます。
また、決断力を高めるためには、「フレーム」を知ることも重要です。フレームとは、物事を考える際の枠組みや視点のことです。例えば、「コスト vs. ベネフィット」「短期 vs. 長期」「リスク vs. リターン」などがフレームとなります。これらのフレームを使い分けることで、より良い決断ができるようになります。
「コミュニケーション力」の意外な工夫
コミュニケーション力は、ビジネスパーソンにとって欠かせないスキルです。しかし、コミュニケーション力を高めるためには、意外な工夫が必要です。
安達さんは、「会話なんて、コツは2つしかない。相手が話したいことを聞いてあげること。相手が聞きたいことだけ話すこと」と言います。つまり、自分が話したいことを一方的に話すのではなく、相手の関心事に合わせたコミュニケーションが重要なのです。
また、人と会うときは、「その人の趣味や、好きなもの」を必ず聞くことも大切です。「私におすすめはありますか?」と尋ね、教えてもらったらとりあえず試してみる。このような小さな工夫が、相手との関係構築に大きく貢献します。
さらに、会議の場で議論する前に関係者全員に対して個別に話を通しておくことも、コミュニケーション力の一つです。これは、デロイトトーマツコンサルティングのような大きな組織では当たり前の文化だったようです。事前の根回しをすることで、会議をスムーズに進行させることができます。
「考え抜く力」が教えてくれる本質
考え抜く力は、物事の本質を見抜くために必要な能力です。仕事ができる人は、日々の習慣として考え抜くことを実践しています。
例えば、「なぜ、自分のつくったものは読まれないのか?」「なぜ、自分のつくったものは使われないのか?」といった問いを立て、考え抜くことで、ビジネスの嗅覚を磨くことができます。
安達さんによれば、ビジネスの本質とは「つくり、告知し、売ること」です。この本質を理解し、実践することで、ビジネスパーソンとしての成長が促されます。また、ビジネスパーソンがこの能力を身に着ける最適な道は、副業をすることだと安達さんは提案しています。
会議で評価される人の特徴
会議は、ビジネスパーソンの能力が最も顕著に表れる場の一つです。
では、会議で評価される人にはどのような特徴があるのでしょうか。
最初に案を出す勇気
安達さんは、「一番偉いのは最初に案を出す人」だと言います。
会議の場で最初に案を出すことには勇気が必要ですが、それだけの価値があります。
なぜなら、最初の案は議論の土台となり、その後の議論の方向性を決定づけるからです。
また、最初に案を出すことで、自分のアイデアや考えを示す機会を得ることができます。
これにより、周囲からの評価や信頼を得ることができるのです。
ただし、単に案を出せばいいというわけではありません。出す案の質も重要です。そのためには、事前の準備が欠かせません。会議の前に十分な情報収集や分析を行い、質の高い案を準備しておくことが大切です。
相手の立場に立って考える力
会議で評価されるもう一つの特徴は、相手の立場に立って考える力です。自分の意見を主張するだけでなく、他者の視点や立場を理解し、それを踏まえた上で議論を進めることが重要です。
特に、頭のいい人は正論を主張しがちですが、それだけでは人は動きません。相手の気持ちや状況を理解し、それに合わせたコミュニケーションを取ることが必要です。
安達さんは、頭のいい人が陥りやすい罠として、以下の3つを挙げています。一つ目は、自分でやれてしまうので助けを求めるのが苦手なこと。二つ目は、能力が高いがゆえに他の人に対する「期待」を持ちにくいこと。三つ目は、正論を主張して抵抗勢力を論破しようとすることです。これらの罠に陥ると、敵を作り、孤立し、足を引っ張られて出世できなくなってしまいます。
出世するための唯一の方法
ビジネスの世界で出世するためには、どのような方法があるのでしょうか。
安達さんは、出世するための唯一の方法として、上司を助けて成果を上げさせることを挙げています。
上司を助けて成果を上げさせる
組織内で出世するためには、上司から評価してもらう必要があります。しかし、上司は選べません。だからこそ、その時の直属の上司に合わせて上司を支援し、常に上司から評価してもらうことが絶対的に必要なのです。
具体的には、上司の特徴をつかみ、上司の得意なところを発揮させ、上司を出世させることが重要です。出世した上司が、あなたを引き上げてくれるというのが日本の出世街道なのです。
また、うまく助けを求める人は、上にかわいがられることも多いと安達さんは言います。人は頼られることが好きなのです。自分一人で抱え込むのではなく、適切に助けを求めることも、出世するための重要なスキルです。
「頭がいい人」が陥りやすい3つの罠
前述したように、頭のいい人が必ずしも出世するとは限りません。むしろ、頭のいい人は以下の3つの罠に陥りやすいのです。
一つ目は、自分でやれてしまうので助けを求めるのが苦手なことです。その結果、仕事を部下から取り上げたり、人に頼ったり相談することができず、独断に走る傾向があります。
二つ目は、能力が高いがゆえに他の人に対する「期待」を持ちにくいことです。人は「期待」されていないと感じれば、その人についてこようとは思いません。
三つ目は、正論を主張して抵抗勢力を論破しようとすることです。優秀であるがゆえに、普通の人である相手の気持ちになって考えることができず、抵抗勢力の本音を汲み取ってあげて丸め込むことができずに、敵を作ってしまいます。
これらの罠を避けるためには、自分の能力や知識を過信せず、常に謙虚な姿勢で周囲と協力することが大切です。
仕事を任されたときの黄金ルール
仕事を任されたとき、どのように対応すれば良いのでしょうか。安達さんは、仕事を任されたときの黄金ルールとして、以下の2つを挙げています。
納期と成果レベルの確認
仕事を任されたら、まず納期を確認することが重要です。いつまでに完了すべきかを明確にすることで、計画的に仕事を進めることができます。
また、具体的な成果のレベルを、仕事の依頼者と合意することも大切です。「どの程度の品質が求められているのか」「どのような形式で提出すべきか」など、成果物に関する具体的な要件を確認しておくことで、後々のミスマッチを防ぐことができます。
これらの確認を怠ると、自分が思っていた以上の成果を求められたり、納期に間に合わなかったりするリスクがあります。仕事を始める前に、これらの点をしっかりと確認しておくことが、仕事を成功させるための第一歩なのです。
前例を探す重要性
仕事を任されたとき、自分でゼロから考えるのではなく、前例を探すことも重要です。過去に同様の仕事が行われていれば、そのノウハウや成果物を参考にすることで、効率的に仕事を進めることができます。
前例を探す方法としては、同僚や先輩に聞く、社内のデータベースを検索する、インターネットで調べるなどがあります。これらの方法を駆使して、できるだけ多くの情報を集めることが大切です。
ただし、前例をそのまま真似するのではなく、自分なりのアレンジや改善を加えることも忘れてはいけません。前例を参考にしつつも、より良い成果を目指すという姿勢が、仕事ができる人の特徴です。
感想・レビュー
安達裕哉さんの『仕事ができる人が見えないところで必ずしていること』を読んで、最も印象に残ったのは「やってみたい」と「やってみた」の違いについての考察です。私たち誰もが「いつかやってみたい」と思うことはたくさんありますが、実際に行動に移す人は少ないものです。安達さんが言うように、行動することで初めてデータが取れ、それを基に改善していくことができるのだと強く感じました。
1万人以上のビジネスパーソンとの対話から生まれた知恵
本書の強みは、著者が1万人以上のビジネスパーソンと対峙してきた経験から導き出された知見にあります。理論だけでなく、実際のビジネスの現場で通用する実践的なアドバイスが満載です。
特に印象的だったのは、コミュニケーションに関する部分です。「相手が話したいことを聞いてあげること。相手が聞きたいことだけ話すこと」というシンプルな原則が、実は最も効果的なコミュニケーション方法だということに気づかされました。
また、人と会うときに「その人の趣味や好きなもの」を聞き、教えてもらったらとりあえず試してみるという具体的なアドバイスも、すぐに実践できそうです。こうした小さな工夫が、人間関係の構築に大きく貢献するのだと思います。
暗黙知を形式知にした実践的ガイド
本書のもう一つの強みは、ビジネスの世界で「暗黙知」とされていることを「形式知」に変換している点です。「なぜあの人は仕事ができるのか」「なぜあの人は評価されるのか」といった疑問に対して、具体的な理由や方法を示してくれています。
例えば、会議で最初に案を出すことの重要性や、上司を助けて成果を上げさせることが出世につながるという指摘は、多くのビジネスパーソンにとって目から鱗の内容ではないでしょうか。
また、頭のいい人が陥りやすい3つの罠についての分析も非常に興味深いものでした。頭がいいことが必ずしも仕事の成功につながるわけではなく、むしろ足がかりになることもあるという指摘は、多くの人にとって新鮮な視点ではないでしょうか。自分の能力を過信せず、周囲と協力することの重要性を改めて考えさせられました。
本書を読んで、ビジネスの世界で成功するためには、単なる知識や能力だけでなく、人間関係の構築や相手の立場に立った考え方が不可欠だということを実感しました。これらは学校では教えてくれない、実社会で身につけるべき重要なスキルです。
まとめ
安達裕哉さんの『仕事ができる人が見えないところで必ずしていること』は、ビジネスパーソンとして成長したい人にとって、非常に価値のある一冊です。著者が1万人以上のビジネスパーソンとの対話から導き出した知見は、理論だけでなく実践的なアドバイスとして提示されています。
本書の核となる5つの能力「実行力」「決断力」「コミュニケーション力」「考え抜く力」「働きかけ力」を意識し、日常の小さな習慣から変えていくことで、誰でも「仕事ができる人」に近づくことができるでしょう。
特に印象的だったのは「やってみたい」と「やってみた」の違いについての考察です。行動することの重要性を改めて認識させてくれる、背中を押してくれる一冊だと感じました。
「できる風な人」から「本当にできる人」になるための道標として、ビジネスパーソンなら一度は読んでおくべき本だと思います。