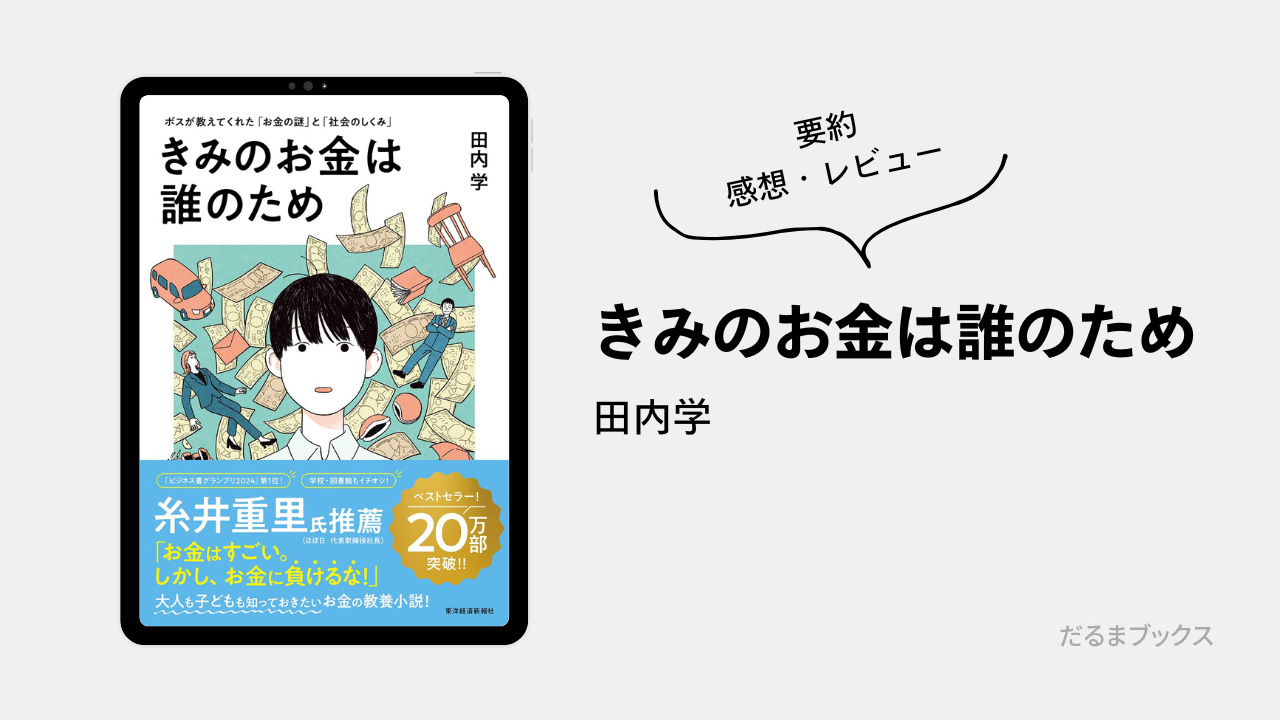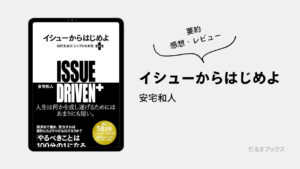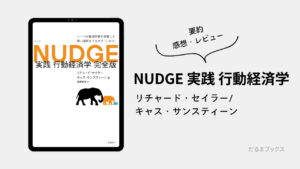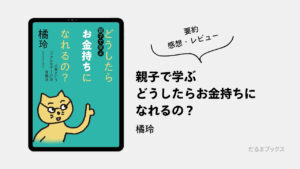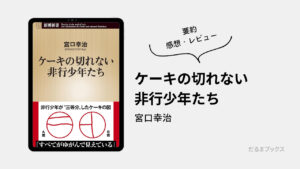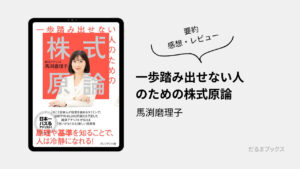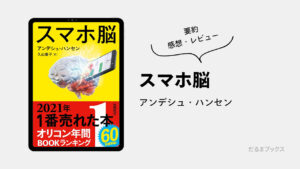お金の本質とは何か。
私たちは、日々お金を
- 使い
- 稼ぎ
- 貯める
ことに必死ですが、そのお金の「正体」を本当に理解しているのか。
元ゴールドマン・サックスのトレーダーである田内学さんの著書「きみのお金は誰のため」は、
- 中学生の少年
- 投資銀行員の女性
- 謎の大富豪「ボス」
の3人から学ぶお金の本質と社会の仕組みを鮮やかに描き出しています。
お金の不思議な世界へようこそ
中学生の優斗と投資銀行員の七海が出会う
物語は雨の日から始まります。中学2年生の佐久間優斗は、進路指導面談で「年収の高い仕事がいい」と答えたことで担任から長々と説教され、帰りが遅くなってしまいます。そんな中、謎めいた屋敷の前で投資銀行に勤める七海という女性に声をかけられ、一緒に屋敷の中へと足を踏み入れることになります。
優斗は正直な子です。お金より大事なものがあると言われても納得がいかない。結局のところ、先生だってお金のために働いているのではないか。そんな疑問を抱えた彼の目の前に現れたのは、「ボス」と呼ばれる謎の大富豪でした。
七海は投資で莫大な資産を築いたというボスに話を聞きに来たのですが、ボスは意外なことを言います。「お金もうけの方法は教えない」と。代わりに彼が教えたいのは、「お金の正体」についてでした。
謎の大富豪「ボス」との奇妙な講義
ボスは小さな指を立てながら、お金にまつわる3つの真実を告げます。
- お金自体に価値はない。
- お金で解決できる問題はない。
- みんなでお金を貯めても意味はない。
優斗も七海も、そんなわけがないと反論。
でも、ボスはこれらの謎を解き明かせば、お金の正体が見えてくると言うのです。そして、「この建物の本当の価値がわかる人に屋敷をわたす」という条件を出します。
こうして、優斗と七海はボスの屋敷に通うことになり、「お金の正体」と「社会のしくみ」についての講義が始まるのです。
この設定は、一見するとファンタジーのようですが、実は私たち読者を経済の本質へと導くための巧みな仕掛けなのです。中学生の優斗の純粋な疑問と、投資銀行員の七海の専門的な視点が交差することで、読者は様々な角度からお金について考えることができます。
お金の本質を紐解く3つの謎
ストーリーはボスが言う3つの謎の解説へ
お金自体には価値がない?
ボスの最初の謎「お金自体には価値がない」に、優斗は強い疑問を持ちます。
そんな彼を前にボスは
「毎年大量のお金が燃やされている。だからお金には価値がない」と言い放ちます。
実は、お金とは「誰かに働いてもらうためのチケット」なのです。
私たちがお金を払って商品やサービスを買えるのは、そのお金を受け取って陰ながら働いてくれる人がいるからです。
例えば
カフェでドリンクを買うとき私たちはお金がドリンクに変わると錯覚しがちですが、実際には
- 店舗で働いているスタッフ
- その物件を貸してくれている人
- コーヒー豆を作ってくれている人
- 材料を届けてくれている人たち
によって作られているのです。
つまり、紙幣や硬貨そのものには価値がなく、それが「通貨として使えるチケット」であることを国が保証しているから価値があるのです。
お金で解決できない問題とは
2つ目の謎は「お金で解決できる問題はない」というもの。
一見すると矛盾しているように思えますが、ボスの説明によるとお金自体は何も解決できず、実際に問題を解決するのは「人間の働き」だということ。
例えば
病気になったとき、治療費としてお金を払いますが、実際に治すのはお金ではなく医師や看護師、薬を開発した研究者の方たち。お金はただ、それらの人々の労働に対する「ありがとう」を形にしたものに過ぎません。
この視点は、私たちがお金に対して持つ執着を見直すきっかけになるのではないでしょうか。
お金は目的ではなく、人々の幸せや社会の発展のための手段であるということを、物語は教えてくれるのです。
みんなで貯金しても意味がない理由
3つ目の謎「みんなでお金を貯めても意味がない」も、深い洞察を含んでいます。
個人がお金を貯めることには意味がありますが、社会全体が貯蓄に走ると経済は縮小してしまいます。
現代の日本では、老後の不安からみんながお金を貯め込む傾向がありますが、それが経済の循環を滞らせる原因になっています。お金が使われなければ、誰かの収入にならず、結果として社会全体が貧しくなってしまうのです。
私たちは自分のお財布のことだけでなく、社会全体のお金の流れを考える必要があるのです。
社会の仕組みを読み解く
格差問題の真相に迫る
物語が進むにつれ、ボスは現代社会の大きな問題である「格差」についても語り始めます。「格差の謎:退治する悪党は存在しない」というテーマで、格差の原因と解決策について考察します。
格差は単純に「悪い人がいるから」生まれるわけではありません。それは社会システムの結果であり、特定の誰かを悪者にしても解決しない問題なのです。重要なのは、格差を生み出すシステムそのものを理解し、改善することです。
ボスは格差を完全になくすことは不可能だとしつつも、極端な格差は社会の分断を招き、結果として全員が不幸になると説明します。適度な格差は努力のインセンティブになりますが、チャンスの平等が保たれることが重要だと語るのです。
未来への贈与という考え方
ボスが語る「社会の謎:未来には贈与しかできない」というテーマは、世代間の関係について考えさせられます。私たちは未来の世代に対して「贈与」しかできないという考え方です。
現在の世代が未来の世代から「借りる」ことはできても、未来の世代に「貸す」ことはできません。なぜなら、未来の世代はまだ存在していないからです。だからこそ、私たちは未来のために投資し、より良い社会を「贈与」する責任があるのです。
この考え方は、環境問題や少子高齢化、財政赤字など、世代を超えた問題を考える上で重要な視点を提供してくれます。私たちの今の選択が、未来の世代の可能性を広げるか狭めるかを決めるのです。
私たちはひとりじゃない
物語のクライマックスで明かされる「最後の謎:ぼくたちはひとりじゃない」は、お金を通じた人々のつながりについて語っています。
お金は単なる交換手段ではなく、「ありがとう」を伝えるメディアでもあります。私たちが何かを買うとき、それは多くの見知らぬ人々の労働に対する感謝の気持ちを表しているのです。
この視点から見ると、経済活動は冷たい取引ではなく、人々の温かいつながりの表現とも言えます。私たちは知らず知らずのうちに、お金を通じて社会の中で支え合って生きているのです。
物語を通して学ぶ経済の基礎
中学生にもわかる経済の仕組み
本書の素晴らしさは、複雑な経済の仕組みを中学生にもわかるように説明している点にあります。専門用語をほとんど使わず、身近な例を通して経済の本質を伝えているのです。
例えば、国の借金について考えるとき、家計の借金と同じように考えがちですが、実はまったく性質が異なります。国の借金の多くは自国民に対するものであり、単純に「返済すべきもの」と考えるのは適切ではないのです。
また、インフレとデフレについても、物価の上下だけでなく、賃金や資産価値の変動も含めて総合的に考える必要があることを、わかりやすく説明しています。
日常生活に潜むお金の謎
私たちの日常生活には、お金に関する謎がたくさん潜んでいます。なぜ物価が上がるのか、なぜ貯金だけでは老後の問題は解決できないのか、なぜ貿易赤字が問題なのか。
本書では、こうした疑問に対して、経済学の難しい理論ではなく、人間の活動という視点から答えを導き出しています。例えば、物価が上がるのは単にお金の量が増えたからではなく、人々の働き方や社会構造の変化が関係しているのです。
このように、日常の疑問から出発して経済の本質に迫るアプローチは、読者の理解を深める上で非常に効果的です。
著者・田内学さんの経歴
ゴールドマン・サックスでの16年間
著者の田内学さんは、1978年兵庫県生まれ。灘高等学校を卒業後、東京大学工学部機械情報工学科に進学しました。大学院修了後の2003年にゴールドマン・サックス証券株式会社に入社し、以後16年間、日本国債、円金利デリバティブ、長期為替などのトレーディングに従事しました。
金融の最前線で活躍していた田内さんですが、2019年に退職。その後、「お金の向こう研究所」を設立し、社会的金融教育家として活動を始めました。金融のプロフェッショナルとしての経験を活かしながら、一般の人々にもわかりやすくお金の本質を伝える活動を続けています。
金融のプロから見た「お金」の本質
田内さんがゴールドマン・サックスという金融の最前線で働いた経験から導き出した結論は、意外にも「お金は偉くない。そして経済は、お金でなく人を中心に考えないといけない」というものでした。
これは単なる道徳的な主張ではなく、現実を踏まえて論理的に導き出された結論です。田内さんは、資本主義のど真ん中にいたからこそ、お金の限界と本質を見抜くことができたのでしょう。
「経済とは、経世済民の略で、本来は「世を経(おさ)め、民を済(すく)う」という意味があります。民をすくうことを目的にしていたはずなのに、お金自体を目的にすることが増えている現代社会」という田内さんの言葉は、私たちに経済の本来の目的を思い出させてくれます。
小説仕立ての経済教養本
読みやすさと学びの両立
本書の大きな特徴は、小説仕立てになっていることです。難解な経済理論を直接説明するのではなく、中学生の優斗と投資銀行員の七海がボスから学ぶという物語を通して、読者も一緒に学んでいく構成になっています。
この形式により、経済や金融の前提知識がなくても、スムーズに内容を理解することができます。また、物語としての面白さもあるため、最後まで飽きることなく読み進めることができるでしょう。
「読者が選ぶビジネス書グランプリ2024」で総合グランプリを受賞し、20万部を超えるベストセラーになったのも、この読みやすさと学びの深さが両立しているからではないでしょうか。
登場人物たちの成長物語
本書は単なる経済解説書ではなく、登場人物たちの成長物語でもあります。
最初は「年収の高い仕事がいい」と考えていた優斗が、ボスの講義を通してお金の本質を理解し、自分の価値観を見直していく過程が描かれています。また、プロの投資銀行員である七海も、金融の世界で当たり前と思っていたことを改めて問い直し、新たな気づきを得ていきます。
この成長物語があることで、読者も自分自身の価値観や生き方を振り返るきっかけを得ることができるのです。
感想・レビュー
経済の難しい話をわかりやすく
本書を読んで最も印象に残ったのは、難解な経済の話題をこれほどわかりやすく、しかも面白く説明できるということです。経済や金融というと、専門用語が飛び交い、複雑な数式が出てくるイメージがありますが、本書にはそうした難解さがありません。
特に「お金自体には価値がない」という一見すると衝撃的な主張も、読み進めるうちに納得できるようになります。お金は単なる紙切れであり、その価値は社会的な約束事に過ぎないという事実。そして、真の価値は人々の労働や創造性にあるという視点は、私たちのお金に対する見方を根本から変えてくれます。
また、「お金とは「ありがとう」を渡すこと」という考え方も心に響きました。私たちが日常的に行っている買い物や支払いは、実は多くの人々への感謝の表現だったのです。この視点に立つと、経済活動が単なる冷たい取引ではなく、人々のつながりや支え合いの表現であることがわかります。
心に響くラストシーン
本書のラストシーンは、多くの読者の心を打つようです。「ハッとするような言葉の連続。ラストでは涙が溢れてきた」という50代の経営者の感想にもあるように、単なる経済解説を超えた感動があります。
最後の謎「ぼくたちはひとりじゃない」で明かされる、お金を通じた人々のつながりと支え合いの真実は、読者に深い気づきを与えてくれます。私たちは知らず知らずのうちに、お金という仕組みを通じて社会の中で支え合って生きているのです。
この気づきは、お金に対する見方だけでなく、社会や人生に対する見方も変えてくれるでしょう。お金を目的とするのではなく、人々の幸せや社会の発展のための手段として捉え直すことで、より豊かな人生を送ることができるのではないでしょうか。本書の最終章では、ボスが語る「ぼくたちはひとりじゃない」という真実に多くの読者が感動しています。「ギャン泣きしてください」と言われるほど心を揺さぶるラストシーンは、お金という切り口から人間のつながりの大切さを教えてくれるのです。
物語の終盤では思いもよらぬ展開に衝撃を受け、そして感動を覚えます。序盤にはまったく想像していなかった展開に涙しながら、あたたかい気持ちで読み終えることができるでしょう。「きみのお金は誰のため」という言葉の意味を、しみじみと噛み締めることができる結末となっています。
まとめ
『きみのお金は誰のため』は、お金の本質と社会の仕組みを小説形式でわかりやすく解説した一冊です。元ゴールドマン・サックスのトレーダーである田内学さんが、金融の最前線で得た知見をもとに、中学生にもわかる言葉で経済の本質を伝えています。
「お金自体には価値がない」「お金で解決できる問題はない」「みんなでお金を貯めても意味がない」という三つの謎から始まり、格差問題や世代間の関係、そして人々のつながりについて深く考えさせられます。
「読者が選ぶビジネス書グランプリ2024」で総合グランプリを受賞したこの本は、単なる経済解説書ではなく、私たちの価値観や生き方を見つめ直すきっかけを与えてくれる作品です。お金の向こう側にある「人とのつながり」や「社会への貢献」の大切さを教えてくれる、心温まる経済教養小説と言えるでしょう。