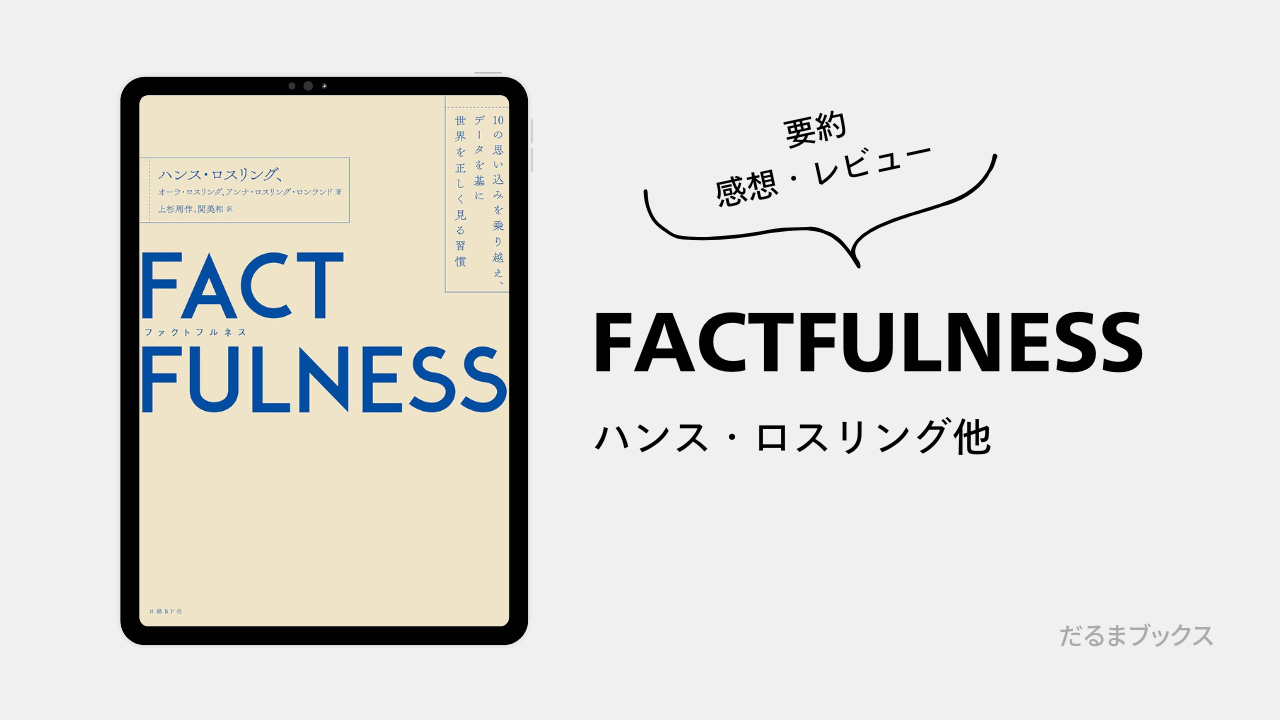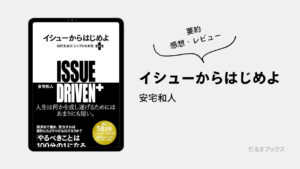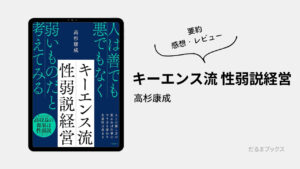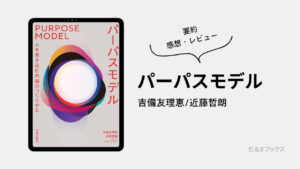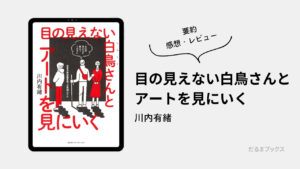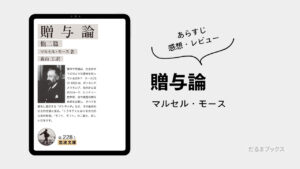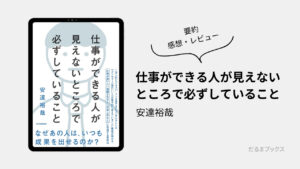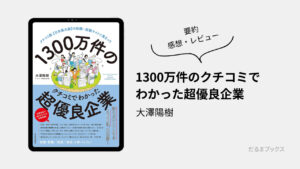世界はどんどん悪くなっている——そう思い込んでいませんか?
スウェーデンの医師・公衆衛生学者ハンス・ロスリングさんの遺作となった「FACTFULNESS」は、私たちが無意識に持つ10の思い込みを指摘し、データに基づいて世界を正しく見る習慣の大切さを説いています。
ビル・ゲイツさんが「これまで読んだ中で最も重要な本の一冊」と絶賛し、世界中で話題となったこの本。私たちが思っている以上に、実は世界は良くなっているという事実と、それを見誤ってしまう人間の本能について、ロスリングさん一家が情熱を込めて伝えてくれる一冊です。
「FACTFULNESS」とは
ハンス・ロスリングさんのプロフィール
ハンス・ロスリングさんは1948年、スウェーデンに生まれた医師であり、公衆衛生学者です。彼はスウェーデンにおける国境なき医師団の立ち上げに関わり、WHOやUNICEFなどの国際援助機関でアドバイザーを務めました。しかし、彼の名が世界的に知られるようになったのは、TED講演での活躍がきっかけでした。
ロスリングさんのTED講演「How not to be ignorant about the world(世界について無知にならない方法)」は、YouTubeで2800万回以上も再生される人気を博しました。彼は統計データを動くバブルチャートで視覚化し、世界の現状について私たちが持つ誤解を次々と覆していきました。その熱意あふれるプレゼンテーションは、多くの人々の心を動かしたのです。
残念ながら、ロスリングさんは2017年に膵臓がんで亡くなりましたが、「FACTFULNESS」は彼の遺作として、息子のオーラさんと娘婿のアンナさんによって完成されました。
本書の概要と世界的な評価
「FACTFULNESS」とは、「事実やデータに基づき、正しく世界を読み解く」という意味です。本書は、私たちが世界について持つ様々な思い込みを、実際のデータを用いて検証し、より正確な世界観を持つことの重要性を説いています。
本書の冒頭では、世界に関する13の質問が読者に投げかけられます。例えば「現在、低所得国に暮らす女子の何割が、初等教育を修了するでしょう?」といった問いです。驚くべきことに、これらの質問に対する世界中の人々の正答率は非常に低く、チンパンジーがランダムに答えた場合の正答率(約33%)よりも低いという結果が示されています。
つまり、私たちは世界について「無知」なのではなく、「誤った知識」を持っているのです。そして、その誤った認識を生み出す原因として、ロスリングさんは人間が持つ10の「本能」(認知バイアス)を挙げています。
この本は、出版後すぐに世界的なベストセラーとなりました。特に、マイクロソフト創業者のビル・ゲイツさんが「これまで読んだ本の中で最も重要な本の一冊」と絶賛し、2018年に大学を卒業した人のうち、希望者全員にこの本をプレゼントしたことでも話題になりました。
ビル・ゲイツさんも絶賛した理由
なぜビル・ゲイツさんはこの本をそこまで高く評価したのでしょうか。それは、この本が単なる「ポジティブ思考」を勧めるものではなく、データに基づいた冷静な世界観を提示しているからでしょう。
ゲイツさん自身も「タイム」誌のインタビューで「データを見ると世界は良くなっている」と述べており、ファクトフルネスの考え方に共感していることがうかがえます。彼は、テクノロジーの力で世界の問題を解決しようとする立場から、正確な現状認識の重要性を強く感じていたのでしょう。
また、本書が提唱する「ファクトフルネス」という考え方は、ビジネスの世界でも非常に重要です。感情や思い込みではなく、データに基づいた意思決定を行うことは、ビジネスリーダーにとって欠かせないスキルだからです。
10の本能とその克服法
ギャップ本能:世界を二分して考えてしまう傾向
ギャップ本能とは、世界を「先進国と途上国」「富裕層と貧困層」のように二つのグループに分けて考えてしまう傾向のことです。しかし、現実の世界はそれほど単純ではありません。
例えば、かつては「先進国」と「途上国」という二分法が一般的でしたが、現在の世界はもっと複雑です。ロスリングさんは世界を所得レベルによって4つのグループに分けて考えることを提案しています。レベル1(1日1ドル以下)、レベル2(1〜4ドル)、レベル3(4〜16ドル)、レベル4(16ドル以上)という区分です。
この視点で見ると、多くの国々がレベル2やレベル3に位置しており、単純な二分法では捉えられない世界の多様性が見えてきます。例えば、中国やブラジルといった国々は、もはや「途上国」というカテゴリーでは正確に表現できないのです。
ギャップ本能を克服するには、「大多数」に目を向けることが重要です。極端な例に目を奪われず、分布の全体像を見る習慣をつけましょう。また、平均値だけでなく、分布の幅にも注目することで、より正確な世界理解につながります。
ネガティビティ本能:悪いニュースに注目してしまう心理
ネガティビティ本能とは、良いニュースよりも悪いニュースに注目してしまう人間の性質です。メディアは視聴率や購読数を上げるために、しばしば悲惨なニュースを強調します。そして私たちの脳は、そうした否定的な情報に敏感に反応するようにできているのです。
例えば、「高齢者ドライバーによる事故が増えている」というニュースを見ると、私たちはそれが事実だと思い込みがちです。しかし、実際のデータを見ると、交通事故による死亡者数は年々減少しています。また、高齢者だけでなく、10〜20代のドライバーも同程度に事故を起こしやすいという事実もあります。
ネガティビティ本能を克服するには、良いニュースにも目を向ける意識的な努力が必要です。また、「悪い」と「良くなっている」は両立することを理解しましょう。現状は悪くても、以前よりは改善していることが多いのです。
さらに、メディアの報道には偏りがあることを認識し、常にデータで検証する習慣をつけることも大切です。
直線本能:直線的な成長を想定してしまう思考パターン
直線本能とは、変化が常に一定の速度で直線的に進むと考えてしまう傾向です。しかし、現実の多くの現象は、S字カーブや指数関数的な変化を示します。
例えば、新興国の経済成長は、初期段階では緩やかですが、ある時点から急速に加速し、その後再び緩やかになるS字カーブを描くことが多いです。また、技術の進歩は指数関数的に加速することがあります。
直線本能を克服するには、様々な曲線の形を理解し、データの傾向を見極める力を養うことが重要です。特に、指数関数的な成長は人間の直感では捉えにくいため、意識的に考える必要があります。
また、予測をする際には、単純な直線的予測ではなく、様々な可能性を考慮した複数のシナリオを検討することも有効です。
恐怖本能:危険を過大評価してしまう本能
恐怖本能とは、リスクを過大評価してしまう傾向です。人間の脳は、危険に対して敏感に反応するようにできています。これは、かつての狩猟採集時代には生存に役立ちましたが、現代社会では必ずしも合理的な判断につながりません。
例えば、多くの人が飛行機事故を恐れますが、統計的には自動車事故の方がはるかに危険です。また、テロや殺人といった暴力的な事件は大きく報道されますが、実際には世界の暴力による死亡率は減少傾向にあります。
恐怖本能を克服するには、リスクを冷静に計算する習慣をつけることが重要です。感情的な反応に流されず、実際のデータに基づいてリスクを評価しましょう。また、恐怖を煽るような報道に対しては、批判的な視点を持つことも大切です。
さらに、恐怖は私たちの注意を狭め、より大きな問題から目をそらさせることがあります。例えば、テロへの恐怖が、より多くの命を奪っている気候変動や貧困といった問題への対応を遅らせることがあるのです。
サイズ本能:単独の数字の重要性を誤解する傾向
サイズ本能とは、単独の数字を見て、その大きさだけで重要性を判断してしまう傾向です。しかし、数字は常に比較の文脈の中で理解する必要があります。
例えば、「昨年、この病気で1000人が死亡した」という情報だけでは、その重大性を正確に判断できません。人口10万人の小さな国での1000人と、人口10億人の大国での1000人では、意味が大きく異なります。
サイズ本能を克服するには、数字を常に比較の中で見る習慣をつけることが重要です。割合や率を使って考えたり、適切な分母を意識したりすることで、より正確な理解につながります。
また、大きな数字に圧倒されず、それを身近な単位に分解して考えることも有効です。例えば、国家予算のような巨大な数字は、一人当たりの金額に換算すると理解しやすくなります。
データで見る世界の真実
世界の貧困は実は減少している
「世界の貧困は増加している」と思っている人は多いかもしれませんが、実際のデータはそれを否定しています。極度の貧困(1日1.90ドル未満で生活する人々)の割合は、1800年には85%でしたが、1975年には50%、そして2017年には9%まで減少しました。
この劇的な改善は、グローバル化による経済成長、教育の普及、医療の進歩など、様々な要因によるものです。特に中国やインドといった人口大国での貧困削減が、世界全体の数字に大きく貢献しています。
もちろん、依然として約7億人が極度の貧困の中で生活しており、問題が解決したわけではありません。しかし、長期的なトレンドとしては確実に改善しているのです。
このような事実を知ることは、単に楽観的になるためではなく、何が効果的だったのかを学び、残された課題に取り組むためにも重要です。
教育と医療の驚くべき進歩
教育と医療の分野でも、世界は驚くべき進歩を遂げています。
教育に関しては、初等教育を修了する子どもの割合が大幅に増加しています。特に女子教育の普及は顕著で、低所得国においても現在では約60%の女子が初等教育を修了しています。これは、多くの人が想像する20%という数字をはるかに上回っています。
医療面では、5歳未満児の死亡率が劇的に減少しています。1800年には約44%の子どもが5歳の誕生日を迎える前に亡くなっていましたが、現在ではその割合は4%未満です。また、平均寿命も世界全体で大幅に延びており、1800年の約30歳から現在は約72歳になっています。
ワクチンの普及、抗生物質の発見、公衆衛生の改善など、様々な要因がこの進歩に貢献しています。特に、かつては「途上国」と呼ばれていた地域でも、基本的な医療サービスへのアクセスが大幅に改善されているのです。
これらの進歩は、人類の協力と知恵の結晶であり、将来に向けての希望を与えてくれます。
環境問題の実態と誤解
環境問題については、悲観的なニュースが多く報じられていますが、ここでも誤解が少なくありません。
確かに、気候変動や生物多様性の喪失など、深刻な環境問題が存在します。しかし、一方で多くの環境指標が改善していることも事実です。
例えば、大気汚染は先進国では大幅に改善しています。ロンドンのスモッグや日本の四日市ぜんそくなど、かつての深刻な公害問題は、適切な規制と技術革新によって解決されました。また、オゾン層の破壊についても、国際的な協力によってフロンガスの使用が規制され、オゾン層は回復傾向にあります。
さらに、再生可能エネルギーのコストが急速に低下し、普及が進んでいます。太陽光発電のコストは過去10年で約90%減少し、風力発電も大幅にコストダウンしています。
これらの事実は、環境問題を軽視してよいという意味ではありません。むしろ、人類が協力して取り組めば、環境問題も解決できるという希望を示しているのです。
ファクトフルネスの実践方法
日常生活での情報との向き合い方
ファクトフルネスを日常生活で実践するには、まず情報に接する際の姿勢を変えることが重要です。
ニュースやSNSの情報を鵜呑みにせず、「本当にそうなのか?」と疑問を持つ習慣をつけましょう。特に、感情を強く揺さぶるような情報には注意が必要です。そうした情報ほど、私たちの認知バイアスを刺激し、冷静な判断を妨げる可能性があります。
また、情報源の多様性も重要です。自分と同じ意見の情報ばかりに触れていると、確証バイアスに陥りやすくなります。意識的に異なる視点の情報にも触れることで、より balanced な世界観を持つことができます。
さらに、長期的な視点を持つことも大切です。日々のニュースは短期的な変動に焦点を当てがちですが、長期的なトレンドを見ることで、より正確な世界理解につながります。
メディアリテラシーの重要性
メディアリテラシーとは、メディアからの情報を批判的に読み解く能力のことです。ファクトフルネスを実践するうえで、このスキルは不可欠です。
メディアは中立ではありません。どのメディアも、意識的か無意識的かを問わず、特定の視点や価値観に基づいて情報を選択し、伝えています。また、視聴率や購読数を上げるために、センセーショナルなニュースを強調する傾向があります。
こうしたメディアの特性を理解したうえで、情報を批判的に読み解く姿勢が重要です。ニュースを見る際には、「なぜこのニュースが今報道されているのか」「何が報道されていないのか」を考えてみましょう。また、見出しだけでなく、記事の全文を読み、データの出典や調査方法にも注目することで、より正確な情報を得ることができます。
さらに、SNSの時代には、自分の考えに合う情報だけが表示される「フィルターバブル」の問題もあります。意識的に多様な情報源に触れ、異なる視点からの意見も取り入れることが、メディアリテラシーを高めるうえで欠かせません。
統計データの正しい読み方
統計データは、ファクトフルネスの実践において重要な道具ですが、その読み方には注意が必要です。
まず、数字を見る際には、単独の数値ではなく、比較の文脈で理解することが大切です。例えば、「この国の平均所得は3000ドルである」という情報だけでは、その国の豊かさを判断できません。他国との比較や、過去からの変化を見ることで、より正確な理解につながります。
また、平均値だけでなく、分布にも注目しましょう。例えば、平均所得が高くても、一部の富裕層が全体の数字を引き上げているだけかもしれません。中央値や分布の幅を見ることで、より実態に近い理解ができます。
さらに、グラフの軸の取り方にも注意が必要です。縦軸のスケールを操作することで、同じデータでも印象が大きく変わることがあります。グラフを見る際には、軸のスケールを確認する習慣をつけましょう。
ロスリングさんは、データを視覚化する際の工夫も多く行っています。特に、動くバブルチャートは、時間の経過とともに変化する複数の指標を同時に表現できる優れた方法です。こうした視覚化ツールを活用することで、複雑なデータも直感的に理解できるようになります。
残りの5つの本能
一般化本能:カテゴリーに当てはめて考えてしまう傾向
一般化本能とは、個々の事例をカテゴリーに当てはめて考えてしまう傾向です。カテゴリー化は情報処理を効率化するために必要ですが、過度の一般化は誤った認識につながります。
例えば、「アフリカ」という言葉を聞くと、多くの人は貧困や紛争といったネガティブなイメージを思い浮かべるかもしれません。しかし、アフリカ大陸には54の国があり、その経済状況や文化は実に多様です。ルワンダのように急速な経済成長を遂げている国もあれば、モーリシャスのように比較的豊かな観光立国もあります。
一般化本能を克服するには、カテゴリーの多様性を認識することが重要です。「典型的な例」に惑わされず、データの分布全体を見る習慣をつけましょう。また、例外に注目することで、自分の思い込みを修正する機会にもなります。
さらに、自分自身がどのようなカテゴリー化をしているかを意識することも大切です。無意識のうちに持っている偏見や固定観念に気づくことが、より正確な世界理解の第一歩となります。
運命本能:運命は変えられないと思い込む心理
運命本能とは、ある特性や状況が固定的で変えられないと考えてしまう傾向です。「この国は昔から貧しい」「あの民族は争いが絶えない」といった考え方は、この本能の表れです。
しかし、歴史を振り返ると、多くの国や地域が劇的に変化してきたことがわかります。例えば、韓国は1960年代には世界最貧国の一つでしたが、現在は先進国の仲間入りを果たしています。また、かつて「ヨーロッパの火薬庫」と呼ばれた西欧諸国は、第二次世界大戦後、EUという平和的な共同体を形成しました。
運命本能を克服するには、変化の可能性を認識することが重要です。「常に」「絶対に」「永遠に」といった言葉を使う際には注意が必要です。また、過去の成功事例に学び、変化のメカニズムを理解することも有効です。
さらに、自分自身の可能性についても同様です。「私はこういう性格だから」と思い込むのではなく、成長と変化の可能性を信じることが、より豊かな人生につながります。
単一視点本能:単一の視点でしか見ない問題
単一視点本能とは、複雑な問題を単一の視点や要因だけで理解しようとする傾向です。しかし、現実の多くの問題は、複数の要因が絡み合った複雑なシステムです。
例えば、貧困の問題を考える際、「教育の不足」だけに注目するのは単一視点的です。実際には、教育だけでなく、保健医療、インフラ、ガバナンス、国際貿易など、様々な要因が複雑に絡み合っています。
単一視点本能を克服するには、複数の専門家の意見を聞くことが有効です。異なる分野の専門家は、同じ問題でも異なる側面に注目します。また、「なぜ?」という問いを繰り返すことで、問題の根本原因に迫ることができます。
さらに、システム思考を身につけることも重要です。個々の要素だけでなく、要素間の相互作用や、時間の経過による変化にも注目することで、より深い理解につながります。
犯人捜し本能:誰かを責めたくなる心理
犯人捜し本能とは、何か悪いことが起きたとき、誰かを責めたくなる傾向です。責任者を特定することで、問題が理解できた気になり、安心感を得られるからです。
例えば、経済危機が起きると、政治家や銀行家など、特定の集団を非難する声が高まります。もちろん、彼らに責任がないわけではありませんが、複雑な経済システムの問題を個人の責任だけに帰するのは単純すぎます。
犯人捜し本能を克服するには、システムの問題に目を向けることが重要です。個人の行動は、その人が置かれたシステムや構造によって大きく影響されます。「誰が悪いのか」ではなく、「どのようなシステムがこの問題を生み出したのか」を考えることで、より建設的な解決策が見えてきます。
また、自分自身の失敗についても同様です。他人を責めるのではなく、システムの改善に目を向けることで、同じ失敗を繰り返さない仕組みを作ることができます。
焦り本能:即断即決したくなる衝動
焦り本能とは、緊急事態に直面したとき、即座に行動しなければならないと感じる傾向です。この本能は、火事や洪水などの緊急事態では命を救うこともありますが、複雑な社会問題に対しては、しばしば誤った判断につながります。
例えば、テロ攻撃の直後には、市民の自由を制限する法律が急いで制定されることがありますが、冷静に考えれば、そうした対応が本当に効果的かどうかは疑問です。
焦り本能を克服するには、「小さな一歩」の価値を認識することが重要です。大きな問題も、一度に解決しようとするのではなく、段階的に取り組むことで、より確実な成果が得られます。
また、決断を急がせようとする圧力に注意しましょう。「今すぐ決めないと手遅れになる」という言葉には、しばしば商業的な意図が隠れています。重要な決断ほど、十分な情報と時間をかけて検討する価値があります。
ロスリングさんの人生哲学
医師としての経験から学んだこと
ハンス・ロスリングさんは、医師としてのキャリアをスウェーデンで始め、その後アフリカのモザンビークで公衆衛生の改善に取り組みました。この経験は、彼の世界観に大きな影響を与えています。
モザンビークでの生活は決して楽ではありませんでした。内戦の混乱、限られた医療資源、言語の壁など、様々な困難に直面しました。しかし、そうした環境の中でも、ロスリングさんは現地の人々の知恵と強さに感銘を受けたといいます。
特に印象的だったのは、現地の伝統的な助産師たちとの協働です。当初、西洋医学の知識だけで現地の問題を解決しようとしていたロスリングさんでしたが、現地の知恵と西洋医学を組み合わせることで、より効果的な医療を提供できることに気づきました。
この経験から、ロスリングさんは「上から目線」の援助ではなく、現地の人々との対等なパートナーシップの重要性を学びました。また、データに基づいた冷静な判断の大切さも、医師としての経験から得た教訓です。
TED講演で伝えてきたメッセージ
ロスリングさんが世界的に知られるようになったのは、TEDでの講演がきっかけでした。彼の講演は、動くバブルチャートを使った視覚的なプレゼンテーションと、情熱的な語り口で多くの人々を魅了しました。
彼のTED講演で一貫して伝えられていたメッセージは、「データに基づいて世界を見れば、多くの指標が改善している」ということです。乳幼児死亡率の低下、平均寿命の延伸、極度の貧困の減少など、様々なデータが世界の改善を示しています。
しかし、ロスリングさんは単純な楽観主義者ではありませんでした。彼は「可能主義者(ポシビリスト)」を自称し、根拠のない楽観論も悲観論も避け、データに基づいた現実的な見方を提唱していました。
また、彼の講演の特徴は、ユーモアを交えた語り口にもありました。深刻なテーマでも、時折ジョークを挟むことで、聴衆の関心を引きつけ、メッセージを効果的に伝えていました。
最期まで取り組んだライフワーク
ロスリングさんは、2017年に膵臓がんで亡くなりましたが、最期まで「ファクトフルネス」の普及に取り組みました。彼は自分の余命が限られていることを知りながらも、この本の執筆を最優先し、息子のオーラさんと娘婿のアンナさんと共に作業を進めました。
彼のライフワークは、単に統計データを広めることではなく、人々の世界観を変えることでした。彼は、誤った世界観が不適切な政策や資源配分につながり、結果として多くの人々の生活に悪影響を及ぼすと考えていました。
特に、先進国の人々が途上国について持つステレオタイプ的な見方を変えることに力を注ぎました。「途上国」という一括りの概念自体が時代遅れであり、世界はもっと複雑で多様だということを、データを通じて示そうとしたのです。
ロスリングさんの遺志は、ガップマインダー財団によって引き継がれています。この財団は、誰もが使える無料の統計ツールを提供し、データに基づいた世界理解の普及に取り組んでいます。
感想・レビュー
目から鱗の統計データの数々
この本を読んで最も驚いたのは、私自身が世界について多くの誤解を持っていたことです。冒頭の13の質問に対する自分の回答を振り返ると、ほとんど間違っていました。特に、女子教育や極度の貧困の減少など、実際には大きく改善している指標について、私は悲観的な見方をしていたことに気づかされました。
ロスリングさんが提示する統計データは、まさに「目から鱗」の連続です。例えば、世界の平均寿命は1800年には約30歳でしたが、現在は72歳以上に延びています。また、極度の貧困層の割合は、1800年の85%から現在は9%まで減少しています。こうしたデータを見ると、人類の進歩の凄まじさを実感せずにはいられません。
特に印象的だったのは、「レベル4」の視点です。世界を所得レベルで4つに分けて考えるという発想は、単純ながら非常に効果的です。「先進国」と「途上国」という二分法では見えなかった世界の多様性と変化が、この視点を通すと鮮明に見えてきます。
思考の枠組みを変える体験
この本の真の価値は、単に事実を教えてくれることではなく、思考の枠組み自体を変えてくれることにあります。10の本能について学ぶことで、自分の思考パターンを客観的に見つめ直す機会が得られました。
特に「ネガティビティ本能」の説明は、私のメディア接触の仕方を見直すきっかけになりました。悪いニュースに引きつけられるのは人間の自然な傾向ですが、それによって世界の全体像を見誤ってはいけないと気づかされたのです。
また、「直線本能」についての説明も目からウロコでした。変化は必ずしも直線的ではなく、S字カーブや指数関数的な変化をすることが多いという指摘は、将来予測を考える上で非常に重要な視点です。
この本を読んだ後、ニュースを見る目が変わりました。「この報道は10の本能のどれを刺激しているだろう?」と考えながら情報に接することで、より冷静な判断ができるようになった気がします。
現代社会を生きる知恵としての価値
「ファクトフルネス」の教えは、単なる知識以上の、現代社会を生きる上での実践的な知恵としての価値があります。情報過多の時代に、何を信じ、どう判断するかは、私たちの日常生活に直結する問題だからです。
特に、SNSやインターネットの普及により、誤った情報や偏った見方が瞬時に広がる現代では、ファクトフルな思考法はますます重要になっています。「いいね」を集めやすい刺激的な情報ではなく、地道なファクトチェックに基づいた判断をする習慣は、デジタル社会を健全に生きるための必須スキルと言えるでしょう。
また、ビジネスの世界でも、ファクトフルネスの考え方は非常に有用です。市場調査や戦略立案において、自分たちの思い込みやバイアスに気づき、データに基づいた冷静な判断をすることは、成功への近道となるはずです。
ロスリングさんの「可能主義者」という立場も、現代を生きる上での賢明な姿勢だと感じました。根拠のない楽観論や悲観論に流されず、データに基づいて現実的に考え、行動する——そんな姿勢が、複雑な問題が山積する現代社会では特に求められている——そんな姿勢が、複雑な問題が山積する現代社会では特に求められているのではないでしょうか。
「ファクトフルネス」は単なる知識の本ではなく、私たちの思考の枠組みを根本から変える可能性を秘めています。世界を正しく見るという行為は、より良い未来を創るための第一歩なのです。ロスリングさんが遺した知恵は、これからの時代を生きる私たち全員への貴重な贈り物だと感じずにはいられません。
まとめ
ハンス・ロスリングさんの「FACTFULNESS」は、私たちが無意識のうちに持っている10の思い込みを指摘し、データに基づいて世界を正しく見る習慣の大切さを説いた一冊です。世界は思っているよりもずっと良くなっており、極度の貧困や乳幼児死亡率、識字率など、多くの指標が改善していることが、豊富なデータで示されています。
この本の真の価値は、単に事実を教えてくれることではなく、私たちの思考の枠組み自体を変えてくれることにあります。ネガティビティ本能や直線本能など、10の本能について学ぶことで、自分の思考パターンを客観的に見つめ直す機会が得られます。
ロスリングさんが提唱する「ファクトフルネス」という考え方は、情報過多の現代社会を生きる上での実践的な知恵として、これからますます重要になっていくでしょう。データに基づいた冷静な判断ができる「可能主義者」として世界と向き合うことが、より良い未来を創るための第一歩なのです。