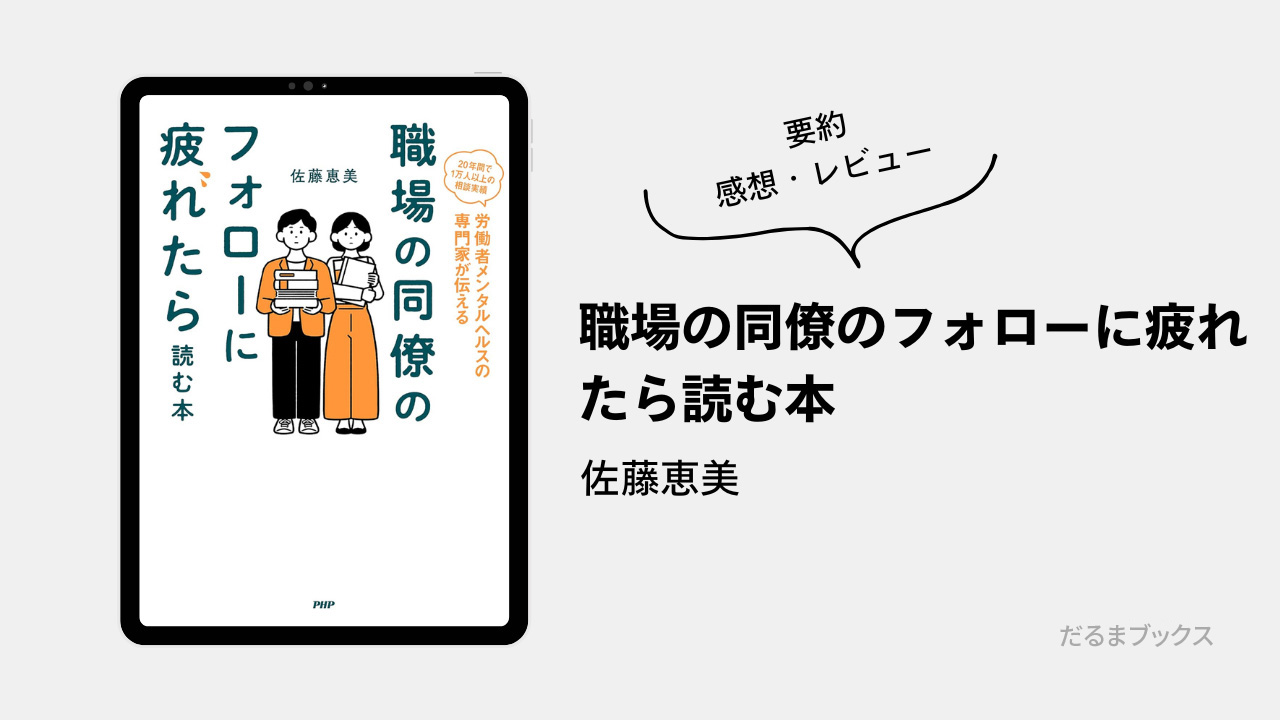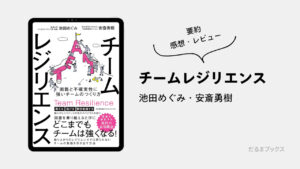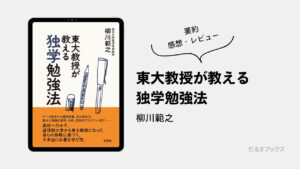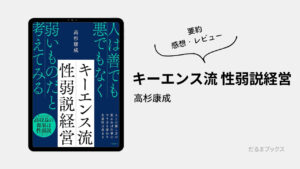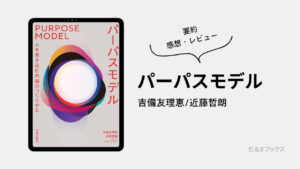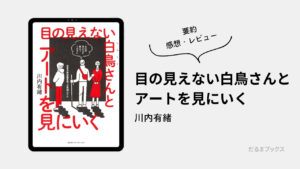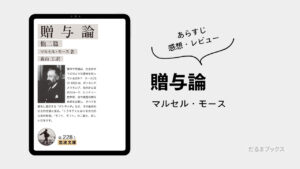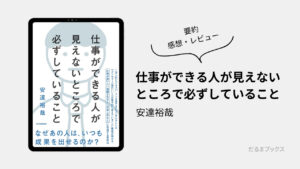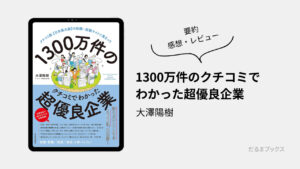現代の職場では、人手不足や業務の複雑化により、同僚のフォローに疲れてしまう人が増えています。特に「面倒見がいい人」ほど、知らず知らずのうちに心身の疲労を蓄積させてしまいがち。
佐藤恵美さんの新刊『職場の同僚のフォローに疲れたら読む本』は、20年間で1万人以上の相談実績を持つ労働者メンタルヘルスの専門家による、職場でのフォロー疲れを軽減するための実践的なアドバイスが詰まった一冊です。
本書の概要と著者紹介
労働者メンタルヘルスの専門家・佐藤恵美さんとは
佐藤恵美さんは、精神保健福祉士、公認心理師、キャリアコンサルタント、臨床発達心理士という多彩な肩書を持つ、労働者メンタルヘルスの専門家です。1970年生まれの東京都出身で、北里大学大学院医療系研究科産業精神保健学を修了し、医科学修士の学位を取得されています。
埼玉県内の精神科単科病院医療相談室での勤務を経て、東京都内の医療法人社団弘冨会神田東クリニック副院長、同法人MPSセンター副センター長を務められました。2020年には「メンタルサポート&コンサル沖縄」を設立し、現在は沖縄に在住しながら、県内外の企業や官公庁に対してさまざまなメンタルヘルスサービスを提供。年間500人以上にカウンセリングを行っています。
著書には『もし部下が発達障害だったら』『「判断するのが怖い」あなたへ』(いずれもディスカヴァー携書)、『ストレスマネジメント入門』(共著、日経文庫)などがあり、日本産業精神保健学会理事も務めるなど、第一線で活躍されています。
1万人以上の相談実績から生まれた一冊
本書は、佐藤さんが20年間で1万人以上の働く人の相談に乗ってきた経験から生まれました。その膨大な実績の中から「これは効果がある」と実感している方法を厳選して紹介しています。
現代の職場では、人手不足や業務の複雑化により、同僚のフォローに疲れてしまう人が増えています。本書の目的は、そんな「職場の同僚のフォローに疲れているあなたのしんどさを軽くすること」。余裕のない職場環境の中でも、つぶれずに生き抜くための技術が詰まっています。
佐藤さんは本書の中で、「職場における仕事のやり方や仕組みなど、自分の『外側』に働きかける」ことと、「人のフォローがしんどくなる背景を知って、自分の『内側』を変える」ことの2つのアプローチを提案しています。特に後者の「内側」への働きかけに重点を置いているのが本書の特徴です。
職場の「名もなきフォロー」とは何か
増え続ける「フォロー疲れ」の現状
現代の職場では、「フォロー疲れ」に悩む人が急増しています。佐藤さんが挙げる典型的な例としては、「人はどんどん減るのに、やることは次々と増える職場」「なんの意味があるの?と感じてしまう不毛な作業」「なかなか仕事を覚えられない不器用な若手の指導」「朝、急に休む連絡をしてきた子育て中の同僚のフォロー」「言い訳ばかりで考えを変えない先輩とのやりとり」「いつも仕事を丸投げしてくる上司のお膳立て」などがあります。
これらは公式の業務分掌表には載っていない「名もなきフォロー」とも言えるもので、実際の業務量や精神的負担は想像以上に大きいものです。しかも、こうした「フォロー」は評価されにくく、やればやるほど当たり前のことと見なされがちです。
特に「面倒見がいい」と周囲から思われているタイプの人は、よく気がついて、見過ごせず、ついがんばりすぎてしまう傾向があります。そうした人ほど、知らず知らずのうちに心身の疲労を蓄積させてしまうのです。
産業構造の変化と人手不足が生み出す問題
フォロー疲れが増加している背景には、日本の産業構造の変化と慢性的な人手不足があります。少子高齢化による労働人口の減少、働き方改革による労働時間の制限、そして多様な働き方の浸透により、職場の人員配置は常に綱渡り状態です。
かつての日本企業では、ある程度の余剰人員を抱えることで、突発的な事態にも対応できる体制を維持していました。しかし、グローバル競争の激化や株主重視の経営スタイルへの移行により、そうした「余裕」は失われつつあります。
結果として、一人一人の負担は増加し、誰かが休んだり、業務のペースが落ちたりすると、それをカバーするために他のメンバーが「フォロー」に追われる構図が生まれています。こうした状況は、今後も続いていくことが予測される時代の潮流だと佐藤さんは指摘しています。
フォローする立場のメンタルが危ない理由
休職ドミノの恐怖
佐藤さんは、フォローする側の人間のメンタルヘルスが悪化すると、職場全体に深刻な影響を及ぼす可能性があると警鐘を鳴らしています。特に危険なのが「休職ドミノ」と呼ばれる現象です。
これは、まず一人が体調を崩して休職すると、その人の仕事を引き継いだ人が過重労働によって疲弊し、次に休職してしまう。さらにその人の仕事を引き継いだ別の人も倒れる…という連鎖反応が起きることを指します。
特に現代の職場は人員に余裕がないため、一人が抜けるだけでも残りのメンバーへの負担は大きく増加します。そこにさらに二人目、三人目と休職者が出ると、職場機能が著しく低下し、最悪の場合、部署や組織全体が機能不全に陥ることもあります。
佐藤さんは、こうした事態を防ぐためにも、フォローする側の人間が自分自身のメンタルヘルスケアを怠らないことが重要だと強調しています。
「1人抜けたらアウト」のギリギリ職場
現代の多くの職場は「1人抜けたらアウト」という危うい均衡の上に成り立っています。業務効率化や人件費削減の名目で人員が最小限に抑えられた結果、一人でも欠けると途端に崩れ去るような脆弱な体制になっているのです。
こうした職場では、誰かが休むと即座に他のメンバーがその穴を埋めなければならず、そのフォローの負担は想像以上に大きなものとなります。特に「できる人」「責任感の強い人」ほど、フォロー業務を引き受けがちで、その結果、過重な負担を背負い込んでしまいます。
佐藤さんは、このような状況下では、自分自身の限界を見極め、必要に応じて「NO」と言える勇気も必要だと説きます。すべてを引き受けようとすれば、最終的には自分自身が倒れてしまい、結果として誰も助けられなくなってしまうからです。
なぜ人のフォローが嫌になるのか
終わりが見えないフォローの心理的負担
人のフォローが特に辛く感じられる理由の一つに、「終わりが見えない」という不確実性があります。例えば、新人の育成であれば、いつかは一人前になって自立してくれるという希望があります。しかし、慢性的な人手不足や組織の構造的問題によるフォローは、いつまで続くのか見通しが立たないことが多いのです。
佐藤さんによれば、人間は「いつまで続くのか分からない苦痛」に対して特に強いストレスを感じる生き物だと言います。終わりの見えない負担は、心理的な消耗感を倍増させるのです。
また、フォローする側は往々にして「自分がやらなければ誰もやらない」という責任感から、無理をして引き受けてしまいがちです。しかし、そうした状況が長期化すると、次第に「なぜ自分ばかりが」という不公平感が募り、やがて強い不満やバーンアウト(燃え尽き症候群)につながっていきます。
認識のズレが生む軋轢
フォローする側とされる側の間には、しばしば認識のズレが生じます。フォローする側は「こんなに大変な思いをして助けているのに」と感じる一方、フォローされる側は「自分は当然の権利として助けてもらっている」と考えていることがあります。
このズレは、特に世代間や価値観の違いによって拡大します。例えば、ワークライフバランスを重視する若手社員と、仕事一筋で生きてきた年配社員の間では、「仕事への取り組み方」に関する基本的な考え方が異なることが少なくありません。
佐藤さんは、こうした認識のズレを放置すると、フォローする側の不満が蓄積され、やがて爆発してしまう危険性があると警告しています。問題解決のためには、まず互いの認識の違いを理解し、コミュニケーションを通じて歩み寄ることが重要だと説いています。
自分の疲れには気づきにくい
疲労のサインを見逃さないために
私たちは自分自身の疲労に気づきにくいものです。特に「面倒見がいい人」「責任感の強い人」ほど、自分の限界を超えても頑張り続ける傾向があります。佐藤さんは、自分の疲れに早めに気づくことが、メンタルヘルスを守る上で非常に重要だと強調しています。
疲労のサインとしては、「イライラしやすくなる」「集中力が続かない」「些細なことで感情的になる」「睡眠の質が低下する」「食欲の変化」「頭痛や肩こりなどの身体症状」などがあります。これらのサインが現れたら、それは体と心からの「休息を求めるSOSサイン」だと受け止めるべきです。
佐藤さんは、こうした疲労のサインを客観的に把握するための方法として、日々の体調や気分の変化を記録することを勧めています。例えば、朝起きた時の気分を10点満点で評価し、それを継続的に記録することで、自分の調子の波を可視化することができます。
「面倒見がいい人」が陥りやすい罠
「面倒見がいい人」は、他者からの期待や評価に敏感な傾向があります。「頼りにされることで自己価値を確認している」という心理が働いているため、断ることに強い抵抗感を持ちます。
こうした人は、他者からの「ありがとう」や「助かった」という言葉に喜びを感じ、それが行動の原動力になっています。しかし、それが行き過ぎると、自分の限界を超えてまで他者のニーズに応えようとしてしまいます。
佐藤さんは、「面倒見がいい人」が陥りやすい罠として、以下のような思考パターンを挙げています。「断ると嫌われるのではないか」「自分がやらなければ誰もやらない」「人に頼るのは迷惑をかけることだ」「完璧にやらなければならない」などです。
これらの思考パターンに気づき、適切に対処することが、自分自身を守りながら他者との健全な関係を築く鍵となります。佐藤さんは、自分の限界を認識し、時には「NO」と言える勇気も必要だと説いています。
自分にエネルギーを補充する方法
睡眠の質を高める具体的テクニック
佐藤さんは、心のエネルギーを回復させる最も基本的かつ効果的な方法として、質の良い睡眠を挙げています。脳と体を休ませるためには、何よりも睡眠が重要なのです。
ある研究によれば、6時間以下の睡眠を1〜2週間続けると、日中の認知能力が著しく低下し、まるでワインを2〜3杯飲んだのと同じくらいの思考力しか保てなくなるとのこと。そうなると、人のフォローをする場面でも、相手の状態を適切に把握し、自分の感情をコントロールしながら対応することが難しくなります。
佐藤さんは、質の良い睡眠のための具体的なテクニックとして、以下のようなものを紹介しています。
まず、就寝前のルーティンを確立すること。例えば、寝る1時間前からはスマホやパソコンの使用を控え、温かいお風呂に入る、ストレッチをする、リラックスできる音楽を聴くなど、体と心を睡眠モードに切り替えるための儀式を作ります。
また、寝室の環境を整えることも重要です。適切な温度(18〜23度程度)、湿度(40〜60%程度)、静かさ、暗さを確保し、快適な寝具を用意することで、睡眠の質は大きく向上します。
さらに、カフェインやアルコールの摂取にも注意が必要です。カフェインは摂取後6時間以上も体内に残るため、午後以降は控えめにすべきです。また、アルコールは入眠を助けるように感じられますが、実は睡眠の質を低下させ、夜中の覚醒を引き起こす原因となります。
パワーナップで脳を効率的に休める方法
適切な睡眠時間を確保できない日々が続く場合、佐藤さんが推奨するのが「パワーナップ」と呼ばれる短時間の昼寝です。これは英語の「nap(昼寝)」と「power up(パワーアップする)」を組み合わせた造語で、文字通り、エネルギーをチャージしてパワーアップするための昼寝を意味します。
パワーナップの理想的な時間は15〜30分程度。これは深い睡眠に入る前の浅い睡眠状態で休息を取ることで、起きた後の睡眠慣性(だるさや頭の重さ)を最小限に抑えながら、脳を効率よく休めることができます。
実践方法としては、昼休みなどの時間を利用して、椅子にもたれかかったり、デスクに伏せたりして目を閉じるだけでも効果があります。その際、アイマスクをしたり、イヤホンで外の音を遮断したりすると、より効果的です。
ただし、午後3時以降にパワーナップを取ると、夜間の睡眠の妨げになる可能性があるため、できるだけ昼から午後2時頃までの間に行うことが望ましいでしょう。また、30分以上の昼寝は深い睡眠に入ってしまうため、起きた後にかえって疲労感を感じることがあります。
佐藤さんは、パワーナップを日常的に取り入れることで、午後の集中力低下を防ぎ、人のフォローに必要な精神的エネルギーを維持できると説明しています。特に、人のフォローが多い日や、重要な会議やプレゼンテーションがある日には、積極的にパワーナップを取り入れることを推奨しています。
疲れきらない技術を身につける
休憩効果を最大化する方法
佐藤さんによれば、休憩の取り方にも技術があります。ただ漫然と時間を過ごすのではなく、効果的な休憩方法を知ることで、短時間でも高い回復効果を得ることができるのです。
まず重要なのは、「完全に仕事から離れる」ということ。休憩時間中にメールをチェックしたり、仕事の話をしたりすると、脳は休息モードに入れません。スマホを見る代わりに、窓の外を眺めたり、深呼吸をしたりするだけでも、脳の回復効果は大きく異なります。
また、休憩の頻度も重要です。長時間集中して働き続けるよりも、短い休憩を定期的に取る方が効果的だと言われています。例えば、「ポモドーロ・テクニック」と呼ばれる時間管理法では、25分の集中作業と5分の休憩を繰り返すことで、高い生産性を維持することができます。
さらに、休憩中の活動内容も重要です。スマホでSNSをチェックするような「受動的休憩」よりも、軽いストレッチや短い散歩などの「能動的休憩」の方が、脳と体の回復効果が高いことが研究で示されています。特に自然の中で過ごす時間は、ストレスホルモンの低下や集中力の回復に効果的です。
佐藤さんは、「休憩は贅沢ではなく、生産性を維持するための必要な投資」だと強調しています。適切な休憩を取ることで、フォロー業務に必要な忍耐力や共感力を維持することができるのです。
職場で人目を避けて休める場所の見つけ方
職場で適切に休息を取ることは、理想的ではありますが、現実には難しいことも多いでしょう。特に「休んでいる姿を見られたくない」という心理が働くことも少なくありません。佐藤さんは、そんな状況でも効果的に休息を取るための工夫を紹介しています。
まず、会社の中で「人目につかない場所」を見つけることが大切です。例えば、あまり使われていない会議室、図書スペース、休憩室の隅、非常階段の踊り場などが候補になります。事前にそうした場所をリストアップしておくと、必要な時にすぐに移動できます。
また、「休憩しているように見えない休憩方法」も有効です。例えば、資料を持って移動するふりをして、実は少し遠回りして気分転換するといった方法です。あるいは、トイレに行くついでに、洗面所で深呼吸をしたり、顔を洗ったりするのも効果的です。
さらに、「仕事の合間の小さな儀式」を作ることも推奨しています。例えば、お気に入りのハーブティーを一杯飲む時間、窓の外を3分間眺める時間、好きな音楽を一曲だけ聴く時間など、短くても自分だけの特別な時間を作ることで、心理的な回復効果が得られます。
佐藤さんは、「休息は隠れてするものではない」という考え方が理想的ではあるものの、現実の職場環境では難しいことも多いと認めています。そのような状況では、こうした工夫を取り入れながら、自分なりの休息方法を確立することが大切だと説いています。
職場と自分の関係を見直す
自分の「外側」と「内側」への働きかけ
佐藤さんは、職場でのフォロー疲れを解消するためには、「外側」と「内側」の両方からのアプローチが必要だと説きます。
「外側」への働きかけとは、職場環境や仕事の仕組みなど、自分を取り巻く環境に対する働きかけを指します。例えば、業務の優先順位を明確にする、無駄な会議や報告書を減らす、業務の標準化やマニュアル化を進める、必要に応じて人員増強を上司に相談するなどが挙げられます。
一方、「内側」への働きかけとは、自分自身の考え方や感じ方を見直すことです。例えば、完璧主義を手放す、「NO」と言える勇気を持つ、自分の限界を認識する、他者からの評価に過度に依存しないなどが含まれます。
佐藤さんによれば、多くの人は「外側」の変化ばかりに目を向けがちですが、実は「内側」の変化の方が、より大きな効果をもたらすことが多いと言います。なぜなら、外部環境の変化には限界がありますが、自分自身の捉え方や反応の仕方は自分でコントロールできるからです。
例えば、同じフォロー業務でも、「また余計な仕事が増えた」と捉えるか、「自分のスキルアップの機会だ」と捉えるかで、感じるストレスの度合いは大きく変わります。また、「完璧にやらなければならない」という思い込みを「ある程度できればいい」に変えるだけでも、心理的な負担は軽減されます。
佐藤さんは、外側と内側の両方にバランスよく働きかけることで、職場でのフォロー疲れを効果的に軽減できると説いています。
つぶれずに生き抜くための技術
佐藤さんは、現代の余裕のない職場環境の中でつぶれずに生き抜くための具体的な技術として、以下のようなものを紹介しています。
まず、「境界線を引く勇気」を持つことが重要です。自分の仕事とそうでないものの境界線、自分の責任範囲と他者の責任範囲の境界線を明確にし、必要に応じて「ここまでは引き受けられるが、それ以上は難しい」と伝える勇気が必要です。
次に、「自分の価値観を大切にする」ことも重要です。周囲の期待や評価に振り回されるのではなく、自分が本当に大切にしたいものは何かを見極め、それに基づいて行動することで、心の安定を保つことができます。
また、「小さな成功体験を積み重ねる」ことも効果的です。大きな目標だけを見つめると挫折感を味わいやすいですが、日々の小さな成功体験を意識的に作り、それを喜ぶ習慣をつけることで、自己効力感を高めることができます。
さらに、「助けを求める勇気」も必要です。一人で抱え込まず、適切なタイミングで上司や同僚、場合によっては専門家に助けを求めることは、決して弱さではなく、むしろ賢明な選択だと佐藤さんは強調します。
最後に、「自分を許す」という姿勢も大切です。完璧を求めすぎず、時には失敗することも、疲れることも、休むことも自分に許すことで、長期的に心身の健康を維持することができます。
佐藤さんは、これらの技術を身につけることで、どんな職場環境でも自分らしく、健康に働き続けることができると説いています。そして、それは決して「諦め」や「妥協」ではなく、むしろ自分自身を大切にするための積極的な選択だと強調しています。
感想・レビュー
現代の職場環境を映し出す鏡
この本を読んで最も印象的だったのは、佐藤さんが描き出す現代の職場の姿が、あまりにもリアルだということです。人手不足、業務の複雑化、評価制度の矛盾、世代間ギャップ…これらの要素が絡み合って生み出される「フォロー疲れ」という現象は、多くの働く人が日々感じているものの、なかなか言語化できていなかった問題ではないでしょうか。
佐藤さんは、この問題を単なる個人の能力や性格の問題として片付けるのではなく、社会構造や組織の在り方にまで視野を広げて分析しています。それでいて、「だから仕方がない」と諦めるのではなく、その中でも自分を守りながら生き抜くための具体的な方法を示してくれているのが素晴らしいと感じました。
特に印象的だったのは、「名もなきフォロー」という概念です。業務分掌表には載っていないけれど、実際には多くの時間と労力を費やしている「見えない仕事」の存在を明確に指摘したことで、多くの読者は「そうそう、これのことだったんだ!」と膝を打つことでしょう。
実践的なアドバイスの数々
本書の最大の魅力は、理論や分析だけでなく、すぐに実践できる具体的なアドバイスが満載されていることです。佐藤さんの20年にわたる相談実績から生まれた知恵は、どれも現実的で、しかも効果が期待できるものばかりです。
例えば、パワーナップの取り方、効果的な休憩方法、職場で人目を避けて休める場所の見つけ方など、日常の中ですぐに取り入れられるテクニックが豊富に紹介されています。これらは小さな工夫ですが、積み重ねることで大きな違いを生み出すことでしょう。
また、「自分の外側と内側への働きかけ」という考え方も非常に実践的です。環境を変えることだけに焦点を当てるのではなく、自分自身の捉え方や反応の仕方を見直すという視点は、どんな状況でも応用できる普遍的な知恵だと感じました。
佐藤さんの文章は、専門家らしい的確さと、同時に読者に寄り添うような温かみを兼ね備えています。読んでいると、まるで経験豊かな先輩や信頼できるカウンセラーと対話しているような安心感があります。
まとめ
『職場の同僚のフォローに疲れたら読む本』は、現代の職場で多くの人が抱える「フォロー疲れ」という問題に正面から向き合い、その解決策を提示した貴重な一冊です。佐藤恵美さんの20年にわたる相談実績から生まれた知恵は、理論的な裏付けと実践的な有用性を兼ね備えています。
本書を読むことで、なぜ人のフォローがこれほど疲れるのか、自分の疲れにはなぜ気づきにくいのか、そして何より、どうすれば疲れを軽減し、自分を守りながら働き続けることができるのかが理解できるでしょう。
余裕のない時代だからこそ、自分自身を大切にする技術を身につけることが重要です。この本は、そのための具体的な道筋を示してくれる、働く全ての人にとっての心強い味方となることでしょう。