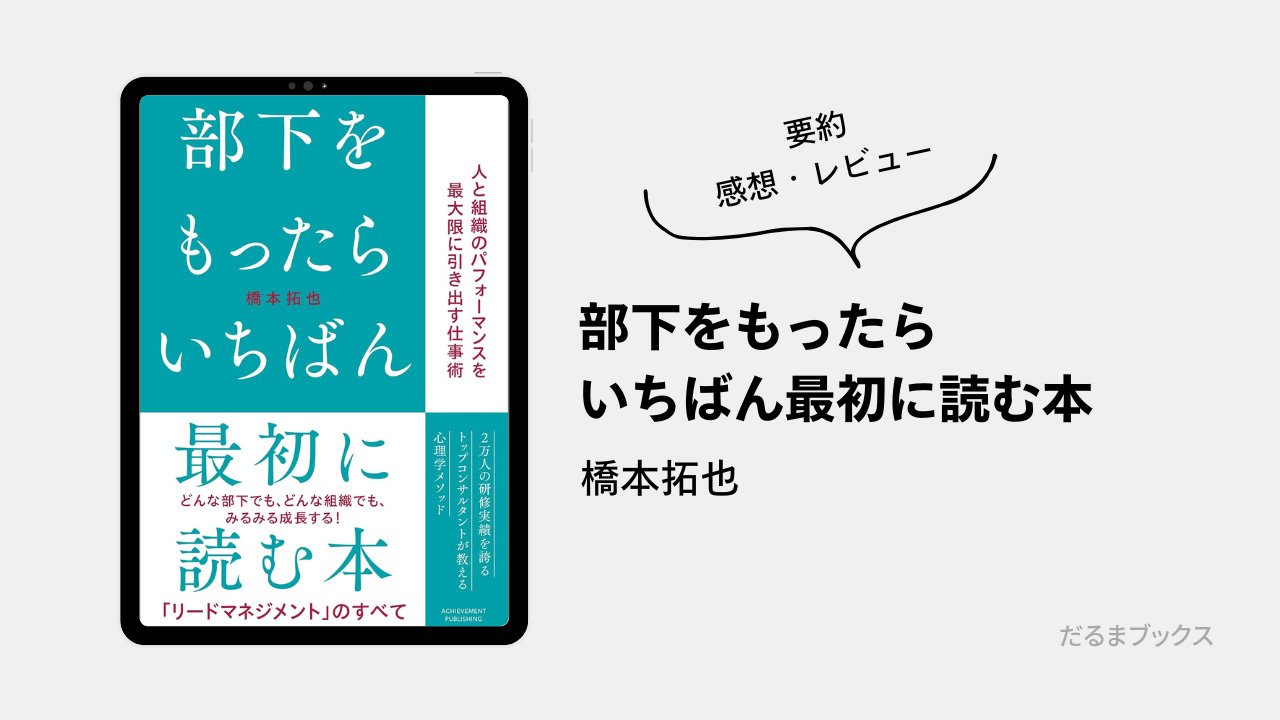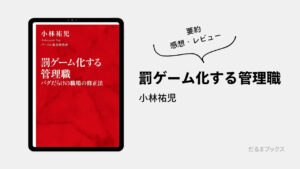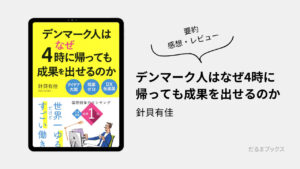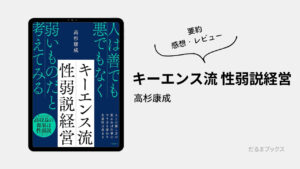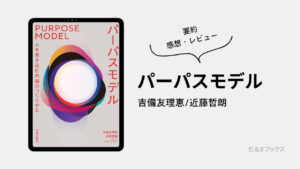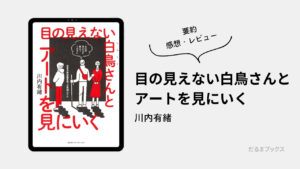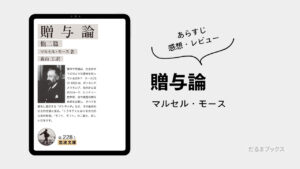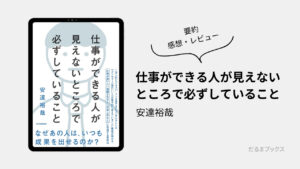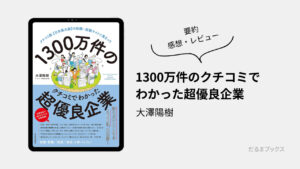会社で初めて部下を持つ立場になったとき、多くの人が戸惑いを感じるでしょう。
プレイヤーとして優秀だった人が、必ずしも優れたマネジャーになれるとは限りません。
橋本拓也さんの「部下をもったらいちばん最初に読む本」は、マネジメントを「技術」として捉え、好業績と良好な人間関係の両立を目指す一冊です。
本書は2025年のビジネス書グランプリで、総合グランプリとマネジメント部門1位を獲得した注目の一冊でもあります。
「部下をもったらいちばん最初に読む本」の基本情報
この本は、その名の通り初めて部下を持つ立場になった人向けの指南書。
しかし、中堅のマネジャーが自身のマネジメントを振り返る意味でも十分に参考になる内容となっています。
本書の最大の特徴は、マネジメントを
「センスや経験に頼るものではなく、学べば誰でも身につけられる技術である」
とし、多くの人が難しいと感じるマネジメントを、具体的な方法を提示して解消してくれます。
本書は、2024年9月6日にアチーブメント出版から刊行。
出版後すぐにAmazonランキングで、
- 実践経営・リーダーシップ管理
- 経営学
- 企業・経営
の3部門で1位を獲得!
紀伊国屋書店をはじめとする全国5書店でもランキング1位を獲得するなど、大きな反響を呼んでいます。
さらに、2025年のビジネス書グランプリでは総合グランプリとマネジメント部門1位という栄誉に輝き、増刷も決定。
橋本拓也さんのプロフィール
橋本拓也さんは、アチーブメント株式会社の取締役営業本部長であり、トレーナーとしても活躍されています。
千葉大学を卒業後、2006年にアチーブメント株式会社に入社。入社1年目という早い段階で新規事業の責任者に抜擢され、家庭教師派遣事業を立ち上げましたが、5年後にその事業は閉鎖されています。
2008年からメンバーマネジメントに携わるようになりましたが、異動や退職が多く、ご自身の言葉を借りれば「7年間マネジメントの無免許運転期間」を過ごしたそうです。
その後、世界60か国以上で学ばれている「選択理論心理学」を土台にしたマネジメント手法に取り組み始めたことで、マネジメントのあり方が劇的に変化。
メンバーと組織の飛躍的な成長を実現し、2021年には新卒初の執行役員、2022年には取締役に就任されました。
現在は130人以上のメンバーマネジメントに携わり、2023年に開講したマネジメント講座は1年でシリーズ累計1000人以上が受講。
また、企業経営者や管理職、ビジネスパーソンらが年間1.8万人以上受講するセミナー「頂点への道」講座シリーズのメイン講師を務めるなど、これまでに研修を担当した受講生は2万人に上るという実績の持ち主です。
本書の全体像
初めて部下を持つ人向けの指南書
本書は、プレイヤーからマネジャーへと役割が変わったばかりの人々を主な対象としています。優秀なプレイヤーがマネジャーとして抜擢されることは、ビジネスの世界では珍しくありません。しかし、プレイヤーとして求められるスキルとマネジャーとして求められるスキルは大きく異なります。
橋本さんは自身の経験から、マネジャーになったときに「我流で教えてしまう」ことが、多くの問題の原因になると指摘しています。伝えたことをメンバーが実行できず成果が出せないことで、マネジャーとメンバーの人間関係がギクシャクし、どんどん悪化してしまうという悪循環に陥りがちです。
本書では、そうした「マネジメントの無免許運転」から脱却し、組織パフォーマンスを最大化させるための具体的な方法が示されています。
7つの基本原則
本書で提唱されている「リードマネジメント」は、以下の7つの基本原則に基づいています。
第一に、「マネジメントは技術である」という認識です。マネジメントはセンスや才能ではなく、学習と実践によって誰でも習得できる技術だと位置づけています。
第二に、「部下を変えることはできないが、部下自身は変わることができる」という前提です。他者の行動を直接コントロールすることはできませんが、部下が自ら変わりたいと思うような環境や関係性を構築することはできます。
第三に、「信頼関係の構築が最優先」という原則です。部下との信頼関係なくして、効果的なマネジメントは成り立ちません。
第四に、「個人の成長支援」の重要性です。部下一人ひとりの成長を支援することが、チーム全体の成果向上につながります。
第五に、「水質管理」の必要性です。組織の「水質」、つまり組織文化や雰囲気を良好に保つことが、メンバーのパフォーマンスに大きく影響します。
第六に、「委任する技術」の習得です。適切に仕事を委任することで、マネジャー自身の仕事の質と量を管理し、メンバーの成長も促進できます。
第七に、「仕組み化する技術」の活用です。好業績と良好な人間関係を両立させるためには、効果的な仕組みづくりが欠かせません。
これらの原則に基づき、本書では具体的なマネジメント技術が体系的に解説されています。
第1章:部下との信頼関係構築の基本
初対面で信頼を勝ち取る方法
部下との関係において、最も重要なのは信頼関係の構築です。橋本さんは、初対面の段階から信頼関係を築くための具体的な方法を提示しています。
まず重要なのは、「マネージャーとチームメンバーの関係性は、バスの運転手と乗客に似ている」という考え方です。チーム・組織をバスとするなら、マネージャーは運転手、メンバーは乗客です。運転手である以上、どこへ向かうのか、どのルートで進むのかを明確に示す必要があります。
初対面の場では、自己紹介の仕方一つで印象が大きく変わります。単なる経歴や役職の紹介ではなく、「なぜその仕事をしているのか」「どのような価値観を持っているのか」を伝えることで、人間としての共感を得やすくなります。また、相手の話に真摯に耳を傾け、質問を通じて関心を示すことも、信頼構築の第一歩となります。
コミュニケーションの基本姿勢
信頼関係を築くためのコミュニケーションの基本姿勢として、橋本さんは「リードマネジメント」の考え方を提唱しています。これは、部下の内発的変化を手助けする手法で、他者が行動を直接選択させることはできないという前提に立っています。
具体的には、指示や命令ではなく、質問を通じて部下自身が考える機会を提供することが重要です。「どうすればいいと思う?」「あなたならどうする?」といった問いかけを通じて、部下の主体性を引き出します。
また、一方的に話すのではなく、「聴く」ことに重点を置いたコミュニケーションを心がけることも大切です。部下の話を遮らず、最後まで聞き、理解しようとする姿勢が、信頼関係の構築につながります。
信頼関係を深める日常の習慣
信頼関係は一朝一夕で築けるものではありません。日々の小さな積み重ねが、やがて強固な信頼関係へと発展していきます。
橋本さんは、約束を守ることの重要性を強調しています。どんなに小さな約束でも必ず守り、もし守れない場合は事前に連絡して謝罪するという基本的な姿勢が、信頼の基盤となります。
また、定期的な1on1ミーティングの実施も推奨しています。業務の進捗確認だけでなく、部下の考えや感情を理解する機会として活用することで、より深い信頼関係を築くことができます。
さらに、部下の成功や努力を認め、適切に評価することも重要です。具体的な行動や成果を指摘して褒めることで、部下は自分が見られていると感じ、信頼感が高まります。
第2章:仕事の教え方・伝え方
指示の出し方の基本
仕事の指示を出す際、多くのマネジャーが陥りがちな罠があります。それは、「自分にとって当たり前のことは、部下にとっても当たり前」と思い込んでしまうことです。橋本さんは、この思い込みを捨て、明確で具体的な指示を出すことの重要性を説いています。
効果的な指示の出し方として、以下のポイントが挙げられています。まず、「何のために」その仕事をするのかという目的を明確に伝えること。次に、「いつまでに」「どのレベルで」完了させるべきかという期待値を具体的に示すこと。そして、「どのように」進めるべきかという方法についても、部下の経験や能力に応じて詳細に伝えることが大切です。
また、指示を出した後は、部下に復唱してもらうことで理解度を確認する習慣も推奨されています。「今の指示内容を確認のために教えてもらえますか?」と尋ねることで、認識のズレを早期に発見し、修正することができます。
「教えること」と「任せること」のバランス
マネジメントにおいて難しいのは、「教えること」と「任せること」のバランスです。過度に教えすぎると部下の自主性が育たず、逆に任せすぎると失敗のリスクが高まります。