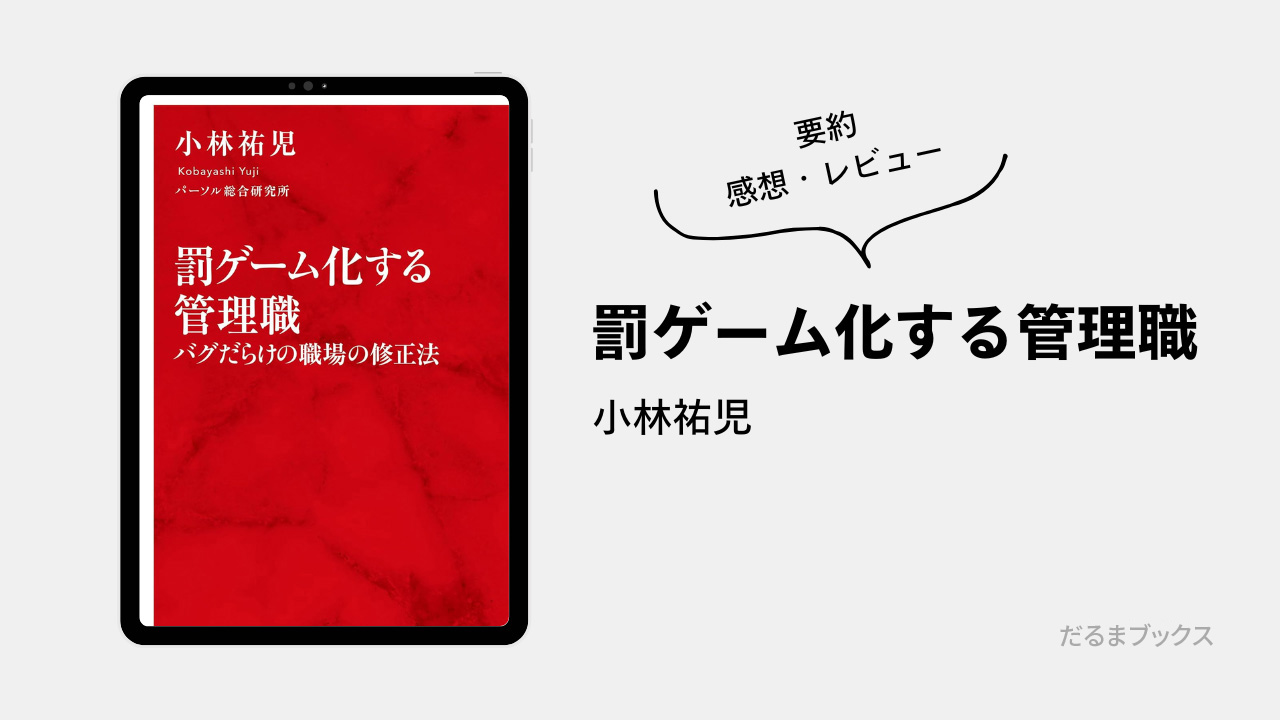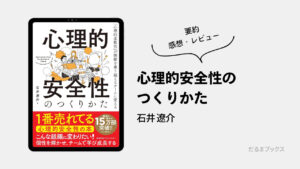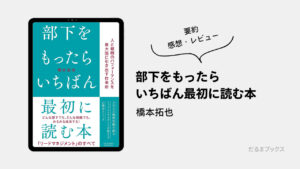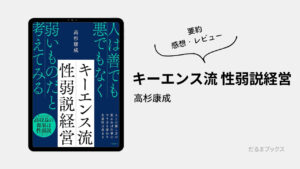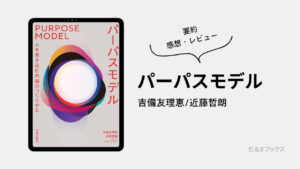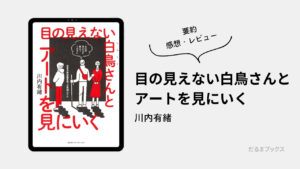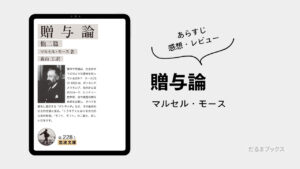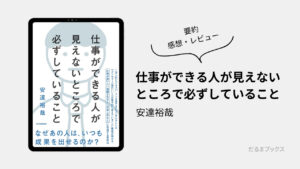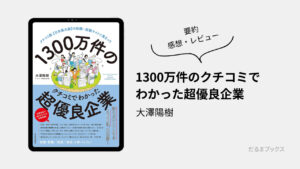かつては憧れの対象だった管理職が、今や「罰ゲーム」と呼ばれるほど避けられる存在になっています。
小林祐児さんの『罰ゲーム化する管理職』は、この現象を多角的に分析し、日本企業における管理職の苦境とその解決策を提示した一冊です。
- 経済の低迷
- 働き方改革
- ハラスメント問題
など、様々な要因が複雑に絡み合い、管理職を「誰もがやりたがらない」ポジションへと変えてしまった実態に迫ります。
「罰ゲーム化」の実態
「管理職になりたくない」という声が若い世代を中心に広がっています。
管理職が避けられる理由
パーソル総合研究所の国際調査によると、日本における「管理職になりたいメンバー層の割合」は21.4%と、調査対象14カ国中で断トツの最下位となっています。
特に40代で管理職意欲が急落する傾向があり、他国では年齢に関わらず管理職を目指し続ける人が多い中、日本では40代までに管理職になれなかった人の多くが「諦める」傾向にあります。
博報堂生活総合研究所の調査データでも、「会社の中で出世したい」という設問に肯定的な回答をする人は1998年の19.1%から徐々に低下し、2022年には13.2%まで落ち込んでいます。
この20~30年の間に、管理職への出世に魅力を感じる人が着実に減少しているのです。
罰ゲーム化の10の要因
小林祐児さんは著書の中で、管理職が「罰ゲーム」と化した要因を10点挙げています。
その根底にあるのは、バブル崩壊以降続く経済の長期低迷です。
「失われた30年」とも呼ばれるこの期間、日本の1人当たりの実質GDP成長率は、1975年からの年平均4%台から1%台へと大きく下落しました。
経済低迷の中で人件費を抑制したい企業は、管理職の数を減らし、組織のピラミッド型階層を減らす「フラット化」を進めました。
意思決定のスピードを速くして事業の成長を促す狙いがありましたが、結果として残った管理職の負担は増大する一方となったのです。
経済低迷とフラット化の影響
組織のフラット化は一見効率的に見えますが、実際には管理職一人あたりの部下の数(管理スパン)が増え、業務負担が著しく増加しました。
さらに、非正規雇用のパート女性やシニア、外国人労働者など、多様な背景を持つメンバーをマネジメントする必要が生じ、コミュニケーションの複雑さも増しています。
デフレ環境下で最適化されたビジネスモデルと人材マネジメントは、短期的には人件費を抑制できても、長期的には管理職の疲弊を招き、組織全体の活力を奪う結果となっているのです。
管理職の現状と課題
過酷な労働環境
現代の管理職は「朝から晩まで会議ばかりで、夜からしか自分の仕事ができない」「メンタルヘルスの不調で、常に部下が欠けている状態で働いている」といった状況に直面しています。課題が次から次へと湧いてきて、管理職の心身をすり減らしていくのです。
特に深刻なのは、管理職の自殺率の高さです。厚生労働省の調査によれば、管理職の自殺率は他の職種と比較して高い傾向にあります。過重労働やストレスが原因となり、最悪の結果を招いているケースも少なくありません。
プレイング・マネージャーの増加
人手不足が深刻化する中、多くの管理職は「プレイング・マネージャー」として、マネジメント業務に加えて自らも現場の業務をこなす二重の負担を強いられています。本来なら部下に任せるべき業務まで自分で処理せざるを得ない状況に陥り、長時間労働が常態化しています。
ある中間管理職は「管理職になって半年だが、プレイングマネージャーとして働いていて、しんどい、辛い、マネージャーの仕事ってなんだろうと思う日々が続いている」と吐露しています。管理職としての役割が明確でないまま、過剰な業務負担を抱え込んでいる実態が浮かび上がります。
ハラスメント懸念と指導の難しさ
近年のハラスメント防止法の施行により、管理職は部下への指導方法にも細心の注意を払う必要が生じました。「パワハラと認定されるのではないか」という不安から、必要な指導さえためらうケースも増えています。
また、テレワークの普及により、部下の仕事ぶりを直接観察できない状況も増え、適切な評価や指導が難しくなっています。こうした環境変化が、管理職の負担をさらに増大させる要因となっているのです。
罰ゲーム化を生み出した社会背景
バブル崩壊後の長期停滞
日本経済の長期停滞は、企業の人件費抑制圧力を高め、管理職の処遇にも大きな影響を与えました。かつては管理職になると大幅な給与アップが期待できましたが、現在では一般社員との給与差が縮小し、責任の重さに見合わない報酬体系になっています。
「失われた30年」の間に、日本企業の国際競争力は低下し、多くの企業が生き残りをかけたコスト削減に走りました。その結果、管理職の数を減らし、一人あたりの負担を増やす構造改革が進められたのです。
人手不足と人件費抑制
少子高齢化による労働人口の減少は、企業の人手不足を加速させています。特に中小企業では、管理職の負担が著しく増大しており、「人は必要だが、これ以上人件費は割けない」というジレンマに陥っています。
非正規雇用の増加も管理職の負担を増やす要因となっています。正社員と非正規社員が混在する職場では、雇用形態ごとに異なるルールや処遇を理解し、適切にマネジメントする必要があり、管理職の業務はより複雑化しています。
年功序列の崩壊と年輪型秩序の出現
従来の年功序列型の人事制度が崩壊し、成果主義的な評価制度が導入される中で、管理職の役割も大きく変化しました。かつては「年上の管理職」が「年下の部下」を指導するのが一般的でしたが、現在では年齢と役職が必ずしも一致しない「年輪型」の組織構造が増えています。
若手管理職が年上の部下をマネジメントする場面も増え、世代間のコミュニケーションギャップが新たな課題として浮上しています。管理職は単なる業務指示だけでなく、多様な価値観や働き方を尊重しながら組織をまとめる高度なスキルを求められるようになったのです。
働き方改革の皮肉な影響
二重の矮小化問題
働き方改革は労働者の健康と生産性向上を目指して導入されましたが、皮肉にも管理職の負担を増大させる結果となりました。時間外労働の上限規制や有給休暇の取得促進は、部下の労働時間を管理する責任を管理職に課し、自らの業務時間を圧迫しています。
小林さんはこれを「二重の矮小化問題」と呼んでいます。部下の労働時間は減少する一方で、管理職自身は労働時間規制の対象外とされることが多く、結果として長時間労働を強いられるという矛盾が生じているのです。
労働時間管理の限界
テレワークの普及により、管理職は部下の労働時間を正確に把握することが困難になりました。「見えない労働」をどう評価し、管理するかという新たな課題に直面しています。
また、労働時間の削減が優先される中で、部下の育成や組織の将来を見据えた取り組みに時間を割くことが難しくなっています。短期的な成果を求められる中で、長期的な視点でのマネジメントが犠牲になっているのです。
生産性向上の欠如
働き方改革の本来の目的は、労働時間の削減と同時に生産性の向上を実現することでした。しかし実際には、労働時間の削減ばかりが注目され、生産性向上のための具体的な施策が不足しています。
その結果、同じ業務量をより短い時間で処理する圧力が高まり、管理職はその調整役として板挟みの状態に置かれています。生産性向上のための投資や業務改革が進まない中で、管理職の負担だけが増大する悪循環に陥っているのです。
罰ゲームからの脱出法
フォロワーシップ・アプローチ
小林さんは、管理職の「罰ゲーム化」を修正する方法として、4つのアプローチを提案しています。その一つが「フォロワーシップ・アプローチ」です。これは、部下へのトレーニングを増やし、管理職と部下が同じ土俵に立てるようにする方法です。
管理職の問題を管理職だけの問題として捉えるのではなく、組織全体の課題として認識し、部下も含めた全員が解決に参加することが重要です。管理職と非管理職が共通の認識を持ち、円滑なコミュニケーションを図ることで、組織全体の効率が向上します。
ワークシェアリング・アプローチ
二つ目は「ワークシェアリング・アプローチ」です。これは、管理職の権限を部下に委譲し、全体の役割や業務量を調整する方法です。具体的には、「デリケーション施策」と「エンパワーメント施策」の二つが提案されています。
「デリケーション施策」では、下位管理職への公的な権限付与や承認プロセスの省略、タテの分業の明確化を行います。「エンパワーメント施策」では、メンバー層へのインフォーマルな役割分担や育成機会の付与、管理職研修などを実施します。これらの施策により、管理職の負担を軽減しながら、部下の成長も促進することができます。
ネットワーク・アプローチ
三つ目は「ネットワーク・アプローチ」です。管理職同士の横・縦・越境のネットワークを作り、情報共有や相互支援を促進する方法です。
管理職は孤独な立場に置かれがちですが、同じ悩みを持つ他の管理職と連携することで、精神的な支えを得るとともに、効果的な解決策を共有することができます。組織の壁を越えたネットワークを構築することで、新たな視点や知見を得る機会も増えるでしょう。
キャリア・アプローチ
四つ目は「キャリア・アプローチ」です。会社の昇進や選抜のやり方を変更し、管理職のキャリアパスを多様化する方法です。
全ての社員が管理職を目指す必要はなく、専門職としてのキャリアパスを充実させることで、個々の適性や志向に合った成長の道筋を提供することが重要です。管理職になることが唯一の出世コースではない、多様なキャリア選択肢を用意することで、真に管理職に適した人材が選ばれる環境を整えることができます。
職場のバグを修正する具体策
デリケーション施策の実践
管理職の負担を軽減するためには、「デリケーション施策」の実践が効果的です。これは、管理職が抱える業務や権限を適切に下位の管理職や部下に委譲する取り組みです。
具体的には、下位管理職への公的な権限付与、承認プロセスの省略、タテの分業の明確化などが挙げられます。特に承認プロセスの簡素化は、意思決定のスピードを高めるとともに、管理職の業務負担を大幅に軽減することができます。
また、タテの分業を明確化することで、「誰が何をすべきか」が組織内で共有され、無駄な確認作業や重複業務を減らすことができます。これらの施策は、管理職の「罰ゲーム化」を解消する上で重要な一歩となるでしょう。
エンパワーメント施策の導入
「エンパワーメント施策」は、部下の能力を引き出し、自律的に行動できる環境を整えることで、管理職の負担を軽減する取り組みです。メンバー層へのインフォーマルな役割分担や育成機会の付与、管理職研修などが含まれます。
部下に適切な権限と責任を与えることで、管理職は細かな業務指示から解放され、より戦略的な業務に集中することができます。また、部下の成長を促進することで、将来の管理職候補を育成することにもつながります。
エンパワーメント施策を成功させるためには、部下の失敗を許容する文化の醸成も重要です。失敗を恐れずにチャレンジできる環境があってこそ、部下は自律的に成長していくことができるのです。
タテとヨコのものさしの柔軟化
組織における評価基準、いわゆる「ものさし」の柔軟化も重要な課題です。従来の「タテのものさし」(上下関係や役職による評価)と「ヨコのものさし」(同じ立場の人との比較による評価)が硬直化していると、管理職も部下も窮屈な環境で働くことになります。
小林さんは、これらのものさしを柔軟化し、多様な働き方や成果を認める評価制度の導入を提案しています。例えば、短時間勤務でも成果を上げた社員を適切に評価したり、管理職としての成果だけでなく、専門性の高さも評価したりする仕組みが考えられます。
ものさしの柔軟化により、管理職は画一的な基準で部下を評価する負担から解放され、個々の強みを活かしたマネジメントが可能になります。同時に、部下も自分の強みを活かした働き方ができるようになり、組織全体の活力が高まるでしょう。
健全なえこひいきの必要性
次世代リーダー候補の早期絞り込み
小林さんは、組織の持続的な成長のためには「健全なえこひいき」が必要だと主張しています。全ての社員を平等に扱うことが理想とされがちですが、限られたリソースの中で次世代のリーダーを育成するためには、早い段階で候補者を絞り込み、集中的に育成することが重要です。
HR総研の企業調査によると、企業規模を問わず「次世代リーダー育成」が最大の課題となっています。特に近年は、優秀な若手が安定した大手企業から去り、スタートアップ企業に流れる傾向が強まっています。20年も会社に奉仕した挙げ句に大した給与も得られずに苦労ばかりする大手企業の管理職像に魅力を感じなくなった若者たちの流出は、日本企業の将来に大きな影を落としています。小林さんは、この状況を打開するためには、早い段階で次世代リーダー候補を見極め、集中的に育成する「健全なえこひいき」が必要だと主張しています。
全ての社員を平等に扱うことが一見公平に見えますが、限られたリソースの中では、将来のリーダーとなる人材を意図的に選抜し、特別な育成機会を与えることが組織の持続可能性につながります。小林さんはこれを「健全なえこひいき」と呼び、従来の属人的な「不健全なえこひいき」とは明確に区別しています。
特別育成プログラムの設計
健全なえこひいきを実践するためには、選抜された次世代リーダー候補に対する特別な育成プログラムが不可欠です。小林さんは、年間で数人から数十人程度を「若手向けの特別研修」という形で召集し、定例的に育成カリキュラムを組むことを提案しています。
このプログラムでは、通常の業務では経験できない挑戦的な課題や、幅広い視野を養うための異業種交流、経営層との対話の機会などを提供します。重要なのは、単に「選ばれた」という事実だけでなく、「あなたを選びました!期待しています!しっかり育てます!」という明確な意思表示です。この「選ばれた感」が、若手リーダー候補の成長を大きく促進するのです。
一方で、選抜されなかった社員に対するケアも重要ですが、それに過度に気を取られると肝心の「選んで育成する」という健全なえこひいきに踏み込めなくなります。日本の人事には明確な意思決定を避ける傾向がありますが、「誰を後継者として育てるか」を明確に決断することが、管理職不足の解消には不可欠なのです。
専門職キャリアパスの確立
健全なえこひいきのもう一つの側面は、管理職以外のキャリアパスの充実です。全ての社員が管理職を目指す必要はなく、専門性を活かした「専門職」としてのキャリアを歩む道も魅力的な選択肢として確立する必要があります。
小林さんは、次世代リーダー候補以外の管理職に対しては、広いジョブ・ローテーションを廃止し、キャリアの職域を限定的にすることで、一定の専門領域でのポータブル・スキルを蓄積できるトレーニングを実施することを提案しています。
専門職としてのキャリアパスが確立されれば、管理職になることを望まない社員も、自分の強みを活かして組織に貢献し、適切な評価と報酬を得ることができます。これにより、管理職への昇進が「罰ゲーム」ではなく、複数あるキャリア選択肢の一つとして健全に位置づけられるようになるでしょう。
感想・レビュー
データに基づいた説得力
小林祐児さんの『罰ゲーム化する管理職』は、単なる印象論や個人的な体験談ではなく、豊富なデータと調査結果に基づいた分析が光る一冊です。パーソル総合研究所の上席主任研究員としての専門性を活かし、国際比較を含む多角的な視点から日本の管理職問題を掘り下げています。
特に印象的だったのは、管理職の「罰ゲーム化」が単なる個人の意識の問題ではなく、バブル崩壊後の経済低迷、働き方改革、ハラスメント問題など、様々な社会的要因が複雑に絡み合った結果であることを明確に示している点です。問題の本質を構造的に捉えることで、対症療法ではなく根本的な解決策を提示することに成功しています。
現代の組織課題への洞察
本書は、現代の日本企業が直面する組織課題を鋭く捉えています。特に、管理職の「罰ゲーム化」が女性活躍推進を阻む大きな壁になっているという指摘は重要です。管理職の負担増大が、特に家庭との両立を重視する傾向がある女性にとって、キャリアアップの障壁となっている実態を浮き彫りにしています。
また、「不健全な平等主義」が日本企業に蔓延していることへの批判も的を射ています。全員を同じように扱うことが一見公平に見えますが、実際には組織の活力を奪い、次世代リーダーの育成を妨げている側面があります。この「平等」と「公平」の違いを明確に示し、「健全なえこひいき」の必要性を説得力をもって論じている点は、多くの日本企業にとって目から鱗の指摘でしょう。
実践的な解決策の提示
本書の最大の魅力は、問題提起だけでなく、具体的かつ実践的な解決策を提示している点です。「フォロワーシップ・アプローチ」「ワークシェアリング・アプローチ」「ネットワーク・アプローチ」「キャリア・アプローチ」という4つの視点から、管理職の「罰ゲーム化」を解消するための方策を多面的に示しています。
特に「健全なえこひいき」の提案は、日本企業の人材育成における根本的な発想の転換を促すものです。全員を平等に扱うことが必ずしも最善ではなく、将来のリーダー候補を早期に見極め、集中的に育成することの重要性を説いています。この考え方は、限られたリソースの中で組織の持続可能性を高めるために不可欠な視点といえるでしょう。
また、管理職の負担軽減のための具体的な施策として、「デリケーション施策」と「エンパワーメント施策」を提案している点も実践的です。これらの施策は、現場の管理職が明日から取り組める具体的なアクションとして示されており、読者にとって大きな価値があります。
まとめ
『罰ゲーム化する管理職』は、日本企業における管理職の苦境とその解決策を多角的に分析した意義深い一冊です。バブル崩壊後の経済低迷、働き方改革、ハラスメント問題など、様々な要因が複雑に絡み合い、管理職を「誰もがやりたがらない」ポジションへと変えてしまった実態を、データに基づいて明らかにしています。
小林祐児さんが提案する「健全なえこひいき」をはじめとする4つのアプローチは、管理職の「罰ゲーム化」を解消し、組織の活力を取り戻すための具体的な道筋を示しています。経営層から現場の管理職まで、日本企業に関わる全ての人にとって、明日からの行動を変える示唆に富んだ内容となっています。
管理職が再び憧れの存在となり、組織全体が活性化するための処方箋を示した本書は、日本のビジネスの現場を救う「希望の書」といえるでしょう。