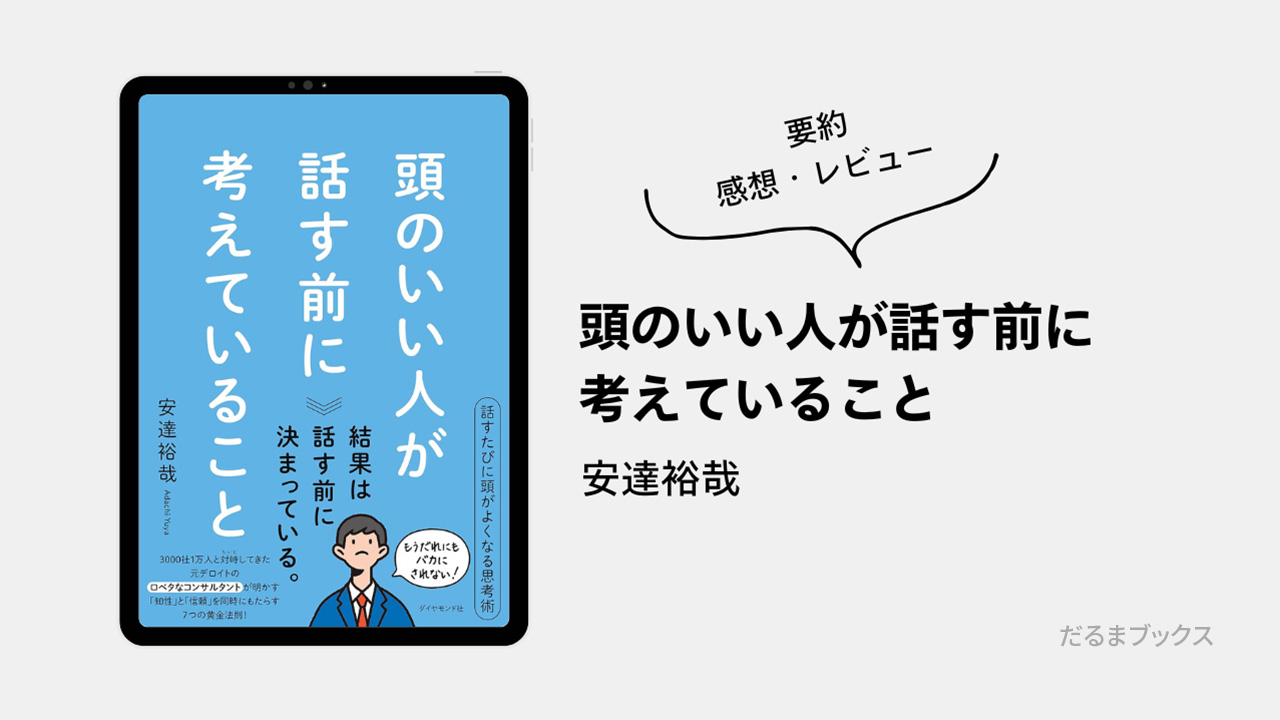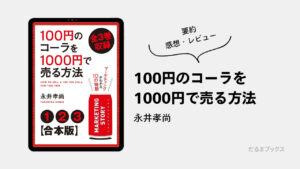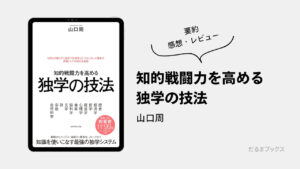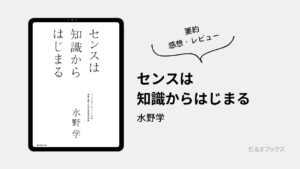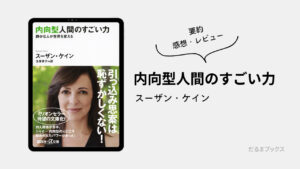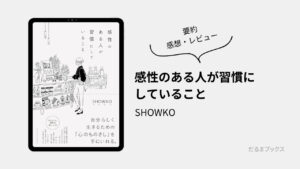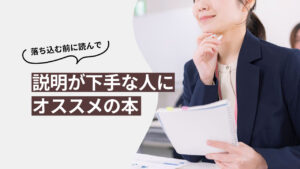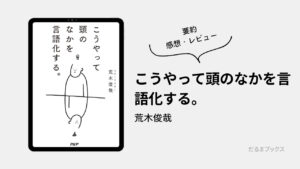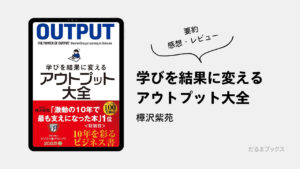「頭のいい人」と呼ばれる人たちは、話す前に何を考えているのでしょうか。
安達裕哉さんの著書「頭のいい人が話す前に考えていること」は、発売からわずか1ヶ月で15万部を突破し、2023年と2024年の2年連続でビジネス書ベストセラー1位を獲得した話題の一冊です。
この記事では、本書のエッセンスを掘り下げながら、日常生活やビジネスシーンですぐに活かせる思考法をご紹介します。
本書の概要と著者紹介
安達裕哉さんのプロフィールと執筆背景
安達裕哉さんは1975年東京都生まれ、1994年に麻布高校を卒業後、筑波大学環境科学研究科を修了されました。理系研究職の道を諦め、デロイト トーマツ コンサルティング(現アビームコンサルティング)に入社。12年間にわたりコンサルティングに従事し、大阪支社長、東京支社長を歴任されました。
その後独立し、現在はティネクト株式会社の代表取締役として、累計1億2000万PVを誇るビジネスメディア「Books&Apps」を運営されています。
3000社以上の経営者と向き合ってきた豊富な経験が、本書の内容に深みを与えています。
安達さん自身、もともとは「口下手」で「頭がいい」とは言えなかったと告白しています。しかし、コンサルティング会社での経験を通じて、「話す前にちゃんと考える」ことの重要性を学び、その思考法を身につけていったのです。本書は、そうした経験から得た知見を、業界を問わず一生使える形に法則化したものです。
「頭のいい人」の定義とは
本書において「頭のいい人」とは、単に知識が豊富な人や学歴が高い人を指すのではありません。安達さんは「頭のよさは他人が決める」と述べています。
つまり、自分がどれだけ頭がいいと思っていても、周囲から「頭がいい」と認められなければ意味がないのです。
真に「頭のいい人」とは、相手の立場に立って考え、相手にとって有益な言葉を選び、信頼を得られる人のことです。IQ(学校的知性)よりもSQ(社会的知性)が重要であり、立場も価値観も違う他人と考えを共有するための論理的思考力を持つ人こそが、「頭のいい人」なのです。
本書で伝えたいこと
本書の核心は「話す前にちゃんと考える」ということです。しかし、「ちゃんと」とは具体的に何を意味するのでしょうか。安達さんは、それを「知性」と「信頼」を同時に得るための7つの黄金法則と、思考を深めるための5つの思考法として体系化しています。
どれだけ考えても、伝わらなければ意味がありません。しかし、話し方のスキルだけでは、人の心は動かせないのです。
コンサルティングの現場で叩き込まれたのは、人の心を動かす「思考の質」の高め方でした。本書は、その思考法を誰でも実践できる形で提示しています。
賢い人の思考プロセスの秘密
話す前に行う3つの思考ステップ
頭のいい人は、話す前に3つの思考ステップを踏んでいます。
まず第一に、「相手の知識レベルを考える」ことです。相手がどの程度の知識や経験を持っているかを想像し、それに合わせた言葉選びや説明の深さを調整します。
専門用語をやたらと使うのではなく、相手が理解できる言葉で話すことが重要です。
第二に、「伝えたい目的を明確にする」ことです。なぜこの話をするのか、何を伝えたいのかを明確にしてから話し始めます。
目的が曖昧なまま話し始めると、話が散漫になり、聞き手を混乱させてしまいます。
そして第三に、「事実と意見を区別する」ことです。何が客観的な事実で、何が自分の主観的な意見なのかを明確に区別して話します。
この区別がつかないと、議論がかみ合わなくなったり、誤解を生んだりする原因になります。
これらのステップを踏むことで、聞き手にとってわかりやすい話となります。
「間」の重要性と活用法
頭のいい人は、「間」を大切にします。安達さんは「とにかく反応するな」という黄金法則を挙げています。
感情にまかせて反射的に反応するのではなく、一呼吸置いて冷静になることが大切です。
心理学の研究によると、怒りが生まれてから理性が働くまでには6秒かかると言われています。この6秒間、何も言わずにいれば、冷静さを取り戻すことができるのです。
感情的になると、言ってはいけないことを口にしてしまい、取り返しのつかない事態を招きかねません。
また、話す前に「相手がどう反応するか」をいくつかのシナリオで想像してみることも重要です。これにより、自分の発言がもたらす可能性のある結果を予測し、より適切な言葉選びができるようになります。
思考の整理術と表現への変換方法
思考を整理するためには、「整理」の思考法が欠かせません。
安達さんは「考えるとは整理すること」と述べています。
具体的には、「結論から話す」ことが重要で、PREP法(結論→理由→具体例→結論)を活用すると、誰でも結論から話せるようになります。
例えば
「この企画は成功する可能性が高いです」
「市場調査の結果、ターゲット層に需要があると分かったため」
「実際に類似商品が売れており、売上も伸びています」
「よって、この企画は進める価値があります」
というように話します。
また、事実と意見を明確に分けることも思考の整理には不可欠です。
「昨年の売上は前年比10%増加した」(事実)と「この調子で行けば今年も増収が見込める」(意見)を混同せずに話すことで、聞き手の理解が深まります。
相手に伝わる話し方の基本原則
論理的思考と感情のバランス
頭のいい人は、論理的思考と感情のバランスを上手く取ります。純粋に論理だけで話すと、冷たい印象を与えかねません。かといって、感情だけに頼ると説得力に欠けます。
安達さんは「人はちゃんと考えてくれる人を信頼する」と述べています。相手のことをちゃんと考えているという姿勢は、言葉だけでなく、仕草や語調、態度からも伝わります。相手の問題に真摯に向き合い、その解決のために自分の頭を使うことで、信頼関係が築かれるのです。
また、「知識は誰かのために使ってはじめて知性になる」という黄金法則も重要です。自分の知識を披露するのではなく、「これから話すことは本当に相手のためになるのか?」という視点を持つことが大切です。
言葉の選び方と表現技術
言葉の選び方も、頭のいい人の特徴です。相手の立場や知識レベルに合わせた言葉選びをし、専門用語や難解な表現は避けます。
例えば、靴屋で接客する際、お客様のニーズを汲み取ることが大切です。予算、デザインの好み、履き心地など、お客様が求めているポイントを見極め、最適な商品を提案することが求められます。自分の知識を一方的に披露するのではなく、あくまでお客様の問題解決に役立てることが肝要なのです。
また、「言語化」の思考法も表現技術の一つです。言語化の質がアウトプットの質を決めます。例えば、映画の感想を「面白かった」だけで終わらせるのではなく、何がどう面白かったのかを具体的に言語化することで、より深い会話が生まれます。
話す順序と構成の組み立て方
話す順序と構成も、伝わりやすさを左右します。前述のPREP法のように、結論から話すことが基本です。
また、話の構成を組み立てる際には、相手の関心や知識レベルを考慮することが重要です。専門的な内容を話す場合は、基本的な概念から説明し、徐々に深い内容へと進めていきます。