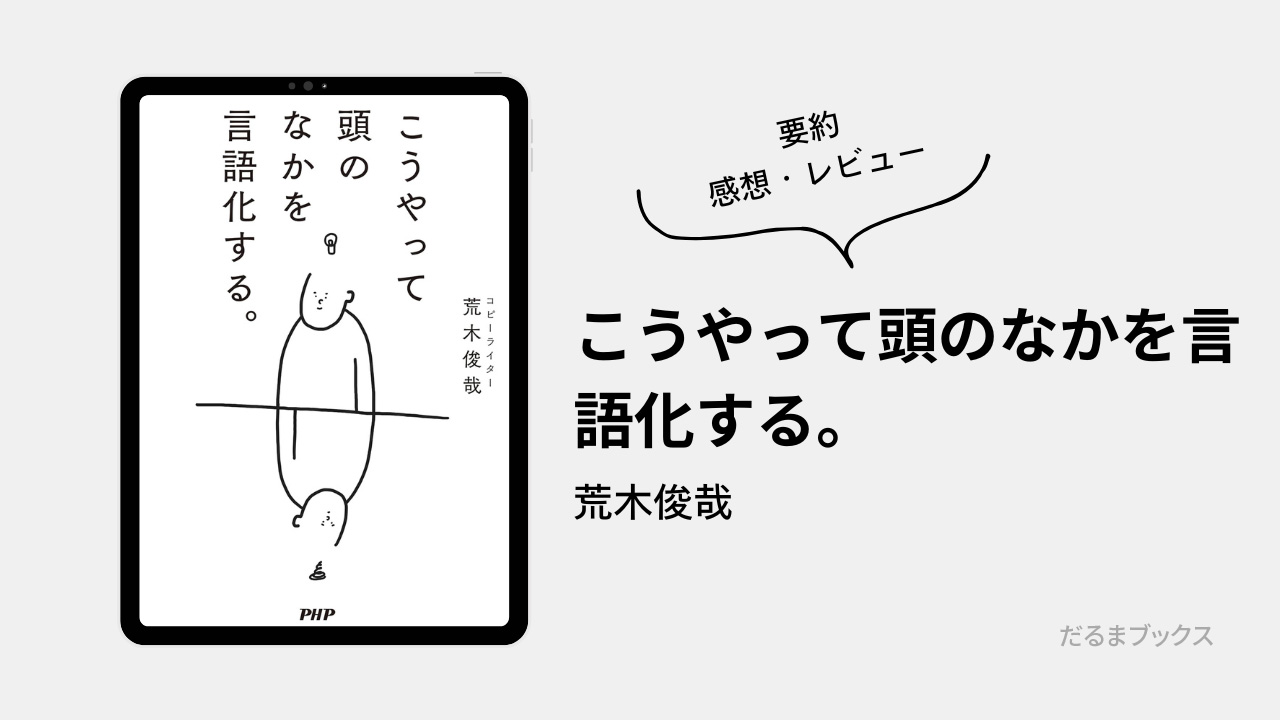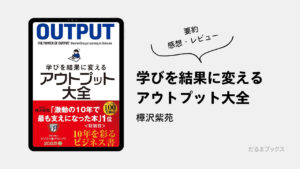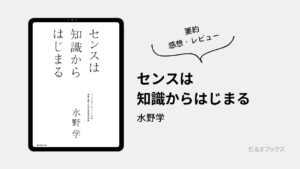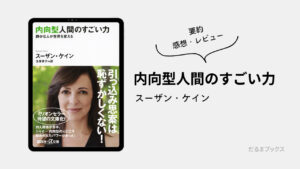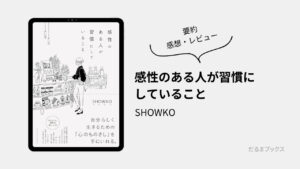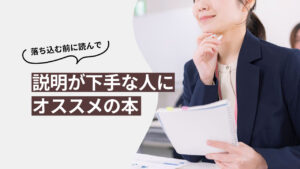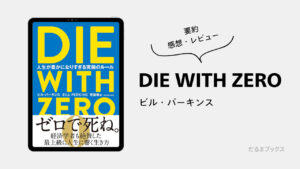「言葉に詰まってモヤモヤする…」そんな経験はありませんか?
- 会議で急に意見を求められて頭が真っ白に
- 自分の気持ちをうまく表現できずに後悔
そんな「言語化できない」悩みを解決するのが「こうやって頭のなかを言語化する。」(荒木俊哉著)です。
世界三大広告賞受賞のトップコピーライターである著者が、20年の経験から編み出した「言語化ノート術」を通じて、頭のモヤモヤを言葉に変える方法を伝える1冊です。
本書の概要
著者プロフィール:世界三大広告賞受賞のトップコピーライター
著者の荒木俊哉さんは、世界三大広告賞をはじめとする国内外で20以上の賞を受賞した一流のコピーライターです。HONDAの「ひとこと」など、私たちの記憶に残る名コピーを手がけてきた方でもあります。
コピーライターとしての仕事は、クライアントの思いを「ひとこと」に凝縮すること。そのためには、相手の話をじっくり聞き、その中から本質を見抜く力が必要です。荒木さんはこの「聞く力」こそが言語化の基本だと説きます。
国家資格キャリアコンサルタントも取得されており、言葉を使って人の成長を支援する仕事にも携わっています。「言語化力は、生きる力そのものだ」という言葉に、著者の信念が表れています。
前著『瞬時に「言語化できる人」が、うまくいく。』からの発展
本書は、10万部を超えるベストセラーとなった前著『瞬時に「言語化できる人」が、うまくいく。』の実践編とも言える一冊です。前著で提唱された言語化の重要性をさらに掘り下げ、より具体的な方法論へと発展させています。
著者自身、新人時代にはなかなか結果を残せず異動の危機に陥ったこともあったそうです。そんな著者が躍進した要因は、日々言語化力を磨いてきたことにあります。言語化力は才能ではなく、正しい方法で訓練すれば誰でも身につけられるスキルだという確信が本書の根底にあります。
1000人以上の体験者の声を活かした新メソッド
本書の「言語化ノート術」は、前著の読者や著者のセミナー参加者など、1000人以上の体験者からのフィードバックを活かして開発されました。約1年という時間をかけて練り上げられたこのメソッドは、「続けやすさ」を最重視した設計になっています。
「問いを立てるのが難しい」「どんな問いを立てたらいいのかわからない」といった声に応え、誰でも簡単に実践できる3ステップの方法を提案しています。1日たった3分で実践できるシンプルさが、このメソッドの最大の特徴です。
言語化力の高い人の特徴
「自分で自分の話を聞く」習慣がある
言語化力の高い人には共通する特徴があります。それは「自分で自分の話を聞く」習慣を持っているということです。
私たちは普段、他者の話を聞くことはあっても、自分自身の内なる声に耳を傾けることは意外と少ないものです。しかし、言語化力の高い人は、自分の頭の中で起きていることに意識的に注意を向け、その声を「聞く」ことを習慣にしています。
例えば、何か決断をするとき、頭の中でどんな思考が巡っているのか、どんな感情が湧いているのかを観察し、それを言葉として捉えようとします。この「自分の頭の中の声を聞く」という行為が、言語化の第一歩なのです。
自問自答を通して思考を深める
言語化力の高い人のもう一つの特徴は、自問自答を通して思考を深めていることです。荒木さんは「思考=自問自答」だと定義しています。
「なぜ、そう思うのか」「なぜ、そう感じるのか」と自分に問いかけることで、漠然とした感覚や印象を言葉に変換していきます。この問いがあってはじめて、人は言葉になっていない思いや意見を言語化しようとするのです。
例えば「この人、なんとなく嫌だ」という感覚があったとき、そのままにせず「なぜ嫌だと感じるのか」と自問自答することで、その理由が明確になり、モヤモヤした感情が一気にクリアになります。
自分の軸を言語化している
言語化力の高い人は、自分の価値観や信念、つまり「自分の軸」を言語化しています。「どう生きたいか」「何を大切にしているか」といった根本的な部分を言葉にすることで、日々の判断や行動に一貫性が生まれるのです。
自分の軸が言語化されていると、様々な場面で迷いや悩みが減っていきます。なぜなら、判断の基準がすでに明確になっているからです。例えば仕事の選択や人間関係の悩みに直面したとき、自分の軸に照らし合わせることで、自分にとって正しい選択がわかりやすくなります。
「自分の人生は自分で決める」という当たり前のことが、実は言語化力によって実現されるのです。
言語化につながる「聞き方」のコツ
「できごと→感じたこと」の順番で聞く
言語化を促すには、聞き方にもコツがあります。荒木さんが提案するのは、「できごと→感じたこと」の順番で聞くという方法です。
人は一般的に、具体的な「できごと」は比較的簡単に言語化できます。一方で、「感じたこと」のような抽象的な思いや意見はなかなか言語化しにくいものです。そこで、まず「できごと」から聞いていくことで、その後の「感じたこと」も引き出しやすくなります。
例えば、「今日のプレゼンはどうだった?」と直接感想を聞くよりも、「今日のプレゼンで印象に残ったことは?」と具体的な出来事を聞いてから、「それを見てどう感じた?」と進めていくほうが、相手は答えやすくなります。この順序は自分自身に問いかける際にも有効です。
アドバイスせず、決めつけない
言語化を促す上で大切なのは、アドバイスしようとしたり、決めつけたりしないことです。特に他者の言語化を手助けする場合、つい「こうすべきだ」「それは〇〇という意味だよね」と解釈を押し付けがちですが、それは避けるべきです。
同様に、自分自身の言語化においても、先入観や固定観念にとらわれず、オープンな姿勢で自分の思考や感情と向き合うことが重要です。無理に納得させようとしたり、決めつけたりすると、自問自答の幅、つまり思考の幅が狭まってしまいます。
言語化のプロセスは、答えを見つけるというよりも、自分の内側にある本当の思いを発見していく旅のようなものです。その旅を豊かにするためには、先入観なく、好奇心を持って自分の内面に耳を傾けることが大切です。
言葉の意味を深める問いかけをする
言語化をさらに深めるには、言葉の意味を掘り下げる問いかけが効果的です。同じ言葉でも、人によって込められた意味は異なります。その人なりの意味を引き出すことで、より深い言語化が可能になります。
例えば、「この仕事は楽しい」という言葉が出てきたとき、「楽しいとはどういう意味?」「どんなときに楽しいと感じる?」と掘り下げることで、その人にとっての「楽しい」の本当の意味が明らかになります。
この問いかけは、他者との対話だけでなく、自分自身との対話においても有効です。自分が何気なく使っている言葉の奥にある本当の意味を探ることで、自己理解が深まり、より精度の高い言語化が可能になります。
「言語化ノート術」の3ステップ
ステップ1:心が動いたできごとをメモする
言語化ノート術の第一ステップは、「ためる」です。日常生活の中で心が動いたできごとと、それに対して感じたことをセットでメモしていきます。
例えば、「プレゼン終了(できごと)→テンション上がった(感じたこと)」というように、シンプルな形で記録します。この段階では深く考える必要はなく、心に引っかかったことを短い言葉でメモするだけで構いません。
このプロセスを通じて、自分がどんなときに心を動かされるのか、どんな感情が湧きやすいのかといったパターンに気づくことができます。また、日常の小さな出来事に意識を向けることで、自分自身への感度が高まっていきます。
ステップ2:「のはなぜか?」を足して問いかける
次のステップは「きく」です。ステップ1でメモした「できごと+感じたこと」に、「のはなぜか?」という問いを足します。例えば、「プレゼン終了でテンションが上がったのはなぜか?」という形です。
この問いに対して、思いつく限りの答えを3分間で5つ以上、ザクザク書き出していきます。最初は表面的な答えかもしれませんが、書き続けるうちに、自分でも気づいていなかった本音や価値観が浮かび上がってくることがあります。
このプロセスは、頭の中のモヤモヤを言葉という形に変換する作業です。「のはなぜか?」という問いが加わっただけで、一気に頭が動き出し、思考が活性化されます。
ステップ3:現時点での結論を1行でまとめる
最後のステップは「まとめる」です。ステップ2で書き出した多くの言葉の中から、同じ言葉や似た言葉、何度も出てくる言葉を見つけて丸をつけます。そして、それらをもとに現時点での結論を1行でまとめます。
この「結論」は、その時点での自分の考えや価値観を凝縮したものです。完璧である必要はなく、今の自分にしっくりくる言葉でまとめられているかどうかが大切です。また、翌日以降に見直して何度でも書き直すことができるので、あまり固く考えず「ゆるく」取り組むことが重要です。
このプロセスを通じて、自分の中にある価値観や考え方のパターンが明確になり、自分自身への理解が深まっていきます。また、この結論を「どうすればもっとわかりやすい表現になるか」という視点でブラッシュアップすることで、自分の頭の中に明確なフレーズとしてストックされていきます。
実践編:5日間で変わる言語化習慣
1日3分で続けられるシンプル設計
言語化ノート術の最大の特徴は、1日たった3分で実践できるシンプルさです。「言語化を習慣にすること」が最も難しいという課題に対応するため、続けやすさを最重視した設計になっています。
朝の通勤時間や、寝る前のちょっとした時間など、日常の隙間時間を活用して取り組めるため、忙しい現代人でも無理なく続けられます。また、特別な道具も必要なく、スマートフォンのメモアプリやノートがあれば十分です。
著者は「とにかく5日間だけやってみてほしい」と言います。たった5日間の実践でも、自分の思考パターンや価値観に気づき、コミュニケーションや意思決定がスムーズになるという変化を実感できるそうです。
具体的な実践例と効果
実際に言語化ノート術を実践した人々からは、様々な効果が報告されています。
あるビジネスパーソンは、仕事の提案前に言語化ノート術を実践することで、自分の提案の核心が明確になり、プレゼンの質が向上したと言います。また、別の人は日常的な人間関係の悩みに対して言語化ノート術を適用し、自分が本当に求めているものが何かを発見できたと報告しています。