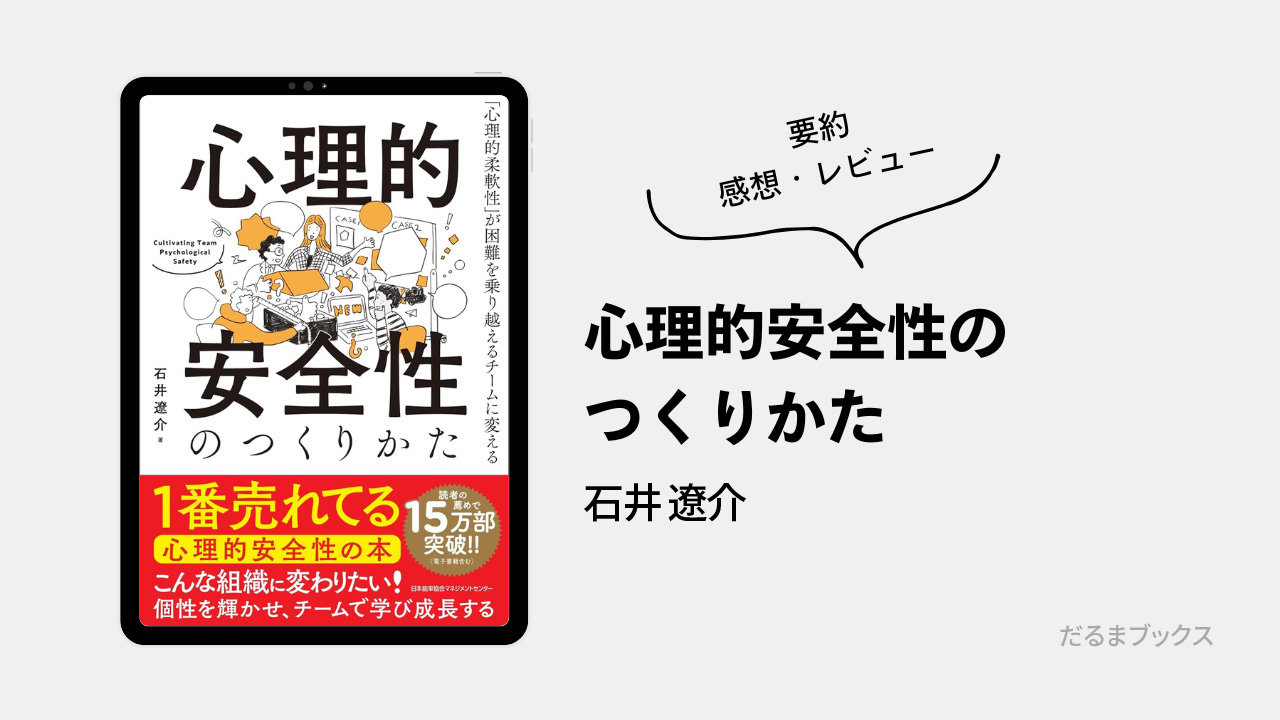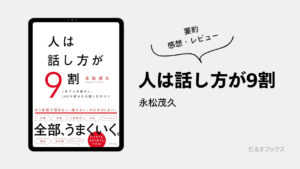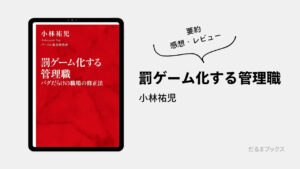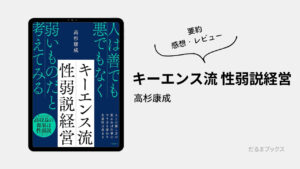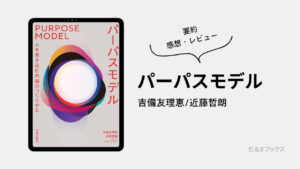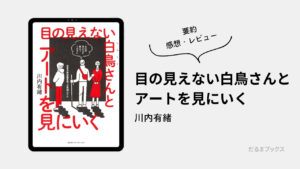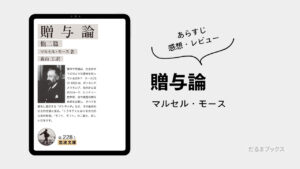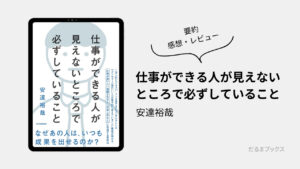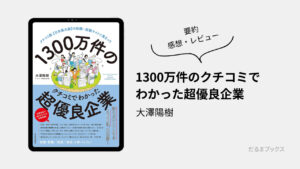仕事の生産性向上に欠かせない「心理的安全性」。
Googleの研究で注目を集めたこの概念を、日本企業の文脈で実践的に解説した石井遼介さんの「心理的安全性のつくりかた」は、単なる理想論ではなく具体的な行動変容のヒントに満ちています。
本書は
- 話しやすさ
- 助け合い
- 挑戦
- 新奇歓迎
という4つの因子を軸に、個人の心理的柔軟性から組織文化の構築まで、段階的なアプローチを提示。
みんなが明日から実践できる、心理的安全性の高め方を学べる一冊です。
心理的安全性とは何か
「心理的安全性」という言葉を聞いたことがある方は多いでしょう。
でも、その本当の意味を理解している人はどれくらいいるでしょうか。
心理的安全性とは、心理学者のエイミー・エドモンドソン教授によって提唱された概念で、「チームの中で対人的リスクを伴う行動をとっても大丈夫だとチームの中で共有されている信念」と定義されています。
つまり、意見を言ったり質問したりしても、無知だとか無能だとか思われないという安心感のことです。これは単なる「仲良しクラブ」や「ヌルい職場」とは全く違います。むしろ、健全に意見を戦わせ、生産的な仕事に集中できる環境のことを指しています。
石井さんは本書で、心理的安全性が高い職場では、報告がネガティブなものであっても隠し事なく事実としてあがってくること、そして困ったときに助け合える風土があることを強調しています。これは単に居心地がいいだけでなく、チームの生産性を高める土台となるのです。
Googleプロジェクト・アリストテレスの発見
心理的安全性が広く知られるようになったきっかけは、Googleが2012年に行った「プロジェクト・アリストテレス」という研究プロジェクトです。Googleは「なぜあるチームは高いパフォーマンスを発揮し、あるチームはそうでないのか」という問いを解明するために、社内の数百のチームを分析しました。
その結果、最も生産性の高いチームに共通していたのが「心理的安全性」の存在だったのです。興味深いことに、チームの効力感(仕事ができると感じていること)と心理的安全性を比較した結果、どちらもパフォーマンスに寄与するものの、心理的安全性の方がより大きな効果を発揮することが明らかになりました。
この発見は、従来の「優秀な人材を集めれば良いチームができる」という考え方に大きな変革をもたらしました。個々の能力よりも、チームの心理的な環境づくりが重要だということが科学的に証明されたのです。
日本企業における心理的安全性の現状
日本企業における心理的安全性はどうでしょうか。残念ながら、多くの日本企業では心理的安全性が十分に確保されているとは言えない状況です。特にリモートワークが急速に広がった昨今、「チーム化がうまくできない」「コミュニケーションが減少して新規プロジェクトが進まない」といった問題を抱える企業が増えています。
しかし石井さんは、これらの問題はリモートワーク以前から潜在していたものが顕在化しただけだと指摘します。例えば、部下を信用できない上司が監視ツールの使用や定期報告などのマイクロマネジメントを行い、さらに心理的安全性を奪っていくという悪循環が生じているケースも少なくありません。
日本企業特有の文化的背景も影響しています。「和を乱さない」という価値観や、失敗を許容しない風土は、心理的安全性の構築を難しくしています。しかし、VUCAと呼ばれる変動性・不確実性・複雑性・曖昧性が高まる現代において、こうした旧来の文化では対応しきれなくなっているのです。
心理的安全性を構成する4つの因子「話助挑新」
話しやすさ因子
心理的安全性の第一の因子は「話しやすさ」です。これは文字通り、チーム内で自由に発言できる雰囲気があるかどうかを指します。具体的には、報告がネガティブなものであっても、隠し事なく「事実としてあがってくる」ようなチームの状態を意味します。
話しやすさが高いチームでは、メンバーが自分の考えや懸念を率直に表現できます。「この意見を言ったら馬鹿にされるかも」「上司に反対意見を言ったら評価が下がるかも」といった恐れを感じることなく、建設的な対話が生まれるのです。
石井さんによれば、話しやすさを高めるための具体的な行動としては、「話す」「聞く」「相槌を打つ」「報告する」「目を見て報告を聞く」「雑談する」「報告という行動自体を褒める」などがあります。これらの行動を意識的に増やしていくことで、チーム内の話しやすさは徐々に高まっていくでしょう。
助け合い因子
第二の因子は「助け合い」です。これは個々がタスクをこなし、各自の責任で積み上げればプロジェクトが完遂されるという仕事の仕方ではなく、個人が困ったときに拠りどころとなる「相談の場」があり、それをチーム全体で共有しながら助け合う風土を指します。
助け合いの文化があるチームでは、「助けを求めることは弱さの表れ」といった考え方はありません。むしろ、適切なタイミングで助けを求めることが、チーム全体の効率を高めると理解されています。
助け合いを促進する行動としては、「相談する」「相談に乗る」「問題を見つける」「助けが必要だと認める」「ピンチをチャンスへかえるアイデアを出し合う」「個人ではなくチームの成果を考える」などが挙げられます。これらの行動が日常的に行われることで、チーム内の信頼関係が深まり、心理的安全性が高まっていくのです。
挑戦因子
第三の因子は「挑戦」です。これは冗談のようなアイデアや仮説を歓迎し、論理的な正解を越えた右脳型のジャンプをチームで試すことができる風土を指します。感性でひらめくイノベーションにトライできる環境が、この「挑戦」因子の本質です。
挑戦の文化があるチームでは、失敗を恐れずに新しいことに取り組む姿勢が評価されます。「前例がないから」「リスクが高いから」という理由で新しいアイデアが却下されることはありません。むしろ、「やってみよう」という前向きな姿勢が尊重されるのです。
石井さんは、心理的安全性の高い職場は決して「ヌルい職場」ではなく、むしろ挑戦することを楽しめる場所だと強調しています。それは仕事そのものが楽しいという動機で働き、なおかつ挑戦するときは周りが助けてくれるという安心感があるからこそ、メンバーは自分の限界を超えた挑戦ができるのです。
新奇歓迎因子
第四の因子は「新奇歓迎」です。これは一人ひとりは本質的に違い、価値観も違っていいという多様性のある風土を指します。どれだけ違っていても包み込むという、SDGsの「誰ひとり取り残さない」にあたる考え方が根底にあります。
新奇歓迎の文化があるチームでは、異なる背景や考え方を持つメンバーが互いを尊重し合います。「みんな同じであるべき」という同調圧力はなく、むしろ多様な視点がチームの強みとして認識されているのです。
人間を同質な集団として一律に扱うことは、マネジメント側の手間を減らします。しかし、このVUCAの時代にチームとして競争力を持つには同質性を前提としたマネジメントではもはや足りません。新奇歓迎は、現代のダイバーシティ&インクルージョンに繋がっているのです。