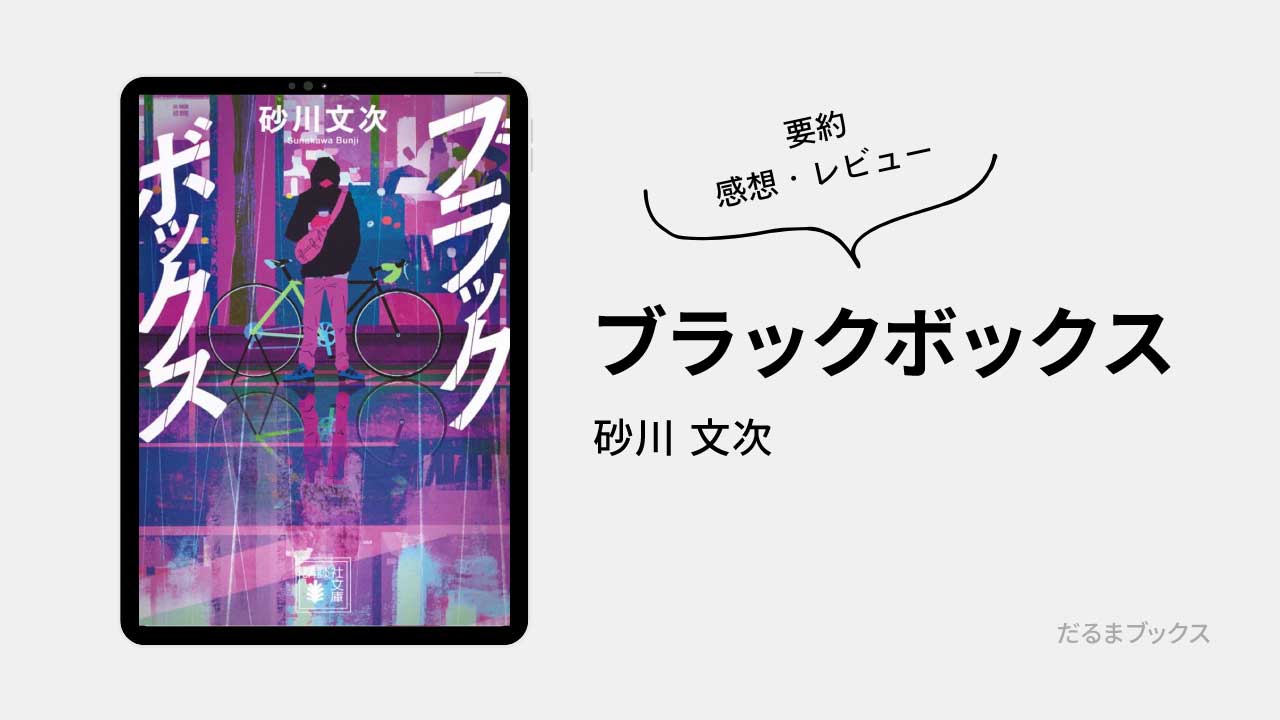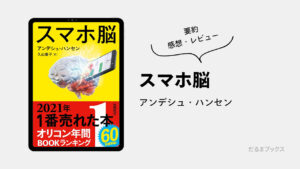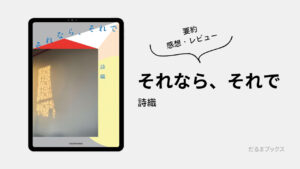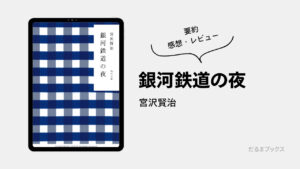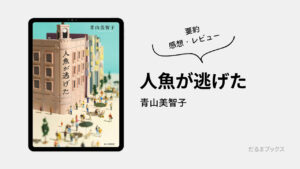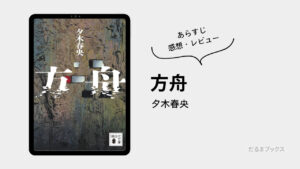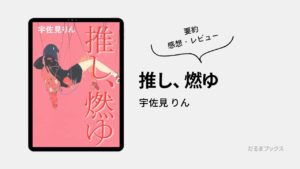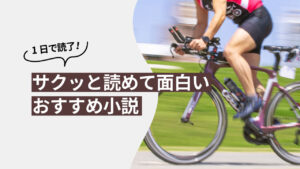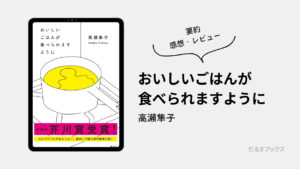砂川文次さんの小説「ブラックボックス」は、
2021年に第166回芥川賞を受賞し、現代社会における若者の生きづらさを鋭く描き出しています。
主人公サクマの内面と社会との関わりを通して、私たちの見えない部分=ブラックボックスに迫る物語です。
作品の基本情報
砂川文次さんの「ブラックボックス」は2022年1月26日に講談社から発売された小説。
全168ページの比較的コンパクトな作品ながら、現代社会を鋭く切り取った内容が評価され、第166回芥川賞を受賞しました。
砂川さんは元自衛官という異色の経歴を持つ作家で、これまでも「戦場のレビヤタン」や「小隊」など、戦争や紛争をテーマにした作品を発表してきました。しかし「ブラックボックス」では舞台をコロナ禍の東京に移し、現代社会を生きる若者の姿を描いています。
この作品の特徴は、リアリティのある硬質な文体で極限状態に置かれた人の心理を描き出している点にあります。砂川さんの文体は無駄がなく、都会的な描写と心理描写の対比が見事です。
あらすじ・ストーリー概要
主人公サクマの日常

物語の主人公・佐久間亮介(サクマ)は30歳を目前に控えた自転車メッセンジャーです。
彼は「ずっと遠くに行きたかった」という漠然とした願望を抱えながら、日々東京の街を自転車で駆け巡っています。
サクマはこれまで自衛隊や不動産の営業、コンビニなど様々な仕事を転々としてきました。
どの仕事も長続きしなかったのは、彼が「暴発的暴力衝動」を抑えられないから。
怠けたがる先輩や、女性社員にちょっかいを出す社長のドラ息子、立場の弱い店員に尊大な態度をとる客など、理不尽な人間を見ると「ブッ飛ばしてぇ」と思わずにはいられず、実際に手を出してしまうのです。
現在の自転車メッセンジャーの仕事は、体力を使って走れば走るほど実入りがある完全歩合制で、サクマの性分に合っていました。しかし、事故があれば全て「自己責任」であり、体力的な限界も必ず訪れます。そのため、サクマは将来への不安を抱えながらも、「ちゃんとしなくちゃ」という思いと「でもちゃんとするっていうのが具体的に何をどうすることなのか」という疑問の間で揺れ動いています。
将来への不安と葛藤
ある日、サクマは営業所の所長・滝本から正社員登用の話を持ちかけられます。正社員になれば福利厚生がつくという魅力はあるものの、業務が多くなる割に給料は安いため、サクマはその話を保留にしてしまいます。
サクマには同棲している女性・円佳がいました。
避妊せずに関係を持ったことで妊娠した円佳と共同生活をしていますが、彼女との関係も深まっているとは言えません。
サクマは円佳に対して身勝手なセックスを強いるだけで、一緒にいても「孤独」を感じています。
結婚についても踏み切れずにいるのです。
このように、サクマは会社員になることや結婚など、「ちゃんとしなきゃ」という気持ちを募らせながらも、どうにも先を切り開けず、悶々とした日々を過ごしていました。
暴発的暴力衝動の問題
サクマの最大の問題は、「一瞬で着火してしまう暴発的暴力衝動」でした。彼は理性が失われ暴力を発動する瞬間を覚えていないと言います。
いつも「気がついたら」暴力事件に発展してしまっているのです。
サクマにとって、この暴力衝動は自分自身が何が飛び出すか分からない「ブラックボックス」のようなものでした。
「なんで自分はあんなことをしたのだろう?」と後から振り返っても、その瞬間の思考回路は理解できないのです。
物語の転換点
決定的な事件
物語は、サクマの悶々とした日常から一転して、大きな事件へと展開します。税金をちゃんと支払っていなかったサクマのもとに、納税督促のために税務署調査官が2人やってきます。「ちゃんとした職業」に就く調査官が「ちゃんと支払え」と言い、その説明が難しいことに加え、調査官の一人が「少し笑った」ように見えたことで、サクマの怒りに火がつきます。
暴力衝動が発動し、サクマは調査官に流血するほどの暴力を加えます。さらに、逃げたもう一人の調査官を追いかけ、そこで運悪く警察官と遭遇し、警察官にも暴力を振るってしまいます。
この事件によって、サクマは刑務所に収監されることになります。
刑務所での気づき
刑務所での生活は、サクマにとって大きな転機となります。刑務所は起床時間から就寝に至るまで、全てがルール化された場所です。そこから外れることは許されず、24時間がんじがらめの環境です。
しかし、意外なことに、サクマはこの刑務所を「『ちゃんと』がある場所」と感じるようになります。これまで「ちゃんとしなくちゃ」と思いながらも具体的に何をすればいいのか分からなかったサクマにとって、刑務所の規則正しい生活は一種の安心感をもたらすのです。
サクマは刑務所での生活を通じて、自分自身と向き合う時間を得ます。そして、これまで自分が「自閉」していたこと、つまり自らを閉じたままで生きてきたことに気づくのです。あらゆる角にぶつかり続けた先に、ほんの少し周りが見えてきて、自分しかいなかった世界に他の人がいることを腹の底から実感できるようになりました。
作品の深層
タイトル「ブラックボックス」の意味
この小説のタイトル「ブラックボックス」には、複数の意味が込められています。
まず一つ目は、「サクマ自身がブラックボックスである」という意味です。サクマは自分の中から何が出てくるか分からない、自分自身が「ブラックボックス」なのです。行動は目に見えても、その思考回路は見えません。モヤモヤと絡まった気持ちは、まさにブラックボックスと言えるでしょう。
二つ目は、「社会システムとしてのブラックボックス」です。サクマはメッセンジャーとして自転車で街を駆け巡る中で、次のように考えます。「昼間走る街並みやそこかしこにあるであろうオフィスや倉庫、夜の生活の営み、どれもこれもが明け透けに見えているようで見えない。」
サクマは様々なオフィスを訪れる中で、「彼らが何かをしているのはどうも確からしいが、さらに踏み込んで何をしているのか知ろうとしても絶対に触れられないものがその奥にある」と感じています。これは、社会の「ちゃんとした部分」へ一歩踏み込めないサクマの心情をよく表しています。
また、タイトルには「自分自身がブラックボックスの中に入っていて、周りが見えていない状態、その中でもがき苦しんでいる様」を指している意味も含まれているかもしれません。
社会批評としての側面
「ブラックボックス」は、コロナ禍における非正規雇用の実態や、現代社会における若者の生きづらさを描いた社会批評としての側面も持っています。
サクマのような非正規雇用者は、コロナ禍で企業活動がストップすれば収入が途絶える不安を抱えています。また、「ちゃんとした生活」への憧れを持ちながらも、具体的に何をすればいいのか分からず悶々とする若者の姿は、現代社会の縮図とも言えるでしょう。
砂川さんは、サクマという一人の若者の姿を通して、現代社会の構造的な問題を浮き彫りにしています。それは、自由化が進む社会の中で、自分で考え行動することを求められながらも、その自由に戸惑い苦しむ人々の姿でもあります。
文学的特徴
砂川文次さんの文体と表現技法
砂川さんの文体は、無駄がなく硬質で、都会的な描写と心理描写の対比が見事です。特に、刑務所内の生活描写のリアリティは、元自衛官という砂川さんの経験が活かされているのかもしれません。
また、この作品はアルベール・カミュの『異邦人』との相似点も指摘されています。主人公が社会の中で疎外感を抱え、ある事件をきっかけに刑務所に収監されるという展開や、その中で自己と向き合うという点で共通しています。
砂川さんの表現技法の特徴は、細部へのこだわりです。サクマが自転車で東京の街を走る描写や、刑務所での日常の描写など、細かい部分まで丁寧に描かれています。それによって、読者はサクマの世界に引き込まれていくのです。
感想・レビュー
現代社会を映し出す鏡としての価値
「ブラックボックス」を読んで最も印象に残ったのは、現代社会における若者の生きづらさを描く視点の鋭さです。サクマのような非正規雇用者が抱える不安や、「ちゃんとしなくちゃ」という呪縛は、多くの読者にとって共感できるものではないでしょうか。
特に、「ちゃんとするっていうのが具体的に何をどうすることなのか」という問いかけは、現代を生きる私たちに突きつけられた問いでもあります。社会の中で「ちゃんと」生きることの意味を、改めて考えさせられました。
また、サクマが抱える「暴発的暴力衝動」と社会の関係性についての考察も興味深いものでした。サクマの暴力は単なる個人の問題ではなく、社会構造の中で生まれた反応とも読み取れます。彼を取り巻く社会情勢、経済状況、人間関係、労働環境が、重苦しく彼にのしかかり、その結果として暴力という形で表出したとも考えられるのです。
砂川さんは、サクマという一人の若者の姿を通して、現代社会の閉塞感や生きづらさを鮮やかに描き出しています。それは、自由化が進む社会の中で、自分で考え行動することを求められながらも、その自由に戸惑い苦しむ人々の姿でもあります。
「ブラックボックス」は、現代社会を映し出す鏡として大きな価値を持つ作品だと感じました。読後、自分自身の生き方や社会との関わり方について、深く考えさせられました。
まとめ
砂川文次さんの「ブラックボックス」は、コロナ禍における非正規雇用者の姿を通して、現代社会の問題を鋭く描き出した作品です。第166回芥川賞を受賞したことで、その文学的価値も広く認められました。
主人公サクマの内面と社会との関わりを通して、私たちは自分自身のブラックボックスと向き合うことになります。「ちゃんとしなくちゃ」という呪縛や、理性を失う瞬間の恐ろしさ、そして刑務所という極限状態での気づきなど、様々な視点から現代社会における人間の在り方を問いかけています。
この作品は、現代日本文学の中でも特筆すべき位置を占めるでしょう。読者に投げかける問いかけの意義は大きく、読後も長く心に残る作品です。