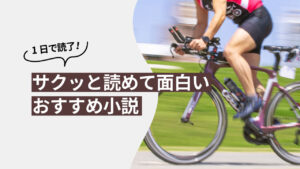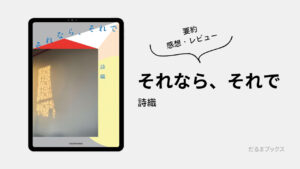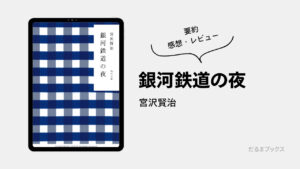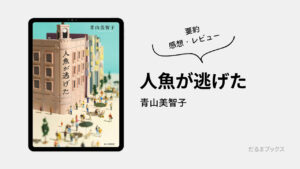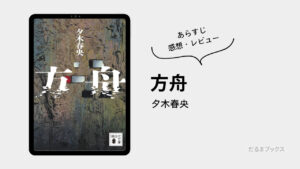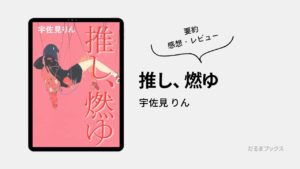高瀬隼子さんの芥川賞受賞作「おいしいごはんが食べられますように」は、一見穏やかなタイトルとは裏腹に、食を通して描かれる人間関係の機微と同調圧力の息苦しさを鋭く描いた作品です。
職場での関係性、恋愛、そして「食べること」への違和感と抵抗を通して、現代社会に潜む不穏さと個人の内面を掘り下げています。
シンプルな文体ながら読者の心をざわつかせる、注目すべき一冊です。
作品の概要
芥川賞受賞の話題作
高瀬隼子さんの中編小説「おいしいごはんが食べられますように」は、
文学雑誌『群像』の2022年1月号に掲載されたのが初出で、同年3月24日に単行本化されました。
芥川賞受賞が発表された7月20日以降、テレビ番組『王様のブランチ』での紹介もあり、30万部を突破するという大きな反響を呼びました。
一見、職場での恋愛を描いた小説のようですが、実際には現代社会における「食」をめぐる価値観や同調圧力、そして人間の多面性を鋭く切り取った作品。
芥川賞選考委員の川上弘美さんは「職場や小さい集団の中での人間関係を立体的に描き、物語の登場人物を通じて一面的にいい、悪いではない、人間の中の多面性がよく描かれている」と評価しています。
食をめぐる人間関係の物語
この小説の最大の特徴は、「食」という日常的な行為を通して、人間関係の複雑さや社会の同調圧力を描いている点です。主人公の二谷は、食べることにあまり重きを置いておらず、むしろ面倒くさいと感じています。しかし、そのことを大っぴらに言えない社会の空気感があります。
恋人の芦川さんが時間をかけて作った手料理を食べても、彼女が寝た後にこっそりカップ麺を食べて、ようやく「晩飯を食べた」気持ちになるという二谷の姿は、現代社会における「食」への価値観の多様性と、それを表明できない窮屈さを象徴しています。
人と食事をするとき、タイミングよく「おいしい」と言わなければならないわずらわしさなど、これまであまり言葉にされることがなかった「食べること」についての、人それぞれ異なる感覚が様々な角度から描かれています。
同調圧力と個人の葛藤を描く
この作品は、表面上は順応しながらも内心で抵抗する主人公・二谷の姿を通して、現代社会における同調圧力と個人の葛藤を鮮やかに描き出しています。二谷は職場でそつなく振る舞い、同僚たちからも好感を持たれていますが、内心では食事という行為に対して嫌悪感に近い感情を抱いています。
「丁寧な暮らし」や「ちゃんとした食」が社会的に支持されている風潮の中で、それに違和感を覚えながらも表立って反発できない二谷の姿は、多くの読者の共感を呼んでいます。実際、この小説を読んだ人からは「自分はそれほどご飯が好きではないのに、好きなふりをしていてしんどかったことに気づいた」という感想も寄せられているそうです。
現代社会における「正しさ」への同調と、それに対する内なる抵抗という普遍的なテーマを、「食」という身近な切り口から描き出した点が、この作品の大きな魅力となっています。
登場人物たち
二谷 – 表面上は順応しながらも内心で抵抗する主人公
主人公の二谷は、職場ではそつなく働き、同僚たちからも好感を持たれている男性です。しかし、彼の内面は複雑で、特に「食べること」に対して独特の感情を抱いています。食事をとるという行為に対し、内心でどこか嫌悪感に近い感情を持ちながらも、それを表に出すことなく生きています。
二谷の特徴的な行動として、恋人の芦川さんが作った夕食を食べた後で、こっそりカップ麺を食べるという場面があります。これは彼にとって、自分のテリトリーに侵入してくる他者の価値観への密かな抵抗の形です。また、芦川さんの手作りお菓子を見えないところで踏み、ぐちゃぐちゃにして捨てるという行為も、表面上は受け入れながらも内心では拒絶するという二谷の二面性を象徴しています。
二谷は故郷では「男の子だから」「長男だから」という理由で、個としての自分を見てもらえなかった経験を持っています。その窮屈で苦しい状況を象徴するのが、彼にとっての「食べること」であり、それは逃げても追いかけてくるものとして描かれています。
芦川さん – 「丁寧な食」を重視する二谷の恋人
芦川さんは二谷の職場の先輩で、かよわく見える女性です。
彼女は「丁寧な食」や「丁寧な暮らし」を重視し、二谷との三度目のデートで、ひとり暮らしの二谷の食生活にアドバイスを始めます。彼女は二谷に対して、体に良くておいしいものを作り、食べさせようとします。
しかし、芦川さんは二谷の部屋に積まれた本には気づかず、話題にもしません。彼女は二谷に親切にしているようでいて、二谷の内面や本当の興味には関心を示していないのです。芦川さんにとっても、二谷は「怒鳴らなくて仕事ができる、ちょうどいい恋人」として存在しています。
芦川さんは職場でも特別な存在として扱われ、多くの人から守られるような立場にあります。しかし、その裏では家族にも見下されているなど、彼女自身も複雑な状況に置かれています。表面的には守られているように見えて、実は誰からも本当の意味で理解されていないという皮肉な状況が描かれています。
押尾 – 二谷と価値観が近い同僚
押尾は二谷の職場の同僚で、二谷と価値観が近い女性です。
彼女は賢く、やがて二谷が「丁寧なごはん」を憎んでいることに気づきます。二谷と押尾が共鳴したのは、嫌いなものが似通っていたからです。弱さを武器にする芦川さんが嫌い、職場の人と大勢で食べるご飯が嫌い、食べ物を前に「美味しいねえ」と言い合わなければならない時間が嫌い、という点で二人は共感し合います。
しかし、押尾は二谷とは異なり、自分の感情に正直に生きる選択をします。彼女は「できないのではなく、必要がないのだ」と言い、同調圧力に屈することなく自分の道を進みます。
最終的に押尾は会社を去っていきますが、それは「良い人材こそ会社に残らない法則」を象徴するような選択として描かれています。
押尾の存在は、同じような違和感を抱きながらも、それに対する対処の仕方が異なる二谷との対比を通して、個人の選択と自由の問題を浮き彫りにしています。
あらすじ
物語は、ある会社で働く二谷を中心に展開します。二谷は職場ではそつなく振る舞い、同僚たちからも好感を持たれています。しかし、内心では特に「食べること」に対して複雑な感情を抱いています。
職場には芦川さんという女性がおり、彼女は皆から守られるような存在です。また、押尾という女性もおり、彼女は二谷と似た価値観を持っています。三人の関係性は、職場という閉じられた空間の中で、微妙なバランスを保っています。
職場では、芦川さんが作ったお菓子が差し入れされることがあり、皆で「うまい!」と言い合う場面があります。二谷はそのような場面を苦行と感じながらも、表面上は合わせて乗り切ります。一方、押尾はそのような同調を拒否する姿勢を見せます。
二谷と芦川さんの恋愛
二谷と芦川さんは恋人関係になります。芦川さんは三度目のデートで、ひとり暮らしの二谷の食生活にアドバイスを始め、二谷をいらつかせます。しかし、二谷は正しいのは芦川さんだと思い、顔は平然としたまま、心の中で毒づくだけです。
恋人になった芦川さんは、かいがいしく二谷に体に良くておいしいものを作り、食べさせようとします。しかし、彼女は二谷の部屋に積まれた本には気づかず、話題にもしません。二谷にとって、部屋の床に積まれた本たちとカップ麺は、必死に守っているものの象徴です。
芦川さんが夕飯を作りにくると、決まって二谷は芦川さんの寝静まった夜中に、ひとりカップ麺をすすります。それは、自分のテリトリーに侵入してくる他者の価値観への抵抗の形です。また、二谷は芦川さんの手作りお菓子を見えないところで踏み、ぐちゃぐちゃにして捨てるという行為も行います。
食べることへの違和感と抵抗
二谷にとって、「みんなで食べるご飯を、おいしいと感じること」は、他人には軽々とできることであり、できない自分が悪いのだと責められる気がするものです。だからこそ、敵視することで、ようやく自分を守ってきました。
押尾はそのような二谷の感覚を理解し、「できないのではなく、必要がないのだ」と言います。自分と似ているようでまるで違う押尾の考えに触れ、一瞬、勇気をもらった気がした二谷は、言うつもりのなかった秘密を打ち明けます。
しかし、二谷は結局、相変わらず職場の人たちにも、芦川さんにも屈し続けます。自分が嫌う古い価値観の中から飛び出せないのです。一方、押尾は最終的に会社を去る選択をします。
物語の核心
「食」を通して描かれる同調圧力
この物語の核心は、「食」という日常的な行為を通して描かれる同調圧力です。「丁寧な暮らし」や「ちゃんとした食」が社会的に支持されている風潮の中で、それに違和感を覚えながらも表立って反発できない状況が鮮やかに描かれています。
特に、みんなで食事をする場面での「おいしい」という言葉の強制力は、現代社会における同調圧力の象徴として機能しています。二谷にとって、「みんなで食べるご飯を、おいしいと感じること」は、他人には軽々とできることであり、できない自分が悪いのだと責められる気がするものです。
また、「丁寧な食」を重視する芦川さんの存在も、現代社会における特定の価値観の押し付けを象徴しています。彼女は二谷に「正しい」食生活を教えようとしますが、それは二谷の内面や本当の興味を無視したものです。
二谷の内面と外面の乖離
物語のもう一つの核心は、二谷の内面と外面の乖離です。二谷は職場ではそつなく振る舞い、恋人の芦川さんにも表面上は従順ですが、内心では強い違和感と抵抗を感じています。
この乖離は、特に食事のシーンで顕著に表れます。芦川さんの手料理を食べた後でこっそりカップ麺を食べる行為や、彼女の手作りお菓子を踏みつぶして捨てる行為は、表面上は受け入れながらも内心では拒絶するという二谷の二面性を象徴しています。
二谷のこのような行動は、自分の本当の感情を表に出せない現代人の姿を映し出しています。彼は自分の内面をさらすことを恐れ、表面上は社会に適応しながらも、密かに抵抗を続けています。
カップ麺という象徴的な抵抗
物語の中で、カップ麺は二谷の抵抗の象徴として機能しています。芦川さんが作った「丁寧なごはん」を食べた後に、こっそり食べるカップ麺は、二谷にとって自分のテリトリーに侵入してきた他者の価値観を祓い清める儀式のようなものです。
また、カップ麺は二谷が必死に守っている自分自身の一部でもあります。彼の部屋の床に積まれた本たちとともに、カップ麺は二谷の内面の象徴として描かれています。
しかし、物語の中で二谷は、押尾との会話の後、カップ麺を食べようとしてやめるシーンがあります。これは、彼が自分の内面と向き合い始めた瞬間を象徴しているとも読み取れます。
作品の特徴
シンプルな文体と深い心理描写
高瀬隼子さんの文体は、シンプルで癖がないながらも、登場人物の複雑な心理を鮮やかに描き出しています。特に二谷の内面の描写は繊細で、表面上は平静を装いながらも、内心では様々な感情が渦巻いている様子が生き生きと伝わってきます。
例えば、芦川さんの手作りケーキを食べるシーンでは、「もったり、甘ったるい、ニチャニチャ」といった表現が用いられ、二谷の嫌悪感が読者に強く伝わってきます。このような表現は、文学的な技巧として非常に効果的です。
また、登場人物の行動や言葉の裏にある本当の感情や意図を、直接的な説明ではなく、細かな描写の積み重ねによって浮かび上がらせる手法も、この作品の特徴です。
日常に潜む不穏さの表現
この作品は、一見平穏な日常の中に潜む不穏さを鮮やかに描き出しています。特に、食事という日常的な行為の中に潜む違和感や圧力、そして人間関係の複雑さが、読者の心をざわつかせます。
物語の中では、「不穏」で「ざわつく」心の乱れを引き起こすような罠が、あちこちに張り巡らされています。例えば、芦川さんの手作りお菓子を食べるシーンや、職場での食事シーンなど、一見何気ない場面の中に、読者の心を揺さぶる要素が散りばめられています。
高瀬隼子さんは、このような不穏さを、過剰な表現や派手な展開ではなく、むしろ抑制された文体と日常的な場面の中に忍ばせることで、より強い印象を読者に与えることに成功しています。それは、私たちの日常にも同じような不穏さが潜んでいることを暗示しているかのようです。
「当たり前」への問いかけ
この作品のもう一つの特徴は、「当たり前」とされていることへの鋭い問いかけです。特に、「食べること」や「おいしいと感じること」が当たり前とされている社会の中で、それに違和感を覚える人の存在を描くことで、私たちが無意識に受け入れている価値観に疑問を投げかけています。
二谷は、「みんなで食べるご飯を、おいしいと感じること」ができない自分を責めながらも、同時にそれを強制する社会に対して密かな抵抗を続けています。この姿勢は、現代社会における「当たり前」の押し付けに対する問題提起として機能しています。
また、押尾の「できないのではなく、必要がないのだ」という言葉は、社会的な「当たり前」に対する強烈な異議申し立てであり、読者に新たな視点を提供しています。
社会的背景
「丁寧な暮らし」ブームと違和感
この作品が書かれた背景には、近年の「丁寧な暮らし」ブームがあります。SNSなどで「丁寧な食」や「丁寧な暮らし」が称揚される風潮の中で、それに違和感を覚える人々の存在も確かにあります。
芦川さんが体現する「丁寧な食」への価値観は、現代社会で一定の支持を得ているものです。しかし、それが時に他者への押し付けになり、息苦しさを生み出すこともあります。この作品は、そのような社会的背景を鋭く切り取っています。
特に、「丁寧な暮らし」が一種のステータスとなり、それができない人を暗に劣った存在として扱う風潮への批判が、この作品には込められています。二谷のカップ麺への執着は、そのような風潮への抵抗の象徴として読み取ることができます。
現代日本の食文化の変遷
この作品は、現代日本の食文化の変遷も背景としています。かつては「家庭料理」が当たり前だった時代から、コンビニ食やインスタント食品が普及し、食の多様化が進んだ現代において、何が「正しい食」なのかという問いは、より複雑になっています。
芦川さんが体現する「手作り」や「丁寧」という価値観と、二谷が密かに求めるカップ麺の手軽さは、このような食文化の変遷の中での価値観の対立を象徴しています。
また、この作品では「食」が単なる栄養摂取の手段ではなく、社会的なコミュニケーションや価値観の表明の場となっている現代社会の姿も描かれています。「みんなで食べて、おいしいと言い合う」という行為が、時に個人の本当の感覚を押し殺すことにつながる皮肉も、鋭く描き出されています。
個人の価値観と社会の期待の衝突
この作品の根底にあるのは、個人の価値観と社会の期待の衝突というテーマです。二谷は、社会的に期待される「正しい食生活」や「正しい感じ方」に違和感を覚えながらも、表面上はそれに合わせようとします。一方、押尾はそのような期待に対して明確な拒否の姿勢を示します。
このような個人と社会の関係性は、食に限らず、現代社会のあらゆる場面で見られるものです。「正しい生き方」や「正しい感じ方」が社会的に規定され、それに合わない人が疎外感を感じる状況は、多くの読者の共感を呼ぶものでしょう。
特に日本社会においては、「空気を読む」ことや「和を乱さない」ことが重視される傾向があり、そのような文化的背景が、この作品の登場人物たちの行動や心理にも影響を与えています。
感想・レビュー
心をざわつかせる不穏な魅力
高瀬隼子さんの「おいしいごはんが食べられますように」を読み終えて、私の心には不思議なざわめきが残りました。この作品の最大の魅力は、一見何気ない日常の描写の中に、読者の心をざわつかせる不穏な要素を忍ばせる技術にあると感じます。
特に印象的だったのは、二谷が芦川さんの手作りケーキを食べるシーンです。「もったり、甘ったるい、ニチャニチャ」という表現は、読者の五感に直接訴えかけるような生々しさがあり、二谷の嫌悪感が痛いほど伝わってきます。このような描写は、高瀬さんの文学的センスの高さを示すものでしょう。
また、この作品が投げかける問い—「当たり前」とされていることへの疑問—は、読者である私自身の日常生活にも新たな視点をもたらしてくれました。「みんなで食べて、おいしいと言い合う」ことが本当に幸せなのか、「丁寧な暮らし」が本当に理想なのか、そのような問いを考えさせられる機会となりました。
共感と違和感が交錯する読書体験
この作品を読んでいて興味深かったのは、登場人物たちに対して共感と違和感が交錯する感覚です。二谷の内面の葛藤には共感する部分がある一方で、彼の行動—特に芦川さんの手作りお菓子を踏みつぶして捨てるような行為—には違和感も覚えます。
しかし、そのような複雑な感情こそが、この作品の深みを生み出しているのではないでしょうか。人間は誰しも、表向きの自分と内面の自分の間で葛藤を抱えています。二谷のような極端な形ではなくとも、社会的な「正しさ」に合わせようとする自分と、本当の気持ちの間で揺れ動く経験は、多くの読者に共通するものでしょう。
また、押尾という存在も非常に興味深いです。彼女は二谷と似た感覚を持ちながらも、それに対する対処の仕方が全く異なります。「できないのではなく、必要がないのだ」という彼女の言葉は、社会的な「当たり前」に対する強烈な異議申し立てであり、読者に新たな視点を提供してくれます。
高瀬隼子さんの視点の独自性
高瀬隼子さんの視点の独自性は、これまであまり言葉にされてこなかった感覚や違和感を鮮やかに言語化する能力にあると感じます。「食べること」や「おいしいと感じること」が当たり前とされている社会の中で、それに違和感を覚える人の存在を描くことで、私たちが無意識に受け入れている価値観に疑問を投げかけています。
また、高瀬さんの文体は、シンプルで癖がないながらも、登場人物の複雑な心理を鮮やかに描き出す力を持っています。特に二谷の内面の描写は繊細で、表面上は平静を装いながらも、内心では様々な感情が渦巻いている様子が生き生きと伝わってきます。
この作品が芥川賞を受賞したのも納得できます。日常の中に潜む不穏さを描き出す力、そして社会的な「当たり前」に疑問を投げかける視点は、現代文学に新たな風を吹き込むものだと感じました。
まとめ
高瀬隼子さんの「おいしいごはんが食べられますように」は、「食」という日常的な行為を通して、現代社会における同調圧力や個人の葛藤を鋭く描き出した作品です。シンプルな文体と繊細な心理描写によって、読者の心をざわつかせる不穏な魅力を持っています。
この作品は、私たちが無意識に受け入れている「当たり前」に疑問を投げかけ、個人の価値観と社会の期待の衝突という普遍的なテーマを、「食」という身近な切り口から描き出しています。それは、現代社会を映し出す鏡としての役割も果たしています。
読者それぞれが自分自身の「食」への向き合い方を問い直すきっかけとなる、そんな奥深い作品です。高瀬隼子さんの芥川賞受賞は、このような新たな視点を文学に持ち込んだ功績を評価したものと言えるでしょう。