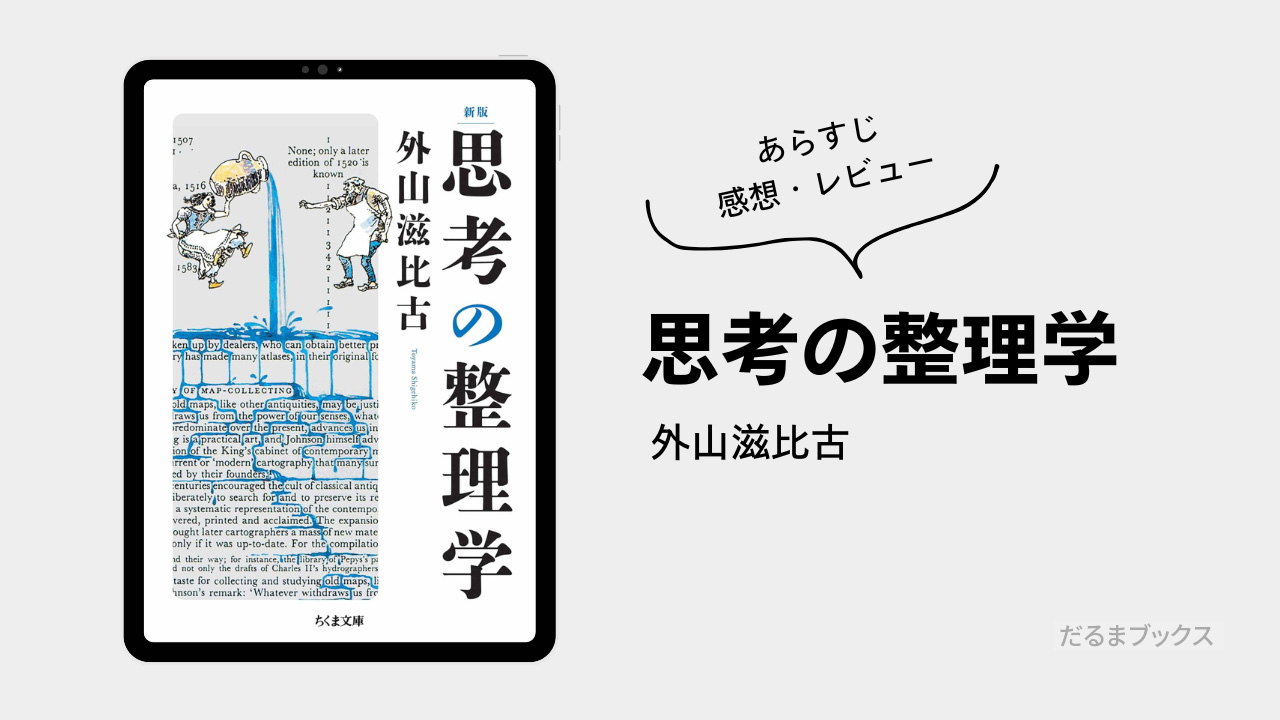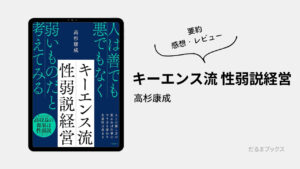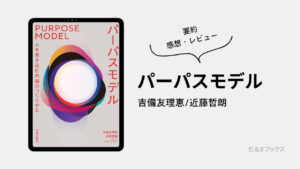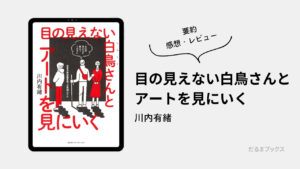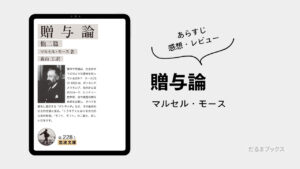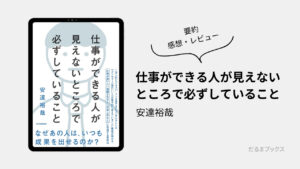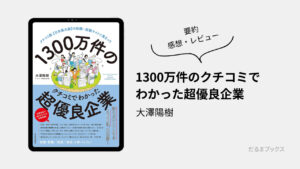思考を整理する方法を知りたいと思ったことはありませんか?
頭の中がごちゃごちゃして、アイデアが浮かんでも形にできない。そんな悩みを解決してくれるのが外山滋比古さんの『思考の整理学』です。この本は1983年に刊行され、40年以上読み継がれている名著。
東大・京大生からも根強い支持を得ている本書には、自分の頭で考え、アイデアを軽やかに離陸させるための具体的な方法が詰まっています。今回は、この思考の整理学の核心に迫り、あなたの思考力を高めるヒントをお伝えします。
グライダー型人間から飛行機型人間へ
私たちの周りには、二種類の人間がいます。一つは知識を受動的に得るだけの「グライダー型人間」。もう一つは自ら考え行動する「飛行機型人間」です。
二種類の人間タイプ
外山さんは、現代社会における人間のタイプを二つに分類しています。一つ目は「グライダー型人間」。このタイプは、学校教育に代表されるような受動的な学習スタイルを持ち、与えられた知識を吸収することに長けています。グライダーは美しく優雅に空を滑空しますが、自力で離陸することはできません。つまり、誰かに引っ張ってもらわなければ飛び立てないのです。
これに対して「飛行機型人間」は、自分の力で地上から飛び立ち、自ら方向を決めて飛んでいくことができます。自分で物事を発明・発見し、能動的に考え行動するタイプです。
現代社会では、情報があふれ、知識だけを持っている「グライダー型人間」の価値は下がっています。一方で、社会の課題を見つけ、自ら解決策を考え出す「飛行機型人間」の価値は高まる一方です。スティーブ・ジョブズやイーロン・マスクのような革新者たちは、まさに「飛行機型人間」の典型と言えるでしょう。
受動的学習からの脱却
では、どうすれば「グライダー型人間」から「飛行機型人間」へと進化できるのでしょうか。外山さんは、学校教育で身につけた知識を否定しているわけではありません。むしろ、その知識をベースにしながら、自分で考える力を養うことの重要性を説いています。
現代の教育システムには問題があります。多くの場合、知識を一方的に与えるだけで、それをどう活用するかという視点が欠けています。テストで高得点を取ることが目的化し、本当の意味での「考える力」が育まれていないのです。
「飛行機型人間」になるためには、受動的な学習から脱却し、自ら問いを立て、答えを探す姿勢が必要です。与えられた情報を鵜呑みにするのではなく、常に「なぜ?」と問いかける習慣を身につけることが大切です。そして、その問いに対する答えを自分なりに考え、行動に移していく。そうした積み重ねが、やがて「飛行機型人間」への進化をもたらすのです。
思考の整理とは何か
思考を整理するとはどういうことでしょうか。外山さんは、思考の整理には二つの重要な側面があると説明しています。
低次の思考から高次の思考へ
一つ目は、「低次の思考をメタ化させ、高次の思考に変換する」ことです。低次の思考とは、いわゆる「思いつき」のこと。本書では「第一次思考」とも呼ばれています。これは断片的な情報に過ぎず、それだけでは大きな価値を生み出しません。
重要なのは、この低次の思考を高次の思考(第二次思考)に変換することです。具体的には、「発酵」「混合」「アナロジー」などの手法を使って思いつきを抽象化し、メタ的な情報に変えていきます。
例えば、ある商品のアイデアが浮かんだとします。それをそのまま形にするのではなく、他のアイデアと組み合わせたり、全く異なる分野の概念を応用したりすることで、より価値の高いアイデアに発展させることができます。これが「思いつき」を「価値を生み出すアイデア」に変える過程なのです。
思考をメタ化するとは、自分の思考を一段高い視点から眺めることでもあります。「なぜこう考えたのか」「この考えにはどんな前提があるのか」と自問自答することで、思考の質を高めていくのです。
忘却の技術
思考の整理の二つ目の側面は、「いかにうまく忘れるか」ということです。私たちの脳の容量は限られています。あれもこれもと記憶しようとすると、かえって思考する余裕がなくなってしまいます。
外山さんは、人の頭は在庫を抱えすぎた工場のようにぐちゃぐちゃになってはいけないと言います。必要な情報を取捨選択し、不要なものは思い切って忘れる。そうすることで、頭の中にスペースが生まれ、新たな思考が生まれやすくなるのです。
忘却の最も効果的な方法は「睡眠」です。人間の脳は睡眠中に、その日得た情報を整理し、重要なものとそうでないものを選別します。本書では、1日7時間以上の睡眠を取ることが推奨されています。十分な睡眠を取ることで、脳は自然と必要な情報を残し、不要な情報を忘れていくのです。
しかし、忙しい現代人にとって、毎日十分な睡眠を確保するのは難しいかもしれません。そこで外山さんは、人為的に忘却を促す方法も提案しています。一つはメモを残すこと。重要なことは忘れないように書き留めておき、それ以外のことは忘れてしまう。特に、自分に対する問いかけの形でメモを残すと効果的です。
もう一つは、全く別の問題に取り組むことです。行き詰まった問題から一度離れ、全く異なる活動に没頭する。散歩に出かけたり、友人と遊んだり、趣味に打ち込んだりすることで、脳はリフレッシュし、元の問題に対する新たな視点が生まれることがあります。
思考を整理する具体的な方法
思考を整理するための具体的な方法として、外山さんは二つの重要なアプローチを提案しています。
書くことの力
一つ目は「とにかく書いてみる」ことです。外山さんは、「考える行為は立体的、書く行為は線状的」だと説明しています。頭の中では複数の考えが同時に存在し、複雑に絡み合っていますが、それを紙に書き出す際には、必然的に一つずつ順番に書くことになります。
この過程で、頭の中であいまいだった優先順位が明確になり、思考が整理されていくのです。書くことで、自分が本当に言いたいことは何なのか、どの順番で伝えるべきなのかが見えてきます。
書く際のポイントは、一度書き始めたら途中で止まらず、結論まで書き切ることです。途中で立ち止まると、思考の流れが途切れてしまいます。まずは一気に書き上げ、その後で推敲するというプロセスが効果的です。
推敲の段階では、単なる文言の修正ではなく、構造的な変更が必要になることもあります。例えば、文章の一部を前半に移動させたり、結論部分を強化したりといった大胆な「手術」を施すのです。そうして推敲を重ね、最終的に無駄のない簡潔なタイトルがつけられるようになれば、思考の整理は完成したと言えるでしょう。
書くという行為は、思考を外部化し、客観的に見つめ直す機会を与えてくれます。頭の中だけでぐるぐる考えているときには気づかなかった矛盾や飛躍が見えてくることもあります。また、書くことで思考が定着し、後から振り返ることも容易になります。
異質な他者との対話
思考を整理するもう一つの方法は、「自分とは異なる思考を持つ人と話す」ことです。生物学の用語で「インブリーディング(近親交配)」という言葉がありますが、同じ分野の人ばかりと話していると、思考が狭い範囲で循環し、新たな発想が生まれにくくなります。
自分とは異なる専門性や価値観を持つ「異質な他者」と対話することで、自分のアイデアの不足している部分に気づいたり、思いもよらない方向に発想が広がったりすることがあります。異なる視点からの質問や意見は、自分の思考の盲点を照らし出し、より深い理解や新たな発見をもたらすのです。
また、対話の過程で自分の考えを言葉にすることも重要です。思考の整理は、なるべく多くの「チャネル」を通すことで進みます。頭で考え、手で書き、口で話し、さらに相手の反応を受け止める。こうした複数のチャネルを経由することで、思考はより洗練されていくのです。
対話の相手は必ずしも専門家である必要はありません。むしろ、その分野に詳しくない人に説明することで、自分の理解の浅さや説明の不十分さに気づくことがあります。「素人にもわかるように説明する」という姿勢は、自分の思考を整理する上で非常に有効なのです。
情報の整理と活用法
情報過多の現代社会では、膨大な情報をどう整理し、活用するかが重要な課題となっています。外山さんは、効果的な情報整理の方法についても詳しく解説しています。
メモの取り方
情報を整理する上で欠かせないのが「メモ」です。外山さんは、メモの取り方にもコツがあると言います。
まず、スクラップの方法です。興味を引いた記事や情報をただ切り抜いて保存するだけでは不十分です。なぜその情報に興味を持ったのか、どんな点が重要だと思ったのかを簡単にでも書き添えておくことで、後から見返したときに文脈が理解しやすくなります。
次に、カードやノートの活用法です。外山さんは、情報をカード化することを推奨しています。一枚のカードには一つのアイデアや情報だけを書き、それを自由に並べ替えたり組み合わせたりすることで、新たな発想が生まれやすくなります。現代ではデジタルツールを使って同様のことができますが、物理的なカードの持つ触感や空間的な配置の自由さには独自の価値があります。
さらに、メタ・ノートの作成も重要です。これは、自分が取ったメモやノートを俯瞰し、そこから見えてくるパターンや傾向をまとめたノートのことです。個々の情報の断片からより大きな全体像を把握するために役立ちます。
メモを取る際のポイントは、自分の言葉で書くことです。本や記事の内容をそのまま写すのではなく、自分なりに咀嚼して書き留めることで、理解が深まり、記憶にも残りやすくなります。また、疑問形でメモを残すことも効果的です。「なぜこの現象が起こるのか?」「この理論は他の分野にも応用できるのか?」といった問いかけは、後から見返したときに思考を活性化させます。
つんどく法
外山さんが提唱する情報活用法の一つに「つんどく法」があります。これは、同じテーマに関する本を複数集めて、短期間のうちに集中して読むという方法です。
一冊の本を読んだだけでは、その著者の視点や偏りに影響されがちです。しかし、同じテーマについて複数の著者の本を読むことで、多角的な視点が得られ、より立体的な理解が可能になります。
また、記憶が薄れる前にまとめることも重要です。本を読んだ直後は内容をよく覚えていますが、時間の経過とともに忘れていきます。複数の本を読み終えたら、できるだけ早くその内容を比較・検討し、自分なりの見解をまとめておくことが大切です。
つんどく法の利点は、分野の全体像を把握しやすくなることです。一冊だけでは見えてこない、その分野の共通認識や論争点、最新の動向などが見えてきます。また、複数の本を並行して読むことで、一冊の本の偏りや不十分な点を補完することもできます。
この方法は、新しい分野を学ぶときに特に効果的です。最初から専門書に取り組むのではなく、まずは入門書や概説書を複数読んで全体像を把握し、その後で興味を持った部分について専門的な文献に進むというステップを踏むことで、効率的に学習を進めることができます。
知的活動の3つのレベル
外山さんは、知的活動には3つのレベルがあると説明しています。それぞれのレベルで思考の整理の方法も異なります。
既知のことの確認
一つ目のレベルは「既知のことの確認」です。これは、自分がすでに知っていることを再確認し、整理する段階です。
基礎知識の重要性は、どんな分野でも変わりません。複雑な問題を解決するためには、まず基本をしっかり押さえておく必要があります。既知のことを確認することで、自分の知識の土台を強化し、より高度な思考の準備をするのです。
確認読書も、このレベルの知的活動の一つです。一度読んだ本を再読することで、初読時には気づかなかった点に気づいたり、自分の理解が深まったりすることがあります。特に、初読から時間が経った後の再読は、自分の成長を実感する機会にもなります。
このレベルでの思考の整理は、知識を体系化し、関連付けることが中心となります。バラバラに覚えていた知識を、相互の関係性を意識しながら整理していくのです。例えば、歴史上の出来事を単なる年表として覚えるのではなく、因果関係や時代背景との関連で理解することが大切です。
未知のことの理解
二つ目のレベルは「未知のことの理解」です。これは、自分がまだ知らない新しい知識や概念を学び、理解する段階です。
新しい知識を獲得する方法はさまざまですが、外山さんは「つなぎ合わせる」ことの重要性を強調しています。全く新しいことを一から学ぶのは難しいものです。しかし、既に持っている知識と関連付けることで、理解が容易になります。
例えば、新しい言語を学ぶ際、その言語の単語や文法を既知の言語と比較することで、共通点や相違点が見えてきます。また、専門用語を学ぶときも、その言葉の語源や構成要素を分析することで、意味を推測しやすくなります。
理解のプロセスも重要です。外山さんは、理解には時間がかかることを強調しています。難解な文章も繰り返し読んでいると、いつのまにか「なんとなく親しい気持ち」を持つようになります。これは、未知の対象とわかろうとする人間が、少しずつ変化して通じ合うところまで近づいていく過程なのです。
また、理解を深めるためには、比喩の力も重要です。既知から未知を類推する際、比喩の作用が大きな役割を果たします。私たちが未知の言葉を理解できるのも、この比喩の方法による発見があるからだと言えるでしょう。例えば、「電子」という目に見えない粒子を理解するために、「小さな球」というイメージを用いることがあります。これは、既知の「球」という概念を使って、未知の「電子」を理解しようとする試みです。
新しい世界への挑戦
三つ目のレベルは「新しい世界への挑戦」です。これは、既存の枠組みを超えて、全く新しい発想や創造を生み出す段階です。
外山さんは、この段階では「解釈すら拒む」ような対象に挑戦することが重要だと説きます。一度や二度では理解できないような難解な文献や問題に、何度もぶつかっていく。そうすることで、やがて少しずつおぼろげながら理解が進んでいくのです。
この過程では、読む人が自分の想像力、直観力、知識などをその限界まで総動員して、ついには「自分の解釈」に至るという思考的活動が求められます。外山さんは、日本における漢文の素読を例として挙げています。これは音声だけで意味は全く教えない幼児期の教育法ですが、一見乱暴なようでありながら、一挙に「新しい世界に挑戦する」という読みの本丸に突入するような試みであり、実際にすぐれた未知を読む読者を育成したと考えられています。
創造的思考を育むためには、異なる分野の知識を組み合わせることも効果的です。例えば、音楽と数学、文学と科学といった一見関係のない分野を結びつけることで、新たな発想が生まれることがあります。外山さんは、こうした「異質な結合」から生まれる創造性を重視しています。
また、セレンディピティ(偶然の発見)を活用することも大切です。計画通りに物事を進めるだけでなく、時には予想外の出来事や失敗から学ぶ姿勢を持つことで、思いもよらない発見につながることがあります。例えば、フレミングがペニシリンを発見したのは、実験中のカビの繁殖という「失敗」がきっかけでした。こうした偶然の発見を見逃さない感性を養うことも、創造的思考には欠かせません。
感想・レビュー
『思考の整理学』を読んで、最も印象に残ったのは、思考とは単なる知識の蓄積ではなく、それをいかに整理し、活用するかが重要だという点です。現代は情報過多の時代。スマートフォンやインターネットの普及により、私たちは膨大な情報に常に晒されています。しかし、情報を得ることと、それを自分の思考に取り入れることは全く別の問題なのです。
現代社会における本書の価値
本書が書かれたのは1983年、まだインターネットが一般的ではない時代でした。それにもかかわらず、外山さんの指摘する「情報過多」の問題は、現代においてより深刻になっています。SNSやニュースサイト、動画配信サービスなど、私たちの注意を引くメディアは増える一方です。そんな中で、自分の頭で考え、情報を取捨選択する能力は、ますます重要になっているのです。
私自身、本書の「つんどく法」を実践してみました。同じテーマの本を数冊集めて、短期間で読み通す。すると、一冊だけでは見えてこなかった視点や論点が浮かび上がってきます。著者によって強調点が異なり、それぞれの主張の背景も見えてくる。これは、単に本を読むだけでなく、その内容を比較・検討することで、より深い理解につながるのだと実感しました。
また、メモの取り方も変えてみました。以前は本の内容をそのまま書き写すことが多かったのですが、本書を読んでからは、自分の言葉で要約したり、疑問形でメモを残したりするようになりました。すると、後から見返したときに、単なる情報の記録ではなく、自分の思考のきっかけとして機能するようになったのです。
著者の文体と説得力
外山さんの文体は、学術書にありがちな堅苦しさがなく、エッセイとして非常に読みやすいものになっています。専門用語を多用せず、身近な例を挙げながら説明するスタイルは、読者の理解を助けます。
特に印象的なのは、具体例の豊富さです。「グライダー型人間」と「飛行機型人間」という比喩や、「つんどく法」といった独自の方法論など、抽象的な概念を具体的なイメージに置き換える技術は見事です。これは、本書で説かれている「未知のことを理解する」ための方法論が、実際に本書自体にも活かされているということでしょう。
また、外山さんの主張には説得力があります。それは、単なる理論ではなく、著者自身の長年の経験から導き出された知見だからでしょう。文学者としての研究、執筆、教育の経験が、随所に活かされています。「これは私の経験だが」という書き出しで始まるエピソードは、読者に親近感を抱かせるとともに、その主張の信頼性を高めています。
まとめ
『思考の整理学』は、単なる思考法や記憶術の本ではありません。それは、私たちが情報とどう向き合い、どのように自分の頭で考えるかという、より本質的な問いに迫る一冊です。
外山さんが提唱する「グライダー型人間」から「飛行機型人間」への進化は、現代社会においてより重要性を増しています。与えられた情報を受動的に受け取るだけでなく、自ら考え、創造する力が求められているのです。
本書から学べる最も重要なことは、思考の質を高めるためには、情報の量ではなく、その整理の仕方が重要だということでしょう。書くこと、対話すること、忘れることなど、外山さんが提案する方法は、どれも日常生活の中で実践できるものばかりです。
思考の整理学の核心は、自分の頭で考えることの楽しさと重要性を再認識させてくれることにあります。情報過多の時代だからこそ、この本の価値は色あせることなく、むしろ増しているのではないでしょうか。