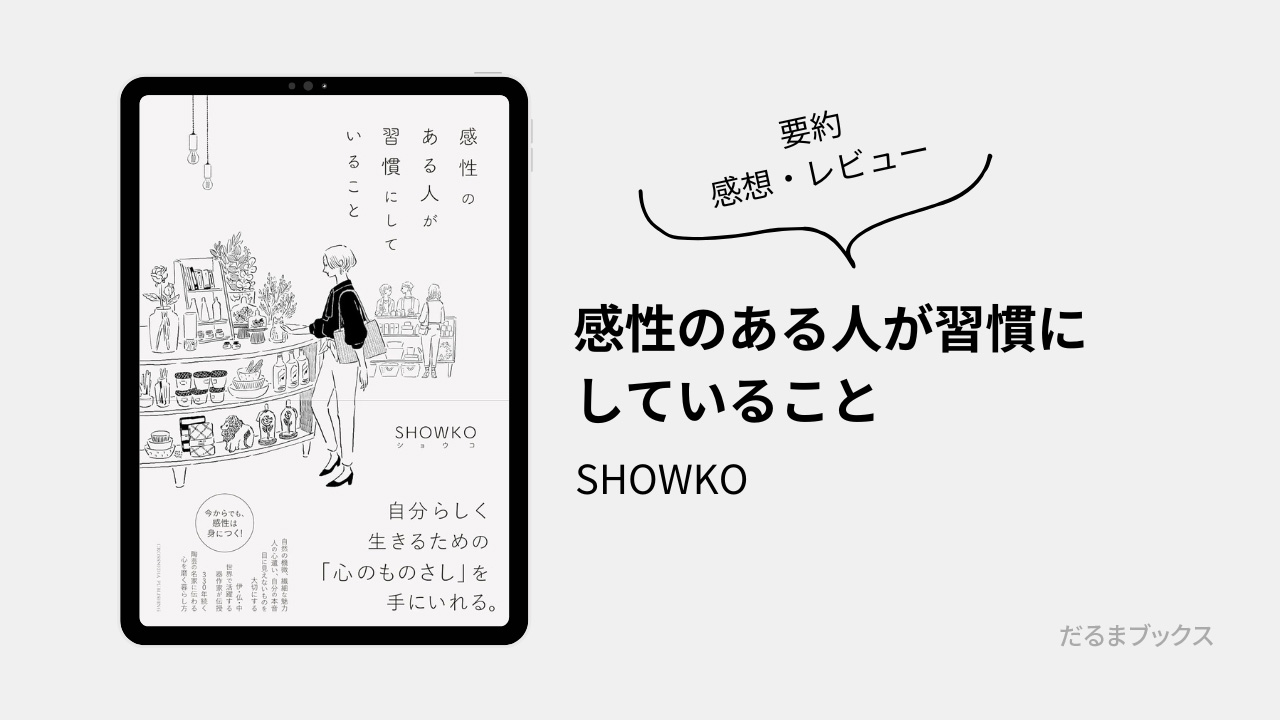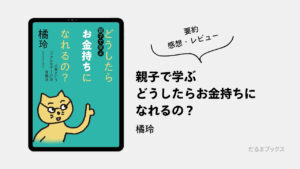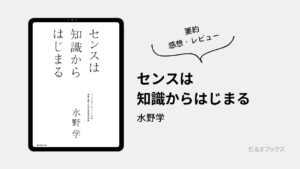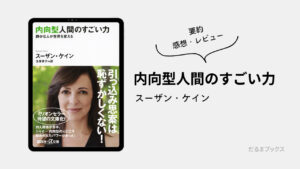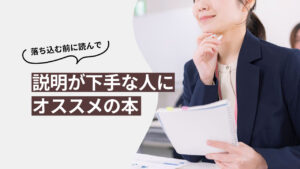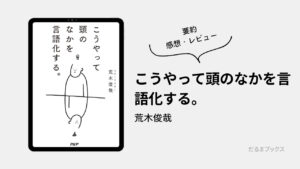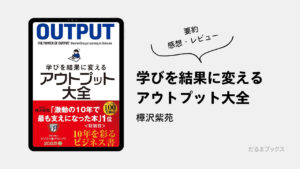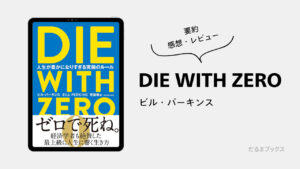京都で330年の歴史を持つ茶道具の窯元に生まれ、世界で活躍する陶芸家SHOWKOさんの著書「感性のある人が習慣にしていること」。
この本では、感性は生まれつきの才能ではなく、日々の習慣によって養われるものだという視点から、具体的な実践法が解説されています。
正解のない時代に自分で答えを見つける力、繊細な美しさに気づく目、そして自分らしい選択ができる感性を磨くヒントが詰まった一冊です。
感性のある人とは
正解のないことに自分で答えを出せる人
現代社会では、正解が一つではない問題に直面することが増えています。そんな時、自分なりの答えを導き出せる人こそが感性のある人といえるでしょう。SHOWKOさんは、感性とは「目に見えないものに価値を感じる力」だと定義しています。
たとえば、料理を作る時、レシピ通りに材料を計量して作るのではなく、その日の気分や食材の状態を見て、少し味付けを変えてみる。そんな微調整ができる人は、感性が豊かだといえます。感性のある人は、マニュアルや他人の評価に頼るのではなく、自分自身の感覚を信じて判断することができるのです。
自分の価値観で選択ができる人
感性が豊かな人は、自分の価値観をしっかりと持っています。流行に流されず、「これが好き」「これが心地よい」という自分だけの基準で選択することができます。
SHOWKOさんは、自分の工房で作品を制作する際、流行のデザインや他の作家の作風に影響されるのではなく、自分が本当に表現したいものを追求しています。そうした姿勢が、世界で評価される独自の作風につながっているのでしょう。
感性のある人は、他人の目を気にしすぎず、自分の内側から湧き上がる感覚を大切にします。そして、その感覚に従って選択することで、自分らしい人生を歩んでいくのです。
人の繊細な気持ちに理解を示せる人
感性が豊かな人は、自分の感覚だけでなく、他者の繊細な気持ちにも敏感です。言葉にされていない感情や、微妙な表情の変化から、相手の本当の気持ちを読み取ることができます。
たとえば、会話の中で相手が少し言葉を詰まらせたとき、その背後にある感情に気づくことができるのは、感性の豊かさの表れです。また、空気を読むという日本人特有の感覚も、感性の一つといえるでしょう。
SHOWKOさんは、茶道の家に生まれ育ったことで、「もてなし」の心を自然と身につけたといいます。相手の立場になって考え、相手が何を求めているかを察する力。それは、感性を磨くことで培われる大切な能力なのです。
感性を高める5つの習慣
SHOWKOさんは、感性を高めるために大切な5つの習慣を紹介しています。これらは特別なものではなく、日常生活の中で意識的に取り入れることができる習慣ばかりです。
観察する習慣
感性を高める第一歩は、日常の中で「観察する習慣」を身につけることです。私たちは普段、多くのものを見ていますが、本当の意味で「観察」しているとは限りません。ただ漠然と見るのではなく、意識的に細部まで注意を向けることが大切です。
例えば、通勤や通学の道すがら、いつもと同じ景色の中に季節の変化を見つけたり、行きつけのカフェで使われている食器の質感や色合いに注目したりすることから始められます。観察力を高めることで、今まで気づかなかった世界の美しさや面白さに気づくようになるのです。
整える習慣
感性を磨くためには、自分の身の回りの環境を「整える習慣」も重要です。部屋が散らかっていると思考も散らかりがちですが、空間が整理されていると、心も整い、感性が研ぎ澄まされていきます。
SHOWKOさんは、毎朝工房に入る前に、作業台を丁寧に拭き、道具を配置し直すことから一日を始めるそうです。この小さな儀式が、創作活動に向けて心を整える大切な時間となっています。
整えるのは物理的な環境だけではありません。心を整えることも同様に大切です。例えば、朝の数分間、静かに呼吸を整えたり、夜寝る前に一日を振り返る時間を持ったりすることで、心の中の雑念を取り除き、感性を磨く土台を作ることができます。
視点を変える習慣
感性を高めるためには、物事を多角的に見る「視点を変える習慣」も欠かせません。私たちは無意識のうちに、自分の経験や価値観に基づいた「初期設定」で物事を判断しがちです。しかし、その初期設定を疑い、別の角度から見てみることで、新たな発見や気づきが生まれます。
例えば、いつも使っている道具の別の使い方を考えてみたり、困った状況をチャンスと捉え直してみたりすることで、創造性が刺激されます。SHOWKOさんは、陶芸の技法においても、伝統的な方法にとらわれず、自分なりの解釈や新しい技法を取り入れることで、独自の表現を生み出しています。
視点を変えるためには、異なる文化や価値観に触れることも効果的です。旅行や読書、異業種の人との交流など、自分の世界を広げる経験を積極的に取り入れることで、柔軟な思考力と豊かな感性が育まれていくのです。
好奇心を持つ習慣
感性を磨くためには、子どものような純粋な「好奇心を持つ習慣」が大切です。大人になるにつれて、「こんなことを聞いたら恥ずかしい」「知らないことを知られたくない」という思いから、好奇心を抑え込んでしまうことがあります。しかし、感性を高めるためには、そうした恥ずかしさを手放し、素直に「知りたい」「やってみたい」という気持ちを大切にすることが必要です。
SHOWKOさんは、新しい土や釉薬に出会うたびに、「これはどんな風に焼き上がるだろう」と実験を重ねるそうです。失敗を恐れず、好奇心に従って試行錯誤することが、独自の技法の開発につながっています。
好奇心を持ち続けるためには、自分の「好き」の領域を広げることも大切です。いつも同じジャンルの本や音楽ではなく、あえて普段触れないものに挑戦してみる。そうした小さな冒険が、感性を豊かにする栄養となるのです。
決める習慣
感性を磨くためには、「決める習慣」も重要です。日常生活では、大小さまざまな選択を迫られますが、その一つ一つの選択に意識を向け、自分の感覚で決断する習慣をつけることで、感性は鍛えられていきます。
例えば、服を選ぶとき、流行や他人の評価ではなく、自分が本当に心地よいと感じるものを選ぶ。レストランでメニューを選ぶとき、値段や人気ではなく、その日の自分の気分や体調に合わせて選ぶ。そうした日常の小さな決断の積み重ねが、自分の感性を信頼する力を育てていくのです。
SHOWKOさんは、作品制作の過程でも、「この色合いでいいのか」「この形は美しいか」と常に自問自答し、自分の感覚を信じて決断しています。そうした決断の連続が、独自の作風を形作っているのでしょう。
観察する習慣を身につける方法
肌感覚で気温を当ててみる
感性を磨くための具体的な方法として、SHOWKOさんは「肌感覚で気温を当てる」ことを勧めています。現代では、スマートフォンで気温をすぐに確認できるため、自分の感覚を使う機会が減っています。しかし、朝起きて窓を開け、外の空気を肌で感じ、「今日は何度くらいだろう」と予想してみる。そして実際の気温と比較する。この小さな習慣を続けることで、微細な変化に気づく感覚が鍛えられていきます。
最初は5度も10度も違うかもしれませんが、続けていくうちに、徐々に精度が上がっていくはずです。そして、気温だけでなく、湿度や気圧の変化なども感じ取れるようになるでしょう。こうした感覚の鋭さは、料理や創作活動など、さまざまな場面で役立つものです。
同義語を学び言葉の世界を広げる
感性を磨くもう一つの方法は、「言葉の世界を広げる」ことです。私たちは言葉を使って思考し、感情を表現します。そのため、語彙が豊かであればあるほど、より繊細な感覚や思いを捉えることができるようになります。
例えば、「美しい」という言葉一つとっても、「麗しい」「艶やか」「清楚」「優美」など、微妙なニュアンスの違う言葉があります。そうした同義語を学び、使い分けることで、自分の感覚をより正確に表現できるようになります。
SHOWKOさんは、日記を書く際に、その日感じたことを言葉にする習慣を持っているそうです。「今日の空は何色だったか」「あの人の声のトーンはどんな感じだったか」など、感覚を言葉に置き換える訓練をすることで、観察力と表現力の両方が高まっていくのです。
五感をフルに使って世界を感じる
感性を磨くためには、視覚だけでなく、聴覚、嗅覚、味覚、触覚という五感すべてを使って世界を感じることが大切です。現代社会では、視覚情報が優位になりがちですが、他の感覚も意識的に使うことで、より豊かな体験ができるようになります。
例えば、食事をするとき、ただ味わうだけでなく、食材の香りや食感、色合い、盛り付けの美しさなど、あらゆる角度から楽しむ。音楽を聴くとき、メロディだけでなく、楽器の音色や演奏者の息遣いにも注意を向ける。そうした意識的な体験の積み重ねが、感性を豊かにしていくのです。
SHOWKOさんは、陶芸の修行時代、目隠しをして土の感触だけで形を作る訓練をしたそうです。視覚に頼らず、触覚だけで形を捉える経験が、立体感覚を磨く上で大きな助けになったといいます。このように、普段あまり意識していない感覚を鍛えることで、新たな気づきや発見が生まれるのです。
整える習慣のポイント
身の回りの環境を整理する
感性を磨くためには、自分の身の回りの環境を整えることが重要です。散らかった部屋では、心も落ち着かず、細やかな感覚に意識を向けることが難しくなります。逆に、整理された空間では、心が静まり、感性が研ぎ澄まされていくのです。
SHOWKOさんは、「整理整頓は感性を磨くための土台づくり」だと言います。必要なものと不要なものを区別し、必要なものは使いやすく配置する。そうした基本的な整理整頓の習慣が、感性を育む環境を作り出すのです。
特に大切なのは、自分が創造的な活動をする場所です。仕事のデスク、料理をするキッチン、趣味に没頭する空間など、そうした場所を丁寧に整えることで、創造性が自然と湧き上がってくるようになります。物理的な空間が整うと、心の中の空間も整い、新しいアイデアや感覚が生まれやすくなるのです。
心を整える時間を持つ
環境だけでなく、心を整えることも感性を磨く上で欠かせません。日々の忙しさの中で、心が雑念や不安で満たされていると、繊細な感覚に気づくことができなくなります。そのため、意識的に心を整える時間を持つことが大切です。
SHOWKOさんは、朝起きてすぐの時間を「心の整理整頓」の時間にしているそうです。静かに呼吸を整え、その日やりたいことを思い浮かべる。そうすることで、一日の方向性が定まり、余計な迷いや不安が減るといいます。
心を整える方法は人それぞれですが、瞑想や深呼吸、散歩、お気に入りの音楽を聴くなど、自分なりのリラックス法を見つけることが大切です。そうした時間を日常に組み込むことで、感性を磨くための心の余裕が生まれてくるのです。
視点を変える習慣の作り方
「初期設定」を疑ってみる
感性を磨くためには、自分の「初期設定」、つまり無意識のうちに持っている前提や思い込みを疑ってみることが大切です。私たちは、自分の経験や教育、文化的背景によって形成された「当たり前」の中で生きています。しかし、その「当たり前」を一度疑ってみることで、新たな視点や発想が生まれるのです。
例えば、「器は丸いもの」という初期設定があるとします。しかし、その設定を疑い、「なぜ器は丸いのだろう?」「四角い器や不定形の器はどうだろう?」と考えてみる。そうした問いかけから、新たなデザインや使い方が生まれるかもしれません。
SHOWKOさんは、伝統的な陶芸の技法を学びながらも、「なぜこの工程が必要なのか」「別のやり方はないのか」と常に問いかけることで、独自の表現方法を見つけてきたといいます。初期設定を疑う習慣は、創造性を高め、感性を磨く上で非常に重要なのです。
常識にとらわれない本質的な発想
SHOWKOさんは、「本当に美しいと思うかどうか」「本当に心地よいと感じるかどうか」という自分自身の感覚を大切にしています。流行や評判に流されず、自分の内側から湧き上がる感覚を信じることで、独自の美意識や価値観が育まれていくのです。
例えば、インテリアを選ぶとき、「今年のトレンドカラーだから」という理由ではなく、「この色を見ると心が落ち着く」という自分の感覚で選ぶ。服を買うとき、「人気ブランドだから」ではなく、「この素材が肌に心地よい」という理由で選ぶ。そうした小さな選択の積み重ねが、自分だけの美意識や価値観を形作っていくのです。
本質的な発想を持つためには、「なぜ」という問いかけを大切にすることも重要です。「なぜこの形が美しいと感じるのか」「なぜこの音色が心地よいのか」と自問自答することで、表面的な評価ではなく、本質的な価値を見抜く力が養われていきます。
好奇心を持つ習慣の育て方
自分の「好き」の枠を広げる
感性を磨くためには、「好奇心を持つ習慣」も欠かせません。好奇心とは、新しいものや未知のものに対する関心や探究心のことです。子どもは生まれながらにして好奇心に満ちていますが、大人になるにつれて、「これは自分に関係ない」「これは自分の専門外だ」と線引きをしてしまいがちです。しかし、感性を磨くためには、そうした線引きを取り払い、さまざまなものに興味を持つことが大切です。
SHOWKOさんは、「自分の『好き』の枠を広げる」ことを勧めています。例えば、いつも同じジャンルの本ばかり読んでいるなら、あえて違うジャンルの本を手に取ってみる。いつも同じ種類の音楽ばかり聴いているなら、別のジャンルの音楽にも耳を傾けてみる。そうした小さな冒険が、感性の幅を広げていくのです。
また、好奇心を持つためには、「わからない」ことを恥じる気持ちを手放すことも大切です。大人になると、「知らないことを知られたくない」という思いから、質問をためらったり、新しいことに挑戦するのを避けたりしがちです。しかし、感性を磨くためには、そうした恥ずかしさを乗り越え、素直に「知りたい」「やってみたい」という気持ちを大切にすることが必要です。
新しいことに挑戦する姿勢
好奇心を育てるもう一つの方法は、「新しいことに挑戦する姿勢」を持つことです。人間は、慣れ親しんだ環境や習慣の中にいると、感覚が鈍くなりがちです。しかし、新しい環境や経験に身を置くことで、感覚が研ぎ澄まされ、感性が磨かれていくのです。
例えば、いつもと違う道を通って帰ってみる、行ったことのないレストランで食事をしてみる、初めての趣味に挑戦してみるなど、日常の中に小さな「新しさ」を取り入れることから始められます。そうした経験の積み重ねが、感性を豊かにしていくのです。
SHOWKOさんは、陶芸の世界でも常に新しい挑戦を続けています。伝統的な技法を学びながらも、新しい素材や道具を試したり、異なる文化や芸術から着想を得たりすることで、独自の表現を生み出しているのです。こうした挑戦の精神が、感性を磨く上で大きな役割を果たしているといえるでしょう。
決める習慣の重要性
選択の理由を言葉にしてみる
感性を磨くためには、「決める習慣」も重要です。日常生活では、大小さまざまな選択を迫られますが、その一つ一つの選択に意識を向け、自分の感覚で決断する習慣をつけることで、感性は鍛えられていきます。
特に大切なのは、「選択の理由を言葉にしてみる」ことです。なぜその選択をしたのか、どんな感覚や価値観に基づいているのか、それを言葉にすることで、自分の感性がより明確になっていきます。
例えば、服を買うとき、「なぜこの服を選んだのか」を考えてみる。「この色が好きだから」「この素材が肌に心地よいから」「この形が自分の体型に合っているから」など、選択の理由を具体的に言葉にしてみることで、自分の好みや価値観が明確になっていきます。
SHOWKOさんは、作品制作の過程でも、常に「なぜこの形にするのか」「なぜこの釉薬を使うのか」と自問自答し、選択の理由を明確にしているそうです。そうした意識的な選択の積み重ねが、独自の作風を形作っているのでしょう。
日常の小さな決断を意識する
決める習慣を身につけるためには、日常の小さな決断を意識することも大切です。朝、何を着るか、昼食に何を食べるか、帰り道にどのルートを選ぶかなど、普段は無意識に行っている選択にも意識を向けてみることで、自分の感覚や好みがより明確になっていきます。
特に重要なのは、他人の評価や流行に流されず、自分の感覚を信じて決断することです。「みんながこれを選んでいるから」「この選択が一般的だから」という理由ではなく、「自分がこれを選びたいから」という理由で決断する習慣をつけることで、感性は磨かれていくのです。
SHOWKOさんは、「決断力は感性の表れ」だと言います。迷いや不安から決断を先延ばしにするのではなく、その時点での自分の感覚を信じて決断する。そうした姿勢が、感性を磨く上で大切なのです。
感性を磨くための日常の工夫
言葉を感情的に「書き殴る」習慣
感性を磨くための具体的な方法として、SHOWKOさんは「言葉を感情的に書き殴る習慣」を勧めています。日記やメモ帳に、その日感じたことや考えたことを、文法や表現を気にせず、感情のままに書き出してみるのです。
例えば、美しい夕焼けを見たとき、「きれいだった」で終わらせるのではなく、「空が燃えるように赤く染まり、雲の輪郭が金色に輝いていた。見ているだけで胸が熱くなるような、切なさと喜びが入り混じった不思議な気持ちになった」など、感情や感覚をできるだけ具体的に言葉にしてみるのです。
こうした習慣を続けることで、自分の感情や感覚をより細やかに捉える力が養われ、感性が磨かれていきます。また、言葉にすることで、漠然とした感覚がより明確になり、自分自身の感性への理解も深まっていくのです。
主体的な人付き合いの大切さ
感性を磨くためには、「主体的な人付き合い」も大切です。多様な価値観や感性を持つ人との交流は、自分の感性を広げ、深める上で大きな刺激となります。
ただし、ここで重要なのは「主体的」であることです。周囲の空気に流されて付き合うのではなく、自分が興味を持ち、尊敬できる人と積極的に関わることが大切です。また、相手の価値観や感性を一方的に取り入れるのではなく、対話を通じて自分の感性と照らし合わせ、吸収すべきものを選び取る姿勢も必要です。
SHOWKOさんは、さまざまな分野の専門家や作家と交流することで、自分の視野を広げ、感性を磨いてきたといいます。そうした出会いが、作品制作にも新たな刺激や着想をもたらしているのでしょう。
感想・レビュー
SHOWKOさんの「感性のある人が習慣にしていること」を読んで、最も印象に残ったのは、感性は特別な才能ではなく、日々の習慣によって磨かれるものだという視点です。これは、多くの人にとって希望となる考え方ではないでしょうか。
私自身、「センスがいい人」「感性が豊かな人」というと、生まれつき特別な才能を持った人というイメージがありました。しかし、本書を読むことで、感性は日々の小さな習慣の積み重ねによって育まれるものだと知り、自分にもできるかもしれないという希望が湧いてきました。
特に共感したのは、「観察する習慣」の大切さです。現代社会では、スマートフォンやパソコンの画面に意識を奪われ、周囲の環境に注意を向ける機会が減っています。しかし、SHOWKOさんが提案するように、肌感覚で気温を当ててみたり、足裏の感覚を意識してみたりするなど、五感を使って世界を感じる習慣を取り入れることで、日常がより豊かになるのではないかと思いました。
また、「整える習慣」も心に響きました。物理的な環境だけでなく、心の中も整えることの大切さ。忙しい日常の中で、心を静める時間を持つことの重要性を改めて感じました。
本書は、具体的な実践法が多く紹介されているので、読んですぐに試してみることができるのも魅力です。「視点を変える習慣」として紹介されている「初期設定を疑ってみる」という考え方は、創造性を高める上でとても参考になりました。
SHOWKOさんの文章は、静かな語り口ながらも説得力があり、読んでいると自然と「やってみよう」という気持ちになります。330年続く茶道具の窯元に生まれ、世界で活躍する陶芸家としての経験に基づいた言葉だからこそ、重みがあるのでしょう。
この本は、感性を磨きたいと思っている人はもちろん、日常に小さな変化や豊かさを取り入れたいと思っている人にもおすすめしたい一冊です。
まとめ
SHOWKOさんの「感性のある人が習慣にしていること」は、感性は生まれつきの才能ではなく、日々の習慣によって磨かれるものだという視点から、具体的な実践法を紹介した一冊です。「観察する習慣」「整える習慣」「視点を変える習慣」「好奇心を持つ習慣」「決める習慣」という5つの習慣を身につけることで、誰でも感性を高めることができるというメッセージは、多くの人に希望を与えるものでしょう。日常の小さな変化に気づき、自分の感覚を信じて選択し、好奇心を持って新しいことに挑戦する。そうした習慣の積み重ねが、豊かな感性を育み、自分らしい人生を歩む力となるのです。