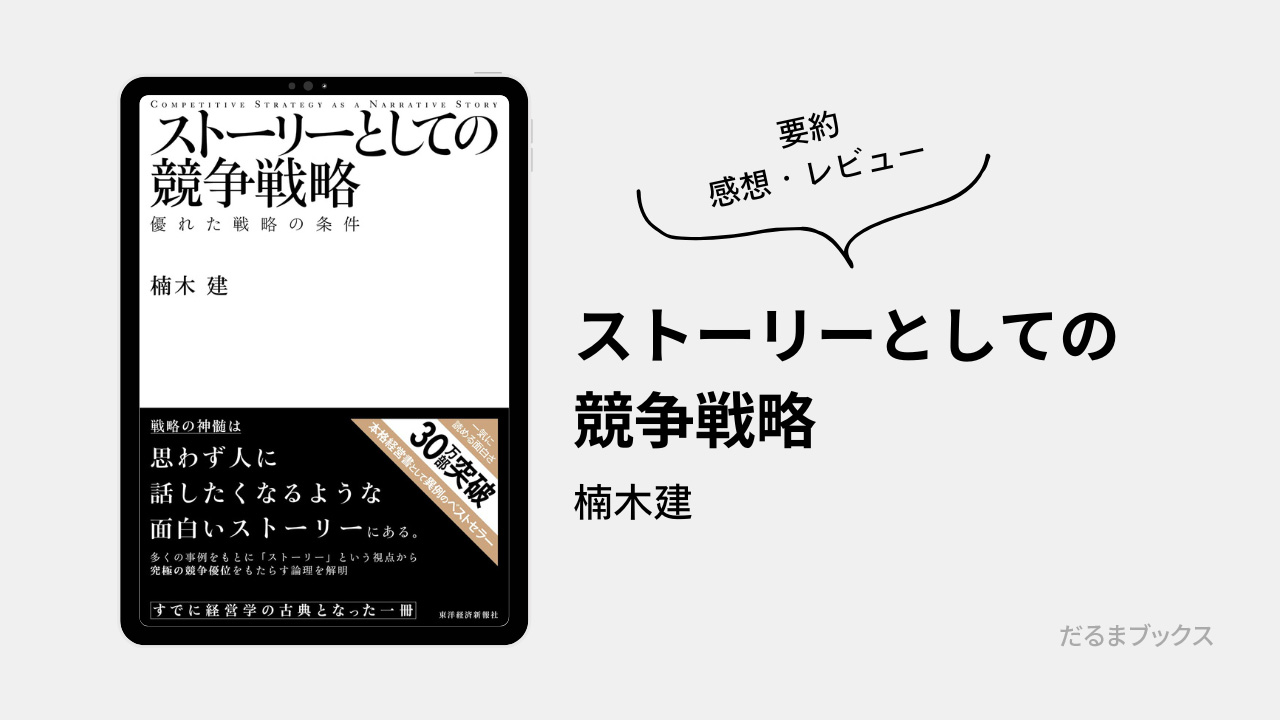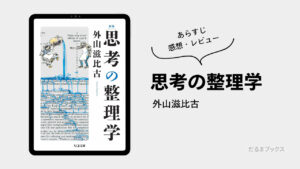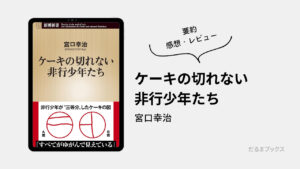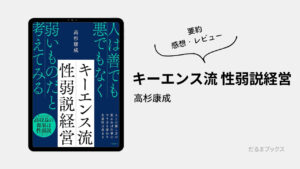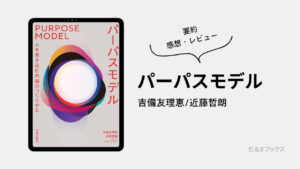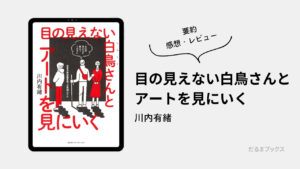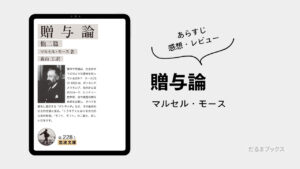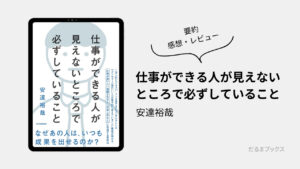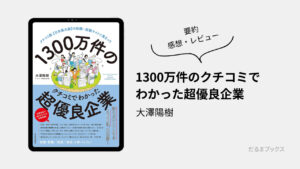ビジネスの世界で「戦略」という言葉をよく耳にしますが、その本質を理解している人は意外と少ないのではないでしょうか。
楠木建さんの著書「ストーリーとしての競争戦略」は、戦略とは単なる計画や目標の羅列ではなく、「思わず人に話したくなるような面白いストーリー」であるべきだと説きます。
本書では多くの企業事例を通じて、競争優位をもたらす戦略の本質を「ストーリー」という視点から解き明かしています。
本書の概要
著者プロフィール
楠木建さんは、一橋大学大学院国際企業戦略研究科の教授として、競争戦略とイノベーションを専門に研究されています。1964年東京生まれで、1992年に一橋大学大学院商学研究科博士課程を修了されました。一橋大学商学部助教授および同イノベーション研究センター助教授などを経て、2010年より現職に就かれています。
著書には「Dynamics of Knowledge, Corporate System and Innovation」(共著)や「Management of Technology and Innovation in Japan」(共著)、「Hitotsubashi on Knowledge Management」(共著)、『知識とイノベーション』(共著)などがあります。ビジネススクールで経営学を教える立場から、まるで面白い講義を受けているかのような、どんどん話を聞きたくなる構成で本書を書き上げられました。
「ストーリーとしての競争戦略」とは何か
本書のタイトルにもなっている「ストーリーとしての競争戦略」とは、単なる打ち手や施策の集まりではなく、それらが有機的につながり、時間的な展開を持った「物語」として戦略を捉える考え方です。
楠木さんは、戦略とは「違いをつくって、つなげる」ことだと説きます。競合他社との「違い」を作り出し、その個別の違いを組み合わせ、つなげることで初めて戦略が生まれるのです。そして、その戦略が「ストーリー」として語れるかどうかが重要なポイントになります。
優れた戦略には、思わず誰かに話したくなるような面白いストーリーがあります。そのストーリーが組織の中で共有され、一人ひとりが自分の役割を理解することで、ビジネスは総力戦になるのです。
本書の構成
本書は全7章から構成されています。
第1章「戦略は「ストーリー」」では、戦略をストーリーとして捉える視点の重要性について説明しています。第2章「競争戦略の基本論理」では、競争優位の源泉となる「違い」について詳しく解説しています。第3章「静止画から動画へ」では、個別の打ち手(静止画)から、それらがつながったストーリー(動画)への転換について語られています。
第4章「始まりはコンセプト」では、戦略ストーリーの起点となるコンセプトの重要性について、第5章「「キラーパス」を組み込む」では、戦略の中核となるクリティカル・コアについて解説しています。第6章「戦略ストーリーを読解する」では、実際の企業の戦略ストーリーを分析し、第7章「戦略ストーリーの「骨法10ヶ条」」では、優れた戦略ストーリーを作るための10の原則が示されています。
戦略の本質とは「違いをつくって、つなげる」こと
競争優位の源泉
戦略の根本にある考え方は、競合他社との「違い」を作り出すことです。完全競争の状態では利益を生み出すことが難しいため、他社との差異にこだわることが重要になります。プレイヤー間に違いがあれば、完全競争にならず、利益を生み出すチャンスが生まれるのです。
しかし、単に「違い」を作るだけでは不十分です。その「違い」が持続可能なものでなければ、すぐに模倣されてしまい、競争優位は失われてしまいます。持続可能な競争優位を築くためには、模倣困難な「違い」を作り出す必要があります。
「違い」のつくり方
「違い」をつくる方法はさまざまですが、本書では特に重要なポイントとして、「コンセプト」の明確さを挙げています。コンセプトとは、その企業や事業が提供する価値の本質を表すものです。例えば、スターバックスのコンセプトは「サードプレイス(第三の場所)」、つまり家でも職場でもない、第三の居場所を提供することです。
このようなコンセプトが明確であれば、それに基づいて一貫した「違い」を作り出すことができます。コンセプトがぶれなければ、戦略もぶれません。
個別の要素をつなげる重要性
「違い」を作るだけでなく、それらをつなげることも重要です。個別の打ち手や施策がバラバラでは、戦略とは言えません。それらがつながり、組み合わさり、相互作用する中で、初めて長期的な利益が実現されます。
楠木さんは、このつながりを「因果関係の論理」と表現しています。最終的な長期利益というゴールに向かって、「なぜ儲かるのか」「なぜそれができるのか」「なぜそうなっているのか」という「なぜ」を追求することで、打つべき施策のつながりが見えてくるのです。
マブチモーターの戦略ストーリー事例
「大量生産によるコスト競争力で勝つ」というストーリー
本書では、マブチモーターの戦略ストーリーが詳しく紹介されています。マブチモーターは小型直流モーターの世界的メーカーで、その戦略は「大量生産によるコスト競争力で勝つ」というシンプルなものでした。
しかし、このシンプルな戦略の背後には、緻密に組み立てられたストーリーがありました。マブチモーターは、モーターの標準化という革新的な打ち手と、早期からの海外生産戦略によって、圧倒的なコスト競争力を実現したのです。
モーターの標準化という革新的な打ち手
マブチモーターの戦略の核心は、モーターの標準化にありました。従来、モーターは各製品に合わせてカスタマイズするのが一般的でしたが、マブチモーターは標準化されたモーターを大量生産することで、圧倒的なコスト競争力を実現しました。
この標準化戦略は、一見すると顧客ニーズに応えないように見えるかもしれません。しかし、標準化によって実現された低コストと高品質は、多くの顧客にとって魅力的な価値提案となりました。
早期からの海外生産戦略
マブチモーターのもう一つの重要な打ち手は、早期からの海外生産戦略でした。労働コストの低い国々で生産することで、さらなるコスト削減を実現しました。
これらの打ち手が有機的につながり、「大量生産によるコスト競争力で勝つ」という戦略ストーリーを形成しました。このストーリーは、マブチモーターの社員全員に共有され、一人ひとりが自分の役割を理解することで、組織全体が一丸となって戦略を実行することができたのです。
優れた戦略ストーリーの条件
ストーリーの5C
楠木さんは、優れた戦略ストーリーの条件として「5C」を挙げています。これは、競争優位(Competitive Advantage)、コンセプト(Concept)、構成要素(Components)、クリティカル・コア(Critical Core)、一貫性(Consistency)の頭文字を取ったものです。
競争優位は、戦略の最終的な目標であり、他社が達成できない価値を生み出すことです。コンセプトは、戦略の起点となる価値提案です。構成要素は、戦略を構成する個別の打ち手や施策です。クリティカル・コアは、戦略の中核となる要素で、他社が模倣しにくい部分です。一貫性は、これらの要素をつなぐ因果論理のことを指します。
コンセプトの明確さ
優れた戦略ストーリーの条件として特に重要なのが、コンセプトの明確さです。コンセプトとは、その企業や事業が提供する価値の本質を表すものであり、戦略ストーリーの起点となります。
例えば、先ほど触れたスターバックスのコンセプトは「サードプレイス(第三の場所)」です。このコンセプトが明確であるからこそ、スターバックスは一貫した戦略を展開することができました。
クリティカル・コアの存在
もう一つ重要な条件が、クリティカル・コア(Critical Core)の存在です。クリティカル・コアとは、戦略の中核となる要素で、他社が模倣しにくい部分です。
例えば、スターバックスの場合、クリティカル・コアは「直営方式による店舗運営」でした。一般的なコーヒーチェーン店がフランチャイズ方式を採用する中、スターバックスはあえて初期コストもかかり、リスクもある直営店方式を選択しました。この選択が、「サードプレイス」というコンセプトを実現するための重要な要素となったのです。
静止画的戦略論と動画的戦略論の違い
アクションリストとの違い
楠木さんは、従来の戦略論を「静止画的戦略論」と呼び、本書で提唱する「ストーリーとしての競争戦略」を「動画的戦略論」と位置づけています。
静止画的戦略論の典型が「アクションリスト」です。これは、やるべきことのリストを並べただけのもので、それぞれの施策がどのようにつながり、全体としてどのように事業を駆動するのかが説明されていません。楠木さんは、多くの企業の戦略がこのアクションリストになっていると指摘しています。
一方、動画的戦略論では、個別の施策がどのようにつながり、時間的な展開を持って事業を駆動するのかが重視されます。それは、映画を観るように、ストーリーでしか語ることができないものなのです。
ビジネスモデルとの違い
ストーリーとしての競争戦略は、ビジネスモデルとも異なります。ビジネスモデルは「どんな構成要素で利益を出すのか」を説明するものですが、戦略ストーリーは「構成要素がどういう流れでその事業を駆動させるのか」という時間的展開に注目します。
ビジネスモデルが静的な構造を示すのに対し、戦略ストーリーは動的なプロセスを描き出します。この違いが、ビジネスモデルと戦略ストーリーの大きな違いです。
時間的展開の重要性
動画的戦略論の特徴は、時間的展開を重視することです。戦略は時間とともに展開し、変化していくものです。その変化のプロセスを含めて戦略を捉えることが重要なのです。
「ストーリーとしての競争戦略」の流れは、コンセプトがあり(起)、構成要素があり(承)、クリティカル・コアがあることで(転)、競争優位を実現する(結)というものです。この時間的な展開があってこそ、戦略はストーリーとして語ることができるのです。
戦略ストーリーが人を動かす理由
面白いストーリーの特徴
なぜ戦略がストーリーであることが重要なのでしょうか。それは、面白いストーリーには人を引きつける力があるからです。楠木さんは、優れた競争戦略には「人に話したくなるような面白いストーリーがある」と述べています。
面白いストーリーの特徴として、因果関係の蓋然性が高いこと、構成要素間のつながりの数が多いこと、時間軸でのストーリーの拡張性・発展性が高いことが挙げられます。これらの特徴を持つストーリーは、好循環と繰り返しを生み出し、持続可能な競争優位につながります。
組織内での共有しやすさ
戦略がストーリーであることのもう一つの利点は、組織内で共有しやすいことです。数字や図表だけでは伝わりにくい戦略も、ストーリーとして語ることで、組織のメンバー全員に理解されやすくなります。
楠木さんは、「ストーリーの共有は勝負を総力戦に持ち込むための条件として大切です」と述べています。ストーリーを全員で共有していれば、自分の一挙手一投足が戦略の成否にどのように関わっているのか、一人ひとりが理解した上で日々の仕事に取り組めます。戦略がどこか上のほうで漂っている「お題目」でなく、「自分の問題」になるのです。
長期的な一貫性の維持
戦略ストーリーのもう一つの利点は、長期的な一貫性を維持しやすいことです。ストーリーには一貫した論理があり、それに沿って戦略を展開することで、ぶれない経営が可能になります。
例えば、マブチモーターの「大量生産によるコスト競争力で勝つ」というストーリーは、長年にわたって一貫して維持されてきました。このような一貫性が、持続可能な競争優位につながるのです。
感想・レビュー
戦略思考の新たな視点
本書を読んで最も印象に残ったのは、戦略を「ストーリー」として捉える視点の新鮮さです。これまで戦略というと、難しい顔をして考えるもの、数字や図表で表現するものというイメージがありましたが、本書はそのイメージを一変させてくれました。
戦略とは、思わず人に話したくなるような面白いストーリーであるべきだという主張は、非常に説得力があります。確かに、優れた戦略を持つ企業の話を聞くと、思わず誰かに話したくなるような面白さがあります。それは、単なる成功事例ではなく、一貫した論理を持ったストーリーだからこそ、心に残るのでしょう。
実務への応用可能性
本書の素晴らしい点は、理論だけでなく、実務への応用可能性も高いことです。「戦略ストーリーの5C」や「戦略ストーリーの骨法10ヶ条」など、具体的な指針が示されているため、自分自身の仕事や組織の戦略を考える際に役立てることができます。
特に、「なぜ」を追求することの重要性は、どんな仕事にも応用できる視点です。「なぜそれが必要なのか」「なぜそれが効果的なのか」と問い続けることで、表面的な理解から本質的な理解へと深めていくことができます。
読みやすさと事例の豊富さ
500ページを超える本格的な経営書でありながら、本書は非常に読みやすく、あっという間に読み終えることができました。それは、楠木さんの語り口の魅力もさることながら、豊富な事例が盛り込まれているからでしょう。マブチモーター、スターバックス、アマゾン、サウスウエスト航空など、様々な企業の戦略ストーリーが具体的に紹介されており、理論だけでなく実践的な理解を深めることができます。
特に印象的だったのは、「三枚のお札」という昔話を用いて戦略ストーリーの本質を説明している部分です。難解な理論も、身近な物語に置き換えることで、非常にわかりやすく伝わってきました。このような語り口の工夫も、本書の魅力の一つです。
まとめ
「ストーリーとしての競争戦略」は、戦略を「思わず人に話したくなるような面白いストーリー」として捉える新しい視点を提供してくれる一冊です。戦略とは「違いをつくって、つなげる」ことであり、それが時間的な展開を持ったストーリーとして語れるかどうかが重要だという主張は、非常に説得力があります。
本書を読むことで、戦略を考える際の新たな視点を得ることができるでしょう。単なるアクションリストや静止画的な戦略論ではなく、動画的な戦略ストーリーを構築することの重要性を理解することができます。ビジネスパーソンはもちろん、組織運営に関わる全ての人にとって、価値ある一冊だと思います。