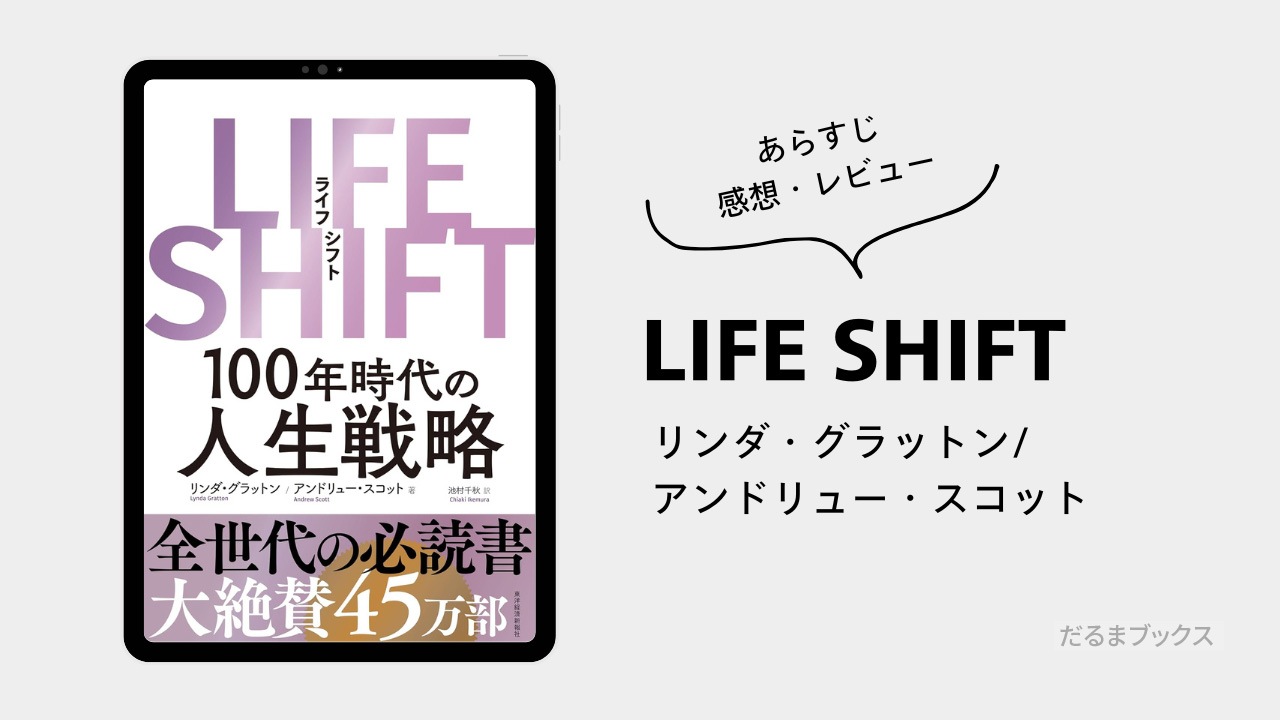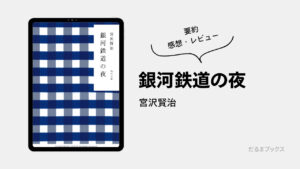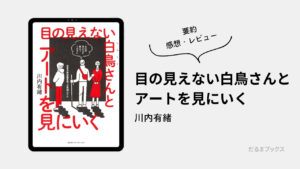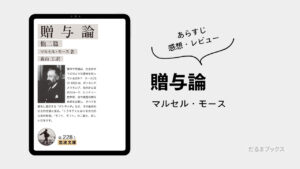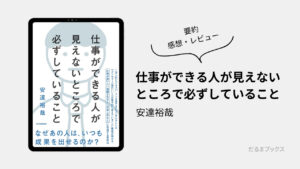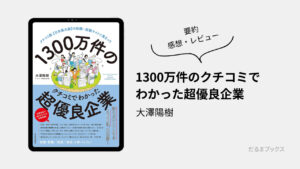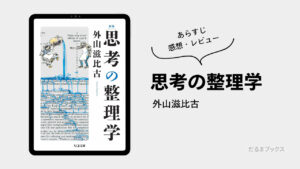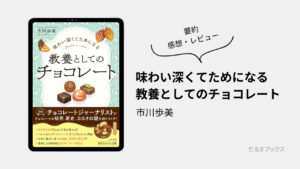人生100年時代をどう生きるか——。リンダ・グラットンさんとアンドリュー・スコットさんによる『LIFE SHIFT』は、長寿社会を迎える私たちに新たな人生設計の指針を示してくれます。
従来の「教育→仕事→引退」という3ステージモデルから脱却し、マルチステージの人生へとシフトする必要性を説く本書は、15カ国語に翻訳された世界的ベストセラーとなりました。
お金だけでなく、健康や人間関係といった「無形資産」の重要性にも光を当て、100年ライフを豊かに生きるための戦略を提案しています。
「LIFE SHIFT」とは?100年ライフの衝撃
『LIFE SHIFT』は、2016年に出版されるやいなや世界中で大きな反響を呼んだ一冊です。日本でも「人生100年時代」という言葉とともに広く知られるようになりました。この本が投げかける問いは単純明快です。「もし100年生きるとしたら、あなたはどう生きますか?」
この問いかけは、私たちの人生設計の根本を揺るがします。これまでの常識では、人は70〜80年ほど生きるものとされてきました。しかし医学の進歩により、2007年に日本で生まれた子どもの半数は107歳まで生きる可能性があるとされています。つまり、いま50歳未満の日本人の多くは100年以上生きる時代を過ごすことになるのです。
しかも単に長生きするだけでなく、「いま80歳の人は、20年前の80歳よりも健康だ」と著者は指摘します。私たちはより若く、より健康に長い時間を過ごすという、かつてないチャンスを手にしているのです。
著者プロフィール:リンダ・グラットンさんとアンドリュー・スコットさん
『LIFE SHIFT』の著者であるリンダ・グラットンさんは、イギリスの組織論学者で、ロンドン・ビジネス・スクールの教授です。1955年、イングランドのリヴァプールに生まれ、リヴァプール大学で心理学を専攻してPhDを取得しました。ブリティッシュ・エアウェイズの主任心理学者を経て、1989年からロンドン・ビジネス・スクールで教鞭を執っています。
グラットンさんは人材論、組織論の世界的権威として知られ、2011年には経営学界のアカデミー賞とも称されるThinkers50ランキングのトップ12に選ばれました。フィナンシャル・タイムズ紙では「今後10年で未来に最もインパクトを与えるビジネス理論家」と評され、『ワーク・シフト』など一連の著作は20カ国語以上に翻訳されています。
共著者のアンドリュー・スコットさんは、経済学の権威として知られています。オックスフォード大学トリニティ・カレッジで文学士号を取得後、ロンドン大学ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスで理学修士号、オックスフォード大学オール・ソウルズ・カレッジで博士号を取得しました。ハーバード大学やオックスフォード大学で教鞭を執った後、現在はロンドンビジネススクールの経済学部教授を務めています。
ビジネスサイクル、金融・財政政策、そして長寿化を専門とするスコットさんは、教育優秀授業賞を複数回受賞するなど、その教育者としての才能も高く評価されています。
15カ国語に翻訳された世界的ベストセラー
『LIFE SHIFT』は、出版後すぐに世界中で話題となり、15カ国語以上に翻訳されました。日本でも2016年10月に東洋経済新報社から出版され、ベストセラーとなりました。
本書の影響力は、単に売上部数にとどまりません。世界を代表する知識人たちからも高い評価を受けています。『劣化国家』の著者として知られるニーアル・ファーガソンは「明快でタイムリー、オリジナルで書きぶりも素晴らしく、そしてとても恐ろしい」と評し、『国家はなぜ衰退するのか』の著者ダロン・アセモグルは「より健康で長寿になる私たちの人生に関する迫真のケーススタディ。私たちの知っている世界とはまったく別の未来がくるだろう」と称賛しています。
2017年には、グラットンさんが日本の人生100年時代構想会議メンバーに唯一の外国人として招聘されるなど、その影響は政策レベルにまで及んでいます。
「LIFE SHIFT」の核心:3ステージモデルの崩壊
『LIFE SHIFT』の最も重要なメッセージは、従来の「3ステージモデル」が崩壊しつつあるという指摘です。これまで多くの人が歩んできた人生は、「教育→仕事→引退」という3つのステージで構成されていました。20歳前後まで教育を受け、65歳までバリバリ働き、その後は引退して余生を楽しむ——。この単線的な人生設計が、長寿化によって成り立たなくなっているのです。
従来の「教育→仕事→引退」という人生設計の限界
従来の3ステージモデルは、平均寿命が70〜80年程度の社会を前提としていました。しかし、人生が100年を超える時代には、このモデルはいくつかの点で破綻します。
まず、財政面での問題があります。65歳までの働きで、その後の35年間の生活を賄うのは非常に困難です。企業年金や国の年金だけをあてにして生きることは、もはや現実的ではありません。
また、精神的な側面からも問題があります。テレビの前やゴルフコースで過ごすには、35年という期間はあまりに長すぎます。「老後=人生のおまけ」という考え方自体を捨てる必要があるでしょう。
さらに、技術革新によって労働市場は急速に変化しています。今後数十年で職種は大きく入れ替わるでしょう。一度受けた教育だけで一生を過ごすことは難しくなっています。
100年生きる時代の新たな課題
100年生きる時代には、新たな課題が生じます。その一つが、「自分はどう生きるか」という問いへの向き合い方です。グラットンさんは、「100歳になった自分が、いまの自分をどう見るか」を考えることの重要性を指摘しています。長寿化という現象の核心は、自分自身の人生をどのようなものにしたいかという問いに真摯に向き合うことにあるのです。
また、長寿化は社会全体に大きな変革をもたらします。人々の働き方や教育、結婚の時期や相手、子どもをつくるタイミングも変わります。余暇時間の過ごし方も、社会における女性の地位も変わるでしょう。そして、最も大きく変わることが求められるのは個人です。私たちは親の世代とは異なる選択をすることになり、私たちの子どもたちも私たちとは違う決断をするのです。
「LIFE SHIFT」が提案するマルチステージの人生
3ステージモデルの代わりに、グラットンさんとスコットさんが提案するのが「マルチステージの人生」です。これは、人生を複数の異なるステージに分け、それぞれのステージで異なる活動や役割を担うという考え方です。
複数のキャリアと柔軟な生き方
マルチステージの人生では、一つの職業に固執するのではなく、複数のキャリアを持つことが奨励されます。本書では、「エクスプローラー」「インディペンデント・プロデューサー」「ポートフォリオ・ワーカー」といった新しいステージが出現すると予測しています。
「エクスプローラー」は、自分を見きわめ、選択肢を広げることを重視するステージです。大学卒業後、すぐに就職を考えるのではなく、まずは自分の可能性を探る時間を持つことが推奨されています。
「インディペンデント・プロデューサー」は、独立して価値を生み出すステージです。会社に依存せず、自分自身のスキルや知識を活かして収入を得る方法を模索します。
「ポートフォリオ・ワーカー」は、複数の仕事や活動を組み合わせて働くスタイルです。一つの仕事に依存するリスクを分散させ、多様な経験を積むことができます。
人生の各ステージにおける選択肢の多様化
マルチステージの人生では、各ステージでの選択肢が多様化します。20代から60代という時期を、仕事一辺倒、キャリアアップ一筋で過ごすのではなく、仕事・学び・遊びのバランスをとりつつ、柔軟に人生を組み立てていくことが重要です。
また、結婚や子育てのタイミングも、従来の常識にとらわれる必要はありません。本書では、「結婚相手を選ぶ際は慎重に」とアドバイスしています。100年という長い人生を共に過ごすパートナーを選ぶのですから、当然と言えるでしょう。
さらに、レクリエーション(余暇)ではなく、リ・クリエーション(自己の再創造)に時間を使うことの重要性も強調されています。単に時間を潰すのではなく、自分自身を成長させる活動に時間を投資することが、長い人生を豊かに過ごすカギとなるのです。
長寿時代の資産管理と考え方
100年生きる時代には、資産管理の考え方も変える必要があります。従来は、有形資産(お金や不動産など)の蓄積が重視されてきましたが、長寿時代には無形資産の重要性が増します。
無形資産の重要性:人間関係・健康・学び
本書では、無形資産を「生産性資産」「活力資産」「変身資産」の3つに分類しています。
「生産性資産」は、主に仕事に役立つ知識やスキルのことです。これらは、収入を得るための基盤となります。しかし、技術革新が進む現代では、一度身につけたスキルが陳腐化するスピードも速くなっています。そのため、常に学び続け、スキルをアップデートする必要があります。
「活力資産」は、健康や、良好な家族・友人関係のことです。長い人生を健康に過ごすためには、若いうちから健康管理に気を配ることが重要です。また、良好な人間関係は精神的な支えとなり、幸福感を高めます。
「変身資産」は、変化に応じて自分を変えていく力のことです。長い人生の中では、社会環境や技術が大きく変化します。そうした変化に適応し、自分自身を変革していく能力が求められるのです。
これらの無形資産は、「よい人生」を送るうえで価値があるだけでなく、有形資産の形成を後押しするという点でも重要です。例えば、高いスキル(生産性資産)は収入増加につながり、健康(活力資産)は医療費の削減につながります。
財政面での新しい戦略
長寿時代の財政面での戦略も、従来とは異なります。本書では、「共働きの本当のリスクは、消費水準を下げられないこと」と指摘しています。二人分の収入に合わせたライフスタイルを構築してしまうと、片方が働けなくなった場合に大きな問題が生じます。
また、金融商品を買うときは、パンフレットの細部に気をつけ、手数料をチェックすることの重要性も強調されています。長期間にわたる投資では、わずかな手数料の違いが大きな差となって現れるからです。
さらに、個人と企業の間で、産業革命に匹敵するほどの激しい争いが起きると予測しています。企業は利益を最大化するために労働コストを抑えようとし、個人は自分の価値を高めようとします。この緊張関係の中で、個人は自分の権利を守るために交渉力を高める必要があるのです。
「LIFE SHIFT」が描く未来の働き方
長寿化と並んで、私たちの生き方に大きな影響を与えるのが技術革新です。特にAIと機械化の進展は、労働市場に大きな変化をもたらすでしょう。
AIと機械化が変える雇用環境
本書では、労働市場に存在する職種が、これから数十年で大きく入れ替わると予測しています。特に、定型的な作業はAIやロボットに置き換えられる可能性が高いです。
一方で、創造性や対人関係のスキルを必要とする仕事は、依然として人間が担う領域として残るでしょう。ハーバード大学ロー・スクールのマイケル・サンデル教授の言葉を借りれば、「利他の精神、寛大な精神、連帯感、市民精神は、使用すると枯渇する資源とは違う。使うことにより発達し、強く成長する筋肉に似ている」のです。
このような変化に対応するためには、テクノロジーの進展によって代替されにくい仕事のスキルを身につけることが重要になります。具体的には、創造性、問題解決能力、感情知性、対人関係スキルなどが挙げられます。
新しい職業とキャリアの可能性
技術革新は、新しい職業やキャリアの可能性も生み出します。例えば、データサイエンティストやAIエンジニアといった職業は、数十年前には存在しませんでした。
また、デジタル技術の発達により、場所や時間に縛られない働き方も可能になっています。リモートワークやフリーランスとして働く人が増加し、「ギグエコノミー」と呼ばれる働き方も広がっています。
こうした変化は、個人にとっては挑戦でもありチャンスでもあります。従来の組織に依存せず、自分自身のスキルや知識を活かして収入を得る道が開かれているのです。
人間関係と家族の形の変化
長寿化は、人間関係や家族の形にも大きな変化をもたらします。特に、パートナーシップのあり方や世代間の関係性が再構築されることになるでしょう。
パートナーシップの新しい形
本書では、「男女の役割分担が変わる。質の高いパートナー関係が必要になる」と指摘しています。長い人生を共に過ごすためには、従来の固定的な役割分担ではなく、柔軟に役割を調整していくことが求められます。
また、「数十年単位での役割の調整が必要。高度な信頼関係と徹底した計画が不可欠」とも述べられています。例えば、一方がキャリアに集中する時期には、もう一方が家庭を支える役割を担い、その後役割を交代するといった柔軟な対応が必要になるのです。
さらに、長寿化によって、結婚や子育てのタイミングといった柔軟な対応が必要になるのです。
さらに、長寿化によって、結婚や子育てのタイミングも変化しています。結婚の時期が遅くなり、子どもの数が減少する一方で、高齢の家族や親族が増えるという現象が起きています。本書では、こうした四世代家族の中で、高齢者が若者の思考を刺激し、メンター役を務め、若者が高齢者を支える機会が生まれると指摘しています。
世代間の関係性の再構築
長寿化によって、同時にいくつもの世代が共存するようになると、世代間の関係性も再構築が必要になります。本書では、世代間の摩擦について懸念が示されています。これは、長寿化により同時に複数の世代が共存するようになり、人生のあり方に関する世代間の考え方が食い違うことから生じる問題です。
世代のレッテルは、世代間の共通項よりも相違点を強調し、対立を生みかねないと著者は警告しています。理想的な状態は、人々が世代を超えて資源を共有し、互いに助け合い、大切にし合うことだと述べられています。
また、家族の機能を見直すことの重要性も指摘されています。家族を長期的な人間関係の核と位置づけ、家族のメンバーが資源を共有することにより、長い人生を生き抜くのを助け合い、いざというときに支え合えるようにすることが大切です。優しく支えてくれる家族は、世界の激変に対する緩衝材の役割を果たし、誰かが病気になったり職を失ったりしたときの保険にもなります。
「LIFE SHIFT」から学ぶ実践的なアドバイス
『LIFE SHIFT』は単に長寿化社会の課題を指摘するだけでなく、その時代を豊かに生きるための実践的なアドバイスも提供しています。特に重要なのは、自己変革と学び直しの重要性、そしてライフステージ間の移行を成功させるコツです。
自己変革と学び直しの重要性
長寿時代を生き抜くためには、自己変革と学び直しが不可欠です。本書では、「変身資産」という概念が提唱されています。これは、変化に応じて自分を変えていく力のことで、長い人生の中で環境の変化に適応し、自分自身を変革していく能力を指します。
技術革新のスピードが速まる現代では、一度身につけたスキルがすぐに陳腐化してしまいます。そのため、常に学び続け、スキルをアップデートする必要があります。本書では、「レクリエーション(余暇)」ではなく、「リ・クリエーション(自己の再創造)」に時間を使うことの重要性が強調されています。
また、マルチステージの人生では、「エクスプローラー」の時期を設けることも推奨されています。これは、自分を見極め、選択肢を広げることを重視するステージです。大学卒業後、すぐに就職を考えるのではなく、まずは自分の可能性を探る時間を持つことが大切です。
ライフステージ間の移行を成功させるコツ
マルチステージの人生では、ステージ間の移行をいかにスムーズに行うかが重要になります。本書では、移行を成功させるためのいくつかのコツが紹介されています。
まず、移行の前に十分な準備をすることが大切です。次のステージで必要となるスキルや知識を事前に身につけておくことで、移行のハードルを下げることができます。
また、移行の際には、周囲のサポートを得ることも重要です。家族や友人、メンターなどの支えがあると、精神的な負担が軽減されます。本書では、深い人間関係や広い人間関係は長い時間をかけなければ築けないと指摘されています。マルチステージの人生は柔軟性が高く、成長と進化を遂げるチャンスも多いですが、人間関係を深めるために投資しなければ、移行の回数が増える結果として人生が細切れになる危険があります。
さらに、移行の際には、自分自身の価値観や目標を明確にしておくことも大切です。「なぜこの移行をするのか」「移行後にどのような人生を送りたいのか」を明確にすることで、移行の意義が明確になり、モチベーションも維持しやすくなります。
感想・レビュー
100年ライフという視点がもたらす衝撃
『LIFE SHIFT』を読んで最も衝撃を受けたのは、「人生100年」という視点がもたらす既存の価値観や生き方への問いかけの深さです。これまで当たり前だと思っていた「教育→仕事→引退」という人生設計が、長寿化によって根本から揺らいでいることに、ある種の不安と同時に、新たな可能性への期待も感じました。
本書の素晴らしさは、単に「長生きする時代が来る」と警鐘を鳴らすだけでなく、その時代をどう生きるかという具体的な戦略を提示している点にあります。特に、無形資産の重要性に光を当てた視点は新鮮でした。お金や不動産といった有形資産だけでなく、スキル、健康、人間関係といった無形資産にも目を向けることの大切さを、改めて認識させられました。
グラットンさんとスコットさんの文体は、学術書でありながらも読みやすく、具体的な事例やモデルケースを通して複雑な概念を分かりやすく説明しています。「ジャック」「ジミー」「ジェーン」という三人の架空の人物を通して、異なる世代がどのように100年ライフに向き合うかを描いた手法は、読者の理解を深める上で効果的でした。
日本社会への示唆と個人の選択
日本は世界でもトップクラスの長寿国であり、本書が描く「人生100年時代」はすでに現実のものとなりつつあります。しかし、社会制度や企業の仕組み、個人の意識は、まだまだ従来の3ステージモデルを前提としています。終身雇用や年功序列といった日本的雇用慣行も、長寿化社会には適合しにくくなっているのではないでしょうか。
本書を読んで、日本社会が直面している課題の根深さを改めて感じました。少子高齢化、労働力不足、年金問題など、多くの社会問題は長寿化と密接に関連しています。これらの問題を解決するためには、社会全体の意識改革が必要です。
一方で、個人の選択の重要性も強調されています。長寿化時代を生きる私たち一人ひとりが、自分の人生をどう設計するかを主体的に考え、行動することが求められています。「100歳になった自分が、いまの自分をどう見るか」という問いかけは、日々の選択を見つめ直す上で非常に有効な視点だと思いました。
本書を読んで、私自身も自分の人生設計を見直すきっかけを得ました。これまで漠然と考えていた「老後」という概念を、より具体的かつ長期的な視点で捉え直す必要性を感じています。また、無形資産への投資、特に健康や人間関係、学び続ける姿勢の重要性を再認識しました。
まとめ
『LIFE SHIFT』は、人生100年時代を生きる私たちに、新たな人生設計の指針を示してくれる貴重な一冊です。従来の「教育→仕事→引退」という3ステージモデルから脱却し、マルチステージの人生へとシフトする必要性を説いています。
長寿化時代には、お金だけでなく、スキル、健康、人間関係といった「無形資産」の重要性が増します。また、技術革新によって労働市場が急速に変化する中、一度受けた教育だけで一生を過ごすことは難しくなっています。常に学び続け、自己変革する姿勢が求められるのです。
本書が提案する「マルチステージの人生」は、人生を複数の異なるステージに分け、それぞれのステージで異なる活動や役割を担うという考え方です。この柔軟な人生設計によって、長寿化時代を豊かに生きることができるでしょう。
人生100年時代は、課題と同時に大きな可能性も秘めています。本書を読んで、その時代をどう生きるかを考えるきっかけにしてみてはいかがでしょうか。