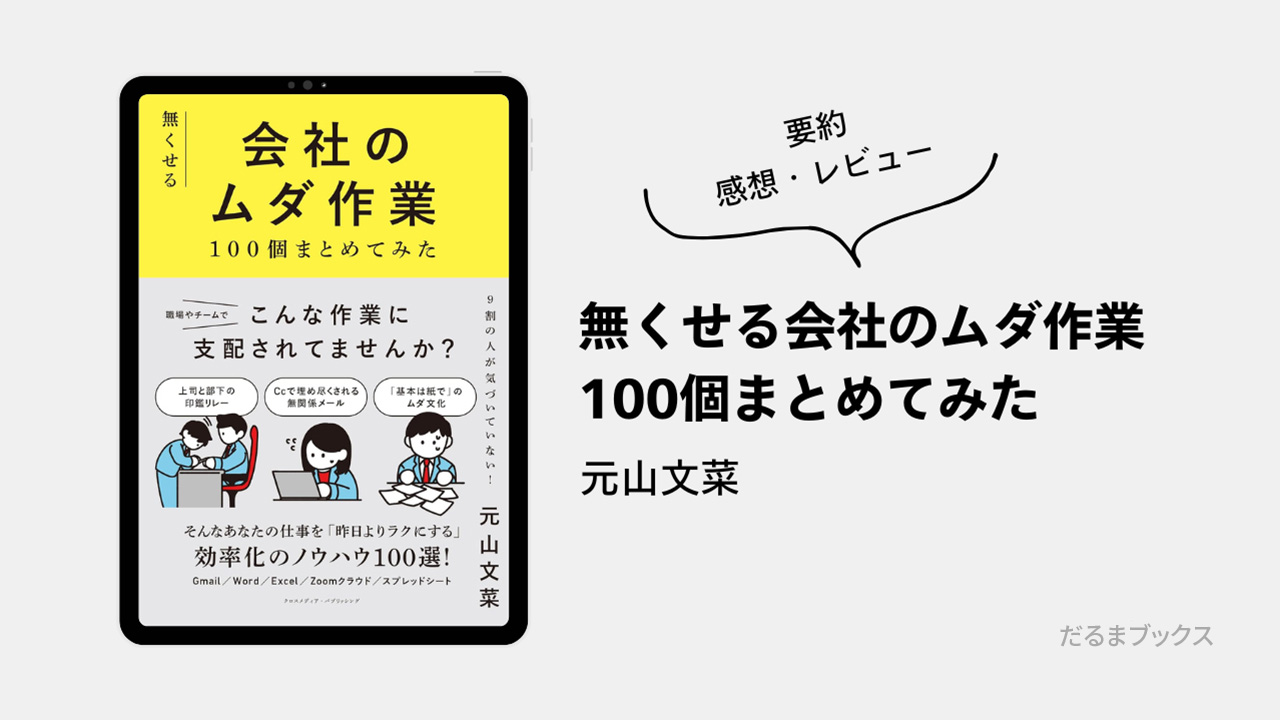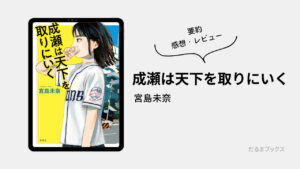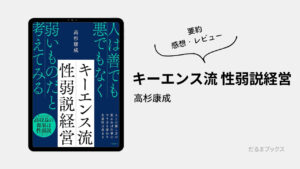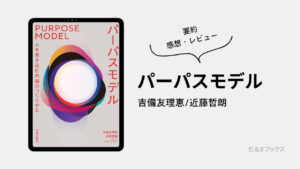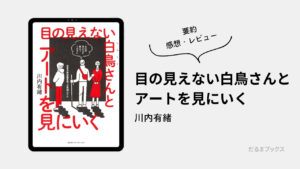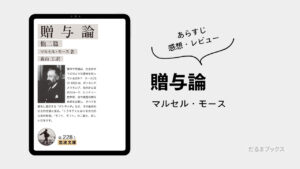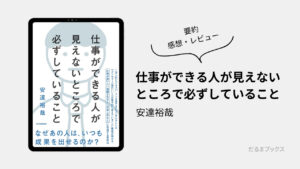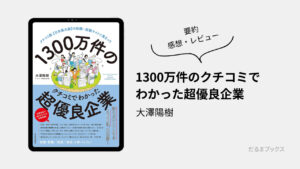会社での無駄な作業に悩んでいませんか?
元山文菜さんの著書「無くせる会社のムダ作業100個まとめてみた」は、日々の業務に潜む100個のムダを洗い出し、その解決策を提案する実用書です。
イラストや図解を交えた読みやすい構成で、業務改善の第一歩を踏み出したい方に最適な一冊。
本記事では、この本の要点と実践的なアドバイスを詳しく解説していきます。
この本の概要
「無くせる会社のムダ作業100個まとめてみた」は、2023年9月1日にクロスメディア・パブリッシングから発売された書籍です。四六判、240ページの手頃なサイズで、価格は1,738円(税込)となっています。
本書は、職場に潜む100個のムダな作業を、イラストや図解を交えてわかりやすく紹介しています。
ExcelやWordなどの基本的なツールでの解決策を提案しており、特別な知識がなくても「今すぐ」始められる内容になっています。
また、「ムダ」が生まれる構造も簡単に解説されているため、問題の再発防止にも役立ちます。
著者・元山文菜さんについて
元山文菜さんは、業務コンサルタントとして活躍する株式会社リビカルの代表取締役です。大学卒業後、サクラクレパスを経て富士通に勤務した後、2017年に独立して現在の会社を設立されました。「多様性×業務改善で、はたらくを楽しむ人を増やしたい」をテーマに、業務や組織構造の再設計を手がけていらっしゃいます。
元山さんは、BPR(ビジネスプロセスリエンジニアリング)、BPO(ビジネスプロセスアウトソーシング)、RPA(ロボティクスプロセスオートメーション)導入支援などを通じて、組織の生産性向上をサポートしています。また、個々人に対する時間管理術の改善も実施し、組織全体の効率化を図る独自のアプローチを持っています。
業務プロセス改善、タイムマネジメント、ダイバーシティマネジメントをテーマにした講演活動も精力的に行っており、以前に『業務改善の問題地図』(技術評論社)という著書も出版されています。
本書の特徴とコンセプト
本書の最大の特徴は、業務改善を難しく考えすぎず、身近な視点から取り組めるようにしている点です。DXや最新テクノロジーといった大掛かりな改革を行う前に、まずは日常業務の中で簡単に改善できるポイントに焦点を当てています。
「それ、メールじゃなくてよくない?」といった素朴な疑問から始まり、9割の人が気づいていない会社の「ムダ」を洗い出していきます。イラストを使った説明は一目見てパッと理解できるため、忙しいビジネスパーソンでもすぐに実践できる工夫がされています。
また、本書は目次を見て気になる箇所から読むこともできるので、自分に関係する問題から直ちに取り組めるという実用性の高さも魅力です。
ムダ作業の分類と全体像
本書で紹介されている100個のムダ作業の分類方法
本書では、100個のムダ作業を体系的に理解できるよう、7つのカテゴリーに分類しています。具体的には「業務」「管理」「共有」「処理」「コミュニケーション」「会議」「組織」の7つです。この分類によって、自分の職場や部署で特に問題となっている領域を特定しやすくなっています。
例えば、「業務」カテゴリーでは日常的な作業フローの非効率さに焦点を当て、「管理」カテゴリーでは過剰な管理体制や形骸化したルールの問題を取り上げています。「共有」カテゴリーでは情報共有の方法や頻度に関する問題、「処理」カテゴリーでは書類処理や決裁プロセスの煩雑さを指摘しています。
「コミュニケーション」カテゴリーでは無駄な連絡や非効率な伝達方法、「会議」カテゴリーでは会議の運営方法や準備の問題、そして「組織」カテゴリーでは組織構造や意思決定プロセスに関する課題を扱っています。
最も多いムダ作業のカテゴリー
本書の分析によると、最も多くのムダ作業が集中しているのは「コミュニケーション」と「会議」のカテゴリーです。これは多くの企業に共通する傾向で、特に日本企業では顕著に見られる問題とされています。
コミュニケーションに関するムダとしては、「察してちゃん」と呼ばれる、自分の考えを明確に伝えず相手に察することを求める行動パターンや、「きまぐれ上司のご機嫌取り」といった非生産的な人間関係のムダが挙げられています。
会議に関するムダとしては、目的が不明確な会議の開催や、必要以上に長い会議時間、参加する必要のない人まで巻き込む過剰な会議設定などが指摘されています。これらは時間の無駄だけでなく、組織全体のエネルギーを消耗させる要因にもなっています。
ムダ作業を見つける視点
ムダ作業を見つけるためには、「当たり前」と思っている業務プロセスを疑ってみることが重要です。本書では、以下のような視点からムダを発見するヒントが提供されています。
まず、「なぜこの作業が必要なのか」という根本的な問いかけをすることです。長年続けてきた業務の中には、すでに目的を失っているにもかかわらず、習慣で続けられているものが少なくありません。
次に、「誰のために行っている作業なのか」という視点です。顧客や取引先のためではなく、単に社内の慣習や上司の好みに合わせるために行われている作業は、見直しの余地があります。
さらに、「この作業は本当に人間がやる必要があるのか」という問いも重要です。定型的で反復的な作業は、テクノロジーの活用によって自動化できる可能性があります。
このような視点を持つことで、日常業務の中に潜むムダを発見し、改善のきっかけをつかむことができるのです。
会議に関するムダ作業
不必要な会議の特徴
会議は企業活動において重要なコミュニケーションの場ですが、その一方で最もムダが生じやすい場面でもあります。本書では、不必要な会議の特徴として、まず「目的が不明確」であることを挙げています。「定例会議だから」という理由だけで開催される会議は、参加者の時間を無駄にするだけでなく、組織全体の生産性を低下させる要因となります。
また、「参加者が多すぎる」会議も問題です。本当に必要な人だけを招集せず、関係者全員を呼んでしまうケースが多く見られます。これにより、一部の人にとっては全く関係のない議題についても最後まで付き合わなければならない状況が生まれます。
さらに、「準備不足」の会議も効率を著しく下げます。議題や資料が事前に共有されていないため、会議中に初めて内容を把握することになり、その場で十分な議論ができません。結果として、「また改めて会議を設定しましょう」という展開になり、さらなる時間の浪費を招きます。
会議の効率化テクニック
本書では、会議の効率化のために実践できる具体的なテクニックがいくつか紹介されています。まず基本となるのは、「会議の目的と到達点を明確にする」ことです。会議の冒頭で「今日の会議では〇〇について決定します」と宣言することで、議論がぶれることを防ぎます。
次に、「タイムキーパーを設ける」ことも効果的です。各議題にあらかじめ時間配分を決めておき、それを厳守することで、だらだらと長引く会議を防止します。特に重要なのは、会議の終了時間を守ることです。
また、「スタンディングミーティング」の導入も推奨されています。立ったまま行う短時間の会議は、自然と簡潔な議論を促し、長時間の会議を防ぐ効果があります。特に日々の進捗確認や情報共有といった定例的な会議に適しています。
さらに、「会議のオンライン化」も効率化に貢献します。移動時間の削減だけでなく、録画機能を活用することで欠席者も後から内容を確認できるようになります。また、チャット機能を使って並行して質問や意見を出し合うことで、より活発な議論が可能になります。
会議資料作成のムダをなくす方法
会議の準備段階でも多くのムダが発生しています。特に会議資料の作成は、多くの時間と労力を要する作業です。本書では、会議資料作成のムダをなくすための方法として、まず「テンプレートの活用」を挙げています。基本的なフォーマットを統一することで、毎回ゼロから作成する手間を省けます。
次に、「必要最小限の情報に絞る」ことも重要です。詳細なデータや背景情報は必要に応じて別途共有し、会議資料自体はポイントを絞った簡潔なものにすることで、作成時間の短縮と参加者の理解促進の両方を図れます。
また、「資料の事前共有」も効果的です。会議の数日前に資料を配布しておくことで、参加者は事前に内容を把握でき、会議当日はより深い議論に時間を使えるようになります。これにより、会議時間の短縮と質の向上の両立が可能になります。
さらに、「ペーパーレス化」も推奨されています。デジタルツールを活用して資料を共有することで、印刷や配布の手間を省くだけでなく、修正や更新も容易になります。また、環境負荷の軽減にも貢献します。
メールと連絡に関するムダ作業
CCのつけすぎ問題
ビジネスコミュニケーションの中で、メールは最も一般的なツールの一つですが、その使い方には多くのムダが潜んでいます。本書で指摘されている代表的な問題の一つが「CCのつけすぎ」です。
関係者全員にCCを付ける習慣は、一見情報共有の観点から良いように思えますが、実際には多くの弊害を生んでいます。受信者は自分に直接関係のないメールまで確認する必要が生じ、重要なメールを見逃すリスクが高まります。また、メールボックスが膨大なメールで埋め尽くされ、必要な情報を探し出すのが困難になります。
本書では、CCを付ける基準を明確にすることを提案しています。例えば「直接アクションが必要な人にはTo、情報共有が必要な人にはCC」というシンプルなルールを設けることで、不必要なCCを減らすことができます。また、部署や案件ごとにメーリングリストを作成し、個別のアドレスではなくリストにCCを送ることで、受信者の管理を容易にする方法も紹介されています。
返信不要メールの活用法
メールコミュニケーションにおけるもう一つの大きなムダは、不必要な「了解しました」「承知しました」といった返信メールです。これらは送信者に安心感を与える一方で、受信者にとっては処理すべきメールが増えるだけの結果となります。
本書では、この問題を解決するために「返信不要」の文化を広めることを提案しています。具体的には、情報共有だけを目的としたメールには件名や本文に「返信不要」と明記することで、受信者の負担を軽減します。
また、「FYI(For Your Information)」という表記を活用することも効果的です。これは「参考までに」という意味で、返信や何らかのアクションを期待していないことを示します。このような小さな工夫が、組織全体のメールの往復を大幅に減らし、業務効率の向上につながります。
メール処理の時間短縮テクニック
メール処理に費やす時間を短縮するためのテクニックも、本書では詳しく紹介されています。まず基本となるのは「メールチェックの時間を決める」ことです。常にメールをチェックする習慣は、集中力の分散を招き、生産性を低下させます。1日に2〜3回、決まった時間にまとめてメールを処理する習慣をつけることで、効率的に対応できるようになります。
次に、「フォルダ分けとフィルタリング」の活用も推奨されています。重要度や緊急度、プロジェクトごとにフォルダを作成し、自動振り分けのルールを設定することで、優先順位に従ってメールを処理できるようになります。
また、「テンプレートの活用」も時間短縮に効果的です。頻繁に送信する定型文や挨拶文をテンプレート化しておくことで、毎回文章を考える手間を省けます。特に問い合わせへの回答や定期的な報告など、内容が似通ったメールを送る機会が多い場合に有効です。
さらに、「ショートカットキーの活用」も小さいながらも積み重なれば大きな時間短縮につながります。メールソフトの基本的なショートカットキーを覚えることで、マウス操作の手間を省き、スピーディーな処理が可能になります。
資料作成のムダ
誰も読まない資料の特徴
企業活動において、膨大な時間が資料作成に費やされていますが、その多くは実際には誰にも読まれないという現実があります。本書では、「誰も読まない資料」の特徴として、まず「情報過多」であることを挙げています。必要な情報だけでなく、あらゆる情報を盛り込んだ結果、読み手にとって何が重要なのかわからない資料になってしまいます。
また、「目的が不明確」な資料も読まれません。なぜその資料を作成するのか、誰に何を伝えたいのかが明確でないため、読み手の興味を引くことができないのです。
さらに、「視覚的に読みにくい」資料も問題です。文字ばかりで図表が少ない、フォントサイズが小さい、色使いが統一されていないなど、見た目の問題から読む気が失せてしまうケースも少なくありません。
本書では、これらの特徴を持つ資料は、作成に時間をかけた割に効果が薄いため、大きなムダであると指摘しています。
資料作成時間を半減させる方法
資料作成の時間を大幅に削減するためのテクニックとして、本書ではいくつかの具体的な方法を紹介しています。まず基本となるのは「目的と対象を明確にする」ことです。誰に何を伝えるための資料なのかを明確にすることで、必要な情報だけに絞り込むことができます。目的と対象を明確にすることで、資料の構成や内容が自ずと決まってくるため、作成時間の短縮につながります。
次に、「テンプレートの活用」も効果的です。定期的に作成する報告書や提案書などは、基本的なフォーマットを作成しておき、それを流用することで、毎回ゼロから作り直す手間を省けます。会社やチームで共通のテンプレートを用意しておくと、さらに効率化が図れます。
また、「図表の活用」も推奨されています。文章だけで説明するよりも、グラフや表、イラストなどを使って視覚的に表現することで、情報が伝わりやすくなるだけでなく、作成時間も短縮できます。特に数値データは、表やグラフで示すことで、一目で傾向や比較が理解できるようになります。
さらに、「共同編集ツールの活用」も時間短縮に効果的です。クラウド上のドキュメントを複数人で同時に編集できるツールを使うことで、メールでのやり取りや修正の手間を大幅に削減できます。また、最新版の管理も容易になり、古いバージョンを誤って使ってしまうリスクも減らせます。
テンプレート活用のコツ
テンプレートを効果的に活用するためには、いくつかのコツがあります。本書では、まず「目的別にテンプレートを用意する」ことを提案しています。会議資料、提案書、報告書など、用途に応じたテンプレートを準備しておくことで、その都度適切なものを選択できます。
次に、「必要最小限の項目に絞る」ことも重要です。テンプレートに盛り込む項目は、本当に必要なものだけに限定し、シンプルな構成にすることで、使いやすさと効率性を高めることができます。
また、「定期的な見直し」も欠かせません。一度作ったテンプレートをそのまま使い続けるのではなく、実際の使用感や周囲のフィードバックを基に、定期的に改良していくことが大切です。業務内容や組織の変化に合わせて、テンプレート自体も進化させていくことで、長期的な効率化につながります。
さらに、「共有と標準化」も推奨されています。個人だけでなく、チームや部署全体でテンプレートを共有し、標準化することで、資料のフォーマットが統一され、情報の探しやすさや理解のしやすさが向上します。また、メンバー間での引き継ぎもスムーズになります。
報告・連絡のムダ
過剰な報告体制の見直し
ビジネスにおいて、報告・連絡は重要なコミュニケーション手段ですが、その方法や頻度によっては大きなムダを生み出します。本書では、過剰な報告体制の問題点として、まず「時間の浪費」を挙げています。些細な事項まで逐一報告することで、報告する側も受ける側も多くの時間を費やしてしまいます。
また、「情報過多による重要事項の埋没」も問題です。大量の報告の中に本当に重要な情報が埋もれてしまい、結果として重要な判断や対応が遅れる可能性があります。
さらに、「自主性や創造性の阻害」も指摘されています。細かいことまで報告しなければならない文化は、メンバーの自主性や創造性を損ない、「指示待ち」の姿勢を助長してしまいます。
本書では、これらの問題を解決するために、報告すべき事項と報告不要な事項を明確に区別することを提案しています。例えば「通常の範囲内の進捗は週次報告のみ」「予算や納期に影響する問題が発生した場合のみ即時報告」といったルールを設けることで、報告の負担を軽減できます。
効率的な情報共有の仕組み
情報共有の方法を見直すことも、報告・連絡のムダを削減する上で重要です。本書では、効率的な情報共有の仕組みとして、まず「ツールの活用」を提案しています。チャットツールやプロジェクト管理ツールなどを導入することで、リアルタイムでの情報共有が可能になり、メールや対面での報告に比べて時間を節約できます。
次に、「情報の一元管理」も推奨されています。共有フォルダやクラウドストレージを活用して、プロジェクトや業務に関する情報を一箇所に集約することで、必要な情報を探す手間を省き、誰でも最新の情報にアクセスできる環境を整えることができます。
また、「定例報告の標準化」も効果的です。週次や月次の報告は、フォーマットを統一し、必要な情報だけを簡潔に伝えられるようにすることで、作成側も受け取る側も負担を軽減できます。
さらに、「情報のプル型共有」への移行も提案されています。全員に一斉に情報をプッシュするのではなく、必要な人が必要なときに情報を取りに行ける(プルできる)環境を整えることで、情報過多の問題を解消できます。
「報連相」の最適化
「報告・連絡・相談」、いわゆる「報連相」は、ビジネスの基本とされていますが、その運用方法によっては非効率を生み出します。本書では、報連相の最適化のために、まず「目的の明確化」を提案しています。報連相の本来の目的は、業務の円滑な遂行と問題の早期発見・解決にあります。この目的を見失い、形式的な報連相に陥らないよう注意が必要です。
次に、「適切なタイミングと方法の選択」も重要です。緊急性の高い事項は即時報告、定型的な進捗報告は定例会議で行うなど、内容に応じて最適な方法を選ぶことで、効率的なコミュニケーションが可能になります。
また、「権限委譲と信頼関係の構築」も報連相の最適化には欠かせません。上司が部下を信頼し、適切な権限委譲を行うことで、細かい報告の必要性が減り、双方の負担が軽減されます。信頼関係があれば、本当に必要な場面での報連相がスムーズに行われるようになります。
さらに、「フィードバックの質の向上」も推奨されています。報連相に対して、単に「了解」と返すだけでなく、建設的なフィードバックを返すことで、報告する側の成長を促し、次回以降の報連相の質も向上します。
デジタルツール活用で解消できるムダ
おすすめのデジタルツール
業務効率化のためのデジタルツールは数多く存在しますが、本書では特に効果的なツールとして、まず「プロジェクト管理ツール」を挙げています。Trello、Asana、Jiraなどのツールを活用することで、タスクの進捗状況をリアルタイムで共有でき、メールでの進捗報告や状況確認のためのミーティングが不要になります。
次に、「コミュニケーションツール」も推奨されています。SlackやMicrosoft Teamsなどのチャットツールを導入することで、短い質問や確認事項をメールではなくチャットで済ませられるようになり、コミュニケーションのスピードが向上します。
また、「ドキュメント共有・共同編集ツール」も効率化に貢献します。Google WorkspaceやMicrosoft 365などのクラウドベースのツールを使うことで、複数人での同時編集や最新版の管理が容易になり、メールでのファイルのやり取りや版管理の手間を省けます。
さらに、「フォーム作成ツール」も便利です。Google FormsやMicrosoft Formsなどを活用することで、アンケートや申請書などのデータ収集を自動化でき、紙の書類やメールでの情報収集に比べて大幅に効率化できます。
ツール導入の失敗パターン
デジタルツールの導入が必ずしも効率化につながるわけではありません。本書では、ツール導入の失敗パターンとして、まず「目的不明確なツール導入」を挙げています。「流行っているから」「他社が使っているから」という理由だけでツールを導入しても、実際の業務に合わなければ、かえって混乱を招くだけです。
次に、「使い方の教育不足」も問題です。新しいツールを導入しても、使い方の教育が不十分だと、従来の方法との二重運用が発生したり、ツールの機能を十分に活用できなかったりして、効率化につながりません。
また、「過剰な機能のツール選定」も失敗の原因となります。必要以上に高機能なツールを選ぶと、操作が複雑になり、かえって業務効率が落ちることがあります。実際の業務に必要な機能に絞ったシンプルなツールを選ぶことが重要です。
さらに、「ツール乱立」も避けるべき問題です。似たような機能を持つ複数のツールを並行して使用すると、どのツールに情報があるのか分からなくなり、情報の分断や重複が生じます。全社的なツール選定の方針を決め、統一することが大切です。
業務自動化の具体例
業務自動化によって効率化できる具体例として、本書ではいくつかの事例が紹介されています。まず「定型文書の自動生成」です。請求書や見積書など、同じフォーマットで繰り返し作成する文書は、テンプレートとデータを組み合わせて自動生成することで、作成時間を大幅に短縮できます。
次に、「データ入力の自動化」も効果的です。Webフォームやスキャナーを活用して、紙の書類からデータを自動的に取り込むことで、手入力の手間を省き、入力ミスも減らせます。
また、「定期的な報告書の自動作成」も推奨されています。日次や週次の売上レポートなど、定期的に作成する報告書は、データソースとの連携を自動化することで、手作業での集計や資料作成の時間を削減できます。
さらに、「承認フローの電子化」も業務効率化に貢献します。紙の申請書を回覧する代わりに、電子承認システムを導入することで、承認プロセスのスピードアップと透明性の向上が図れます。また、承認状況のリアルタイムでの把握も可能になります。
意思決定プロセスのムダ
決裁フローの簡素化
企業における意思決定プロセスは、しばしば複雑で時間のかかるものになっています。本書では、決裁フローの問題点として、まず「多段階の承認プロセス」を挙げています。些細な案件でも複数の上司や部署を経由して承認を得る必要があると、意思決定に時間がかかり、ビジネスチャンスを逃す原因になります。
また、「形骸化した承認」も問題です。内容を十分に確認せずに承認する「ハンコ押し」の文化は、承認プロセスの本来の目的である「チェック機能」を果たさず、単なる時間のムダになっています。
さらに、「責任の分散」も指摘されています。多くの人が承認に関わることで、誰も最終的な責任を負わない状況が生まれ、問題が発生した際の対応が遅れる原因になります。
本書では、これらの問題を解決するために、決裁フローの簡素化を提案しています。具体的には、案件の重要度や金額に応じて承認レベルを分け、軽微な案件は現場レベルで決裁できるようにすることで、意思決定のスピードを上げることができます。
権限委譲のポイント
効率的な意思決定を実現するためには、適切な権限委譲が不可欠です。本書では、権限委譲のポイントとして、まず「明確な基準の設定」を挙げています。どのような案件をどのレベルで決裁できるのか、金額や影響範囲などの具体的な基準を設けることで、判断に迷うことなく適切な権限行使が可能になります。
次に、「段階的な権限委譲」も推奨されています。いきなり大きな権限を与えるのではなく、小さな権限から徐々に範囲を広げていくことで、委譲される側の成長を促しながら、リスクを最小限に抑えることができます。
また、「フォローアップの仕組み」も重要です。権限を委譲した後も、定期的な報告や相談の機会を設けることで、問題が大きくなる前に対処できる体制を整えることが大切です。
さらに、「失敗を許容する文化」の醸成も欠かせません。権限委譲された側が萎縮せずに判断できるよう、多少の失敗は学びの機会として捉え、責めるのではなくサポートする姿勢が、組織全体の意思決定能力の向上につながります。
迅速な意思決定のコツ
迅速かつ適切な意思決定を行うためのコツとして、本書ではいくつかの方法を紹介しています。まず「情報の整理と可視化」です。判断に必要な情報を整理し、視覚的にわかりやすくまとめることで、本質的な議論に集中でき、意思決定のスピードが上がります。
次に、「判断基準の明確化」も効果的です。事前に「こういう条件なら承認、こういう条件なら却下」という判断基準を設けておくことで、個々のケースでの判断がスムーズになります。
また、「タイムボックスの設定」も推奨されています。「この案件については〇日以内に結論を出す」と期限を決めることで、不必要に長引く議論を防ぎ、適切なタイミングでの意思決定が可能になります。
さらに、「決定事項の明確化と共有」も重要です。何が決まったのか、誰がいつまでに何をするのかを明確にし、関係者全員に共有することで、決定後のアクションがスムーズに進みます。
出社・通勤に関するムダ
リモートワークで解消できる業務
コロナ禍を経て、多くの企業でリモートワークが導入されましたが、その経験から、必ずしも出社が必要でない業務が多いことが明らかになりました。本書では、リモートワークで十分に対応できる業務として、まず「資料作成や分析業務」を挙げています。集中力を要するこれらの作業は、むしろオフィスの雑音や中断のない自宅環境の方が効率的に進められることが多いです。
次に、「オンラインでのミーティングや打ち合わせ」も、物理的な移動を伴わずに実施できます。特に複数拠点をつなぐ会議は、全員がリモート参加することで、移動時間の削減と参加のしやすさを両立できます。
また、「メールやチャットでのコミュニケーション」も、場所を選ばずに行えるため、必ずしも出社する必要はありません。特に社内向けの連絡や情報共有は、デジタルツールを活用することで、どこからでも効率的に行えます。
さらに、「データ入力や集計作業」もリモートで十分に対応可能です。クラウド上のシステムやデータベースを利用することで、オフィスにいなくても必要な情報にアクセスし、作業を進めることができます。
本書では、これらの業務をリモートワークに移行することで、通勤時間の削減だけでなく、集中力の向上や生産性の向上にもつながると指摘しています。
ハイブリッドワークの最適化
コロナ禍を経て、多くの企業がハイブリッドワーク(出社とリモートワークの併用)を導入していますが、その運用方法によっては新たなムダが生じることもあります。本書では、ハイブリッドワークを最適化するポイントとして、まず「出社日の目的明確化」を提案しています。
単に「週に3日は出社」といったルールを設けるだけでなく、「チームミーティングの日」「クライアントとの対面打ち合わせの日」など、出社する目的を明確にすることで、オフィスでの時間を有効に活用できます。
次に、「デジタルファースト」の考え方も重要です。出社している人とリモートワークの人が混在する状況でも、情報格差が生じないよう、基本的な情報共有や連絡はデジタルツールを優先して行うことで、どこにいても同じ情報にアクセスできる環境を整えることができます。
また、「コミュニケーションルールの明確化」も欠かせません。緊急度に応じて連絡手段を使い分ける(緊急時は電話、通常の連絡はチャット、情報共有はメールなど)ことで、リモートワーク中でも適切なコミュニケーションが取れるようになります。
オフィス環境の見直し
出社する必要がある業務については、オフィス環境自体を見直すことでムダを削減できます。本書では、オフィス環境の見直しのポイントとして、まず「フリーアドレス制の導入」を挙げています。固定席を廃止し、その日の業務内容や目的に応じて最適な場所で働ける環境を整えることで、スペースの有効活用とコミュニケーションの活性化が図れます。
次に、「集中ゾーンと協働ゾーンの分離」も効果的です。静かに集中して作業できるエリアと、活発に議論や共同作業ができるエリアを分けることで、それぞれの業務に適した環境で効率よく働くことができます。
また、「ペーパーレス化の推進」も重要です。紙の書類や資料を減らすことで、物理的なファイリングや保管のスペースを削減でき、必要な情報へのアクセスも容易になります。さらに、印刷や配布の手間も省けるため、業務効率の向上にもつながります。
さらに、「適切な会議スペースの確保」も欠かせません。オンライン会議とオフライン会議の両方に対応できる設備を整えることで、場所や参加者の状況に応じて柔軟に会議形式を選択できるようになります。
人間関係のムダ
無駄な社内政治への対処法
企業における人間関係のムダの中でも、特に時間と労力を消費するのが「社内政治」です。本書では、無駄な社内政治への対処法として、まず「透明性の確保」を提案しています。意思決定のプロセスや基準を明確にし、情報を広く共有することで、不透明な駆け引きや忖度の余地を減らすことができます。
次に、「成果主義の徹底」も効果的です。人間関係や上司との親密度ではなく、実際の業績や貢献度で評価する文化を醸成することで、無駄な取り入りや政治的な動きを減らすことができます。
また、「目的の共有」も重要です。組織やプロジェクトの目的を明確にし、全員で共有することで、個人の利害よりも全体の目標達成を優先する風土を作ることができます。これにより、派閥争いや縄張り意識といった非生産的な行動を抑制できます。
さらに、「建設的なフィードバック文化」の構築も推奨されています。批判や非難ではなく、改善を目的とした建設的なフィードバックを日常的に行う文化を作ることで、問題の早期解決と相互理解の促進が図れます。
コミュニケーションの効率化
人間関係におけるムダを減らすためには、コミュニケーションの効率化も欠かせません。本書では、効率的なコミュニケーションのポイントとして、まず「目的に応じた手段の選択」を挙げています。単なる情報共有ならメール、即時の返信が必要ならチャット、複雑な議論が必要なら会議というように、目的に合わせて最適な手段を選ぶことで、無駄なやり取りを減らせます。
次に、「簡潔明瞭な伝え方」も重要です。結論から先に伝え、必要な情報だけを簡潔に伝えることで、相手の理解を促進し、追加の質問や確認の手間を省くことができます。特にビジネスコミュニケーションでは、冗長な説明や余談は避け、ポイントを絞った伝え方を心がけることが大切です。
また、「非同期コミュニケーションの活用」も推奨されています。すべての連絡に即時の返信を求めるのではなく、緊急度に応じて返信のタイミングを調整することで、集中力の分散を防ぎ、効率的に業務を進めることができます。
さらに、「定期的な1on1ミーティング」の実施も効果的です。上司と部下が定期的に1対1で対話する機会を設けることで、日常的な小さな問題や疑問をその場で解決でき、大きな問題に発展する前に対処することができます。
チームワークを損なわないムダ削減
業務効率化を進める際に注意すべきは、チームワークや組織の一体感を損なわないことです。本書では、チームワークを維持しながらムダを削減するポイントとして、まず「全員参加の改善活動」を提案しています。トップダウンで改革を押し付けるのではなく、現場のメンバーも含めた全員参加の形で改善策を考え、実行することで、納得感と当事者意識を高めることができます。
次に、「成功体験の共有」も重要です。ムダ削減によって得られた成果や時間的余裕を可視化し、チーム全体で共有することで、改善活動のモチベーションを維持することができます。小さな成功でも積極的に評価し、称えることが大切です。
また、「コミュニケーションの質の確保」も欠かせません。効率化の名のもとに必要なコミュニケーションまで削減してしまうと、チームの一体感や信頼関係が損なわれる恐れがあります。業務上必要な連絡は簡潔にしつつも、チームビルディングのための交流の機会は意識的に設けることが重要です。
さらに、「適切な評価と報酬」も効果的です。ムダ削減や業務改善に貢献したメンバーを適切に評価し、報酬や昇進などの形で還元することで、継続的な改善活動へのモチベーションを高めることができます。
働き方改革とムダ削減の関係
生産性向上と働き方改革
働き方改革とムダ削減は密接に関連しています。本書では、生産性向上と働き方改革の関係について、まず「時間の質の向上」という観点から説明しています。単に長時間労働を減らすだけでなく、限られた時間の中で最大の成果を出すために、ムダな作業を徹底的に排除することが重要です。
次に、「創造的な業務への時間シフト」も強調されています。ルーティンワークや事務作業などのムダを削減することで生まれた時間を、より付加価値の高い創造的な業務に充てることで、個人の成長と組織の競争力向上の両方を実現できます。
また、「多様な働き方の実現」も重要です。ムダな出社や会議を減らし、リモートワークやフレックスタイム制などの柔軟な働き方を導入することで、育児や介護と仕事の両立、ワークライフバランスの向上が図れます。これにより、多様な人材が活躍できる環境が整います。
さらに、「心理的安全性の確保」も欠かせません。ムダな作業に追われてストレスを感じる状況を改善し、本質的な業務に集中できる環境を整えることで、メンタルヘルスの向上と離職率の低下につながります。
残業削減につながるムダ排除
残業時間の削減は、多くの企業が取り組む課題ですが、単に「早く帰りましょう」と呼びかけるだけでは効果は限定的です。本書では、残業削減のためのムダ排除として、まず「業務の棚卸しと優先順位付け」を提案しています。すべての業務を洗い出し、重要度と緊急度に基づいて優先順位を付けることで、限られた時間の中で本当に必要な業務に集中できるようになります。
次に、「会議時間の短縮」も効果的です。長時間の会議は、その準備と参加で多くの時間を消費します。会議の目的を明確にし、議題と時間配分を事前に決めておくことで、効率的な会議運営が可能になり、残業の削減につながります。
また、「決裁プロセスの簡素化」も重要です。複数の承認者を経由する複雑な決裁プロセスは、書類の作成や修正、待ち時間などで多くの時間を浪費します。権限委譲や決裁基準の明確化により、プロセスを簡素化することで、業務のスピードアップと残業削減が図れます。
さらに、「テクノロジーの活用」も推奨されています。定型的な作業や単純作業は、RPAやAIなどのテクノロジーを活用して自動化することで、人間はより付加価値の高い業務に集中でき、全体の業務量と残業時間の削減につながります。
ワークライフバランスの実現方法
ワークライフバランスの実現は、従業員の満足度向上と生産性向上の両面で重要です。本書では、ワークライフバランスを実現するためのムダ削減として、まず「メリハリのある働き方」を提案しています。集中して働く時間と休息する時間を明確に分け、オンとオフの切り替えを意識することで、効率的に業務を進めながら、プライベートの時間も確保できます。
次に、「タイムマネジメントの徹底」も効果的です。1日の業務スケジュールを計画的に組み、優先順位の高いタスクから取り組むことで、時間内に業務を終えることができます。また、集中力が高い時間帯に重要な業務を配置するなど、自分の特性に合わせた時間管理も重要です。
また、「デジタルデトックス」も推奨されています。常に仕事のメールやメッセージをチェックする習慣は、プライベートの時間まで仕事に侵食されてしまいます。業務時間外はデジタル機器から距離を置く時間を意識的に作ることで、真の休息と充電が可能になります。
さらに、「成果主義の導入」も効果的です。長時間オフィスにいることではなく、実際の成果や貢献度で評価する文化を醸成することで、効率的に業務を進め、早く帰宅するインセンティブが生まれます。これにより、ワークライフバランスの実現と生産性向上の両立が図れます。
ムダ作業を見つけ出す方法
業務の棚卸しのやり方
ムダな作業を削減するための第一歩は、現状の業務を可視化することです。本書では、業務の棚卸しの方法として、まず「業務リストの作成」を提案しています。日々行っているすべての業務を書き出し、それぞれの作業内容、頻度、所要時間、関連部署などを記録することで、全体像を把握することができます。
次に、「業務の分類」も重要です。書き出した業務を「コア業務」「サポート業務」「雑務」などに分類することで、どの領域に時間を費やしているかが明確になります。理想的には、コア業務に最も多くの時間を割くべきですが、実際には雑務に追われているケースも少なくありません。
また、「業務フローの可視化」も効果的です。業務の流れを図式化することで、重複や無駄な工程、ボトルネックなどが見えてきます。特に複数の部署や担当者が関わる業務では、全体のフローを可視化することで、改善点が明らかになります。
さらに、「定期的な見直し」も欠かせません。業務の棚卸しは一度行って終わりではなく、定期的(四半期や半年ごと)に見直すことで、新たに発生したムダや改善の効果を確認することができます。
タイムスタディの実践法
より詳細に業務の実態を把握するためには、タイムスタディ(時間分析)が効果的です。本書では、タイムスタディの実践法として、まず「時間記録の取り方」を説明しています。一定期間(1週間程度)、15分や30分単位で何の業務を行っていたかを記録することで、時間の使い方の実態が明らかになります。
次に、「時間の分析」も重要です。記録したデータを集計し、業務カテゴリー別の時間配分や、時間帯ごとの業務内容などを分析することで、ムダな時間や非効率な作業パターンを特定できます。
また、「中断要因の記録」も効果的です。業務中に発生した中断(電話、メール、同僚からの質問など)とその対応時間も記録することで、集中力を妨げる要因を把握し、対策を講じることができます。
さらに、「改善目標の設定」も欠かせません。分析結果に基づいて、削減したいムダな時間や増やしたい価値ある業務の時間を具体的な数値目標として設定することで、改善活動の方向性が明確になります。
優先順位の決め方
限られた時間と資源の中で最大の成果を上げるためには、適切な優先順位付けが不可欠です。本書では、優先順位の決め方として、まず「重要度と緊急度のマトリクス」を提案しています。すべての業務を「重要かつ緊急」「重要だが緊急でない」「緊急だが重要でない」「重要でも緊急でもない」の4つに分類し、前者から順に取り組むことで、効率的に業務を進められます。
次に、「コストと効果のバランス」も重要です。各業務や改善策に必要なコスト(時間、労力、予算など)と、それによって得られる効果を比較し、投資対効果の高いものから優先的に取り組むことで、限られたリソースを最大限に活用できます。
また、「顧客価値への貢献度」も優先順位を決める上で欠かせない視点です。それぞれの業務が最終的な顧客価値にどれだけ貢献しているかを評価し、直接的に価値を生み出す業務を優先することで、組織全体の成果向上につながります。
さらに、「自分にしかできない業務」の特定も効果的です。自分の専門性や権限が必要な業務は優先的に取り組み、他の人でもできる業務は委託や共有を検討することで、個人の強みを最大限に活かした時間の使い方が可能になります。
ムダ作業を排除するための組織づくり
トップダウンとボトムアップの両立
ムダ作業の排除を組織全体で進めるためには、トップダウンとボトムアップの両方のアプローチが必要です。本書では、この両立のポイントとして、まず「経営層のコミットメント」を挙げています。ムダ削減の重要性と方向性を経営層が明確に示し、率先して実践することで、組織全体の取り組みが加速します。
次に、「現場の声を活かす仕組み」も重要です。実際に業務を行っている現場のメンバーは、ムダや非効率の実態を最もよく知っています。現場からの改善提案を積極的に取り入れる制度や文化を作ることで、実効性の高い改善が可能になります。
また、「中間管理職の役割明確化」も欠かせません。部長やマネージャーといった中間管理職は、経営層の方針を現場に伝えるとともに、現場の声を経営層に届ける橋渡し役として機能することが重要です。彼らがムダ削減の推進役となることで、組織全体の取り組みがスムーズに進みます。
さらに、「権限と責任の適切な配分」も効果的です。ムダ削減に関する一定の権限を現場レベルに委譲することで、スピーディーな改善が可能になります。同時に、その結果に対する責任も明確にすることで、主体的な取り組みを促進できます。
小さな成功事例の共有方法
ムダ削減の取り組みを組織全体に広げるためには、小さな成功事例を効果的に共有することが重要です。本書では、成功事例の共有方法として、まず「具体的な数字での可視化」を提案しています。「この改善によって週に3時間の時間短縮ができた」「月に10万円のコスト削減につながった」など、具体的な数字で効果を示すことで、説得力が増します。
次に、「ストーリーテリング」も効果的です。単に結果だけでなく、どのような問題意識から始まり、どのような工夫や試行錯誤を経て成功に至ったかというストーリーを共有することで、他のメンバーも自分の状況に置き換えて考えやすくなります。
また、「定期的な共有の場」も重要です。月次の全体会議や部門ミーティングなどで、定期的に改善事例を共有する時間を設けることで、継続的な意識向上と新たなアイデアの創出につながります。
さらに、「表彰制度」も推奨されています。特に優れた改善提案や成果を上げたチームや個人を表彰することで、モチベーションの向上と組織全体への波及効果が期待できます。金銭的な報酬だけでなく、社内報での紹介や経営層からの感謝の言葉など、さまざまな形での認知も効果的です。
継続的な改善文化の作り方
一時的なムダ削減ではなく、継続的に改善が行われる組織文化を作ることが、長期的な成功の鍵です。本書では、継続的な改善文化の作り方として、まず「PDCAサイクルの定着」を挙げています。計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Act)のサイクルを組織の日常に組み込むことで、継続的な改善が習慣化します。
次に、「失敗を許容する風土」も重要です。新しい改善策に挑戦した結果としての失敗を責めるのではなく、学びの機会として捉える文化を醸成することで、メンバーの挑戦意欲と創意工夫が促進されます。
また、「定期的な振り返りの機会」も欠かせません。四半期や半期ごとに、改善活動の成果と課題を振り返る機会を設けることで、次のステップへの気づきが生まれます。この振り返りは、数字だけでなく、メンバーの実感や気づきも含めて行うことが大切です。
さらに、「改善の日常化」も効果的です。特別なプロジェクトや活動としてではなく、日々の業務の中で常に改善の視点を持つことを奨励し、小さな工夫や変更をすぐに実践できる環境を整えることで、継続的な改善文化が根付いていきます。
感想・レビュー
実務に即した具体例の豊富さ
この本を読んで最も印象に残ったのは、実務に即した具体例の豊富さです。著者の元山文菜さんは、コンサルタントとしての豊富な経験から、さまざまな業種・業態で実際に見られるムダな作業を的確に捉え、わかりやすく解説しています。
「あるある!」と思わず膝を打ちたくなるような事例が次々と登場し、自分の職場や業務を思い返しながら読み進めることができました。特に「会議」や「メール」に関する章は、多くのビジネスパーソンが日々直面している問題だけに、共感と発見が満載でした。
また、ムダを発見するための視点や考え方も非常に実践的です。「なぜこの作業が必要なのか」「誰のために行っているのか」といった根本的な問いかけは、シンプルでありながら強力な気づきをもたらしてくれます。この本を読んだ翌日から、すぐに職場で実践できる内容になっているのは、ビジネス書として大きな魅力です。
さらに、イラストや図解を効果的に用いて説明されているため、視覚的にも理解しやすく、読みやすさも抜群です。忙しいビジネスパーソンでも、短時間で要点を掴み、すぐに実践に移せる工夫がされています。
読みやすさと実践のしやすさ
本書のもう一つの大きな特徴は、その読みやすさと実践のしやすさです。ビジネス書の中には、理論は素晴らしいものの、実際にどう行動すればよいのかわかりにくいものも少なくありません。しかし、この本は違います。
各章は短く区切られており、気になる箇所から読み始めることができます。また、専門用語や難解な概念に頼ることなく、平易な言葉で説明されているため、業務改善の初心者でも理解しやすい内容になっています。
特に印象的だったのは、各ムダ作業に対して「すぐにできる改善策」と「中長期的な対策」が明確に分けて提示されている点です。これにより、読者は自分の置かれた状況や権限に応じて、適切なアクションを選択できます。明日からすぐに実践できる小さな改善から始め、徐々に大きな変革へとつなげていくステップが示されているのは、非常に実用的です。
また、本書は「こうすべき」という押し付けがましい主張ではなく、「こうしたらどうですか?」という提案型の文体で書かれています。これにより、読者は自分の職場や業務の特性に合わせて、柔軟に取り入れることができます。この姿勢は、多様な働き方や組織文化が存在する現代のビジネス環境に非常にマッチしていると感じました。
他のビジネス書との差別化ポイント
業務改善やムダ削減に関するビジネス書は数多く出版されていますが、本書の差別化ポイントは明確です。まず、「100個」というボリュームの多さが挙げられます。これだけ多くの具体例が示されていると、どんな業種や職種の人でも、自分の状況に当てはまるムダを見つけることができます。
また、多くのビジネス書がDXやAI、最新テクノロジーの導入を前提とした改革を提案する中、本書は「今すぐできる」「特別なツールや知識がなくてもできる」改善策に焦点を当てている点も特徴的です。もちろん、テクノロジーの活用も提案されていますが、それが全てではなく、まずは身近なところから始められる点が現実的です。
さらに、本書は「ムダ」を単に排除すべきものとしてではなく、「価値を生み出す時間を増やすための手段」として位置づけている点も重要です。ムダを削減することで生まれた時間やエネルギーを、より創造的な業務や自己成長、ワークライフバランスの向上につなげるという前向きな視点は、読者に希望と意欲をもたらします。
加えて、個人の努力だけでなく、組織全体でムダを削減するための方法論も示されている点も、他書との差別化ポイントです。個人が頑張るだけでは限界がある中、組織文化や仕組みを変えていくためのアプローチが具体的に示されているのは、非常に価値があります。
まとめ
「無くせる会社のムダ作業100個まとめてみた」は、日常業務に潜むムダを発見し、排除するための実践的なガイドブックです。元山文菜さんの豊富な経験に基づく100個のムダ作業の指摘と、その解決策は、どんな職場でも明日から実践できる具体性を備えています。
本書の最大の魅力は、特別な知識や技術がなくても、すぐに取り組める改善策が豊富に提示されている点です。会議、メール、資料作成など、ビジネスパーソンが日々直面する課題に対して、シンプルかつ効果的な解決策が示されています。
ムダを削減することで生まれた時間を、より価値の高い業務や自己成長、プライベートの充実に充てることができれば、個人の満足度と組織の生産性の両方が向上します。この本は、そのための第一歩を踏み出すための、心強い味方となるでしょう。