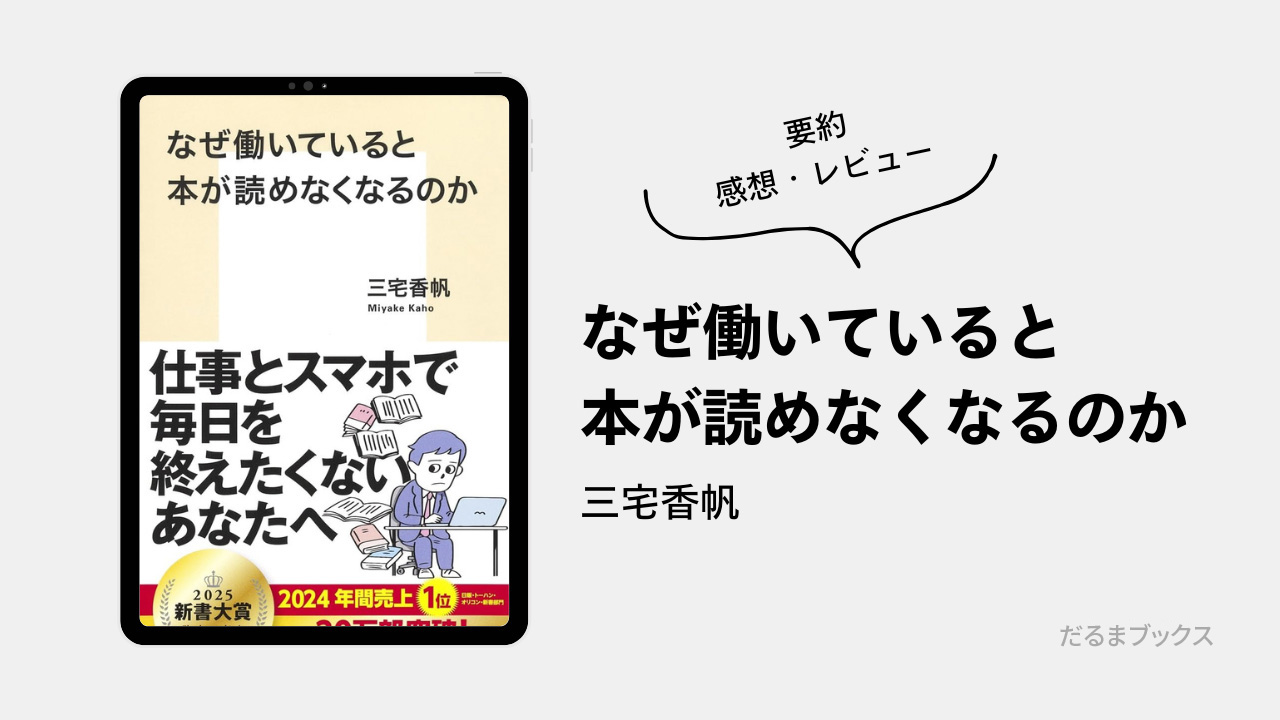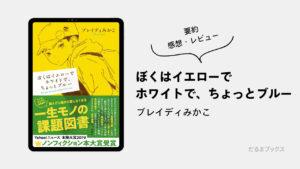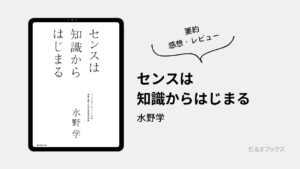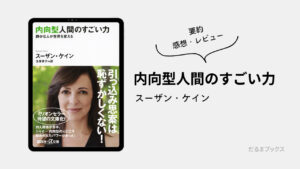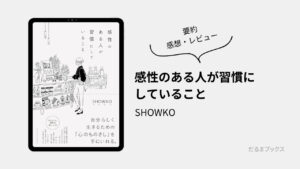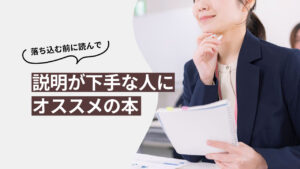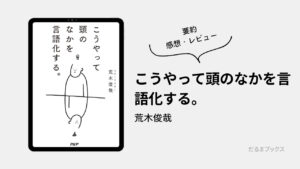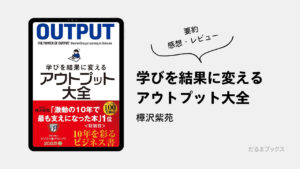現代社会で働く人々の多くが抱える「本が読めなくなった」という悩み。文芸評論家の三宅香帆さんは自身の経験から、この問題の本質に迫る一冊を著しました。
「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」は発売後わずか1週間で10万部を突破し、現代の働き方と読書の関係性を問い直す社会現象となっています。本書は明治時代からの読書と労働の歴史をたどりながら、「全身全霊で働く社会」から「半身社会」への転換を提案する意欲作です。
「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」の基本情報
文芸評論家として活躍する三宅香帆さんは1994年生まれ。幼い頃から本の虫で、大学院在学中に『人生を狂わす名著50』でデビューするなど、本にどっぷり浸かった生活を送っていました。そんな彼女が人材企業に就職した途端、本が読めなくなってしまったという衝撃的な体験が本書の出発点となっています。
本書は2023年1月から11月にかけてWEBサイト「集英社新書プラス」で連載された内容をもとに、2024年に集英社新書から刊行されました。発売後の反響は凄まじく、多くの読者から「私も働いているうちに本が読めなくなりました」という共感の声が寄せられています。
構成としては、明治時代から現代までの読書と労働の関係性を時代ごとに分析し、最終章では「半身社会」という新しい概念を提示しています。三宅さんは「本が読めない」という個人の問題を社会構造の問題として捉え直すことで、現代の働き方に一石を投じているのです。
三宅香帆さんが語る「読書の壁」
三宅さんは本書の冒頭で、自身の経験を赤裸々に語っています。「仕事は楽しく、新入社員のプレゼン大会で1位になったりもしたんですが、あるとき、最近本を読んでないなと。特に学生時代好きだった古典や海外文学などにまったく手が伸びなくなりました。週5日、朝9時半から夜8時過ぎまで働いていると、まともに本が読めない。時間があってもSNSや動画ばかり見てしまう。これってどういうことなんだろうと」
この疑問は、多くの現代人が抱える悩みと重なります。時間がないわけではない。電車に乗っている時間や夜寝る前の時間、スマホを眺めている時間、休日の睡眠時間を読書に充てることは理論上可能なはずです。しかし、なぜか本を開いても、すぐ眠くなったりスマホを見てしまったりしてしまう。
この現象は単なる個人の怠惰ではなく、現代社会の構造に根ざした問題だと三宅さんは指摘します。映画『花束みたいな恋をした』の主人公・麦(菅田将暉)が、大学時代はカルチャーに明るかったのに、働き始めるとパズドラのようなスマホゲームしかできなくなる姿に、多くの同世代が共感したという事実も、この問題の普遍性を物語っています。
現代人が抱える読書の難しさ
現代人が読書に取り組めない理由は、単純に「忙しい」だけではありません。三宅さんは、現代社会における読書の難しさを多角的に分析しています。
まず、インターネットの普及により、情報の取得方法が大きく変化しました。必要な情報だけを素早く得られるインターネットに慣れた私たちは、じっくりと時間をかけて本を読む習慣を失いつつあります。
また、労働環境の変化も大きな要因です。長時間労働や精神的な疲労により、帰宅後に本を読む気力が残っていないという現実があります。そして何より、現代社会では「全身全霊」で仕事に取り組むことが暗黙の了解となっており、読書のような「ノイズ」を含む活動に時間を割くことが難しくなっているのです。
仕事と読書の関係性
三宅さんは、仕事と読書の関係性について興味深い視点を提示しています。かつては仕事と読書は相互補完的な関係にありました。仕事で疲れた心を読書で癒し、読書で得た知識や視点を仕事に活かすという循環が存在していたのです。
しかし現代では、仕事と読書が対立関係に置かれるようになりました。仕事の効率や成果を最大化するためには、読書のような「非効率」な活動を排除すべきだという価値観が広がっています。三宅さんはこの変化を、新自由主義的価値観の内面化と、2000年代に始まった「労働による自己実現」を称賛する風潮に関連付けて分析しています。
「読めない」という感覚の正体
「読めない」という感覚の正体は何なのか。三宅さんはこの問いに対して、「ノイズ」という概念を用いて説明します。
インターネットが普及した現代では、私たちは「ノイズ除去」の欲求を強く持つようになりました。必要な情報だけを効率よく得たいという欲求が強まり、不要な情報=ノイズを排除することが美徳とされるようになったのです。
しかし、読書には本質的に「ノイズ」が含まれています。小説を読めば、物語の展開に予想外の要素が含まれますし、新書や専門書を読めば、自分が求めていた情報以外にも様々な知識に触れることになります。このノイズこそが読書の醍醐味であり、新たな発見や思考の広がりをもたらすものなのですが、効率を重視する現代社会ではこのノイズが邪魔者扱いされてしまうのです。
本書で提示される「読めなくなる理由」
三宅さんは本書の中で、現代人が本を読めなくなる理由を多角的に分析しています。その理由は単に「時間がない」という表面的なものではなく、社会構造や価値観の変化に根ざした深いものです。
時間の断片化と集中力の低下
現代社会では、時間が細切れになる「断片化」が進んでいます。スマートフォンの通知、SNSのタイムライン、短尺動画など、私たちの注意を引く要素が増え続け、一つのことに集中する時間が減少しています。
読書には一定の集中力と時間のまとまりが必要です。しかし、断片化された時間の中では、読書に必要な集中力を維持することが難しくなっています。電車の中で本を開いても、すぐにスマホを取り出してしまう。夜寝る前に読書を始めても、すぐにSNSをチェックしてしまう。このような経験は、多くの現代人に共通するものではないでしょうか。
仕事による精神的疲労の影響
長時間労働や高いストレスを伴う現代の仕事環境は、精神的な疲労を蓄積させます。この疲労が、読書に必要な精神的余裕を奪っているのです。
三宅さんは自身の経験から、「週5日、朝9時半から夜8時過ぎまで働いていると、まともに本が読めない」と述べています。物理的な時間はあっても、精神的な余裕がなければ、読書に取り組むことは難しいのです。
SNSやスマホによる読書習慣の変化
スマートフォンやSNSの普及は、私たちの情報摂取の方法を大きく変えました。短い文章や画像、動画を素早くスクロールして消費する習慣が身についた結果、一冊の本をじっくり読み進める忍耐力が低下しているのです。
三宅さんは、インターネットによって「ノイズ除去の欲求」が強化されたと指摘します。知りたいこと=情報だけを手早く教えてくれるネットの世界に浸っていると、ノイズだらけの本はますます読めなくなるのです。
読書に対する無意識の抵抗感
三宅さんは、現代人が読書に対して無意識の抵抗感を持っている可能性を指摘します。それは「読書は役に立つべきだ」という功利主義的な価値観に関連しています。
2000年代以降、日本社会では「仕事で自己実現すること」が称賛されるようになりました。その結果、読書も「仕事に役立つもの」でなければならないという無意識の圧力が生まれたのです。しかし、本来読書は実用的な目的だけでなく、楽しみや知的好奇心の充足のためにも行われるものです。この価値観の歪みが、読書への抵抗感を生み出しているのかもしれません。
著者が提案する読書との向き合い方
三宅さんは、現代社会における読書の困難さを指摘するだけでなく、その解決策も提案しています。それは「半身社会」という新しい概念を中心としたものです。
「読めない」ことを責めない姿勢
まず三宅さんが強調するのは、「読めない」自分を責めないことの大切さです。本が読めないのは個人の怠惰や意志の弱さではなく、社会構造の問題だと理解することが第一歩です。
「疲れたときは、休もう。……本なんか読まなくてもいい」と三宅さんは言います。この言葉は、本を愛する文芸評論家からの言葉だからこそ、重みがあります。読書に対するプレッシャーを取り除き、自分のペースで向き合うことが大切なのです。
小さな読書習慣の作り方
三宅さんは、無理なく続けられる小さな読書習慣を作ることを提案しています。例えば、通勤電車の中で10分だけ本を読む、寝る前に5ページだけ読むなど、ハードルを低く設定することが重要です。
また、自分の興味や気分に素直に従って本を選ぶことも大切です。「読むべき本」ではなく「読みたい本」を選ぶことで、読書の楽しさを再発見できるでしょう。
仕事と読書を両立させるコツ
三宅さんは、仕事と読書を対立させるのではなく、共存させる方法を模索しています。それが「半身社会」という概念です。
「半身社会」とは、仕事に全身全霊を捧げるのではなく、仕事と個人の時間(読書や趣味など)にバランスよく時間と労力を配分する社会のことです。三宅さんは、「全身全霊」で働くことが当然とされる現代社会から、「半身」の働き方を当然とする社会への転換を提唱しています。
読書の喜びを再発見する方法
三宅さんは、読書の本質的な喜びを再発見することの大切さを説いています。読書は単なる情報収集の手段ではなく、異なる世界や価値観に触れる体験であり、自分自身を豊かにする活動です。
この喜びを再発見するためには、効率や実用性を一旦脇に置き、「ノイズ」を受け入れる姿勢が必要です。予想外の発見や思いがけない感動こそが、読書の醍醐味なのです。
印象的なエピソードから見る読書の意義
本書には、三宅さん自身の経験や他の読者の声など、印象的なエピソードが数多く登場します。これらのエピソードを通して、読書の意義が浮き彫りになっています。
著者自身の読書遍歴
三宅さんは幼い頃から本の虫で、大学院在学中に『人生を狂わす名著50』でデビューするなど、本にどっぷり浸かった生活を送っていました。そんな彼女が会社に就職した途端に本が読めなくなったという経験は、本書の核心部分を形成しています。
「結局、本が読みたすぎて3年半で会社を辞め、文筆専業に」なったという三宅さんの決断は、読書が彼女にとってどれほど重要なものであったかを物語っています。この経験は、多くの読者にとって共感と勇気を与えるものでしょう。
読書が人生に与えた影響
三宅さんは本書の中で、読書が自分の人生にどのような影響を与えたかについても語っています。読書を通じて得た知識や視点は、彼女の思考や価値観を形作り、最終的には職業選択にも影響を与えました。
また、読書は単なる知識の獲得だけでなく、精神的な支えや慰めとしても機能します。三宅さんにとって読書は、忙しい日常から一時的に離れ、異なる世界に身を置くことのできる貴重な時間だったのです。
仕事と読書の相乗効果
三宅さんは、仕事と読書が対立するものではなく、本来は相乗効果を生み出すものであることを指摘しています。読書で得た知識や視点は、仕事における創造性や問題解決能力を高めます。また、仕事での経験は、読書の理解を深め、新たな視点をもたらします。
この相乗効果を生み出すためには、仕事と読書のバランスを取ることが重要です。「全身全霊」で仕事に取り組むのではなく、「半身」のコミットメントで仕事と読書の両方に時間と労力を配分することが、豊かな人生につながるのです。
本書から学ぶ「働く大人の読書術」
本書は単に問題提起をするだけでなく、具体的な解決策も提示しています。三宅さんが提案する「働く大人の読書術」は、多くの読者にとって実践的なヒントとなるでしょう。
隙間時間の活用法
三宅さんは、隙間時間を活用した読書の方法を提案しています。通勤電車の中、昼休み、寝る前のひととき…これらの時間を有効に使うことで、忙しい日常の中でも読書の時間を確保することができます。
ただし、隙間時間の活用には工夫が必要です。例えば、電子書籍を活用する、持ち運びやすい文庫本を選ぶ、読みかけの本を常に持ち歩くなど、自分のライフスタイルに合わせた方法を見つけることが大切です。
読書環境の整え方
三宅さんは、読書に適した環境を整えることの重要性も指摘しています。静かで落ち着ける空間、適切な照明、快適な椅子など、物理的な環境を整えることで、読書への集中力を高めることができます。
また、スマートフォンの通知をオフにする、SNSのアプリを一時的に削除するなど、デジタルな誘惑を排除することも有効です。読書に集中できる環境を意識的に作り出すことが、現代社会では特に重要なのです。
本との付き合い方を見直す視点
三宅さんは、本との付き合い方そのものを見直すことを提案しています。「読むべき本」ではなく「読みたい本」を選ぶこと、読書に対する自分なりの目的や意義を再確認することが大切だと言います。
特に、読書に対する「べき論」から自由になることの重要性を説いています。「この本は読むべきだ」「一日何ページは読むべきだ」といった強迫観念は、読書の楽しさを奪い、かえって本から遠ざかる原因になります。三宅さんは、そうした「べき論」から離れ、自分のペースで、自分の興味に従って読書を楽しむことを勧めています。
また、読書の目的そのものを見直すことも提案しています。読書は単なる知識獲得の手段ではなく、異なる価値観や世界観に触れる体験であり、自分自身を豊かにする活動です。この本質的な意義を再認識することで、読書への向き合い方が変わるかもしれません。
感想・レビュー
三宅香帆さんの「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」は、単なる読書術の本ではありません。それは現代社会における労働と余暇の関係、効率性と豊かさの対立、そして私たちの生き方そのものを問い直す一冊です。
三宅さんの視点が鋭いのは、「本が読めない」という個人的な悩みを、社会構造の問題として捉え直している点です。私たちが本を読めないのは、単に意志が弱いからではなく、「全身全霊」で働くことを求める社会の圧力や、効率性を重視する価値観が内面化されているからだという指摘は、多くの読者の胸に刺さるものでしょう。
特に印象的だったのは、「ノイズ」という概念を用いた分析です。インターネットの普及により、私たちは「ノイズ除去」の欲求を強く持つようになりました。必要な情報だけを効率よく得たいという欲求が強まり、不要な情報=ノイズを排除することが美徳とされるようになったのです。しかし、読書には本質的に「ノイズ」が含まれています。このノイズこそが読書の醍醐味であり、新たな発見や思考の広がりをもたらすものなのですが、効率を重視する現代社会ではこのノイズが邪魔者扱いされてしまうのです。
三宅さんが提案する「半身社会」という概念も魅力的です。仕事に全身全霊を捧げるのではなく、仕事と個人の時間(読書や趣味など)にバランスよく時間と労力を配分する社会。これは単に読書の問題を超えて、私たちの生き方そのものに関わる提案です。
本書を読んで、私自身も自分の読書習慣を振り返りました。確かに、仕事が忙しくなると本を読む時間が減り、読む本も実用的なものに偏りがちです。しかし、三宅さんの言うように、読書には「ノイズ」を含む豊かさがあります。その豊かさを取り戻すためには、仕事と読書のバランスを見直し、「半身」の生き方を模索する必要があるのかもしれません。
三宅さんの文体は明快でありながら深い洞察に満ちています。社会学や文学理論の知識を背景にしつつも、決して難解な専門用語に頼ることなく、読者に寄り添うような語り口で問題の本質に迫っています。このアプローチは、文芸評論家としての三宅さんの力量を示すものでしょう。
まとめ
「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」は、現代社会における読書の困難さを多角的に分析し、その解決策を提示した意欲作です。三宅香帆さんは、「本が読めない」という個人的な悩みを社会構造の問題として捉え直し、「全身全霊」で働くことを求める社会から「半身」の働き方を当然とする社会への転換を提唱しています。本書は単なる読書術の本ではなく、私たちの生き方そのものを問い直す一冊と言えるでしょう。読書を愛する全ての人、そして現代の働き方に疑問を感じる全ての人におすすめの一冊です。