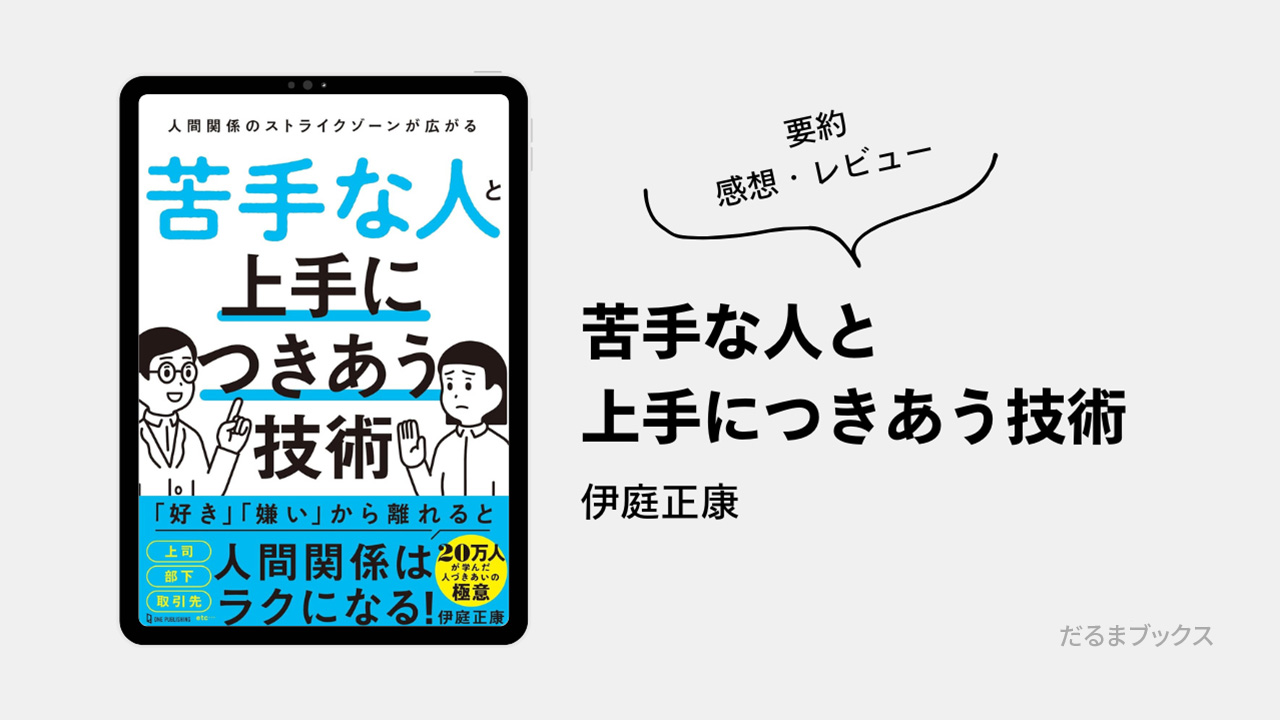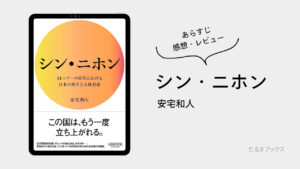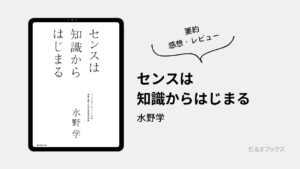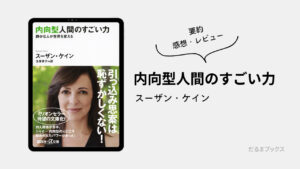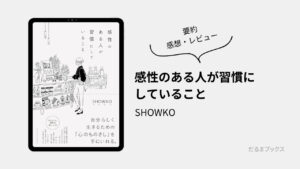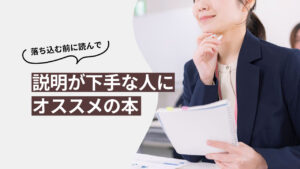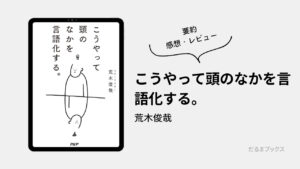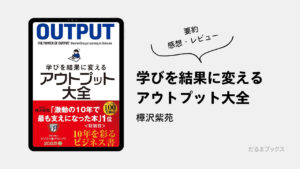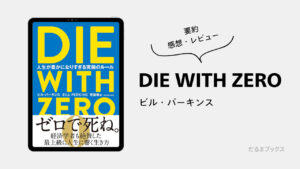人間関係に悩んだことがない人はいないでしょう。特に職場では、
- 苦手な上司
- 性格の合わない同僚
- 言うことを聞かない部下
など「苦手な人」との関わりは避けられません。
この本は、そんな人間関係の悩みに対する処方箋となる一冊です。
「苦手な人と上手につきあう技術」の概要
この本は、作者の伊庭さんが営業職時代に身につけた「苦手な人と上手につきあう技術」を、ソーシャルスタイル理論をベースにした「相性マトリクス」という考え方を軸に解説しています。
これまでに出会った「強敵」をどのようなメソッドを駆使してかわしてきたのか、その具体的な方法が詳細に記されています。
構成は全5章からなり、「苦手な人」の正体から始まり、タイプ分析、心理的テクニック、コミュニケーション術、そして人間関係のストライクゾーンの広げ方まで、段階的に理解を深められる内容となっています。
タイトル:苦手な人と上手につきあう技術
作者:伊庭正康
発売日:2024年12月19日
出版社:ワン・パブリッシング
価格:税込1,650円
サイズ:四六判
ページ数:224ページ
著者・伊庭正康さんのプロフィール
伊庭正康さんは、株式会社らしさラボの代表取締役として活躍する人材育成のプロフェッショナルです。1991年にリクルートグループに入社後、法人営業職として20年以上の最前線経験を持ち、「期待に応えず、期待を超える」をモットーに年間全国一位を4回、累計40回以上の社内表彰を受賞した実績の持ち主です。
営業部長時代には、会議室をバーに変えたり、朝からダンスを取り入れたりと、遊び心あふれる「ワククク」するマネジメントで若手の主体性を引き出し、年商を2年で28億円から46億円へと大幅に押し上げた実績があります。2011年には、一人ひとりのらしさを強みに進化させることをモットーとした研修会社、株式会社らしさラボを設立。現在は年間260回を超える研修、講演、コーチングを行っています。
「草食系と言われる若手の主体性を高める専門家」として知られ、リーダーシップ、コミュニケーション、セールスを専門としています。その楽しく学べる参加型のスタイルが特徴で、実践的なプログラムは好評を博し、リピート率は9割を超えるほど。Webラーニング「Udemy」でも時間管理、リーダーシップ、営業スキルなどの講座を提供し、ベストセラーコンテンツとなっています。
「苦手な人」の正体とは?
なぜあの人が苦手なのか
第1章では、まず「苦手な人」の正体について掘り下げています。世の中は「苦手な人」であふれていて、誰もが何かしらの「苦手な人」を持っているものです。しかし、興味深いのは、あなたのことを「苦手」と思っている人も必ずいるという事実。この相互性を理解することが、人間関係を改善する第一歩となります。
伊庭さんは、「苦手」という感情の正体は、実は自分の評価でしかないと指摘します。つまり、相手の言動や性格そのものではなく、それに対する自分の解釈や評価が「苦手」という感情を生み出しているのです。この視点の転換は、人間関係の悩みを解決する重要なカギとなります。
苦手意識の心理的メカニズム
苦手意識が生まれる心理的メカニズムについても詳しく解説されています。人は自分と似ている人に親近感を抱き、異なるタイプの人に違和感や苦手意識を持ちやすい傾向があります。これは進化の過程で培われた本能的な反応であり、「異質なものへの警戒心」が根底にあるのです。
また、過去の経験が現在の人間関係に影響を与えることも多く、過去に似たタイプの人との間に不快な経験があると、その記憶が無意識のうちに現在の関係性に投影されることがあります。このような心理的メカニズムを理解することで、苦手意識に対する客観的な視点を持つことができるようになります。
誰にでもいる「苦手な人」のタイプ分析
「相性マトリクス」とは
第2章では、「相手を知る」ことで苦手を克服するための「相性マトリクス」が紹介されています。この相性マトリクスは、ソーシャルスタイル理論をベースにしたもので、人の行動パターンを分析するための枠組みです。
相性マトリクスでは、人の行動特性を「主張性」と「感情表現」という2つの軸で分類します。「主張性」は自分の意見や考えをどれだけ積極的に表明するかを示し、「感情表現」は感情をどれだけオープンに表現するかを示します。この2軸によって、人の行動パターンは4つの基本タイプに分類されるのです。
28の設問で相手と自分を知る
本書では、28の設問に答えることで、相手や自分自身のタイプを分析できるページが用意されています。これらの設問は日常的な行動や考え方に関するもので、回答パターンから自分や相手がどのタイプに属するかを判断できるようになっています。
例えば、「会議で積極的に発言するか」「感情を表に出すことが多いか」「計画的に物事を進めるのが好きか」「即断即決するタイプか」といった質問に答えることで、自分や相手の行動パターンが浮き彫りになります。この自己分析と他者分析が、人間関係のトラブルを未然に防ぐ第一歩となるのです。
4つの基本タイプとその特徴
相性マトリクスによって分類される4つの基本タイプとその特徴について詳しく解説されています。
1つ目は「主張性が高く、感情表現も豊か」なタイプで、活発で社交的、情熱的な性格の持ち主です。このタイプの人は決断が早く、リスクを恐れず新しいことに挑戦する傾向がありますが、細部への配慮が不足することもあります。
2つ目は「主張性が高いが、感情表現は抑制的」なタイプで、論理的で効率を重視し、目標達成に強い意欲を持っています。このタイプの人は結果を重視し、直接的なコミュニケーションを好みますが、時に冷たく見られることもあります。
3つ目は「主張性が低く、感情表現も抑制的」なタイプで、慎重で分析的、計画的な性格の持ち主です。このタイプの人は細部に注意を払い、正確さを重視しますが、決断に時間がかかることもあります。
4つ目は「主張性は低いが、感情表現は豊か」なタイプで、協調性が高く、人間関係を重視する傾向があります。このタイプの人は共感力が高く、チームワークを大切にしますが、対立を避けすぎることもあります。
これらのタイプを理解することで、「なぜあの人とは合わないのか」「どうすれば関係を改善できるのか」という疑問に対する答えが見えてくるのです。
苦手な気持ちを減らすテクニック
「嫌い」がなくなる心理的アプローチ
第3章では、苦手な気持ちを減らすための心理的テクニックが紹介されています。伊庭さんは、「期待」しないことの重要性を説いています。人は相手に対して無意識のうちに期待を抱き、その期待が裏切られると不満や苦手意識が生まれます。しかし、相手に対する過度な期待をやめ、ありのままを受け入れる姿勢を持つことで、苦手意識は大きく軽減されるのです。
また、「セルフトーク」法という技術も紹介されています。これは自分自身との内的な対話を通じて、ネガティブな思考パターンを書き換えるテクニックです。例えば、「あの人は私を無視している」という思考を「あの人は今、忙しいのかもしれない」と言い換えることで、感情の変化を促します。
このような心理的アプローチを実践することで、苦手な相手に対する見方が変わり、関係性の改善につながるのです。
感情をコントロールする方法
感情をコントロールするための具体的な方法も詳しく解説されています。まず重要なのは、感情と行動を分離して考えることです。苦手な相手に対してネガティブな感情を抱くことは自然なことですが、その感情に振り回されて不適切な行動をとることは避けるべきです。
感情をコントロールするためのテクニックとして、「一時停止法」が紹介されています。これは、感情が高ぶった時に一旦立ち止まり、深呼吸をして冷静さを取り戻す方法です。また、「視点切り替え法」として、第三者の視点から状況を見直すことで、客観性を保つ方法も紹介されています。
これらのテクニックを日常的に実践することで、苦手な相手との関わりにおいても感情に振り回されず、建設的な関係を築くことができるようになるのです。
争わないコミュニケーション術
対立を避ける会話のコツ
第4章では、苦手な人とは争わないためのコミュニケーション術が解説されています。まず重要なのは、「争わない」という姿勢そのものです。対立や衝突は問題解決につながるどころか、むしろ関係をさらに悪化させることが多いため、意識的に「争わない」選択をすることが大切です。
対立を避ける会話のコツとして、「I(アイ)メッセージ」の活用が紹介されています。これは、「あなたは〜だ」という相手を非難する表現ではなく、「私は〜と感じる」という自分の感情や考えを伝える表現方法です。この方法を使うことで、相手を攻撃せずに自分の思いを伝えることができます。
また、「対立した時は、抽象度を上げる」というテクニックも紹介されています。具体的な事柄で意見が対立した場合、より抽象的な目標や価値観のレベルに話を移すことで、共通点を見出しやすくなるのです。
相手のタイプ別対応法
相性マトリクスで分類した4つのタイプそれぞれに対する効果的なコミュニケーション方法も詳しく解説されています。
「主張性が高く、感情表現も豊か」なタイプには、スピード感を持って対応し、彼らのアイデアや情熱に共感を示すことが効果的です。細かい説明よりも、大きな絵を示し、彼らの創造性を尊重する姿勢が重要です。
「主張性が高いが、感情表現は抑制的」なタイプには、結果や効率を重視した簡潔な対応が効果的です。無駄な社交辞令は避け、要点を絞った論理的な説明を心がけましょう。
「主張性が低く、感情表現も抑制的」なタイプには、詳細な情報と十分な準備が効果的です。急かさず、彼らの分析的な思考プロセスを尊重し、正確さを重視した対応を心がけましょう。
「主張性は低いが、感情表現は豊か」なタイプには、人間関係を重視した温かみのある対応が効果的です。彼らの感情に配慮し、協力的な姿勢を示すことで信頼関係を築くことができます。
このように、相手のタイプに合わせたコミュニケーション方法を実践することで、苦手な相手との関係も大きく改善されるのです。
人間関係のストライクゾーンを広げる
「理解」と「否定しない」の違い
第5章では、人間関係のストライクゾーンを広げるための考え方が解説されています。伊庭さんは、「理解」と「否定しない」の違いに注目しています。すべての人を理解することは現実的には難しいですが、理解できなくても「否定しない」ことは可能です。
「理解」とは相手の考えや感情を自分のものとして受け入れることですが、「否定しない」とは相手の考えや感情の存在を認めることです。この「否定しない」姿勢が、人間関係のストライクゾーンを広げる鍵となります。
伊庭さんは、苦手な人でも10回会えば打ち解けられると言います。これは、継続的な関わりを通じて相互理解が深まり、最初の印象や先入観が修正されていくためです。初対面の印象だけで人間関係を判断せず、時間をかけて関係を育てる姿勢が大切なのです。
実践的な人間関係の築き方
実践的な人間関係の築き方として、「共通点探し」のテクニックが紹介されています。どんなに異なるタイプの人との間にも、必ず何らかの共通点があります。趣味や価値観、目標など、共通点を見つけることで心理的な距離が縮まり、関係性が改善されます。
また、「小さな成功体験の積み重ね」の重要性も説かれています。苦手な相手との間で小さな成功体験(良い会話ができた、協力して問題を解決できたなど)を積み重ねることで、関係性に対するポジティブな認識が形成されていくのです。
これらの実践的なアプローチを通じて、人間関係のストライクゾーンを広げ、より豊かな人間関係を築くことができるようになります。
日常生活での活用法
職場での人間関係改善
本書の内容は、特に職場での人間関係改善に大きな効果を発揮します。職場では異なるタイプの人々と協働する必要があり、相性の良くない相手との関わりも避けられません。そんな環境で、相性マトリクスを活用することで、チームワークの向上や職場の雰囲気改善につながります。
例えば、プロジェクトチームを編成する際に、メンバーのタイプを考慮して役割分担を行うことで、それぞれの強みを活かした効率的なチーム運営が可能になります。また、対立が生じた際にも、相手のタイプを理解していれば、適切な対応方法を選択できるため、問題の早期解決につながります。
伊庭さんは、リクルートでの経験から、多様なタイプのメンバーが協力し合うことで組織のパフォーマンスが向上することを実感しており、その知見が本書に詰まっています。職場での人間関係改善には、まず相手のタイプを理解し、適切なコミュニケーション方法を選択することが重要です。そうすることで、ストレスなく効率的な協働が可能になるのです。
家族や親戚との付き合い方
家族や親戚との関係も、時に悩ましいものです。特に価値観の異なる義理の親や親戚との付き合いは、多くの人が頭を悩ませる問題です。本書では、そうした関係性においても相性マトリクスが活用できることが示されています。
例えば、「異なる価値観を押し付けてくる義理の関係の親とうまくいかない」という悩みに対しても、相手のタイプを理解し、適切な対応を取ることで関係改善が可能です。重要なのは、相手を変えようとするのではなく、自分の対応を調整することです。
伊庭さんは、家族関係においては特に「否定しない」姿勢が重要だと説いています。価値観の違いを認めつつも、互いを尊重する関係を築くことで、家族の絆を深めることができるのです。
医師や専門家との関わり方
日常生活では、医師や専門家など、専門知識を持つ人との関わりも避けられません。「いつも診てもらっている主治医の話し方が高圧的でイヤだ」というような悩みも、相性マトリクスを活用することで解決の糸口が見えてきます。
専門家は往々にして「主張性が高く、感情表現は抑制的」なタイプが多いとされています。そのため、彼らとのコミュニケーションでは、感情的にならず、要点を絞った質問や相談をすることが効果的です。また、事前に質問事項をまとめておくなど、準備をしっかりと行うことで、より建設的な関係を築くことができます。
このように、相性マトリクスは様々な場面で活用できる実用的なツールであり、日常生活のあらゆる人間関係の改善に役立つのです。
感想・レビュー
「相性マトリクス」の実用性
本書を読んで最も印象に残ったのは、「相性マトリクス」の実用性の高さです。人間関係の悩みは誰もが抱えるものですが、その解決法を具体的かつ体系的に示してくれる本書は、まさに現代人必携の一冊と言えるでしょう。
伊庭さんが提唱する「相性マトリクス」は、単なる理論にとどまらず、日常生活のあらゆる場面で活用できる実践的なツールです。28の設問を通じて自分や相手のタイプを分析し、それに基づいた対応策を選択するというアプローチは、非常に合理的かつ効果的です。
特に印象的だったのは、「相手を変えようとするのではなく、自分の対応を調整する」という視点です。人間関係の悩みの多くは、相手に変化を求めることから生じますが、本書はその発想を根本から覆してくれます。自分自身の認識や行動を変えることで、関係性を大きく改善できるという気づきは、読者に大きな希望を与えてくれるでしょう。
人間関係の悩みに効く処方箋
本書は、人間関係の悩みに効く処方箋として、非常に価値のある内容を提供しています。伊庭さんの豊富な経験に基づいた実例や具体的なテクニックは、読者が自分の状況に当てはめて考えやすく、すぐに実践できる点が魅力です。
特に心に響いたのは、「苦手な人でも10回会えば打ち解けられる」という言葉です。初対面の印象だけで人を判断せず、継続的な関わりを通じて相互理解を深めていくという姿勢は、人間関係の可能性を広げてくれます。
また、「理解」と「否定しない」の違いについての解説も非常に示唆に富んでいます。すべての人を理解することは難しくても、否定せずに受け入れることは可能だという視点は、多様性が重視される現代社会において、非常に重要な考え方だと感じました。
本書を読むことで、読者は人間関係に対する新たな視点と具体的な対処法を手に入れることができるでしょう。それは単に「苦手な人」との関係改善にとどまらず、すべての人間関係をより豊かで実りあるものにする可能性を秘めています。
まとめ
伊庭正康さんの「苦手な人と上手につきあう技術」は、人間関係の悩みを抱える全ての人にとって、実践的で価値ある指針を提供してくれる一冊です。「相性マトリクス」という理論をベースに、苦手な人との関係をストレスなく築くための具体的な方法が詳細に解説されています。
本書から得られる最大の学びは、「相手を変えようとするのではなく、自分の対応を調整する」という視点の転換でしょう。また、「理解できなくても否定しない」という姿勢は、多様性が尊重される現代社会において、非常に重要な考え方です。
人間関係の悩みは誰もが抱えるものですが、本書を読むことで、その悩みを解決するための具体的な道筋が見えてくるでしょう。伊庭さんの20万人以上に伝授してきた人づきあいの極意が詰まった本書は、あなたの人間関係を豊かにする大きな一歩となるはずです。